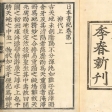精選版 日本国語大辞典 「日本書紀」の意味・読み・例文・類語
にほんしょき【日本書紀】
- 日本最初の勅撰の歴史書。六国史の一つ。「日本紀(にほんぎ)」「書紀」とも。全三〇巻。養老四年(七二〇)舎人(とねり)親王の主裁のもとに完成、朝廷に献じられた記録がみえるが、その編修過程は未詳。第一・二巻は神代、第三巻以下は神武天皇の代から持統天皇の代の終わり(六九七)までを、年紀をたてて編年体に配列してある。その記事内容は、( 一 )天皇の名・享年・治世年数・皇居の所在地を列記した帝紀、( 二 )歴代の諸説話・伝説などの旧辞、( 三 )諸家の記録、( 四 )各地に伝えられた物語、( 五 )詔勅、( 六 )壬申の乱の従軍日記などの私的記録、( 七 )寺院縁起、( 八 )朝鮮・中国の史書の類で構成されている。基本的資料としては「古事記」と関係が深く、「古事記」の撰録者である太安万侶(おおのやすまろ)も編輯者として参加している。「古事記」と同じく天皇を中心とする中央集権国家の確立にあたっての理論的・精神的な支柱とすることを目的としているが、「古事記」が一つの正説を定めているのに比し、諸説を併記するなど史料主義の傾向がある。また、「古事記」が国語表現をでき得る限り表記しようとしているのに対し、歌謡など一部を除いて徹底的な漢文表記である。漢籍、類書、仏典を用いた漢文的潤色が著しい。
百科事典マイペディア 「日本書紀」の意味・わかりやすい解説
日本書紀【にほんしょき】
→関連項目アストン|奄美大島|奄美諸島|伊弉諾尊・伊弉冉尊|伊雑宮|誓|宇治|宇治橋|浦島太郎|餌香市|疫病|大宜津比売神|大津道|大物主神|忍坂|歌徳説話|金田城|上ッ道・中ッ道・下ッ道|記紀歌謡|旧辞|国常立尊|栗隈|元正天皇|遣隋使|越|別天神|後陽成天皇|【さる】田彦大神|釈日本紀|十七条憲法|袖中抄|上宮聖徳太子伝補闕記|続日本紀|神武天皇|辛酉革命|少彦名命|崇神天皇|先代旧事本紀|続浦島子伝記|高安城|橘守部|谷川士清|中世日本紀|月読尊|天皇|豊鍬入姫命|奴国|日本紀竟宴和歌|八紘一宇|一言主神|弁韓|火遠理命|茨田堤|茨田屯倉|任那|三輪山伝説|山口大口費|類聚国史|童謡
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本書紀」の意味・わかりやすい解説
日本書紀
にほんしょき
720年(養老4)に成立した日本初の正史。いわゆる六国史(りっこくし)の第一。神代より持統(じとう)天皇の代までを漢文で編年体に記す。
[黛 弘道]
書名
成立当初「日本紀(にほんぎ)」とよばれたが、平安初期のころから「日本書紀」とよぶようになったと推測される。「日本紀」が国史すなわち勅撰(ちょくせん)の歴史書という普通名詞でもあり、また平安初期に成立した第二の国史を「続日本紀(しょくにほんぎ)」といったので、最初の「日本紀」(正史)をとくに強調するため、わざわざ『日本書紀』といったのではあるまいか。しかし、なぜ「書」の字を加えたか、いまだ適確な説をみない。
[黛 弘道]
成立
その成立時期については『続日本紀』の養老(ようろう)4年(720)5月癸酉(きのとのとり)(21日)条に「先是(これよりさき)、一品舎人親王(いっぽんとねりしんのう)奉勅修日本紀。至是功成奏上。紀卅巻、系図一巻」とあるので明らかであるが、編纂(へんさん)開始の時期や編纂の経緯はかならずしも明らかでない。『日本書紀』の天武(てんむ)天皇10年(681)3月丙戌(ひのえのいぬ)(17日)条に「天皇……詔川嶋(かわしま)皇子・忍壁(おさかべ)皇子(十人略)、令記定帝紀(ていき)及上古諸事」とみえ、天武天皇が川嶋皇子以下に命じて歴史書編纂事業を開始したことが知られるが、一方、『古事記』序文にも天武天皇が舎人稗田阿礼(ひえだのあれ)に命じて「帝皇日継(ていおうのひつぎ)」(帝紀)と「先代旧辞(せんだいくじ)」を誦(よ)み習わせたということがみえる。記紀の2書にみえる編纂事業を同じものとみるか別と考えるかで説が分かれるし、別とすれば両者の前後関係も問題となるが、史料の不足もあっていまだ決定的な説は現れない。
平田篤胤(ひらたあつたね)は両者を同じこととするが、皇子以下の堂々たる陣容と稗田阿礼1人とでは格差がありすぎ、とうてい同一事業とは思えない。一は公的、他は私的事業の感が深い。記紀にいうところを別事とみる説では、まず紀前記後説がある。681年に命じた編纂事業が思うように進捗(しんちょく)しなかったので、天皇は改めて阿礼を相手に記定事業を始めた、というもので、これによれば681年の事業は『古事記』編纂の遠因とはいえるが、直接の起源ではない。次に記前紀後説がある。つまり阿礼を相手に始めた作業が意外に手間取ることを知った天皇は、川嶋皇子以下に命じ別途に編纂事業を開始させた。これが書紀編纂につながるもので、それとは別に阿礼の誦習(しょうしゅう)するところは『古事記』として結実したと説くものである。
なお、681年の当初から『日本書紀』編纂が意図されたとは考えがたいとして、書紀編纂の開始を『続日本紀』和銅(わどう)7年(714)2月戊戌(つちのえのいぬ)条の「詔従(じゅ)六位上紀朝臣(きのあそん)清人(きよひと)、正八位下三宅臣(みやけのおみ)藤麻呂(ふじまろ)、令撰国史」の記事に求める説もある。しかし、清人らの官位が低すぎるのが難点であり、結局目下のところ記前紀後説がもっとも穏当と思われる。
[黛 弘道]
編纂者
先述のごとく編纂総裁は天武天皇皇子舎人親王であり、成立は天武の皇孫元正(げんしょう)女帝の時代である。『日本書紀』が大友皇子の即位を無視したとは『大日本史』の主張であるが、その当否はともかく、天武側の主張が『日本書紀』に強く反映されたであろうことは否定できない。また、編纂当時の実力者藤原不比等(ふひと)の影響を重視する説も近ごろでは人気があるが、過大評価は禁物である。
[黛 弘道]
編纂資料
『古事記』が帝紀と旧辞だけを素材とし、しかも諸説のうち一つの正説を定めて筋を通そうとしたのに対し、『日本書紀』は帝紀、旧辞はいうに及ばず、その他諸家の家記、政府の記録、個人の日記手記、寺院の縁起類、朝鮮側史料、中国史書など多方面にわたる資料を活用し、文章を整えるためにも漢籍、仏典を豊富に引用している。しかも異説を強いて統一せず、一書という形で併記したり、注として付記し、ときに後人の勘校に俟(ま)つ旨を記す。これは、学問的には公平客観的な態度とされようが、国家の正史としては、体裁の面で遺憾なしとしない。『日本書紀』の研究は、成立直後から宮廷における講読という形で盛んに行われ、多くの「私記」がつくられたが、中世以降、神代紀の神道(しんとう)的研究が盛んとなり、これを神典として崇(あが)めるに至り、記紀の神秘的解釈を生じた。この傾向が近代に及び、記紀の科学的研究を阻むことにもなったが、第二次世界大戦後ようやく是正された。
[黛 弘道]
『武田祐吉校注『日本書紀』全6巻(1948~1957・朝日新聞社・日本古典全書)』▽『津田左右吉著『日本古典の研究 上下』(1963・岩波書店)』▽『坂本太郎他校注『日本書紀 上下』(『日本古典文学大系67・68』1965、1967・岩波書店)』▽『黒板勝美編『日本書紀 前・後編』(『新訂増補国史大系』普及版・1971・吉川弘文館)』
改訂新版 世界大百科事典 「日本書紀」の意味・わかりやすい解説
日本書紀 (にほんしょき)
日本最初の編年体の歴史書。720年(養老4)5月,舎人(とねり)親王らが完成。30巻。添えられた系図1巻は散逸。六国史の第1で,後に〈日本紀〉ともよばれ,《古事記》と併せて〈記紀〉という。
内容
巻一と巻二を神代の上と下,巻三を神武紀,以下各巻を1代または数代の天皇ごとにまとめ,巻二十八と巻二十九を天武紀の上(壬申紀とも)と下,巻三十を持統紀とする。文体は漢文による潤色が著しく,漢籍や仏典をほとんど直写した部分もある。記述の体裁は巻三以下を中国の歴史書にならって編年体,すなわち記事を年月日(日は干支で記す)順に排列したために,暦も記録もない古い時代については,物語をその進行に従って分断し適当な年月日に挿入する始末となり,史実としての疑わしさを増し,物語としてのまとまりを失わせた。しかも神武即位を西暦紀元前660年にあたる辛酉の年に設定したので,初期の天皇は不自然な長寿となり,神功(じんぐう)皇后紀でも皇后を《魏志倭人伝》の卑弥呼と考えたので,また120年ほど年代を繰り上げている。
編集に使われた資料は《古事記》のように特定の帝紀(ていき)や旧辞(きゆうじ)だけでなく,それらの異伝も〈一書に曰く〉として注記し,また諸氏や地方の伝承,寺院の縁起,朝鮮や中国の歴史書なども参照している。7世紀初の推古紀のころからはようやく書かれ始めた朝廷の記録も利用し,7世紀後半には個人の日記も加えて,今日から歴史的事実を究明するための資料は豊富となった。ただ大化改新以後も天智紀までは潤色や記録の錯乱があり,ほぼ史実と認められるのは天武紀と持統紀である。なお表記に用いられている漢字や語法は巻ごとに微妙に異なるので,相違に着目して全巻を分類すると,(1)巻一~二,(2)巻三,(3)巻四~十三,(4)巻十四~十六,(5)巻十七~十九,(6)巻二十~二十一,(7)巻二十二~二十三,(8)巻二十四~二十七,(9)巻二十八~二十九,(10)巻三十の10区分,あるいは(2)と(3),(4)と(5)を同類とみる8区分などが可能である。したがって全巻は複数の編集者群により分担して整理執筆されたと想定される。
成立
編集の由来を述べた序文を欠いているために成立過程は明らかでないが,天武紀(下)の10年3月丙戌(17日)条に,川嶋・忍壁(おさかべ)両皇子以下12人の王臣に帝紀と上古諸事(旧辞)の記定を命じたとあるのが,編集の開始とみられている。その後,持統朝には撰善言司が教訓的な歴史物語を作ろうとし,有力豪族の18氏が墓記を提出して諸氏の伝承を記録化し,元明朝には風土記の提出を命じて地方の伝承を集め,紀清人(きのきよひと)と三宅藤麻呂(みやけのふじまろ)に国史の編集担当を命じたことなど,みな《日本書紀》の編集に役立ったのであろうが,これは天智紀以前と天武紀以後との内容の懸隔や,天武紀と持統紀との表現の相違からも確かめられ,結局編集の開始から完成までには40年を要したと認められる。しかし最終段階の編集者は舎人親王以外に明らかでない。太安麻呂(おおのやすまろ)が参加したというのは,子孫の多人長(おおのひとなが)の主張に過ぎず,《日本書紀》が8年前の《古事記》を,内容においても表記においても参考にしていないことは明らかである。
注釈・研究
朝廷では最初の正史として尊重され,完成後まもなくから平安前期まで7回にわたって講書の会が開かれ(日本紀講筵(こうえん)),その記録は《日本紀私記》,講書後の宴会での和歌は《日本紀竟宴和歌》として残された。鎌倉時代には最初の総合的な注釈書として《釈日本紀》,室町時代には《日本書紀纂疏》が書かれたものの,考証学的な研究は近世に入ってからであり,江戸中期以後《日本書紀通証》《書紀集解》《日本書紀通釈》など,いずれも全巻にわたる注釈書が刊行された。明治以後は津田左右吉らによって徹底的な記紀批判が推進される一方,国民教育の分野では記紀の記述をそのまま信ずることが要請されて敗戦を迎えたが,今日では考古学,神話学,文化人類学など関連分野からの分析も深化している。
執筆者:青木 和夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「日本書紀」の解説
日本書紀
にほんしょき
日本最初の官撰国史。全30巻,系図1巻(現存しない)。舎人(とねり)親王らの撰で,720年(養老4)5月21日完成,奏上。編纂の開始は天武朝と推測される。「続日本紀」は「日本紀」と記すが,「日本書紀」が正式の書名であったと考えられる。巻1・2は神代巻で神話的物語。巻3以下には神武から持統までの天皇の代の歴史を中国正史の本紀と同様に編年体で記している。編纂に用いた材料は,「帝紀」「旧辞(きゅうじ)」のみでなく,朝鮮関係史料,諸氏の伝承,地方の伝承,寺院縁起など多様で,7世紀後半からは個人の日記も加わる。また神代を中心に「一書に曰く」として異なる伝承を並記している。文体は正格漢文であるが,中国の正史・古典・仏典による潤色が著しく,「芸文類聚(げいもんるいじゅう)」などの類書を参考にして文章を作っている。雄略・継体以後,朝鮮半島との交渉関係の記事が大きな比重を占め,7世紀初めの推古紀あたりから朝廷の記録をもととしているらしく,史料としての信憑性がます。ただし大化の改新以降も天智紀までは潤色やおそらく壬申の乱による混乱があり,注意が必要で,ほぼ信頼できるのは天武紀・持統紀である。朝廷では最初の正史として重んじられ,10世紀まで7回の講書が行われた。「日本古典文学大系」「岩波文庫」所収。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本書紀」の意味・わかりやすい解説
日本書紀
にほんしょき
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「日本書紀」の解説
日本書紀
にほんしょき
もと『日本紀』といい,平安初期から『日本書紀』と称した。本文30巻,付録系図1巻(現存せず)。舎人 (とねり) 親王・太安万侶 (おおのやすまろ) らが編集にあたった。編纂の始期は不明であるが,720年完成。漢文編年体で,神代から持統天皇に至る天皇中心の国家の成立の歴史を記述しているが,特に神代巻にはかなりの作為や潤色がみられる。古代史研究の重要史料。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
防府市歴史用語集 「日本書紀」の解説
日本書紀
世界大百科事典(旧版)内の日本書紀の言及
【芸文類聚】より
…構成は,北斉の類書《修文殿御覧》360巻に依拠し,天,地から帝王,人,万物にわたる45の部ごとに重要な事項を掲げ,それに関連する詩文を典故を明示して配する。事事を網羅した類書というよりは,むしろ作文のための簡便な参考書であったので,いち早く日本にも将来され,《日本書紀》編纂の際に手本となったという説もある。【勝村 哲也】。…
【神道】より
…そしてその後,神道の語は,道家や仏教の影響下で宗教的な意味を持つようになり,呪術・仙術と同じような意味でも用いられた。漢字・漢語の受容によって表記が可能になった日本では,《日本書紀》の編述に際して,用明天皇即位前紀に〈天皇,仏法を信(う)けたまひ,神道を尊びたまふ〉とあり,孝徳天皇即位前紀に〈(天皇)仏法を尊び,神道を軽(あなず)りたまふ。生国魂社の樹を斮(き)りたまふ類,是なり。…
【日本音楽】より
…
[第1期]
原始日本音楽時代 楽器の出土例がみられる弥生時代から飛鳥時代までにあたるが,楽曲や楽譜が残っていないので明確にはわからない。《古事記》《日本書紀》《風土記》《万葉集》《隋書》倭国伝などの文献中の断片的な記事や,少数の楽器やその演奏を写した埴輪(はにわ)などの出土品により,また日本周辺の原始的姿をとどめる音楽(台湾の原住民の音楽,南洋諸島の音楽)やアイヌ音楽などとの比較類推により,想像するほかはなく,次のように結論されている。歌謡中心の音楽で,伝承歌謡のほかに即興歌謡も多く行われた。…
【日本記】より
…天理図書館吉田文庫)という両部神道の写本にも収められている。中世には《日本書紀》神代巻を解釈することが盛んに行われ,その解釈活動そのものが神道の活動であったが,本曲はこれと同種の活動によって成立したと考えられる。同文が神道書にあることからすると,本曲は独立した曲でありながらも,さまざまな物語が展開される舞曲の世界の起源を示すという意図がかくされているのかもしれない。…
【日本紀講筵】より
…主として平安時代前期に,数回にわたり宮廷で公式の行事として行われた《日本書紀》の講読・研究の会。《釈日本紀》開題に引く〈康保二年外記勘申〉によれば,養老5年(721),弘仁3‐4年(812‐813),承和10‐11年(843‐844),元慶2‐5年(878‐881),延喜4‐6年(904‐906),承平6‐天慶6年(936‐943),および康保2年(965)以後に行われたが,そのうち養老度は完成した《書紀》の披露のためとみられ,弘仁以後が講究を主とするもので,元慶度に至って形式・内容ともにほぼ完成の域に達し,承平度から熱意が薄れて衰退に向かった。…
【日本紀私記】より
…奈良~平安前期に宮廷で行われた《日本書紀》講読の際の記録。《日本書紀私記》ともいう。…
※「日本書紀」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...