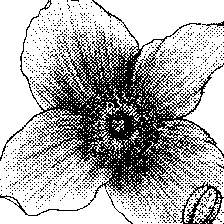改訂新版 世界大百科事典 「メコノプシス」の意味・わかりやすい解説
メコノプシス
Meconopsis
ケシ属に近縁なケシ科の大型の多年草あるいは一年草で,45種が知られる。その大部分はヒマラヤ山系および四川,雲南,甘粛など中国の山岳地帯に分布し,西ヨーロッパにM.cambrica Vig.(英名Welsh poppy)が,カリフォルニアに1種がみられる。多くは有毛。葉形は全縁から羽状深裂まで変化に富み,柔らかく,切ると黄色の乳液が出る。花は単生,または総状花序,散房花序につき,比較的大輪でケシの花に似る。早落性の萼片は,普通2枚,まれに3~4枚。花弁は4~10枚あり,M.cambricaでは黄色であるが,ヒマラヤには,赤色,紫色,青色などさまざまな花色のものがあり,近年,園芸家の注目を集めている。とりわけ青色のM.betonicifolia Franch.,M.grandis Prainなど(いずれの英名もblue poppy)は〈ヒマラヤの青いケシ〉として知られる。子房には4~多数の胎座があり,柱頭が胎座と同数ある点はケシ属と共通の特徴であるが,花柱が明りょうに認められる点により区別される。果実は卵形の蒴果(さくか)。ヒマラヤ高山原産種が多く,日本では夏が高温のため多年草の種は栽培がむずかしい。
執筆者:森田 竜義
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報