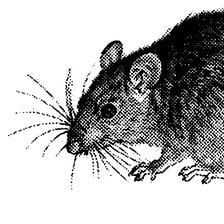クマネズミ
くまねずみ / 熊鼠
black rat
roof rat
[学] Rattus rattus
哺乳(ほにゅう)綱齧歯(げっし)目ネズミ科の動物。熱帯アジアが分布の中心であるが、今日では世界中に生息し、50以上の亜種に分けられている。染色体数から、42本のアジア型、38本のオセアニア型、40本のセイロン(スリランカ)型の3型に大別される。日本には、染色体数42本で小形のニホンクマネズミR. r. tanezumiという家住性の亜種が分布する。尾が頭胴より長く、頭胴長16~20センチメートル、尾長17~24センチメートル、後足長31~35センチメートル、体重100~170グラム。野生種では背面茶褐色、腹面白色であるが、家住性のものでは、全身黒色のものから、背面茶色で腹面黄褐色のものなど多様である。夜行性で、熱帯では樹上生活をしているが、暖帯より寒い地域では家住性となり、家屋、倉庫、畜舎などにすむ。船に侵入するネズミの90%以上が本種である。よく鳴くが、超音波のため人間の耳には聞こえない。果実や草木の種子、穀物、飼料などを主食とし、昆虫の幼虫も食べる。ニホンクマネズミではおもに4~9月に、飼育下では周年繁殖して、1回に2~8頭の子を産む。子は90日で頭胴長15センチメートル、体重100グラムに成熟する。ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアには染色体数38本のヨウシュクマネズミR. r. rattusが分布し、エジプトネズミなどが含まれる。
[土屋公幸]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
クマネズミ
black rat
roof rat
Rattus rattus
耳が大きく,尾の長いイエネズミの1種。齧歯目ネズミ科の哺乳類。体長20cm,尾長23cm前後。体色は褐色から黒色までさまざまである。原産地は東南アジアであるが,住家性となって人為環境に侵入し全世界に広がった。日本にすむものは有史以前に侵入したものと思われるニホンクマネズミと,新しく入ってきたヨウシュクマネズミの2亜種に区別され,後者のほうが大型で色が黒い。前者は山間の農耕地にすみ,後者は都市部にすむ。自然の生息地では木登りを得意とし,巣を木の枝の上につくるなど,なかば樹上生の生活を送っている。したがって,人家に侵入したものも,ドブネズミと異なり,下水などには入らず,もっぱら天井で生活する。また,ビルなどの立体的な構造物の中での生活にも適し,船舶にもしばしば侵入する。このため,フナネズミ,フネネズミと呼ばれることがある。繁殖は5~9月にかけて多く行われ,その他の時期には少ない。雌は1産1~10子,平均6子を生む。
執筆者:今泉 吉晴
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
クマネズミ
齧歯(げっし)目ネズミ科。体長15〜23cm。尾は体よりも長く,耳が大きい。背面は黒褐色,腹面は灰褐色が普通。イエネズミの一種。原産地は東南アジアであるが,住家性となって,今ではほとんど世界中に分布。木登りがうまく,屋内では天井裏などにすむ。普通1腹6子前後,妊娠期間21日。
→関連項目ネズミ(鼠)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
クマネズミ
Rattus rattus; black rat
齧歯目ネズミ科。体長 15~24cm,尾長 15~25cm。尾は体長に等しいかやや長い。耳が大きく,前に倒すと眼をおおうほどである。これらの点で近縁のドブネズミと区別できる。夜行性。人家の天井裏などにすみ,一年中繁殖し,妊娠 21日で5~8子を産む。しかしドブネズミのほうが優勢で,それとの比率は少しずつ減少しているといわれる。インド,ミャンマー,ラオスなどが原産地であるが,現在では住居性の害獣として全世界に分布している。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
クマネズミ
学名:Rattus rattus
種名 / クマネズミ
科名 / ネズミ科
日本にいる動物 / ◎
解説 / 木登りが得意です。ふつう屋内にすみますが、小笠原諸島や南西諸島などでは野外でも生息しています。
体長 / 15~24cm/尾長15~26cm
体重 / 150~200g
食物 / 雑食だが、主に種子、こく物、果実などを好む
分布 / 日本をふくむ世界中
出典 小学館の図鑑NEO[新版]動物小学館の図鑑NEO[新版]動物について 情報
Sponserd by 
クマネズミ
[Rattus rattus].人の住まいなどに棲むネズミの一種.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のクマネズミの言及
【イエネズミ(家鼠)】より
…人家およびその付近の農耕地などにすみ,人間社会に半ば寄生して生活するネズミ。ふつう[ドブネズミ],[クマネズミ],[ハツカネズミ]の3種を指す。これに対し,山野などの自然環境下で野生生活をおくるネズミをノネズミ(野鼠)という。…
【ペスト】より
… 本来ネズミの病気であるペストの歴史は,ネズミの生態の歴史と密接な関係がある。もともとインドからアジア南部にかけて生息していた保菌ネズミ(クマネズミ)が,気候変動による食物連鎖の変動によって移動を始め,しだいに北上し,さらに西進したと思われる。とくに13世紀は東西交流の盛期で,十字軍が東方へ,蒙古が西方へと進み,こうした人と物の動きにつれ,東西を結ぶ交易路いわゆるシルクロードに乗ってペストの伝播が起こった。…
※「クマネズミ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by