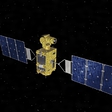日本大百科全書(ニッポニカ) 「低軌道通信衛星」の意味・わかりやすい解説
低軌道通信衛星
ていきどうつうしんえいせい
low earth orbit
高度3万5786キロメートルの静止軌道衛星に比べ、高度が700~2000キロメートルと低い軌道を回る通信衛星。非静止衛星のため、電波の届かないエリアがほとんどなく、低軌道のため通話の遅延が少ない。こうした特性を利用して、全地球的な携帯電話システムが構築され、さまざまな事業が展開された。アメリカのモトローラ社が中心となったイリジウムシステムでは、地上780キロメートルに66機の衛星を打ち上げ、1998年に試験運用が、1999年にサービスが開始された。しかし、資金不足などの理由からサービスを停止、2000年8月にはモトローラ社が衛星の廃棄処分を決定した。ほかにアメリカのロケット会社オービタル・サイエンスとカナダの国際通信事業者テレグローブが中心となったオーブコム社では、1995年4月に地上約825キロメートルに衛星を打ち上げ、2008年5月現在で28機の衛星を使用し運営している。また、アメリカのマイクロソフト社ビル・ゲイツとマッコーセルラー社(現在AT&Tに吸収合併)グレイグ・マッコーの共同構想によって1994年に設立されたテレデシック社では、地上約700キロメートルに合計288機の小型衛星を打ち上げ、2002年にサービスを開始する予定であった。しかしその後、携帯電話の地上システムの充実などで需要の見込みが不透明となったため、2002年に計画は中止となった。なお日本では、2006年(平成18)4月に、高度600キロメートルの低軌道を周回する光衛星間通信実験衛星「きらり」と地上局の間での光通信実験に成功している。
[荒木健次]