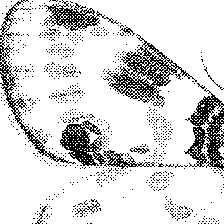改訂新版 世界大百科事典
「ユウマダラエダシャク」の意味・わかりやすい解説
ユウマダラエダシャク (夕斑枝尺)
Abraxas miranda
鱗翅目シャクガ科の昆虫。翅の開張3~4.5cm。体は橙黄色,腹部に黒紋を連ねる。翅は乳白色,灰色の紋が多数ある。前翅基部は橙黄色,その外側に黒褐色帯があり,後角近くに大きな紋がある。日本全土,朝鮮半島,中国東北に分布する。関東から近畿の平野部では,春と夏の2回成虫が出現し,食樹の付近を昼間弱々しく飛ぶし,灯火にも飛来する。幼虫は黒色のシャクトリムシで,淡黄色の帯や線がある。年2回の発生がふつうだが,秋に成虫が羽化することもあって,幼虫はいろいろの発育段階で越冬し,ときには年内に蛹化(ようか)することもある。発育の進んだものほどさなぎの休眠期が長いため,春に第1回目の成虫が羽化する時期はだいたいそろう。マサキ,コマユミ,ツルマサキなどニシキギ科の葉を食べる。マサキの生垣によく発生し,多発すると葉がほとんどなくなってしまう。
執筆者:井上 寛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ユウマダラエダシャク
ゆうまだらえだしゃく / 夕斑枝尺蛾
[学] Abraxas miranda
昆虫綱鱗翅(りんし)目シャクガ科に属するガ。はねの開張は第1化が40~45ミリメートル、第2二化が30~35ミリメートルぐらい。体は橙(だいだい)色の地に黒点をちりばめ、はねは白色で灰色あるいは淡い黒紋がある。前翅基部は橙色で黒帯があり、後角近くに同様の紋がある。斑紋(はんもん)は個体によって変異があり、また東北地方のものは関東地方以西のものより小さい。北海道南部から琉球(りゅうきゅう)諸島の西表(いりおもて)島までと、朝鮮半島、中国東北部に分布。幼虫は黒地に黄色斑や帯のあるシャクトリムシで、マサキ、コマユミ、ツルマサキに寄生する。マサキの生け垣に多発し、葉を丸坊主にすることがある。成虫は春と夏の2回出現し、日中、食樹近くを飛ぶ。
[井上 寛]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ユウマダラエダシャク
学名:Abraxas miranda
種名 / ユウマダラエダシャク
解説 / 昼間にも飛びます。夏に発生するものは、小さいです。
目名科名 / チョウ目|シャクガ科
体の大きさ / (前ばねの長さ)18~26mm
分布 / 北海道~南西諸島
成虫出現期 / 5~6月、8~10月
幼虫の食べ物 / マサキ、コマユミなど
出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報
Sponserd by