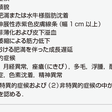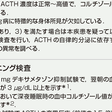内科学 第10版 「Cushing病」の解説
Cushing病(視床下部・下垂体)
慢性的高コルチゾール血症を呈し,特異的な臨床徴候を示す疾患群をCushing症候群という.そのうち下垂体性ACTHの過剰分泌が原因で二次的に高コルチゾール血症をきたしたものをCushing病とよぶ.
分類
ACTH過剰分泌が原因となり二次的に高コルチゾール血症をきたす群をACTH依存性Cushing症候群とよぶ.ACTH依存性Cushing症候群のうち,下垂体原発のものをCushing病とよぶ.下垂体以外の腫瘍においてACTHが産生されるものを異所性ACTH産生腫瘍とよび,そのうちACTHを自律的に分泌させるものを異所性ACTH症候群という. 下垂体ACTH産生腫瘍のうち,ACTHを産生してもほとんど分泌されないものを臨床的にsilent corticotroph adenomaとよぶ.またACTHの自律的分泌があっても典型的なCushing症候群の臨床徴候を示さないものをサブクリニカルCushing病という.Cushing病の治療として両側副腎摘出術が行われる場合がある.その場合,術後にそれまで小さくてわからなかった下垂体腺腫が明らかに増大すると同時にACTH分泌もさらに亢進し,その結果著明な色素沈着をきたすことがある.この状態をNelson症候群という.
病因
Cushing病のほとんどが下垂体のACTH産生微小腺腫(microadenoma:径1cm以下)が原因と考えられている.まれに大きな腫瘍(巨大腺腫マクロアデノーマ)のことがあるが,この場合には腫瘍細胞のACTH産生・分泌能が未熟な場合が多い.下垂体以外で,肺癌や胸腺腫,カルチノイドなどの神経内分泌腫瘍がACTHを生産することがある.これは異所性ACTH症候群という.
疫学
中年女性に多くみられ,男女比は1:4といわれている.1965〜86年にかけて行われた全国調査では,年に約100例程度が新しくCushing症候群症例として診断され,そのうち約50%がACTH非依存性で,Cushing病は40%程度と考えられている.
病理
ACTH産生下垂体腺腫のほとんどは微小腺腫で,好塩基性かつPAS陽性であることが多い.非腫瘍組織のACTH細胞は萎縮しており,しばしば高コルチゾール血症のため細胞質にサイトケラチンフィラメントが集積する.これをクルーク(Crooke)変性という.最近,ACTH産生マクロアデノーマの中で,増大傾向が強く浸潤性で再発しやすい腫瘍細胞が見つかるようになった.これらの腫瘍はCrooke cell adenomaとよばれ,中年女性に多いといわれている.また腫瘍細胞中にACTH関連ペプチドの免疫染色が陽性でも腫瘍外には分泌されない腫瘍がある.これらをsilent corticotroph adenomaという.副腎は両側が過形成を示し,束状層と網状層が厚くなる.
病態生理
下垂体ACTHは視床下部CRHの調節を受けている.分泌されたACTHは全身循環に入り副腎皮質に至る.そこで束状層に作用してコルチゾールの合成と分泌を,網状層に作用してDHEA-Sの合成と分泌を促進させる.血中コルチゾール濃度が上昇すると,視床下部CRHと下垂体ACTHの合成と分泌は抑制される.これをネガティブフィードバックという.さらにCRH-ACTH-コルチゾール系は,夜間に分泌が低下し早朝に亢進するが,その後夜にかけて低下傾向を示す.これを日内変動という.またストレスによってもこの系は賦活化される.このストレス,日内リズム,ネガティブフィードバックをこの系の3大調節因子という. Cushing病の場合は腺腫細胞からACTHが半自律的に合成・分泌され,ネガティブフィードバックに対しては部分的な抵抗性を示す.これを利用したのがデキサメタゾン抑制試験である.一方で血中コルチゾール値が急に減少するとネガティブフィードバックが解除され,ACTH分泌は過大反応を示す.ACTH産生腺腫細胞にはCRH受容体のほかにV1b受容体も発現している.したがって外因性のCRHやバソプレシンに対してACTHが増加反応を示す.V2アゴニストであるDDAVPのV1b受容体に対する親和性は低いが,腫瘍細胞化することにより親和性が亢進する.そのため正常人にDDAVPを投与してもACTH分泌は変化しないが,ACTH産生腫瘍細胞の場合はDDAVPによりACTHの分泌が増加する.この場合,下垂体性と異所性の区別はできない. 慢性高コルチゾール血症になると下垂体のLH,FSH分泌が抑制され生理不順または無月経を引き起こす.またGH系も抑制されるため小児のCushing病では成長が遅延する.さらにTSH系も抑制されるが甲状腺機能低下症になることはほとんどない.また蛋白異化作用のため皮膚および皮下組織の萎縮による菲薄化と皮下溢血,赤色皮膚線状のほか,血管壁の脆弱性による皮下出血もみられる.さらに筋萎縮を示し,内臓脂肪が蓄積するためインスリン抵抗性や中心性肥満を示す.また骨に対しては骨形成の抑制と骨吸収の亢進から骨粗鬆症となる.血液に対しても白血球の増加,リンパ球と好酸球の減少がみられる.慢性的高ACTH血症による色素沈着はおもに関節部や四肢の摩擦部から始まり,爪さらには口唇や口腔粘膜にもみられるようになる.Nelson症候群の場合は,この色素沈着が著明で,さらに腫瘍増大のため視野異常をきたすことがある.
臨床症状
表12-2-12と図12-2-12のように,慢性的高コルチゾール血症による特異的な臨床徴候と非特異的な徴候に分けられる.サブクリニカルCushing病の場合には非特異的所見のみがみられる.
Nelson症候群やCrooke cell adenomaの場合は周辺に浸潤し眼球運動や視野に異常をきたすことがある.
検査成績
1)一般検査:
①末梢血液検査;白血球数増加,リンパ球と好酸球の減少.②生化学検査;低カリウム,低クロール血症(代謝性アルカローシス),ときに高ナトリウム血症,高カルシウム尿症,高脂血症,耐糖能異常(インスリン抵抗性).③骨粗鬆症関連;骨吸収マーカー増加,骨密度減少,骨折像.
2)基本的内分泌検査:
朝の血中ACTH,コルチゾール値,DHEA-S値,尿中遊離コルチゾール値,できれば唾液中コルチゾール値がいずれも正常〜高値.
臨床徴候と一般検査①と②でCushing症候群が疑われたならば,ACTH依存性Cushing症候群の可能性を考えスクリーニング検査に進む.
3)スクリーニング検査(表12-2-12):
①0.5 mgデキサメタゾン抑制試験(必須)のほかに,②深夜血中または③唾液中コルチゾール値,④4 μg DDAVP試験のいずれかを行う.①を満たし,さらに②〜④の1つを満たせばACTH依存性Cushing症候群と考えられ,次の鑑別診断のための確定診断検査を行う.
4)確定診断(表12-2-12):
①8 mgデキサメタゾン抑制試験,②CRH試験,③下垂体MRI検査で腫瘍の検出の3つを満たせば90%以上の確率でCushing病と考えられる.3つを満たさない場合,またはより高い確率を求める場合には④選択的静脈血サンプリング(下錐体静脈洞または海綿静脈洞)を行う.これで異所性ACTH症候群が疑われたならば,全身の画像検査で病巣の検出を行う.サブクリニカルCushing病については表12-2-13を参照のこと.
合併症
高血圧,脂質異常症,肥満,骨粗鬆症などのメタボリック症候群や生活習慣病を合併しやすい.さらにうつ状態が進むと自殺企図の傾向があるので注意を要する.最も注意しなくてはならないことは免疫力の低下による易感染性である.血中コルチゾール値が30 μg/dL以上になると敗血症を生じる可能性が出てくるので,抗真菌薬などの予防的投与も考慮する必要があり,50 μg/dLに近づくと敗血症による死の可能性が高くなるのでコルチゾール合成阻害薬(即効性でメトピロン,遅効性でオペプリム)の投与が必要である.
経過・予後
治療がうまくいかない場合は敗血症で早期に死亡する例を除いても,高血圧や糖尿病を併発して大血管障害や易感染性により死亡する例が一般人よりも数倍多く,平均余命は下垂体非機能性腫瘍例に比べ,より不良であるといわれている.
治療
治療の第一選択は経蝶形骨下垂体腺腫摘出術である.術後1〜4週間で朝の内因性血中コルチゾール値が2 μg/dL以下であれば,その後のACTH分泌能は低下〜正常を示すと考えられる.下垂体腺腫摘出術が成功した場合,視床下部-下垂体-副腎系の回復には約1年かかる.術後ヒドロコルチゾンを20 mg/日程度から補充を開始し,その後漸減して約半年経ち,補充量が10 mg/日以下になったならば内因性の血中コルチゾール値を測定する.その値が5〜10 μg/dL程度であればCRH試験やインスリン低血糖試験を行い,視床下部-下垂体-副腎系の回復を確認した後,補充を中止する.手術ができないか手術しても腫瘍の残存がある場合には,下垂体の定位的照射(ガンマナイフまたはサイバーナイフ)を行う.その効果が出るまではステロイド合成酵素阻害薬(メトピロンやオペプリム)を投与する.最近D2アゴニストであるカベルゴリンやソマトスタチンアナログの有効例が報告されているが,今後出る予定の新しいタイプのソマトスタチンアナログが有望視されている.[須田俊宏]
■文献
千原和夫,他:クッシング病の診断と治療の手引き(平成17年度改訂)およびPre(sub)-clinical Cushing病の診断と治療の手引き(平成17年度新規),pp125-129,厚生労働省,東京,2006.
大磯ユタカ,他:クッシング病の診断の手引きおよびサブクリニカルクッシング病の診断の手引き(平成21年度改訂),pp158-162. 厚生労働省,東京,2010.
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報