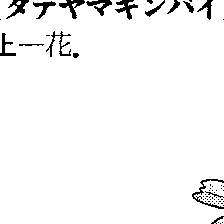改訂新版 世界大百科事典 「タテヤマキンバイ」の意味・わかりやすい解説
タテヤマキンバイ (立山金梅)
Sibbaldia procumbens L.
日本では立山で初めて発見された,黄色の花をもつバラ科の高山植物。高山帯の日向の砂礫(されき)地に見られ,草丈5~10cm,茎は地をはい,木質化する。葉は3出複葉で,長い柄がある。小葉はくさび形をなし,先端は3~5個の鋸歯がある。夏に,茎の先端部分より花茎を出し,花序は散房状で,花は非常に小さい。花弁は5枚,黄色で萼片の方が少し長い。おしべ5本,めしべ5~20本。果実は瘦果(そうか)。本州中部地方と北海道の高山にまれに産し,サハリン,千島からシベリアをへてヨーロッパに,またアラスカからグリーンランドまでと広く北半球の寒帯および高山に分布し,氷河時代の残存植物とみなされている。
タテヤマキンバイ属Sibbaldiaは世界に20種あるが,日本にはこの種のみ産する。キジムシロ属と類縁が近く,同じ属とする人もいる。
執筆者:鳴橋 直弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報