日本大百科全書(ニッポニカ) 「ピナコリン」の意味・わかりやすい解説
ピナコリン
ぴなこりん
pinacolin
脂肪族ケトンの一つ。ピナコロンともいう。構造を表す名称はtert‐ブチルメチルケトンである。ピナコールに硫酸を作用させると生成し、この反応はピナコール転位として知られている。
快いにおいをもつ無色の液体。水にはわずかしか溶けないが、エタノール(エチルアルコール)、エーテルなどほとんどの有機溶媒と任意の割合で混じり合う。有機合成試薬、溶媒として用いられる。
[廣田 穰 2015年7月21日]
[参照項目] | |
[補完資料] |

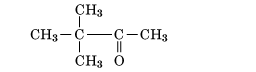
 ) 1.3944
) 1.3944