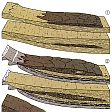日本大百科全書(ニッポニカ) 「オリストストローム」の意味・わかりやすい解説
オリストストローム
おりすとすとろーむ
olistostrome
巨大岩塊を含む大規模な海底地すべり堆積(たいせき)物。従来のスランプ礫岩(れきがん)、海底地すべり礫岩といわれていたもののうち、通常の地質図に示されるほど広く分布するものは、これに含まれる。小礫から長径数キロメートルに至る大小さまざまのレンズ状の小岩体やブロック(地塊)が泥質基質中に不規則に入っており、普通の礫岩とは明らかに異なる。その岩質には、大陸棚起源の堆積岩、蛇紋岩などの超塩基性岩、橄欖(かんらん)岩、玄武岩などのオフィオライト組合せから花崗(かこう)岩質岩石までさまざまある。これらのブロックはオリストリスolistolithとよばれる。
成因的には次の3通りが知られている。すなわち、(1)オリストストロームを含む地層と同一累層(るいそう)に由来する表層すべりによるもので、半固結ないし未固結状態のときに生成したもの。(2)それを含む正常層よりも時代的に古い同一堆積盆地内の他の地層に由来するもの。(3)別の堆積盆地から移動してきたナップの先端部が崩壊したもの、などである。
[岩松 暉 2016年2月17日]
最新 地学事典 「オリストストローム」の解説
オリストストローム
olistostrome
外来の岩塊や,一連の地層のうち下位の未固結~固結した地層に由来する岩塊が,泥質の基質中に乱雑に含まれる堆積物。含まれる岩塊はオリストリス(olistolithまたはolistolite)と呼ばれ,その大きさは礫サイズから径数kmに及ぶ。元来は,1955年にG.Floresが提唱した用語で,Floresの定義は,通常の地層に挟まれ,地図に示される程度の十分な連続性をもち,岩相的・岩質的にも雑多な物質の混在で特徴づけられ,半流動状に堆積した堆積物。含まれるオリストリスが,オリストストロームが挟まれる同一の地層に由来するものをendolistostrome, 同一の地層以外の地層や岩石に由来するものをallolistostromeと区別することがある。
執筆者:久富 邦彦
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「オリストストローム」の意味・わかりやすい解説
オリストストローム
olistostrome
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「オリストストローム」の意味・わかりやすい解説
オリストストローム
→関連項目メランジ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
岩石学辞典 「オリストストローム」の解説
世界大百科事典(旧版)内のオリストストロームの言及
【乱堆積】より
…これは,地層が比較的急速に堆積し,地層の固結がまだ十分進んでいない状態で,堆積した斜面の傾斜が何らかの原因により増加したような場合に,斜面崩壊が原因で水中地すべりが生じたものである。大規模な地層の地すべりによって生じた地層をオリストストロームolistostromeと呼ぶ。(2)崩壊構造collapse structure 上にのるやや重い堆積物が下の軟らかい堆積物中に,荷重による変形により,めりこんでいる構造をいう。…
※「オリストストローム」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...