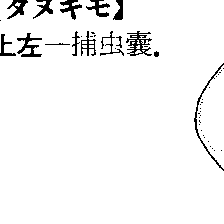タヌキモ
Utricularia japonica Makino
根をもたず,池や水田などに浮遊するタヌキモ科の多年生食虫植物。厳密な意味での茎や葉をもたない。茎状器官は長く伸び,ところどころで分枝する。葉状器官は互生し,細かい枝状で平たく,多数の捕虫囊(ほちゆうのう)をもつ。この栄養組織形態がタヌキの尾に似ているところから,タヌキモの名がついた。夏,10~20cmの花茎を水面上につき出して,数個の黄色花を総状につける。萼は卵形で2片からなり,花冠は仮面状となって,基部に距を1本もつ。下唇は中央部がふくれ,頂部は褐色を呈する。2本のおしべと1本のめしべをもつ。冬季,茎状器官は著しく節間が短くなり,先端が葉状器官でおおわれて球状となって,水底に沈み越冬する。アジア北東部に広く分布し,日本全国にみられる。類似種としてノタヌキモU.aurea Lour.があるが,葉状器官が四方に枝状に伸び立体的であり,空中に出る花茎に鱗片葉状器官がなく,一年草である点で異なる。
執筆者:近藤 勝彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
タヌキモ
たぬきも / 狸藻
[学] Utricularia × japonica Makino
Utricularia vulgaris L. var. japonica (Makino) Tamura
タヌキモ科(APG分類:タヌキモ科)の多年草。イヌタヌキモとオオタヌキモの雑種。根はなくて池沼に浮遊し、球形の越冬芽をつくり、水底に沈んで冬を越す。葉は密に互生して左右に広がり、平面上に3~4回羽状に細裂する。多数の捕虫嚢(のう)をつけ、水中の微小な動物をとらえて消化吸収する。花茎は高さ10~25センチメートル、広卵形の鱗片葉(りんぺんよう)をつける。7~9月、距(きょ)のある黄色花を開く。果実は成熟しない。本州と九州に分布する。名は、茎の先の葉が房状に密集している形をタヌキの尾に見立て、水中に生えることによる。
タヌキモ属は、花は多くが総状につき、萼(がく)は2裂する。世界に約250種ある。日本には13種の記録がある。
[高橋秀男 2021年10月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
タヌキモ
タヌキモ科の水生食虫植物。日本全土に分布する。多年生で植物体は柔らかく,葉は糸状の裂片に細かく分かれ,所々に小さい捕虫袋をつける。夏〜秋,水上に直立する花茎をたて,上半に数個の花をまばらにつける。花冠は黄色で仮面状をなし,径1.5cm,短い距がつく。葉が茎についたようすをタヌキの尾にみたててこの名がある。同属にコタヌキモ,ヒメタヌキモ,ノタヌキモ,フサタヌキモなどがある。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のタヌキモの言及
【食虫植物】より
…すべて独立栄養者として,葉や茎にクロロフィルをもち光合成を行う一方,従属栄養的な性質ももち,獲物の小動物から窒素やリン等を摂取する。世界で,モウセンゴケ科([モウセンゴケ]属約90種,モウセンゴケモドキ属1種,[ハエトリグサ]属1種,[ムジナモ]属1種),サラセニア科([サラセニア]属8種,ランチュウソウ属1種,キツネノメシガイソウ属約10種),ウツボカズラ科([ウツボカズラ]属約70種),フクロユキノシタ科([フクロユキノシタ]属1種),ビブリス科(ビブリス属2種),ディオンコフィル科(トリフィオフィルム属1種),タヌキモ科([ムシトリスミレ]属47種,[タヌキモ]属約150種,ゲンリセア属約15種,ビオブラリア属1種,ポリポンポリックス属2種)が知られる。日本にも2科4属21種の自生が認められる。…
※「タヌキモ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by