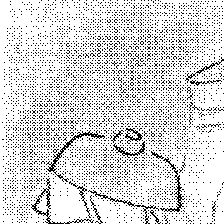虫の垂衣 (むしのたれぎぬ)
平安時代に主として婦人の旅行者などが,乗馬や徒歩のとき,笠の周囲に薄い布を長く垂らした被り物。正しくは〈枲垂衣〉と書く。当時の婦人は外出時に衣をかぶったり(衣被(きぬかずき)),その上から市女(いちめ)笠をかぶったりして顔を隠したが,旅行には便宜上笠に薄い布をとじつけて,顔を隠すと同時に,道中の風塵(ふうじん)や害虫を避けた。〈むし〉というのは多年生草本のカラムシ(苧,苧麻),またはケムシ(枲)の〈ムシ〉の意である。虫の垂衣には一幅ごとに飾りとしてあげまき結びにしたひもを垂らしたものもあるが,多くは実用的なものであった。
執筆者:日野西 資孝
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
虫の垂衣
むしのたれぎぬ
平安~室町時代に主として女性が旅行の際などに用いた,笠のまわりに薄い布を長く垂らしたかぶりもの。虫という名がついたのは,垂衣の原料として大麻より上等のカラムシ (苧麻) が材料に用いられたことからきている。苧麻は感触がよく,当時織物の原料として国内で広く生産されていた。女性がこれを使う目的は,一つには顔を隠すことであり,またほこりや害虫を避けるためであった。 (→被衣〈かつぎ〉 , 壺装束 )
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
虫の垂衣【むしのたれぎぬ】
虫垂(むしたれ)とも。平安時代の婦人が旅行のときなどに用いたかぶり物。笠の周囲に薄い布をとじつけたもので,顔を隠すとともに風塵や害虫を避けた。一説にカラムシの繊維で織った布を用いたところからこの名がある。→市女笠
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by