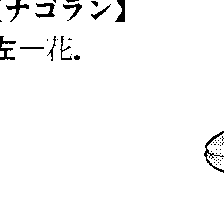ナゴラン
Sedirea japonica (Linden.et Reichb.f.) Garay et Sweet
ラン科の常緑の着生ランで,伊豆諸島以西の西日本,琉球の常緑樹の幹に着生する。和名は沖縄本島の名護にちなむ。茎は短く,肥厚はしない。2列生の葉が3~5枚あり,狭長楕円形で,長さ8~15cm,5~8月,葉腋(ようえき)から長さ5~12cmの花茎を出し,数花をつける。花はやや大きく径約3cm,淡黄白色で,側萼片に褐色の横縞,唇弁に紅紫色の斑紋がある。唇弁は3裂し,側裂片は小さく,中央裂片はへら形で,前方に突き出る。前方に湾曲した太い距がある。従来はエリデス属Aeridesに分類されたが,最近,固有属として取り扱うことが多い。常緑の葉や美しい花を観賞するため栽培される。
執筆者:井上 健
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ナゴラン
なごらん / 名護蘭
[学] Sedirea japonica (Lindenb. et Reichb.f.) Garay et Sweet
ラン科(APG分類:ラン科)の常緑多年草。茎は短く、葉は2列互生に並んで3~6枚を密につけ、長さ8~15センチメートル。5~8月、葉腋(ようえき)から長さ5~12センチメートルの花茎を出し、径約3センチメートルの淡黄白色花を3~10個開く。側萼片(がくへん)に褐色の横縞(よこじま)、唇弁に紅紫色の斑紋(はんもん)がある。唇弁は3裂し、側裂片は小さく、中央裂片はへら形で前方に突き出る。前方に湾曲した太い距(きょ)がある。樹上や岩上に着生し、伊豆諸島以西の西日本、沖縄、朝鮮半島、中国南部に分布する。名は、沖縄の名護(なご)で採集されたことによる。
[井上 健 2019年5月21日]
ヘゴ材につけるか、鉢底に木炭を入れて通気をよくし、ミズゴケで鉢植えとする。温度の高い所でよく育ち、夏は半日陰で、冬は凍らない程度に管理する。
[猪股正夫 2019年5月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ナゴラン
ラン科の常緑多年草。本州中部〜沖縄,朝鮮半島の暖地の樹上や岩上にはえる。葉は3〜5枚が短い茎に2列につき,狭長楕円形で厚くて硬い。夏,腋生の下垂した花茎に数花をつける。花は径1.5〜2cm,基部には前方を向いた袋状の距(きょ)があり,花被片は淡緑色を帯びた白色で,紫紅色の斑点がある。名は沖縄本島の名護にちなむ。
→関連項目エリデス|ラン(蘭)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ナゴラン(名護蘭)
ナゴラン
Aerides japonicum
ラン科の常緑多年草。紀伊半島や四国,九州など暖地の樹上や岩上に着生する。茎は短く斜上し,下部に多数の太くて長い気根を出す。長楕円形で厚い葉は1株に3~5枚が密に互生する。6~8月に,6~15cmの花茎を垂らし,4~10個の花を総状につける。花は径 1.5~2cmで,淡緑を帯びた白色で唇弁や側萼片に淡紅色の斑紋がある。沖縄の名護岳に生えることからこの名がつけられた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by