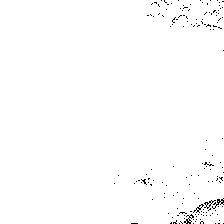ミナミコメツキガニ
Mictyris brevidactylis
十脚目ミナミコメツキガニ科の甲殻類。甲長1cmほどのカニで,干潮時の干潟を群れをなし,餌を食べつつ歩き回る。体をもち上げて前へ歩く姿が,いかにも勇ましい印象を与えarmy crabとかsoldier crabの英名がある。ただし,水分の少ない干潟の場合には群れをなして歩き回ることはなく,砂泥中で餌を食べ,不用となった砂泥を表面にトンネル状に押し上げる。甲は後方にやや広い球形で,鰓域(さいいき)が大きく膨らみ,深い溝で他の甲域から分けられている。はさみ脚は左右同大で,両指とも砂泥をすくうのに適している。歩脚は細長く,コメツキガニ(スナガニ科)のような鼓膜構造はない。外形に雌雄差はなく,雄の腹部も幅広い。種子島が北限で東南アジアまで分布するが,オーストラリアからは近縁のM.longicarpus,M.platypes,M.livingstoniの3種が知られている。それぞれ形態だけでなく,生態も少しずつ異なっている。
執筆者:武田 正倫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ミナミコメツキガニ
Mictyris guinotae
軟甲綱十脚目ミナミコメツキガニ科 Mictyridae。甲長 1.5cm。甲は強く盛り上がり,全体として球形で,後縁が板状に突出する。大型個体は青色を帯びているが,小型の個体では褐色。長い歩脚で体を持ち上げて前方へ歩く。定着した巣穴をもたず,危険を感ずると体をねじこむように回転して,すみやかに砂泥中にもぐる。干潮時に干潟表面の餌を食べながら群れをなして移動する。しかし,干潟がやや硬い場合は表面を歩かず,砂泥中にトンネルを掘りながら摂餌し,不要の砂を干潟表面に押し上げるため,表面はみみずばれのように見える。鹿児島県種子島から琉球列島各地に生息する個体群は,2010年に東アジア産の種とは別種とされた。なおミナミコメツキガニ科は 1属 5種からなり,群れをなして歩くという生態から兵隊ガニ soldier crabあるいは軍隊ガニ army crabと総称される。(→甲殻類,十脚類,節足動物,軟甲類)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ミナミコメツキガニ
みなみこめつきがに / 南米搗蟹
[学] Mictylis brevidactylus
節足動物門甲殻綱十脚(じっきゃく)目ミナミコメツキガニ科に属するカニ。種子島(たねがしま)からマレー諸島あたりまで分布し、ヒルギの茂るマングローブ湿地に群生する。甲長・甲幅とも1.5センチメートルほどで、一見、コメツキガニに似ているが、眼柄(がんぺい)が短く、甲の後縁が板状。定住のための巣穴をもたず、干潮時に餌(えさ)を求めて群れで移動する。ただし、底質が硬いと砂泥中で餌をあさり、表面に砂泥を盛り上げる。オーストラリアに近縁の3種がすみ、そのうちミクティリス・ロンギカーパスM. longicarpusがよく知られている。ミナミコメツキガニ類は群れをなして前へ歩くようすからsoldier crab(兵隊ガニの意)とよばれる。
[武田正倫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by