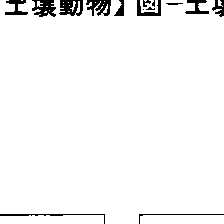日本大百科全書(ニッポニカ) 「土壌動物」の意味・わかりやすい解説
土壌動物
どじょうどうぶつ
土の中で生活する動物。土壌生物には、菌類、バクテリア、藻類などの微生物、植物の埋土種子(まいどしゅし)、ミミズやモグラに代表される土壌動物などがある。このうち土壌動物といわれる仲間は、分類学的には原生動物から脊椎(せきつい)動物の哺乳(ほにゅう)類まで8門78目あるいはそれ以上の動物群を含んでいる。また、土壌動物は全般に小形であるが、大きさは千差万別で数十マイクロメートルから数十センチメートルのものまである。また、土壌中にとどまって生活する期間も、生活史のすべてを土壌中で過ごすもの、生活史のほとんどの時期を土の中で過ごすが成体となるとときどき地表に出るもの、幼虫の時期だけ土壌中に滞在するものなどまちまちである。このように多種多様な土壌動物を端的に定義することはむずかしいが、青木淳一(1935―2022)は「土壌動物とは、大形動植物遺体をも含めた土壌環境に、永続的あるいは一時的に生息し、そこでなんらかの活動を行っている動物群」と定義している(1973)。したがって、土壌中に不活動期(卵や蛹(さなぎ)など)の間だけ滞在するものや、越冬や夏眠のためだけ滞在するものは除外されている。土壌動物は土壌中という生息場所に適した次のような形態的な特徴をもっている。
(1)空間が狭いため小形化している。
(2)移動しやすいように円筒形か扁平(へんぺい)で細長い体形をしている。
(3)歩脚(ほきゃく)は短く、ないものもある。
(4)昆虫では飛ぶ必要がないため、はねのないものが多い。
(5)暗黒の土壌中では体色はじみで白色化しているものもある。
(6)目が退化しているものもある。
土壌動物は地球上の陸地のあらゆる場所に生息しているが、環境の変化に敏感である。とくに、人間の影響で自然が変化を受けると、生息する種類が減少したり、種類が入れ替わったりする。このことを利用して土壌動物を指標生物として用い、自然の豊かさの目安とする試みが提案されている。この方法は、ミミズ、ヤスデ、ダンゴムシ、アリなど34の動物群の出現の有無によって点数をつけるもので、小学生でも高学年になればできる方法であるため、学校教育の現場やクラブ活動にも取り入れられ、またしばしば環境アセスメント(環境影響評価)にも組み込まれるようになっている。
[青木淳一・原田 洋]
生息密度と現存量
生息密度や現存量は1平方メートル当りの個体数や重量で表すことが多く、肉眼で見える大形の動物は50センチメートル(または25センチメートル)四方の方形枠を何個か調査して算定する。肉眼では見えない小形の動物は5センチメートル×4センチメートル、深さ5センチメートルの採土缶を何個か打ち込み、これから算定することが普通である。生息場所や季節の違いによって生息密度や現存量は大きく変化する。森林では、線虫、ヒメミミズ、ササラダニ、トビムシなど腐食性動物の生息密度は高く、1平方メートル当り合計10万~100万個体となる。一方、カニムシ、クモ、甲虫のような肉食性の捕食者の密度は合計100~数千個体と少ない。現存量は暖かい所ほど大きな値を示すことが多い。ハイマツ群落(0.8グラム)より亜寒帯針葉樹林(3グラム)で大きく、それより冷温帯落葉樹林(20~50グラム)、さらに暖温帯照葉樹林(50~100グラム)で大きい値となっている。
[青木淳一・原田 洋]
土壌動物の働き
土壌動物のおもな働きは、有機物の粉砕と土壌の耕耘(こううん)とに大別される。粉砕は、土壌動物が落ち葉や落ち枝のような植物遺体を食料として摂取し、糞(ふん)として排出することによって行われる。動物の消化管を通った粒子の細かい有機物には、バクテリアや菌類などの微生物が増殖しやすく、植物が養分として利用する無機物に分解されやすい。また、微生物によってある程度変質した植物遺体は、それらの影響を受けないものより動物に摂食されやすい。つまり両者は有機物の分解過程で互いに作用しあい分解を促進している。土壌動物が粉砕する落ち葉の量は相当多く、1年間に1平方メートル当りダンゴムシが15グラム、キシャヤスデが60グラムの落ち葉を摂食したという研究がある。またミミズが1か月に14グラムのシイの葉を摂食し、この重さはシイの葉110枚に相当するという報告もある。粉砕は植物遺体ばかりでなく、動物の死体や糞などの動物遺体についてもシデムシやコガネムシの仲間によって行われる。
粉砕や分解は微生物との共同作業であったが、土壌の耕耘・攪拌(かくはん)は土壌動物の単独作業である。土の中を生活の場としているため、移動することによって土壌の耕耘が自然に行われることになる。すなわち、地表近くの有機物を地下に動かし、地下の貧養な土壌を地表に運び出して有機物と土壌とを混合する。また、孔隙(こうげき)をつくることによって土壌の通気性や通水性を高めてくれる。とくに移動力の大きいミミズは土壌耕耘にもっとも大きな働きをしている。たとえば、クソミミズは1年間に1平方メートル当り3.8キログラムの糞塊(径2ミリメートルぐらいの小さい粒の糞からなる)を地表に排出し、土壌中に3.1リットル分の空間を形成したという報告がある。実際には食べた土をすべて糞塊として地表に排出したわけではないので、土壌耕耘量はさらに大きな値となる。
[青木淳一・原田 洋]
採集法
野外で採取した土壌試料から動物を分離・抽出するには、動物の体の大きさや特性を利用した次の三つの方法がある。
(1)ハンド・ソーティング 白布の上で落ち葉や土壌を篩(ふるい)にかけ、落下した動物をピンセットと吸虫管を使用し、肉眼で採集する方法で、ミミズ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヨコエビ、ハサミムシ、アリ、ゴミムシ、ムカデ、ヤスデ、クモなど体長2ミリメートル以上の大形土壌動物を対象とする。
(2)ツルグレン装置 上方から電球で照射し、篩の上の土壌試料を乾燥させることによって動物を漏斗(ろうと)を通して下方に移動落下させ、下受け瓶の中に集める装置である。カニムシ、ダニ、トビムシ、カマアシムシ、微小な甲虫など小形節足動物を採集するのに有効である。
(3)ベールマン装置 土壌中の水に依存して生活している線虫、ヒメミミズ、クマムシなどの小形の湿性動物を抽出する方法である。これは土壌試料を水に浸した状態で、泳ぎ出してくる動物をゴム管の中に集めるという湿式の抽出装置である。
(2)、(3)の採集法は、体長2ミリメートル以下の肉眼ではなかなかみつけることが困難な微小動物を対象とする。
[青木淳一・原田 洋]
『青木淳一著『土壌動物学――分類・生態・環境との関係を中心に』(1973・北隆館)』▽『渡辺弘之著『土壌動物のはたらき』(1983・海鳴社)』▽『青木淳一・渡辺弘之監修『土の中の生き物――観察と飼育のしかた』(1995・築地書館)』▽『青木淳一編著『日本産土壌動物――分類のための図解検索』(1999・東海大学出版会)』▽『渡辺弘之著『土壌動物の世界』(2002・東海大学出版会)』
改訂新版 世界大百科事典 「土壌動物」の意味・わかりやすい解説
土壌動物 (どじょうどうぶつ)
soil animals
Bodentiere[ドイツ]
落葉や土の中で生活している動物。土壌微生物(細菌,カビ)まで含める場合,土壌生物と呼ばれる。
種類
土壌動物の中でだれでも知っているのはモグラ,ミミズ,アリであろう。さらにジグモ,ヤスデ,ムカデ,ワラジムシ,ダンゴムシ,ケラ,ハサミムシ,オサムシ,キセルガイなどがある。これらは肉眼でも見つけることができるので,大型土壌動物と呼ばれている。しかし,このほかにも目につきにくい小さな動物,例えばダニ,カニムシ,コサラグモ,トビムシ,カマアシムシ,ハネカクシ,ヒメミミズ,センチュウ(線虫)などがたくさん生息しており,これらは小型土壌動物と呼ばれている。もっと小さなアメーバ,ミドリムシ,ゾウリムシなどの仲間も土粒の隙間のわずかな水の中にすんでおり,微小土壌動物と呼ばれる。以上の動物はすべて一生の間土壌中で生活するものであるが,セミ,コガネムシやアブ,ハエ,ガのあるもののように,卵や幼虫の時代だけを土中で過ごすものもある。地上を走り,飛ぶ動物は大型で美しいものが多いため目につきやすいが,実は土の中こそもっとも多くの種類の動物たちが住んでいるにぎやかな世界なのである。
生態
土壌動物は種類が多いので,その食生活もいろいろである。ミミズやワラジムシのように腐りかけた落葉などを食べるもの(腐食者)がもっとも多く,次いでモグラ,ムカデ,オサムシ,クモのように他の動物をとらえて食べるもの(肉食者)が多く,わずかではあるがセミの幼虫,ネアブラムシ,センチュウのあるもののように生きた植物の根を栄養源にするもの(植食者)もある。
多くの土壌動物は自分で穴を掘る力がないので,落葉の隙間,倒木の下,やわらかい腐植の中などに潜り込んで生活するため,地表から10cmくらいの深さまでの浅いところにもっとも多くの動物が集まっている。しかし,なかにはモグラやケラのように強力な前足で土を掘ったり,ミミズのように体が細長く,土の中に体をこじ入れたり,土を食べながら穴を掘ることのできるものや,大勢が協力して大あごで土粒をくわえて地上に運び出すアリなどでは,地下数mの深さにまでトンネルを掘ることができる。わずかでも土があり植物(コケだけでもよい)があるところには,必ず土壌動物がすみついている。森林や草原はもちろんのこと,果樹園,畑,庭,道路の植込みの下にもいる。しかし,それぞれの種類によって好きな場所がある。多くの土壌動物は自然のよく保たれた森林で,地表に落葉が深々と積もっているようなところを好むが,アリのように草地や裸地の土を好むものもある。ミミズは酸性の強い針葉樹林を好まない。
生態系における働き
地面には毎年毎年多量の落葉が積もる。枯枝や倒れ木,まつぼっくり,はがれ落ちた樹皮,動物の死体や糞などもある。これらは生物遺体detritusと呼ばれ,自然が出したごみのようなものと考えてもよい。これらはいつの間にか姿形を変えて土になっていくが,それは何の働きによるのであろうか。細菌(バクテリア)や菌類(カビ)などの微生物がこれらの生物遺体を分解してくれるということは,よく知られている。しかし,この分解作業に土壌動物がおおいに協力してくれていることはあまり知られていない。
落下してまもない新鮮な落葉はヤスデ,ダンゴムシ,ワラジムシが,腐りかけの落葉や枝はササラダニ,トビムシ,ミミズが,大きな朽木はシロアリ,ゴキブリ,クワガタムシの幼虫などが,ネズミやヘビの死体はシデムシが,シカやウサギなどの糞はセンチコガネやマグソコガネが,それぞれ食べものとしてかみ砕き,糞として排出する。その糞は土壌微生物にバトンタッチされてさらに分解が進められる。また逆に,微生物によってある程度分解されかかったものが,土壌動物によって好んで食べられる。もちろん,これらの働きは土壌動物の中でも腐食者と呼ばれるものに限られる。
土壌動物の数はきわめて多い。例えば,本州のふつうの森林では,地面1m2について,ミミズ5~20匹,ヤスデ20~100匹,ワラジムシ,ダンゴムシ50~300匹,ヒメミミズ1万~4万匹,トビムシ2万~5万匹,ササラダニ2万~6万匹,センチュウ50万~500万匹くらいの数が見られることが多い。これだけ多くの動物たちが,冬もほとんど休まずに一年中,微生物とともに落葉などを土にかえす作業に取り組んでいる。人間が工場でつくり出した物は別として,自然界で生産されたものから出た自然のごみは,何一つ残らず,自然の土壌の中にすむ“解体屋たち”によって豊かな土となり,再び植物の養分として利用されるしくみになっている。豊かな土壌は土壌生物がいきいきと活動しているところに存在する。人目につかぬ暗い土中の世界で,自然界の物質循環にとって重要な働きをしている土壌動物は,同じ地球上に住む人間にとってたいせつな共存者であるといえよう。
執筆者:青木 淳一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
最新 地学事典 「土壌動物」の解説
どじょうどうぶつ
土壌動物
soil fauna
土壌(動植物遺体を含む)中で生活する動物。動植物遺体や糞の粉砕,摂食による有機物と土壌の混合,土壌中での移動などの生活作用により,腐植の形成,団粒の生成,土壌の攪拌等に大きな役割を果たしている。便宜上,体長によって大型(>2mm, ミミズ・アリ・シロアリ等),中型(0.2~2mm, ダニ・トビムシ・線虫等),小型(0.2mm>,原生動物)に分けられる。
執筆者:松井 健・渡辺 彰
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...