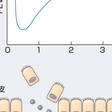関連語
精選版 日本国語大辞典 「好塩基球」の意味・読み・例文・類語
内科学 第10版 「好塩基球」の解説
好塩基球(アレルギーに関与する細胞・分子)
好塩基球が遊離するメディエーターはマスト細胞と似るが,表面マーカーやサイトカインによる機能制御システムについては好酸球との共通点が多い.好塩基球が表面に発現する免疫グロブリン受容体としては,FcεRIのほかにFcγRⅡ(CD32)がある.前者はIgE依存性の活性化を惹起し,後者はおもに抑制性シグナルを伝える.刺激を受けて産生するサイトカインとしては,特にIL-4,IL-13が重要であり,Th1サイトカインは産生しない.この性質に基づき好塩基球は,ある局面ではTh2優位環境の誘導に決定的な役割を有することが推測されている.血液中で白血球の0.5~1%を占めるにすぎない好塩基球は,血液中のヒスタミンのほぼすべてを含有しており,長い間,組織中のマスト細胞と類似した機能を発揮する補助的な細胞と考えられていた.しかし,実際にはマスト細胞とは別個の役割を有するとの知見が徐々に集積されてきている.鼻腔,気道,皮膚に対する抗原暴露直後に生ずる即時型アレルギー反応(即時相)の終結後,抗原暴露の4~8時間後から再び局所でアレルギー反応が出現するが,この遅発相(図10-22-5)において,局所に好塩基球の集積がみられるとともに,採取された組織液の解析により,好塩基球と共通するメディエーターのプロフィール(ヒスタミン陽性,LTC4陽性,PGD2陰性)がみられ,好塩基球の機能的関与が示唆されている.
従来は,動物実験においてごく少数の好塩基球を解析することは難しく,マスト細胞とは別個の独自の機能をin vivoで証明するのは不可能であったが,近年の研究の進展により好塩基球のみを除去する実験系が開発され,好塩基球の関与を明瞭に提示することが可能となった.マウスでの解析により,IgE依存性に起こる反応は即時相や遅発相だけでなく,その後に再び遷延性の局所炎症(超遅発相)が惹起されること,そしてこの反応には好塩基球が必須であることが判明している.マウスの知見とヒトの病態とを照合する作業が必要ではあるが,気管支喘息など慢性のアレルギー疾患の病態において,おそらく,この細胞の関与がいままで考えられていたよりも強く,何らかの局面では数の上で少数の好塩基球が司令塔の役割を果たしていることが想定される.[山口正雄]
■文献
Barnes PJ: New therapies for asthma: is there any progress? Trends Pharmacol Sci, 31: 335-343, 2010.
Hsu FI, Boyce JA: Biology of mast cells and their mediators. In: Allergy: Principles and Practice, 7th ed (Adkinson NF Jr, Bochner BS, et al eds), pp311-328, Mosby, Philadelphia, 2009.
羅 智靖:マスト細胞:感染防御の最前線からアレルギーまで.アレルギー病学(山本一彦編),p55-63,朝倉書店,2002.
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
栄養・生化学辞典 「好塩基球」の解説
世界大百科事典(旧版)内の好塩基球の言及
【血球】より
…赤血球(2)白血球 白血球と総称されるものは,大きさ,核の特徴,細胞質の顆粒などから5種類に分類される。まず,顆粒をもった白血球が最も多く,顆粒の染色性から,淡紫紅色の顆粒(中性の色調)を有するものを好中球,粒状の橙色(酸性)顆粒を有するものを好酸球,濃い青紫色で粗大な顆粒をもった血球を好塩基球という。この3種の白血球は,共通して顆粒を有することから顆粒球と総称される。…
【白血球】より
…骨髄で生産され,体内に侵入した病原微生物や異物を貪食する。好中球,好酸球,好塩基球の3種がある。 好中球はエオジン‐メチレンブルー染色で顆粒が中間的な淡桃~淡紫赤色に染まることから名づけられた。…
※「好塩基球」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...