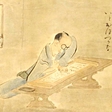関連語
日本大百科全書(ニッポニカ) 「木版印刷」の意味・わかりやすい解説
木版印刷
もくはんいんさつ
版材に木を使った凸版印刷。もっとも古い印刷方法で、7世紀ごろから中国で経典、仏像、紙幣などの印刷に使っていた。木版には板目木版と木口(こぐち)木版とがある。板目木版は、朴(ほお)や桜の材を縦に切った板を版材(版木)とし、これに彫刻をする。この版に刷毛(はけ)で水性インキをつけ紙を当て、その上からバレンで擦って印刷をする。文字の種類の多い日本では、活版印刷発明後も江戸時代までは出版に使われていた。木口木版は、つげ材を横に切った板に彫刻した版である。板目木版に比べて非常に堅いので、白抜きの図柄が多い。木口木版はイギリスで開発され、ヨーロッパで使用されていたので西洋木版という人もある。味わいのある印刷物ができる。
[平石文雄]
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「木版印刷」の意味・わかりやすい解説
木版印刷
もくはんいんさつ
wood block printing
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「木版印刷」の解説
木版印刷
もくはんいんさつ
中国で始まり,日本では奈良時代の百万塔陀羅尼がはじめとされる。仏教の経典を木版刷にすることが多く,室町時代に中国版式の五山版が新しく発展。近世初期,朝鮮の技術が入り,江戸時代に最盛期をむかえた。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
世界大百科事典(旧版)内の木版印刷の言及
【版本】より
…ここでは狭義の版本だけを取り上げることとする。義浄三蔵(635‐713)の《南海寄帰内法伝》によれば,インドでも型をもって多数の小塔を造り,印板を使用して経文を絹などに印刷したのを見かけたとあり,その他傍証とするに足るものも存するから,厳密な意味での木版印刷術の発祥地はインドであるかもしれない。しかし木版印刷の盛行を招来したのは中国人であった。…
※「木版印刷」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
2月17日。北海道雨竜郡幌加内町の有志が制定。ダイヤモンドダストを観察する交流イベント「天使の囁きを聴く集い」を開く。1978年2月17日、同町母子里で氷点下41.2度を記録(非公式)したことにちなむ...