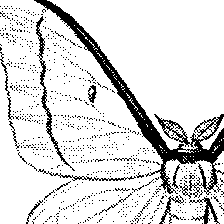オオミズアオ (大水青)
Actias artemis
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
オオミズアオ
おおみずあお / 大水青蛾
[学] Actias artemis
昆虫綱鱗翅(りんし)目ヤママユガ科に属するガ。はねの開張90~100ミリメートル。はねは細長く、後ろばねは尾状に伸び、雄ではとくに長い。薄い青色の地に白鱗を散布し、前後翅とも小さい眼状紋があって、内側は紫黒色線で縁どられる。北海道から屋久(やく)島まで全国的に普通で、よく灯火に飛来する。春と夏の2回出現し、夏に出る雄は黄色みが強く、波状の外横線が明瞭(めいりょう)なことが多い。国外では朝鮮、シベリア、中国に分布する。幼虫はバラ科、ブナ科、カバノキ科などの樹木の葉を食べる緑色のイモムシで、背面各節の突出部から長い刺毛が生えている。蛹(さなぎ)で冬を越す。本種に似て、幼虫がハンノキ属の樹木に寄生するオナガミズアオA. gnomaも日本に分布している。
[井上 寛]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
オオミズアオ
Actias artemis; luna moth
鱗翅目ヤママユガ科。大型のガで前翅長 50~65mm。翅は青白色で黄色の眼状紋をもち,前翅前縁は赤褐色に縁どられる。後翅に長い尾状突起があるが,雌では雄よりはるかに短く幅広い。体も青白色毛におおわれるが,両前翅基部間の背面は赤褐色である。成虫は年2~3回発生する。幼虫の食草はクリ,サクラ,リンゴ,ウメ,カエデなど。日本全土,朝鮮,中国北部,シベリアなどに分布し,本州,四国,九州産を亜種 A. a. aliena,沖縄産を亜種 A. a. xeniaという。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「オオミズアオ」の意味・わかりやすい解説
オオミズアオ
鱗翅(りんし)目ヤママユガ科のガの1種。開張100mm内外,青白色の優雅な大型のガで後翅は長く後方に突出する。日本全土,シベリア東部,中国などに分布。幼虫はウメ,サクラ,カエデなどの木の葉を食べ,蛹(さなぎ)で越冬,成虫は年2回,春と夏に現れる。近似種にオナガミズアオがある。オナガミズアオは準絶滅危惧(環境省第4次レッドリスト)。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
オオミズアオ
学名:Actias aliena
種名 / オオミズアオ
目名科名 / チョウ目|ヤママユガ科
解説 / さなぎで越冬します。
体の大きさ / (前ばねの長さ)50~75mm
分布 / 北海道~九州
成虫出現期 / 4~5月、7~8月
幼虫の食べ物 / サクラ、クリ、ハンノキなど
出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報
Sponserd by