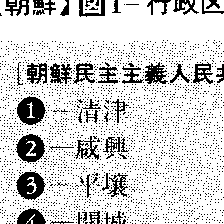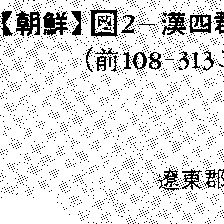精選版 日本国語大辞典 「朝鮮」の意味・読み・例文・類語
ちょうせんテウセン【朝鮮】
- 朝鮮半島とその付属島からなる地域。東は日本海、西は黄海に面し、南は朝鮮海峡、北は豆満江と鴨緑江によって画される。伝説では檀君王倹の朝鮮に始まるが、中国の史書によると前三世紀、北西部に箕子(きし)朝鮮、つづいて前二世紀衛氏朝鮮が興り、のち漢の武帝が楽浪以下四郡を設けた。古来北方には沃沮(よくそ)・濊貊(わいばく)、南方に韓族が居住し、馬韓・弁韓・辰韓の三部数十国に分かれていたが、四世紀中頃高句麗(こうくり)・百済(くだら)・新羅(しらぎ)の三国鼎立を経て、七世紀末に新羅が統一を完成、国家体制が整備され文化が発展した。一〇世紀に高麗、一四世紀李氏朝鮮と、王朝が代わり近代を迎えた。一九一〇年、日本に併合され、四五年、日本の敗戦で解放されたが、のち、三八度線を境に分断され、四八年南に大韓民国、北に朝鮮民主主義人民共和国が成立した。五〇~五三年の朝鮮戦争を経て現在に至る。
改訂新版 世界大百科事典 「朝鮮」の意味・わかりやすい解説
朝鮮 (ちょうせん)
Chosǒn
ユーラシア大陸の東縁から日本列島へ突き出した半島部と大小3400余個の付属諸島からなる地域。面積は約22万1000km2で,ほぼイギリス本国に匹敵する。1948年以後は,南半部の大韓民国(9万9000km2,人口は1996年現在,4523万)と,北半部の朝鮮民主主義人民共和国(12万1000km2,人口は1996年推計で2390万)とに分かれている。
朝鮮の名は,14世紀末から約500年間この地域を支配した李氏朝鮮王朝(李朝)によって広まったが,《史記》の箕子のくだりに朝鮮の名がみられるように紀元前にすでにこの名があったとされる。例えば《東国輿地勝覧》(1481)は〈朝日が鮮明なるところ〉として朝鮮の由来をあげている。李朝時代の学者,李瀷(りよく)は朝は東方,鮮は鮮卑族の意と解釈した。英語のKoreaは高麗の発音(Koryǒ)からきたもので,世界にまたがる大帝国を築いた元が伝えたものであろう。なお,朝鮮の異称や雅号として,〈三千里錦繡江山〉(南北が3000朝鮮里に及ぶ),〈槿域〉(ムクゲの花が咲くところ),〈青丘〉,〈鶏林〉(もとは新羅の異称),〈韓〉〈海東〉などがある。
自然
地形の特徴
朝鮮は地形上,東・西朝鮮湾頭をつないだ北部と南部の二つに大きく区分できる。北部は平北~蓋馬(かいま)地塊であり,日本海(朝鮮では東海という)に沿って北東から南西方向に走る咸鏡山脈を頂点に北西方向に緩傾斜の斜面が広く分布している。この地塊は鴨緑江・豆満(とまん)江対岸の長白山脈と一体のもので,本質的には半島部ではなく大陸に属する。結晶片岩,花コウ片麻岩類からなり,始生代以後海進の影響を大きく受けなかった安定地塊のため,堆積岩層の分布が少ない。山脈西側斜面は鴨緑江・豆満江の流域をなすが,土砂の流出が非常に少なく,嵌入(かんにゆう)曲流する河道の沿岸にはほとんど平地を発達させていない。東・西朝鮮湾線の南部は本来の半島部というべきもので,日本海寄りを南北に走る太白山脈を頂点に,西側に広い緩斜面を形成している。この斜面は長いあいだの風化・浸食作用によって土砂の流出が極度に進み,固い岩層が残丘状に残り,これらが太白山脈から南西方向の支脈(小白山脈)となっている。咸鏡山脈,太白山脈の日本海側は断層作用によって急崖が形成されており,落下した土砂による狭い海岸平野が延々と続いている。平北~蓋馬地塊は南が隆起し,北が沈降した傾動地塊であり,半島部は東が隆起し,西が沈降した傾動地塊である。
中国との国境をなす鴨緑江・豆満江はともに白頭山に発し,広大な流域面積を有するが,風化・浸食作用の少ない固い岩盤上を流れるため,嵌入曲流が発達しているが,沿岸にほとんど平地を形成していない。半島部の漢江,洛東江,錦江は山地から多量の土砂を運び,流域に多数の盆地平野を形成している。河口まで流れ出た土砂は強い潮流によって沖合に流されるため,デルタ平野はあまりみられないが,広大な干潟地を形成しているのが特色である。大同江の中・下流には露出した石灰石が広く分布し,カルスト地形をみせる楽浪準平原となっている。日本海側の河川は短く,急傾斜であり,土砂流出量が多く,砂州,潟湖などの独特の地形を多数形成している。
内陸にはこじんまりした盆地が多数みられ,古代からこれらが住民の主たる生活舞台となってきた。広い海岸平野としては北から清川江河口の博川平野,大同江・載寧江合流点の平壌・載寧平野,漢江下流の金浦平野,錦江,万頃江,東津江が連なる湖南平野,栄山江流域の羅州平野,洛東江下流の金海平野がある。日本海側のみるべき平野としては竜興平野のみである。海岸線は東海岸と西北海岸は単調だが,所々に天然の良港がみられる。中西海岸以南と南海岸はきわめて複雑な海岸線をもち,南西から南海岸にかけては数千の島が散在する多島海となっている。西海岸は潮差が大きく,中部の京畿湾の8mを最高に北の竜岩浦で4.7m,南の群山で6.2mに及んでおり,この海域に流入する河川が運び込む土砂によって広い干潟地が発達している。
気候と植生
四季が明確な温帯に属するが,南北に約1000kmと長いため,緯度によって気候の差が激しい。年平均気温は南部13℃前後,中部11℃,北部山岳地帯は4℃ほどである。大陸の東端にあるため大陸性気候の影響を強く受けて気候の年較差が大きく,中部でも夏に30℃を超す日が30日以上,冬には-15℃に下がることも少なくない。降水量は中・南部が1200~1300mmなのに対し,北部は700~800mmと少ない。6~9月に2/3以上の降水がかたより,冬には非常に少ない。干害が農業にとっての最大の脅威であった朝鮮では,古くから雨によせる関心は高く,祈雨祭や測雨器の発達をみた。植生では,アカガシを主とする暖帯照葉樹林が南部の沿岸地帯に,また北部山岳地帯が亜寒帯森林となっているほか,大部分の地域はナラ,カシ,モミなどを主とする温帯落葉樹林である。しかし,太白山地を除く大部分の山地は李朝時代や植民地時代に行われた山林政策によって人手が入り,自然林から人工林に移行している。北部山地はカラマツ,モミなどの針葉樹林が繁茂し,朝鮮の山林資源の宝庫となっている。
海流
黄海は水深が浅く,優勢な海流の影響が弱いうえ,冬の水温が低く,よい漁場とはなっていない。日本海側は北上する対馬海流と南下するリマン海流が交錯する世界的な漁場となっている。ニシン,メンタイ(スケトウダラ),タラ,イカが代表的な魚種である。
地域区分
朝鮮半島はソウルから元山に至る楸可嶺地帯を境として北部と南部に分かれ,北部は狼林山脈を境として咸鏡道中心の東北部を関北とよび,平安道を中心とし黄海道を含めた西北部を関西とよぶ。京畿道,江原道,忠清道を中部地方とし,全羅道,慶尚道,済州島(現在は済州道をなす)を南部地方とする。また京畿・忠清両道をさして畿湖,江原道を関東,全羅道を湖南,慶尚道を嶺南とよぶ場合もある。李朝初期の15世紀から行われた咸鏡,平安,黄海,江原,京畿,忠清,慶尚,全羅の8道制は自然地理を加味したすぐれたものであったが,日本の植民地時代には,行政的に咸鏡,平安,忠清,慶尚,全羅の5道をそれぞれ南北2道に分けた13道制をしき,現在は南北の両国家において,9道ずつの行政区画を行っている。朝鮮の各地方に関しては8道の各項目を,また現在の行政区分に関しては〈大韓民国〉〈朝鮮民主主義人民共和国〉の項目を参照されたい。
執筆者:谷浦 孝雄
民族と文化の伝統
朝鮮半島における人類の活動は,約50万年前の旧石器時代から始まっている。近年,朝鮮半島全土から数段階に時期区分することのできる旧石器が多数発見され,前期旧石器から後期旧石器をへて中石器時代の設定すら可能な長期にわたる人類の祖先の存在が知られるようになった。
現在の朝鮮人の直接の祖先とみられる新石器時代人の出現は,前4000年ころとする説が有力である。旧石器時代の文化活動には,それほど明確な地域差はみられないが,新石器時代以後には朝鮮独自の文化がみられるとともに,他の地域で発生し,周辺の各地に波及した文化(〈大〉文化)を受容して,朝鮮文化の内容を豊富にしてきた。この時期の生産様式は,自然物採集を主としており,シベリアから伝わった櫛目文土器を使用していた。前15世紀ごろから間接的に中国の農耕文化を受け入れていたが,前7世紀以後には北方の騎馬民族から青銅器文化を受容し,前3世紀には中国の鉄器文化をもった衛氏朝鮮が建国した。このように,朝鮮民族は北方・西方の文化を吸収しながら,独自の文化を形成した。
朝鮮人
朝鮮人は,人種的にはモンゴル系の黄色人種で,形質的には日本人にもっともよく似ている。身長,頭形,顔形,血液型,指紋などでは,日本人と満州族とにもっとも関係が密で,中国人とはそれほど類似していない。北部の朝鮮人は満州族に,南部は日本人に似ているが,例外として,モンゴル帝国の占領下にあった済州島人の頭形は満州族に近く,平安南道・南北黄海道人の頭形はもっとも華北型に近い。ツングース族に属する満州族や東部シベリアの古アジア諸族などが,前40世紀ごろから朝鮮半島に移住し,これより前に南方から移住してきた人々と共存していたとも考えられている。
朝鮮人は南北各地の諸種族が混交したものであるが,種族による文化の相違はあまりみられず,時代を下るにしたがって同一民族として共通の文化圏をもつようになった。例えば前記の衛氏朝鮮以降は,北部には高句麗を中心とした高句麗文化圏が成立し,南部には三韓時代の韓族文化を基盤とした百済文化と新羅文化が栄えた。その後には,北方には高句麗文化を継承した渤海文化と南方には統一新羅の文化が栄えたが,高麗の成立とともに,これらの文化の融合をはかりながら,独自の朝鮮文化を完成させた。
二つの開国神話
朝鮮文化の完成した時期,その文化要素に〈大〉文化と地域文化との融合がはかられたことを示す好個の事例として,朝鮮の開国神話をあげることができる。朝鮮には檀君神話と箕子神話との二つの開国神話があるが,これらは高麗時代に成立したもので,前者は民間信仰を,後者は儒教を背景にしたものである。檀君神話は中国尭帝即位50年に,天神の子と熊の化身とのあいだに生まれた檀君が平壌城で建国するが(前2333年が檀君紀元),1500年後,箕子が朝鮮に封ぜられたので,山神になったという。この神話は北方の熊信仰,南方の聖地信仰などを基礎としたもので,はじめ平壌地方の固有信仰であったが,モンゴル侵略に抵抗した高麗農民が檀君を開国の始祖神として民族的な団結をはかった。朝鮮王朝(李朝)の国号採用に当たっても,箕子朝鮮と並んで檀君朝鮮の朝鮮が有力な根拠とされた。19世紀末の民族意識の高揚期に,檀君は再び開国神として信仰され,大倧教や檀君教という新宗教が成立して現在にいたっている。
箕子朝鮮は,《史記》などによれば,周の武王が殷の王族箕子を華北地方に封じ,朝鮮王としたとされる。前108年に漢の武帝が朝鮮に漢四郡をおいたことから,華北の朝鮮王箕子を朝鮮開国の始祖とする伝説が中国人のあいだに生まれた。高麗時代に儒教が発展すると,箕子を開国の始祖とする神話が高麗儒者のあいだで生まれ,その後,朝鮮の知識人に支持されたが,自国文化尊重の気運におされ,しだいに衰退した。このように西方や北方の勢力を結集したモンゴルの侵略とこれに対抗,あるいは追従するなかで,民族文化を形成していったことをうかがうことができるであろう。
→朝鮮神話
侵略に対処する山城
朝鮮はユーラシア大陸の東端にある半島で,大陸の諸民族の中では比較的民族間の戦争の少ないところである。しかし,日本のように民族間の戦争をほとんど意識しない社会とは異なり,日常生活の中でもこの点に留意してきた。その対策として,大陸諸民族の支配階層にみられるように,支配者間の連帯を強化してきた。これは漢の武帝の侵略以来,中国王朝に追随して自己の勢力を安定・拡張しようとするいわゆる事大主義である。
これに対して,地域住民の利益を擁護しようとする地方勢力(地方豪族だけでなく住民の勢力)もまた,原始社会時代より形成されてきた。侵略に対抗する地域住民の活動を端的に示すものに朝鮮の集落構造,都市計画としての居城と山城(さんじよう)との組合せがある。例えば高句麗は,《三国史記》によれば,西暦3年に王都を国内(中国吉林省集安)に移し,尉那巌城を築いたとあるが,この尉那巌城は典型的な朝鮮式山城で,平地にある王都国内城には王宮,官庁,王都民の住居などがあり,日常生活は国内城で営まれていた。しかし,高句麗は遼東・楽浪両郡をはじめ夫余国などと対立していたので,異民族の侵入にあたって,国王,軍隊のみならず王都民を避難させる場所として,王都の背後の山岳に尉那巌城を築いたのである。この山城は,244年の魏の侵略をはじめ,異民族の侵入に際してしばしば使用された。高句麗は強力な軍事力をもつ北方騎馬民族や中国王朝と境を接していたので,王都だけではなく各地に山城をつくって,住民の避難所とした。また,朝鮮南部にも集落を防衛する城郭だけでなく,住民の避難所としての山城が各地につくられた。このような山城は朝鮮独自の文化で,住民尊重の朝鮮文化・社会構成の特徴を示すものである。山城は,異民族の侵略が度重なる北方では城壁や城門に巨石を用いた巨大なものが多く,異民族侵略の少ない南方では,小型の山城を使用していた。しかし,14世紀以降,倭寇の侵略にあうと,南方の山城も強大になり,組織化された。豊臣秀吉の侵略時には,これに対抗するため100城以上の山城が築城され,義兵の根拠地にもなった。近代の抗日義兵闘争や現代の朝鮮戦争でも,これらの山城が使用されていることは,注目すべきであろう。
→山城(さんじょう)
言語と文字
原始時代の朝鮮には多くの系統を異にする種族と言語があったが,《魏志》東夷伝によれば,3世紀の朝鮮には濊(わい),貊(はく),韓,倭の4民族がおり,その後しだいに南部の韓族が勢力を得,新羅の統一によって朝鮮民族の形成基盤ができた。ただ,民族形成の過程や地形の複雑さから地域文化が強固に残存し,方言が発達した。言語構造は日本語ともっともよく似ており,アルタイ語系統とされている。音韻構造も原始時代までさかのぼると,日本語とかなり類似していたとみられる。
三国時代の金石文をみると,北魏を主とする中国北朝系の文字が5世紀前半までに高句麗に受容され,6世紀前半までに百済へ,6世紀後半までに新羅へ,それぞれ伝えられた。6世紀後半には新羅系統の文字が山陰,関東など日本各地に伝えられた。中国の文字文化が朝鮮に入るとき種々の文化変容が起こり,高句麗では省略文字,新羅では複合文字など異体文字が使用された。これらの異体字は政治的に重要な個所(王名,始祖名,官職名,官位名,貴族の名前等)に集中しており,政治的な自立を主張したものとみられる。また,文体も朝鮮語風に,主語・述語の順に記述することなどもみられるが,王朝側が文体を指定するなど,言語,文章の統一をはかる政策をとっていた。こうして朝鮮の文字文化は三国抗争期に始まり,地方勢力との結合をはかるために積極的に文字文化が利用された。これは王朝の権威を誇示するとともに,言語文化の統一により民族文化の高揚をはかることになった。のちの李朝建国後まもない15世紀の朝鮮は,朱子学の興隆による漢文全盛の時代であるが,同時に訓民正音(1446)によって朝鮮文字(ハングル),朝鮮文の創製された時代でもあり,言語,文学の民族化の時代でもあった。ハングルの創製は朝鮮文化史上きわめて大きな意義をもっている。
→朝鮮語 →ハングル
宗教の習合にみる固有性
朝鮮文化は,軍事的・政治的圧力を背景として北方,西方の異文化を受容しながら成長した。従来の考え方では,受容された〈大〉文化のみに注目し,地域文化を軽視する傾向があった。例えば統一新羅時代から高麗時代にかけては仏教が盛行し,李朝時代には儒教がこれに代わったとされている。しかし,これは支配階層の文化のみを見たもので,仏教受容の当初から儒教と仏教とは同時に受容され,両者相携えて発展しただけでなく,固有の信仰をも発展させたことをみのがしている。
三国時代の中国文化受容には,朝鮮文化の特色を示すものが少なくない。例えば,高句麗の小獣林王時代(371-384)には,仏教が初めて受容されただけでなく,大学をたて,儒教教育を始め,律令(成文法)を公布して,儒教的な政治形態をとった。このように,仏教の渡来が儒教文化の発展をうながし,儒・仏相携えて発展するのは百済の場合も同様であった。さらに,仏教文化の受容は固有の信仰をも発達させた。高句麗では625年に,唐で道教が盛んなのを知ってこれを取り入れている。このように,儒・仏・道三教を積極的に受容するだけでなく,在来の信仰もあわせて,新しい信仰を作り出すところに朝鮮の特色がみられる。近代の19世紀なかばに生まれた民衆宗教である東学が,西学(天主教,カトリック)を意識しながら儒・仏・道三教の結合を唱え,また朝鮮の民間信仰を土台にしている点などはその典型である。
貴族文化と庶民文化
貴族文化と庶民文化とは,その政治的・経済的基盤を異にすることから,前者が〈大〉文化を,後者が地域文化をそれぞれ基盤にしており,相違点が少なくない。反面,同一社会を形成するこの両文化には当然共通する所も少なくない。この間の事情を古代の貴族文化を通じて見てみたい。
そのひとつとして彫刻では,統一新羅時代に本尊や脇侍など諸仏にすぐれたものが多い。現在残っているものには石仏が多く,小型の金銅仏や末期の大型鉄仏がみられる。慶州市吐含山の石窟庵には,この時代の代表的な石仏が集まっており,本尊の釈迦如来座像は盛唐様式に,新羅独自の繊細華麗な手法を加味している。これをとりまく22の仏像は半肉彫りではあるが,いずれも端正な容姿で,そのうちのいくつかの像には遠く西域系の容貌をそなえたものがあり,新羅文化の広がりを示している。吐含山麓の仏国寺には,金銅仏の代表作といわれる毘盧舎那仏と阿弥陀仏の座像があり,安定感と迫力とがある。この時代には10~20cmの金製の小仏像が貴族の持仏として尊重され,数多く残っている。9世紀中ごろ以降の鉄仏には,宝林寺や到彼岸寺の毘盧遮那仏座像などがあり,やや生硬なところもあるが,庶民的な力強さもあり,高麗仏への発展を予想させる。
高麗時代の彫刻には庶民性の豊かなものが多く,論山の灌燭寺や林川の大烏寺の弥勒立像では庶民的な顔だちが見られ,安東郡河回の木製仮面などに見られるユーモラスな表現へとつながっていく。李朝時代になると彫刻が衰え,この種の地域文化としては,ソウル湖巌美術館所蔵の白磁俑をあげるに止まる。しかし,その伝統は18世紀以降の絵画に引き継がれ,金弘道の《群仙図》,申潤福の《風俗画帖》などに見られるだけでなく,染付の人物画や動物画には,地域文化のもつ力強さや諧謔性を示すものが少なくない。朝鮮文化は以上のような特質をもちながら,〈大〉文化と固有の地域文化とを巧みに融合させながら,独得の民族文化を作り上げてきたのである。
執筆者:井上 秀雄
生活文化と社会
朝鮮における固有の基層文化と外来文化の重層性は生活文化の側面からもうかがうことができる。
住居と人間関係
基本的な生活空間としての家々は,ほぼ例外なく塀をめぐらした独立的空間をなしている。建物自体への入口としての玄関に相当するものはなく,塀に設けられた大門が内と外との境界となっている。家屋は数十cmの高さに土壇を築いてその上に建てられ,その構造は地方や経済階層によってもちろん異なるが,基本的要素としては,台所(土間),それに続く内房(アンバンanbang),大庁(テチョンtaech'ǒng),大庁をはさんで内房の反対側に越房(コンノンバンkǒnnǒnbang)が配置される。建物の規模が大きくなればさまざまな部屋(房)が付加されるが,内房や越房などの居室部分の床はオンドル,大庁および物置き部屋などは板敷(マルmaru)である。台所に近い戸外にはチャンドクテchangdoktaeという壇があり,ここに調味料やキムチのかめが並んでいる。
大庁は居室ではないが,家の中心的な場所である。ここは天井をはらず,棰木や梁がむき出しになっているが,この梁は建築のときに上梁(サンニャンsangnyang)の儀式をしてすえる最も重要な梁であり,上梁した年月日のほか,家の繁栄を祈願する縁起の良いことば(しばしば竜や亀の文字を含む)が書かれている。大庁の一隅に米や麦を入れたかめを置いたり,あるいは梁の上に韓紙をたたんだものをはりつけたりしているが,これは家の守り神である成主(ソンジュsǒngju)をまつったものである。内房の壁につった棚の上には祖上壺(チョサンタンジchosang-tanji,世尊壺(セジョンタンジsejon-tanji),帝釈壺(チェソクオガリchesǒk-ogari)とも呼ぶ)がまつられている。やはり米や麦を入れた壺であり,祖先神と考えられているが,後述する儒教的祭祀にみられる個別的な祖先ではない。台所には竈神(かまどがみ)(チョワンchowang)がまつられる。全羅道や忠清道の一部では,これは水を入れた小鉢の形で竈の上の壁にまつられている。引越しのときに最初に移すのがチョワンであり,近所の人々がマッチやろうそくをもってあいさつに行くのは,火による浄(きよ)めの意味がある。チャンドクテのそばには宅地神である基主(トジュt'ǒju。穀物を入れた壺にワラをかぶせる)や財運の神のオプǒp(蛇と考えられる)がまつられる。成主,祖先,基主などが穀物を入れた壺(春秋に入れ替える)の形でまつられていることは,古い農耕豊穣神とのつながりを思わせるものであり,部落祭や巫俗(後述)とともに朝鮮の基層文化に属するものである。これら一連の家の神々は,主として家の主婦がまつるものである。
家の空間利用の中に,人間関係を律する基本的原則のいくつかをみることができる。その第一は男女の区別である。内房は主婦と幼い子供たちの居室であり,主人と子供たち以外の男性は入らないのが原則である。これに対して男主人の居室であり外来の客をもてなす部屋が舎廊房(サランバンsarangbang,別途にない場合には越房がこれに当たる)であり,ここには女性は入らない。男女の空間区分は,家屋の規模が大きくなるにつれてさらに強調され,建物自体が分けられるようになる。その場合は舎廊棟(男の空間)は大門(外部)に近い方に,内棟(女子供の空間)はその後方に配置される。このようにして家の中ですら男女を隔離し,特に家族以外の男女の接触を避けることを〈内外(naewoe)する〉という。〈女は自分の故郷の市の立つ日を知らないほど良い〉ということわざもある。
年齢による秩序もまた家の空間利用にあらわれている。幼少時には母親とともに内房で起居するが,6~7歳ごろから男児は父親の舎廊房に移り,青年期には越房などを利用する。もし舎廊棟に二つ以上部屋があれば,父親は大きい舎廊房を,結婚した息子は小さい舎廊房を居室とし,父の死後に大きい舎廊房に移る。社会関係においては相互の地位の上下関係を考慮することが必須であるが,年齢の長幼はその最も重要な基準の一つである。そのため初対面のときにはさまざまな方法で相手の年齢を確認しようとし,同年齢のときには生まれた月日まで尋ねてどちらが年長であるかを確かめる。ここまでゆくといささか冗談めいてくるが,生まれた順序そのものに重大な関心を寄せていることは明らかである。同年者(同甲tonggapという)は最も親しくなりうる者であり,年齢が開くほど礼儀作法に配慮しなければならず,くつろいでつきあうことができなくなる。年長者と同席しているときには気軽な冗談を言うことはできず,酒は横をむいて飲まなければならない。タバコにいたっては父親はもちろん,父親の世代の人の前では全く吸うことができない。友人としてつきあえる人の年齢差は7~8歳までであり,それ以上年齢が違う人々は互いに回避しあう傾向がある。そのために年中行事や通過儀礼などに伴う宴会の席も,年齢に応じて少なくとも三つくらいのグループに分かれることになる。
家と祖先祭祀
塀にかこまれた一つの屋敷に住む人々が,社会的単位としての〈家〉(チプchip)を構成する。家は同居同財にして家計を共にする集団である。一つの屋敷には台所と内房が一つしかない(例外的に済州島では,親子2世代が同居するときは台所を分ける)が,これは主婦が1人だけであることを意味する。主婦の座は姑から長男の嫁に引き継がれる。結婚は嫁入り婚の形をとり(ただし結婚式は妻方の家で行う),次男以下も結婚後しばらくは父母と同居するが,まもなく分家独立する。したがって家族は1世代1夫婦の直系家族の形をとる。財産相続は長男優遇で,家屋を含む財産の大部分は長男が相続し,次男以下には家の事情に応じて分財する。娘には分財しない。長男が後継ぎとなった家を〈大家〉(クンチプk'ǔn-chip),そこから分かれた家を〈小家〉(チャグンチプchagǔn-chip)と呼ぶ。
大小家関係が最も明らかに表れるのは,儒式にのっとって行われる祖先祭祀の面である。祖先祭祀には家祭と墓祭の2種類があり,家祭はさらに忌祭祀(キジェサkijesa)と茶礼(チャリェch'arye)に分かれる。忌祭祀は4世代以内の各祖先の命日に,また茶礼は忌祭祀の対象となるすべての祖先に対して正月や秋夕(陰暦8月15日。〈中秋節〉の項を参照)などの名節に行う。子孫はすべて祭祀に参加する義務があるが,特に家祭を主催する義務は父から長男に受け継がれる。したがって大家とは共通祖先のための家祭の行われる家である。大家,小家という相互の呼称の用いられる範囲は4世代前の祖先(高祖)を共有する範囲とだいたい重複するようである。また同高祖八寸間(〈寸ch'on〉は親等の意味)は,互いに喪に服する有服親の範囲である。5世代以上へだたった祖先のすべてに対する祭祀が墓祭(時享祭(シヒャンジェshihyangje))であり,毎年1回(ふつうは陰暦10月)行う。土葬のため墓は各祖先に1基(夫婦合葬の場合もある)つくられるが,そのひとつひとつをまわって祭祀をするには数日から10日以上もかかることがある。家祭が主としてそれぞれの家の責任において行われるのに対し,墓祭は当該祖先の子孫全員の総体的責任において行われる。祖先を共有する人々はさまざまな規模の〈門中〉(ムンジュンmunjung)という組織をつくっている。門中は,墓祭を行うための資金を確保し,また高名な祖先の遺した文物があればそれを保存するために,共有の財産(位土と呼ばれる田畑,墓地を置く山林,集会を開くための祭閣など)をもち,有司や門長などの役員をおいて事務を処理する。門中の始祖から代々その後継ぎとなってきた家(長男の系統)を宗家(チョンガchongga),その当主を宗孫(チョンソンchongson)と呼ぶが,これは門中の象徴的中心である。
本貫,族譜,門中
出自(同一の祖先の子孫であること)を示すのが姓と本貫である。朝鮮の姓は約260種類と限られているが,多くの姓はさらに系統によっていくつもの氏族に分かれている。この系統を示すのが本貫で,おのおのの氏族の最初の祖先の出身地名を本貫としていることが多い。たとえば金姓には約500の本貫があり,金海金氏とか安東金氏というように区別される。姓と本貫の同じ人(同姓同本)は互いに結婚することができない。出自は厳格な父系制をとっている。
同姓同本の人々の系譜関係を記録したものが族譜である。これは共通の始祖から現在の子孫に至るまでの20~30世代にわたる父系親族全員の記録を,縦の親子関係と横の世代関係に従って整然と記載したものであり,生存中の子孫だけでも数十万人から100万人を超すような族譜もある。
門中は族譜に示された系譜関係に従って,さまざまな世代レベルの祖先を中心に,その子孫たちが構成する組織である。したがって系譜上の遠い祖先を中心とする門中であれば全国各地に居住する多数の親族を結合する組織となりうるが,近い祖先を中心とする門中は同一氏族内での分派の存在を強調する結果となる。これに対し,系譜関係の遠近にかかわらず,同じ地域に住む氏族員で組織されているのが宗親会(チョンチンフェchongch'inhoe)あるいは花樹会(ホアスフェhwasuhoe)である。大都市でも地方の小さな町でも,〈○○(本貫)○(姓)氏○○郡宗親会〉という看板がいたるところで目につくのがそれである。門中と宗親会の二重の組織によって,各氏族は全国に広がる関係のネットワークを形成している。
→家[朝鮮]
儒教と固有文化
男女の区別,年齢の秩序,父系血縁の紐帯(ちゆうたい)は,朝鮮社会での人間関係を律する最も基本的な規範であり,李朝以来の正統的思想である儒教においても,〈男女有別〉〈長幼有序〉〈孝〉というように明示的倫理規範によって支持されてきたものである。これらはしばしば朝鮮の〈伝統的〉文化を代表するもののようにみられる。しかし高麗時代までは族外婚の規定はなかったようであり,また財産相続も子女均分制であった。同姓同本の結婚を厳禁する外婚制は李朝以後に明確になったものである。特に17世紀ごろを境として,財産相続から女子が排除されるようになる。また最も早く編纂された族譜は文化柳氏の永楽譜(1423刊)であるとされているが,父系親族のみを網羅した族譜が発達し一般化したのもほぼ17世紀以降のことである。門中組織の展開も同様である。すなわち厳格な父系出自に基づく氏族制度とは,けっして部族社会時代にまでさかのぼるような古い民族固有のものではない。他方,李朝が儒教を国是としたこと,特に孝が強調されて祖先祭祀が儒式に整備され,また同族敦睦の意識が形成されてきたことが,氏族制度の確立に大きく影響したことはもちろんであるが,中国の制度がそのままもちこまれたのではないことにも注意しよう。たとえば家のレベルでの大小家の区別や門中レベルでの宗孫の存在,つまり長男の系統を重視するのは,儒教思想の影響として説明できない朝鮮独自の現象であり,また祖先の中でも特に高位官職者や有名な学者の存在を強調したり,全国的規模の組織(門中や宗親会)をつくることなども,中国には見られないことである。これらの独自な展開の要因は,国家的レベルでもまた地方社会のレベルでも氏族集団が互いに地位を競いながら成立してきた李朝の政治社会的状況の中に求めるべきであろう。
→儒教[朝鮮]
基層文化を示す洞祭と巫俗
表面的には完全に儒教化されてしまったようにみえる祖先祭祀にも,例えば家祭のときには家の神である成主に供物をそなえること,秋夕茶礼に新穀をそなえること,埋葬や墓葬に際して山神祭を行うことなど,基層文化に属する要素があちこちに姿をのぞかせている。しかし儒教以前の信仰形態を最も明らかに伝えているのは洞祭(トンジェtongje)と巫俗である。
洞祭は地縁社会としてのムラ(マウルmaǔl)の共同祭儀である。祭りの行われる神域は,京畿道,忠清道では山神堂(サンシンダンsanshindang),江原道では城隍堂(ソナンダン),慶尚道,全羅道では堂山(タンサンtangsan),済州島では本郷堂(ポニャンダンponhyangdang),酺祭堂(ポジェダンp'ojedang)などとさまざまに呼ばれているが,樹齢の古い大木が神木・神体とされている。壮年で家内に喪,産,妊娠などの不浄のない男子が祭官,祝官に選ばれ,彼らは祭りの前の数日間は家の大門にしめ縄(〈禁縄〉クムジュルkǔmjul)をはって沐浴斎戒して身を浄める。祭日には真夜中に洞祭堂へ行って供物をそなえ,祝文をとなえる。このときに村人の一年の平安を祈って各戸の世帯主の生年月日を書いた紙を焼くこともある。この後祭官たちは供物の一部を食べる(飲福(ウンボクǔmbok))。祭官以外の人々は直接洞祭に参加せず,翌朝に飲福のみをする。洞祭の祭日は陰暦正月15日(上元)が最も多い。特定の祭官が供物をささげて香をたき,酒をそなえて祝文を読む儀式の形式は儒教的儀礼を模倣したものである。これに対して,数年に1度,職業巫を招いて別神祭(ピョルシンクッpyǒlshinkut)という神祭りをする地方もある。
家の神やムラの神の祭儀が宗教的職能者によらずに行われるのに対し,職業的宗教者のつかさどる巫俗がある。朝鮮の巫俗は東北シベリアのシャーマニズムの系統につらなるもので,古代においては国家宗教の地位にあったが,高麗時代以降は仏教,特に李朝の儒教によって抑圧され,その社会的地位はきわめて低下させられてきた。賽神(クッkut)の司祭である巫覡(ふげき)は,中部以北では万神(マンシンmanshin),全羅道では丹骨(タンゴルtangol),済州島では神房(シンバンshinbang)と呼び,一般的には巫堂(ムーダンmudang)と呼ぶ。ほとんどは女性であるが,済州島では男性も多い。賽神は主として夜間に行い,いくつもの祭次を追ってさまざまな神々を招じ,鉦,鼓,杖鼓などの伴奏にあわせて歌舞し神遊びをする。大規模な賽神には数日を要する。中部以北の万神は,巫病にかかった人が,そのときに憑(つ)いた神を守護神(身主モムチュmomchu)とし,有名な万神の下で修業して入巫する師弟継承の形をとり,賽神においては激しい歌舞を通じて憑依(ひようい)状態になって神おろしして神託をのべることで有名である。巫堂と信者との関係は,賽神の依頼を通じて結ばれる一回契約的なものでもありうるが,より永続的な関係としては,中部以北の場合,病弱な子どものすこやかな成長を願って子どもの姓名と生年月日を書いた命橋(ミョンタリmyǒngtari)という布を万神にそなえ,万神と神親子関係を設定する。命橋によって結ばれた神子たちが,個々の万神の信者の中核をなすことになる。命橋は明図(ミョンドmyǒngdo)という巫霊を象徴する鏡とともに万神の後継者に伝えられる。他方,全羅道の丹骨は,それぞれ場内(ジャンネjangnae)あるいはタンゴルパン(tangolp'an)という専管地域をもち,これは姑から嫁へと世襲される。丹骨や神房は憑依状態による神おろしはしない。洞祭の一形態としての別神祭は古代の共同体祭儀のなごりをとどめているが,今日の巫俗の主流は個人的契機によって随時に行われるものであり,その目的によって憂患賽神(病気治療),財数賽神(財運祈願),死霊祭の3種類がある。また賽神を依頼するのは主として女性である。これは儒教思想によって抑圧されながらも,そのカバーしない領域で,また儒教祭礼から排除された女性の間で,巫俗が役割を果たしてきたことを示している。
相互扶助組織としての契
社会生活のさまざまな領域で相互扶助組織として機能しているのが各種の契(キェkye)である。共通の目的をもつ人々が集まり,共同の基金を設け,それを利用して各人の共通目的を達成するという基本原則によって組織される契は,日本の頼母子講や無尽に相当するもの,婚礼や葬式の資金を調達し,また(特に葬式の)労働扶助を目的とするもの,あるいは友人間の親睦を促進するためのものなど多様なものがある。都市の女性たちの間での契には利殖のための私的金融機関の性格が強くあらわれている。いずれの場合にも対等な個人間の契約的組織であるという原則が貫かれているが,経済的利益を目的とする契の場合でも,契仲間とは親しく信頼できる友人であるという理念が強調される。農村における村落自治を担う組織としても契の形式が利用されることが多く,この場合には異なった父系出自によって分断される村人たちを統合する組織として機能する。しかし基本的に個人間の契約的組織という性格があるために,ムラ組織としての契が地縁的ムラと必ずしも一致しなくなるところに,朝鮮の村落社会構造の重要な特徴があるようである。
キリスト教
最後にキリスト教についてふれておこう。キリスト教は18世紀後半に李承薫らをはじめとする中国を訪れた使節たちによって天主教の名でカトリック系のキリスト教が紹介されたが,幾度かの厳しい弾圧をへて,本格的に布教されるようになったのは19世紀末にプロテスタントの各教派が多数の宣教師を直接派遣するようになってからである。旧韓末(大韓帝国期)から日本の植民地時代にかけて社会福祉や教育(病院や学校運営)にも力を入れながら行われた布教によって信者は急速に増え,都市だけではなく農村部にも多数の教会が建てられている。元来,平壌を中心に北朝鮮では植民地時代を通してもキリスト教が盛んであったが,朝鮮戦争後は教会の存在は知られていない。一方,韓国では朝鮮戦争を契機に南下したクリスチャンを含めて,教会の勢力は大きく拡大している。1983年の時点では韓国の人口の約4分の1,約1000万人が信者またはそれに準ずる人々であるという。
執筆者:嶋 陸奥彦
朝鮮史の特質--前近代史への視点
前近代の朝鮮史を王朝の興亡史としてみるとき,二つの特徴があることに気がつく。一つは,各王朝の存続期間がひじょうに長いことである。実態がなおよく分かっていない古朝鮮(檀君朝鮮,箕子朝鮮,衛氏朝鮮の総称)の時代はさておき,互いに覇を競った高句麗・百済・新羅の三国,三国を統一した新羅(統一新羅)に取って代わった王氏高麗,それをついだ李氏朝鮮(李朝)と,いずれも400年以上続いた王朝である。もう一つは,朝鮮で王朝の交代が行われたときが,いずれも東アジア史上の大変動期にあたっていることである。たとえば,統一新羅から高麗への転換期にあたる10世紀は,中国では唐・宋変革期に,日本では古代律令体制の解体期にあたっている。また高麗から李朝への転換期にあたる14世紀は,中国の元・明交代期,日本の南北朝内乱期にあたっているのである。
これら二つの特徴的な現象は,何を意味しているのだろうか。第2次大戦前の日本の朝鮮史研究者たちは,ここから二つの結論を引き出した。朝鮮史の停滞性と他律性という結論である。しかしこのような朝鮮史観は,今日では克服されつつある。上に述べたような王朝交代の,中国や日本に比べての特異性にも留意しながら,前近代朝鮮史をどのようにとらえるかを考えてみたい。
巨視的にみた社会変動
まず最初に,前近代の歴史の中で重要な位置を占め,しかもある程度詳細に社会の実態を知ることができる統一新羅時代,高麗時代,李朝時代の三つの時代をとりあげ,それぞれの社会の特徴を対比させて,社会変動の状況を巨視的にみてみよう。
(1)支配層の社会的基盤 支配層のあり方をみると,統一新羅時代の支配層は,骨品制という新羅独特の身分制の中の,上層部分によって占められていた。ところで骨品制は本来,新羅の王京人(慶州人)に限定された身分制であった。骨品制の適用範囲は三国統合の過程で若干拡大されるが,それにしても新羅の支配層はごく限られた貴族層から成っていたと考えられるのである。ところが新羅の支配力が衰えはじめる9世紀になると,各地で豪族が台頭してくる。そして彼らは,後三国(新羅,後百済,後高句麗)の内乱期を経る中でいっそうの成長をみせるが,後三国を再統一して高麗王朝を立てた王建も,このような地方豪族の一人であった。王建は各地の有力な豪族と積極的に姻戚関係を結び,彼らの力を借りながら,全国を再統一したのである。高麗初期の支配層を形成したのはこれらの豪族たちであり,統一新羅期の支配層の閉鎖性に比べると,はるかに広い基盤から成っていた。
高麗はやがて科挙制度を取り入れて,官僚制的な国家体制への傾斜を見せるが,科挙及第者であることが支配層になるための不可欠の条件となることはなく,豪族の系統をひく門閥貴族の力も依然として大きかった。ところが李朝時代になると事情が一変する。科挙制度が本格的に確立され,原則として科挙及第者でないと支配層に参加できないようになるのである。そしてこのような変革を推進する中核となったのが,朱子学的理念にもとづく国家体制の建設を目ざした新興の官僚層グループであった。
統一新羅期・高麗前期・李朝前期という三つの時代における以上のような支配層の変化は,支配層をより広い社会的基盤から求めようとする過程の産物であったということができる。このような支配層の社会的基盤の変化とともに,社会の大部分をしめる民衆のあり方も,三つの時代で大きく異なっている。それを端的に示すのが,親族・家族制度の変化である。
(2)親族・家族制度の変化 戦前の日本人研究者たちは,〈朝鮮に於ては永く固有の家族制を守株(しゆしゆ)し,李朝末期に至る迄,殆(ほとん)ど変革の見るべきものなくして,古代の家族制を其のままに踏襲し来れる〉(稲葉君山)として,これを停滞論の根拠の一つとしたのであるが,李朝時代の家族制度は,けっして古代の家族制そのままのものではない。新羅時代の家族制度の実態は,なおよく分かっていないが,一般民衆は姓を持っておらず,名も朝鮮固有のものであったと思われる(〈人名〉の項を参照)。近代以前の日本で庶民が姓を持っていなかったのと同様だったわけである。庶民が姓を持つようになるのは高麗になってからのことで,これは民衆を姓氏集団として把握しようとした高麗の支配政策と関連したものである。
このように朝鮮では高麗時代になって,庶民も中国式の姓(漢字1字,まれに2字)と名を持つようになったのであるが,この時代には同じ姓氏集団の中での結婚も広く行われていた。ところが李朝になって,朱子学が一般民衆にまで浸透するにつれて,同族(本貫を同じくする同姓集団)内の結婚が行われなくなり,このような親族・家族制度が近代まで続くことになったのである。したがって近代になって日本人に知られるようになった,日本とはひじょうに異なる朝鮮の親族・家族制度は歴史とともに古いものではなく,国家の政策や社会のあり方に対応して変遷をたどってきた,すぐれて歴史的な産物であった。
(3)独特の郡県制 支配層のあり方と,民衆の親族・家族制度のあり方とを結びつけるパイプの一つである地方行政制度も,時代によって大きく異なっている。前近代の地方行政制度でもっとも興味深いのは,高麗時代の郡県制である。この時代には,次のような独特の郡県制が行われていた。すなわち〈A郡に属するx県〉という場合,中国ではA郡の地域内にx県が存在しており,A郡とはxおよびx以外のx′,x″等のいくつかの県から成っている地域を指した(ちょうど現在の日本の県と郡とを逆にした形)のであるが,高麗の郡県制は,これとはまったく異なるのである。高麗で〈A郡に属するx県〉という場合,(イ)A郡とx県は別の地域(多くは隣接)であり,A郡の中にx県があるのではないこと,(ロ)〈属する〉とは,x県がA郡の支配を受けるという意味であることの2点に,高麗の郡県制の特異性があらわれている。この場合,中央から官僚が派遣されるのはA郡だけであり,x県には派遣されない。したがって中央からみれば,x県にはA郡を通じての間接的な支配しか及んでいないのである。
このような独特の郡県制が成立したのは,先に見た統一新羅から高麗にかけての支配層の変動と大きくかかわっていた。初期高麗は豪族連合政権的な性格が強かったが,A郡のような地域(これを主邑(しゆゆう)と呼ぶ)はたいてい王建に協力して統一事業に功績のあった豪族の出身地であり,x県のような地域(属邑)は,逆に王建に反逆したような豪族の根拠地であった。そのために属邑は主邑の支配を受けたのであり,この支配に国家は直接関与しなかったのである。
高麗後期になると郡県制は変質しはじめ,李朝に入ってからは,原則としてすべての郡や県に中央から官僚が派遣されるようになるが,重要なのは,同じ郡県制といっても,時代によりひじょうに異なっていることを理解することである。
戦前の日本人研究者のように,実証的な裏づけもなく家族制度の古代以来の不変性を主張したり,史料に〈郡県制〉とあれば文字の同一性からだけでそれを中国のものと同一視したりして,それによって朝鮮史の停滞性を主張するような見方は,研究の進展によってその根拠を失ったといってよいであろう。
時代区分論
前近代の社会変動のほんの一端を上でみたわけであるが,それではこのような社会のあり方の違いをどのように位置付ければよいのであろうか。また違いを生み出した力を,どこに求めたらよいのだろうか。こうした問題を考えるために,前近代の時代区分についての研究状況を概観しておこう。
朝鮮前近代史を世界史の発展段階の中に位置付ける試みを最初に行ったのは,日本の経済学者福田徳三であった。ドイツの歴史学派経済学を学んだ福田は,自足経済(村落経済),都市経済(領域経済),国民経済という世界史の三段階説を前提として,朝鮮は李朝末期にいたるまで,自足経済の段階にとどまっていたとしたのである。そしてそう判断しうる根拠として福田は,第二段階の都市経済を生み出す封建制が,朝鮮の歴史に欠如していたことをあげた。このような福田の封建制欠如論と停滞論的理解は,日露戦争期にあらわれたものであり,日本による朝鮮の植民地化の動きを合理化する役割を果たした。
福田的なとらえ方に対する批判は1920-30年代になって,民族解放運動の進展を背景に朝鮮人研究者の手によって行われはじめた。植民地期の朝鮮人自身による朝鮮史研究を,現在の韓国の研究者たちは社会経済史学,民族史学,実証史学の三つのグループに分けているが,独自の体系的な朝鮮史把握を示して,日本人研究者の朝鮮史像に批判を加えたのは,前二者であった。社会経済史学の立場,これは史的唯物論にもとづく歴史研究のことであるが,この立場を代表する研究者は白南雲(福田徳三の門下)であった。彼はマルクス主義的な発展段階論を朝鮮の歴史にも適用できると考えた。そして三国以前を氏族共産制社会,三国期から統一新羅期までを奴隷制社会,高麗以降を中央集権的なアジア的封建制社会ととらえる時代区分を提唱し,福田らの封建制欠如論を批判した。
白のような社会構成体的な基準にもとづく時代区分とはまったく異なる時代区分の考え方を提示したのは,民族史学の立場に立つ人たちであり,その代表的な研究者が申采浩(しんさいこう)であった。彼は日本の植民地支配を打ち破る力を民族独自の精神に求め,それを歴史の中に見いだそうとして研究を進めた。そして前近代史を,民族精神と中国の文化に倣おうとする事大精神との闘争の歴史ととらえ,12世紀の妙清(みようせい)の乱により事大精神が民族精神を圧倒するに至るとして,この乱を前近代史上の最大の事件と位置付ける独自の時代区分を主張したのである。
解放以後の朝鮮人研究者による時代区分論も,基本的には上の二つの立場を受け継いだ立場で行われている。朝鮮民主主義人民共和国では,古朝鮮を古代奴隷制社会,三国以降を中世封建制社会とする時代区分が今日の定説とされ,基本的には世界史的な社会構成体の各発展段階を朝鮮の歴史に適用する考え方が支配的である。しかし同時に,たとえば,高句麗の遺民たちが建国したとされる渤海を朝鮮史の中に含めるべきだとして,朝鮮史上の最初の民族統一国家を統一(統合)新羅にではなく,高麗に求める考え方などには,民族史学的な方法の影響がうかがえる。
一方大韓民国では,世界史的な各発展段階を朝鮮史に適用しようとする立場,奴隷制・封建制という概念は西欧基準のものであるからそれに代わる別の発展段階論を考えるべきであるとする立場など,さまざまな立場からの時代区分論が百家争鳴的に主張されている。その中でもっとも注目されるのは,民衆史の視点からの時代区分論の提唱である。この考え方は,現在の南北分断体制を克服する主体を民衆に求める立場から,民衆の成長過程として歴史をとらえ直そうとするものである。そこには民族史学の方法を継承,発展させた側面が顕著であるが,このような民衆史的,民族史的な立場からの時代区分論と,マルクス主義的な時代区分論との総合化の試みが,今後の朝鮮史学界における時代区分論の最大の課題であろう。
民衆史としてみた前近代史
しかし民衆史の視点から歴史,特に前近代史をとらえ直すことは,それほど簡単なことではない。朝鮮のように,古い時代から周辺の他民族の侵略をいくたびもこうむってきたり,近代の植民地支配の下で歴史研究の自由が抑圧されてきた歴史を持つ民族の場合には,とりわけそうである。そして現在においては朝鮮と同様に,〈歴史を奪われてきた〉民族の方が多いのであるから,そのような意味でも,民衆史の立場に立った朝鮮前近代史の再構成の試みは注目されなければならない。
民衆史において重要なことは,民衆の日々の労働と生活の歴史を明らかにすることである。たとえば農業の歴史などは,民衆史の重要な一部分をなす。朝鮮農業の歴史はまだよくわかっていない所が多いが,先に見た三つの時代における農業のあり方は,ひじょうに異なっている。統一新羅期の農業はまだきわめて粗放的なもので,牛の利用度や耕地の安定性も低かった。ところが高麗を経て李朝期に入ると,水田における稲の連作や,畑における二毛作が一般に行われるようになる。しかも雨の少ない気候条件を克服するために,稲の生育初期を畑の状態で栽培するという,中国や日本には見られない独特の稲作法(乾田直播法)も,この時代になると確立されてくる。このような農業の発展は,中国の先進的な農業に学びながらもそれを朝鮮の自然条件に見合ったものにするための,農民たちのたゆみない努力の積み重ねの結果であった。
先に見た三つの時代における支配層の違いや,地方統治体制,家族制度の変動なども,究極的には,民衆の日々の労働と生活における発展にもとづいているものと思われる。民衆史の視点から前近代史を再構成するということは,このように民衆の労働と生活における発展が,社会体制全般の変動とどのように結び付いているのかを,具体的に明らかにすることである。現在の朝鮮史研究では,韓国を中心として民衆史への着実な歩みが進められている。民衆史の視点から新しい朝鮮史像が示されるならば,それは〈歴史を奪われてきた〉地域の歴史研究にも大きな示唆を与えることになるであろう。
東アジア史上の朝鮮
朝鮮前近代史をとらえるうえでもう一つの重要な問題は,その東アジア世界との関わりである。農業や高麗の郡県制の例に見られるように,朝鮮では,中国の制度や文化を受け入れながらもそれらが中国の単なる模倣に終わったわけではけっしてない。仏教や儒教,科挙制度なども同様である。今日でも日本人の中には,朝鮮文化を中国文化の亜流にすぎないと考えている人が多いが,それは明らかに誤りである。
中国との関係の問題を,統一新羅から高麗への移行期を例にあげて考えてみよう。統一新羅末期に台頭してきた豪族の中には,日本史でも有名な張保皋(ほこう)(弓福)のように,中国や日本との貿易を成長の足がかりとした者が含まれていた。高麗を創建した王建自身も,海上貿易勢力と密接な関係を持っていた。彼らの視野は国際的であり,唐の滅亡という国際情勢を利用しながら,唐と深く結び付いていた新羅の支配体制を打ち破り,新しい社会を志向した。そして高麗王朝は,後三国の内乱期を通じて示された豪族たちのエネルギー,さらにはその背後にある民衆のエネルギーを吸収すべく唐やのちには宋の制度に学びながら独特の支配体制をうち立てたのであった。あの高麗独特の郡県制は,こうした過程の産物であったといえよう。
この移行期にみられるように,朝鮮においては,旧体制を倒して新しい社会体制を作るためには,中国や北方との関係をも視野に入れなければならない状況がつねにあった。そして新しい社会の支配勢力は,中国の先進的な制度や思想に学びながらも,それに独自の内容をもりこむことにより,強固な支配体制をつくろうとしてきたのである。最初に指摘した前近代史の二つの特徴,すなわち(1)一つの王朝が長く続き,王朝の交代が単なる政権移動に終わるのではなく,広範な社会変動をも伴っていること,(2)その変動期が東アジア史上の変革期とも一致することがなぜ生じたのかは,以上のように考えれば理解できよう。そしてこの二つの特徴が,朝鮮前近代史の停滞性と他律性をけっして意味せず,民衆の成長を基本的な要因としながら,いくつかの段階的な発展をとげてきた歴史であったことも理解されよう。そしてある意味では,朝鮮前近代史の展開の中にこそ,東アジア世界の変動がもっともよく現れているといってよいのかも知れないし,こうした特徴は今日の南北統一問題が東アジア世界に与えているインパクトの強さにまでつながっているのかも知れない。
ひるがえって日本の前近代史をみるとき,朝鮮との大きな違いに気づかされる。たとえば,10世紀に朝鮮で統一新羅から高麗への移行が行われたとき,日本では国際的な変動に連動した政治的・社会的変革が行われなかった。むしろ同じ時期,日本は遣唐使の廃止など鎖国的な体制を強めていくのである。そしてこの鎖国体制は,国風文化の発達を生み出す一方で,日本前近代史の大きな特徴の一つである古代から中世への移行の緩慢さ,なしくずし性(その象徴が古代天皇制の存続)を生み出したのではないだろうか。中国という巨大な文明に隣接し合っている日本と朝鮮の位置を考えるならば,日本前近代史の特徴は,何よりも朝鮮との比較を通じてこそもっとも明らかになるはずである。この点にこそ,日本人が朝鮮前近代史を学ぶ最大の意味があるといえよう。
執筆者:宮嶋 博史
日朝交渉史
ここでは近代に至るまでの日朝交渉史を通観するが,〈加羅〉,〈高句麗〉,〈百済〉,〈新羅〉,〈高麗〉,〈李朝〉などの項目中の日朝交渉に関する記述を併せて参照されたい。
原始,古代
朝鮮半島と日本列島との間では,古くから人々の往来があった。九州や沖縄で発見される縄文前期の土器には,朝鮮で出土する櫛目文土器と共通するものがあり,そのころすでに日朝間に交流のあったことがわかる。また,稲作,青銅器(銅剣,銅矛,銅鐸など)や鉄器を伴う弥生文化は,主として朝鮮半島南部からの集団的な渡来人(帰化人)によってもたらされたと考えられている。その後も2世紀後半には,進んだ鉄工技術と太陽祭祀をもつ朝鮮人集団が断続的に日本に渡来し,3世紀の大和政権は彼らに媒介されて朝鮮南部(辰韓,弁韓など)産出の鉄を確保し,鉄工技術を独占して勢力を拡大していった。そして4世紀後半,大和政権は百済と国交を結び,このとき百済から七支刀が伝来した。また広開土王碑文の倭と高句麗の戦闘記事が示すように,朝鮮南部からの鉄供給ルートの安全維持や百済からの要請に基づいて,朝鮮南部で一時的に軍事行動を展開した。ついで大和政権は,5世紀前半にも百済の対高句麗政策に加担して朝鮮南部に軍事力を投入,さらに5世紀後半には,百済再建への支援と引き替えに,一時,任那(みまな)地方(加羅)に勢力をのばした。しかし,6世紀前半には再建された百済が任那地方に勢力を拡大し,大和朝廷は倭臣らの政治集団を安羅に常駐させることになった。これが《日本書紀》に記されている〈任那日本府〉の実体であったとみられるが,近年,大和朝廷による任那の植民地支配を否定する説も多い。
562年以降は,任那地方を含む加羅諸国が新羅の支配下におかれ,それに伴い大和朝廷は朝鮮半島からの後退を余儀なくされた。一方,以上のような状況の中で,5世紀中ごろから農民を中心とする秦氏集団や,手工業技術者を中心とする漢氏(あやうじ)集団など,大量の朝鮮人が朝鮮南部から西日本各地に移住して,アワ,麦,豆を中心とする朝鮮式畑作技術や,硬質の須恵器の生産技術をもたらし,日本における鉄の国産化も可能にしていった。そして,渡来朝鮮人の中の有力者は,6~7世紀の日本国家の中で一定の政治的地位を世襲する有力豪族となった。また513-554年には,高句麗との対立を深めていた百済から,大和朝廷を味方に引き入れるための外交の一環として諸博士が派遣され,日本にはじめて仏教や儒教,漢字や医学,薬学,易学,暦学などを伝えたが,彼らは日本の古代国家や飛鳥文化の形成に大きな役割を果たした。しかし,隋との厳しい対決を強いられていた高句麗からも,僧慧慈(えじ)が飛鳥寺に派遣されて聖徳太子の師となっており,曇徴も来日し,また新羅も対高句麗・百済戦略上,大和朝廷との接触を強め,7世紀前半にかけてさかんに日本へ使節を派遣し,7世紀前半の日本からの渡唐留学生は多くが新羅船に依存するなど,高句麗,新羅の影響もけっして小さくはなかった。
ついで660年代,新羅・唐連合軍によって百済,高句麗があいついで滅ぼされ,大和朝廷は百済滅亡直後,朝鮮に救援軍を送ったが,敗退した(白村江の戦)。こうした中で,滅亡した百済・高句麗の土地から難をのがれて多くの朝鮮人が日本に移住してきた。関東に勢力をもった高麗王若光もそのときに渡来したものと考えられている。一方,白村江の戦以後,新羅と大和朝廷との外交は,一時途絶したが,新羅は唐とのきびしい対決の中で,日本との対立の緩和につとめ,形式上は日本を〈宗主国〉,新羅を〈朝貢国〉とする形で使節を派遣した。これ以後8世紀初めまで,両国の間ではひんぱんに使節が往来するが(遣新羅使),その間は日本の遣唐使が中断されていたときであり,日本の律令国家の完成にとって新羅は重要な役割を果たした。しかしやがて,対唐関係を改善した新羅が日本に対等外交を要求しはじめると,大和朝廷は〈宗主国〉の地位に固執して新羅との対立を深め,779年には,ついに新羅との外交関係を断絶した。また824年以降,大和朝廷は朝鮮からの渡来民をいっさい禁止し,ますます孤立主義,排外主義を強めていった。しかし他方,779年以降も,日朝間では張保皋の活躍に示されるように,民間人による交易はさかんに行われ,数多くの新羅商船が来日した。そしてこのような関係は中世にも引き継がれていく。
中世
高麗は920年日本に国交を求め,また1019年の刀伊(とい)の入寇に際して日本人捕虜100余人を送り返すが,日本の朝廷は偏狭な国際意識にとらわれて,あくまでも高麗を朝貢国として扱おうとし,国交に応じなかった。しかし,国交未成立にもかかわらず,高麗商人はさかんに日本との間を往来し,日本商人も積極的に高麗との貿易をすすめた。朝廷の閉鎖的姿勢にもかかわらず,平氏政権,鎌倉幕府はともに積極的な開国政策をとり,高麗との貿易を重視し,交易を続けた。しかしやがて,モンゴルの高麗侵略(1231-57)によって日本と高麗の交易は困難となった。また,高麗は元の日本遠征(モンゴル襲来)に動員されるが,長期にわたる高麗の対モンゴル抗戦や,その後の三別抄軍の反乱は,モンゴル(元)の日本遠征をおくらせる役割を果たした。また,疲弊した高麗はさまざまな口実を設けて日本遠征の回避につとめるが,最終的には兵士,軍船,食糧等の分担を強制され,2度にわたる日本遠征に参加させられ,大きな被害をうけた。
一方,モンゴル襲来(1274-81)のあと,日本と高麗の間は断絶状態となり,それに伴って対高麗貿易への依存度の大きかった九州・瀬戸内海沿岸の中小領主層や零細農漁民による朝鮮半島での海賊行為(倭寇(わこう))が増大し,高麗各地に大きな被害を与えた。それは1350年ころから激しさを増し,1370~80年代にピークに達した。高麗政府および李朝(李氏朝鮮)政府は,倭寇の討伐と並行して,室町幕府や西日本の大名に倭寇とりしまりを求め,その結果,1404年李朝と室町幕府の間に国交が樹立されて両国の善隣外交が発足し,経済・文化面の交流がさかんとなった。貿易面では,1443年に癸亥(きがい)約条が結ばれ,15~16世紀の約150年間,多いときには年間200隻もの貿易船が日朝間を往来した。そこでは日本の銅と朝鮮の綿布を中心に,多くの品物が交易され,両国の経済に大きな影響を与えた。また,大蔵経や仏像,仏画,鐘なども大量に日本にもたらされ,水墨画の交流が行われ,高麗茶碗等が伝来されるなど,文化交流もさかんであった。こうした日朝関係は当時の日本にとって,日明関係よりもはるかに重要な意義と緊密さをもっていた。
近世
室町期の平和的,友好的な日朝関係も,室町時代末期の後期倭寇の発生や,とりわけその後の豊臣秀吉の朝鮮侵略(文禄・慶長の役。朝鮮では壬辰・丁酉倭乱という)によって完全に断ち切られた。秀吉の侵略では前後2回,あわせて約30万人の軍隊が朝鮮半島をふみにじり,朝鮮に莫大な被害を与えた。日本軍は学者や陶工,多くの農民や婦女子を日本に連行し,大量の朝鮮本や銅活字を奪った。しかし,李舜臣の率いる朝鮮海軍や各地で立ち上がった義兵の戦いによって日本軍は敗北した。日本の農漁民も,この戦争に人夫や水夫として動員されたほか,軍糧などの負担を強いられた。結局,この侵略戦争は豊臣政権の墓穴を掘り,その崩壊を早めた。その後,江戸幕府は朝鮮との国交回復につとめ,1607年朝鮮と復交し,1609年には日朝通商条約(己酉約条)を結んだ。そして1624年までに3回の回答使兼刷還使,1636-1811年に9回の朝鮮通信使(300~500名の使節団一行)が来日した。鎖国下の日本にとって,朝鮮は,琉球以外には唯一の正式な国交締結国であり,徳川将軍の国際的地位を日本全国に示す絶好の機会として,幕府に重視された。また,使節団一行は幕府だけでなく,途中の各大名によっても盛大に迎えられ,それは同時に両国の文化交流ともなった。他方,この間江戸時代の日本では,壬辰倭乱の際に連行してきた姜沆(きようこう)ら朝鮮人学者や奪ってきた朝鮮本が,日本の朱子学の確立に大きな役割を果たした。また,奪ってきた金属活字によって日本の印刷術が大きく発展し,連行されてきた朝鮮人陶工の手によって日本で初めて磁器生産が行われた。
江戸時代は,以上のように,日朝間の平和的・友好的関係が長期にわたって維持され,そのもとで政治,経済,文化の交流がすすめられた時期であったが,しかしながら,そのような中で,古代以来の朝鮮蔑視観(とりわけ朝鮮を日本の〈属国〉視する考え)が,17世紀ころから徐々に台頭しはじめ,さらに18世紀後半以降,幕末に至ると日本に対する欧米の圧力が強まる中で,日本も隣国朝鮮を侵略して欧米に伍していこうとする主張(林子平,佐藤信淵,橋本左内,吉田松陰など)が強まってきた。1811年から明治維新までの間,日本も朝鮮も国内・国際情勢が緊迫し,日朝間の使節の往来は中断したままであったが,しかし両国の国交は断絶していたわけでなく,貿易は対馬を通して継続されていた。また,幕末以来,朝鮮との連帯によって欧米の侵略に対抗すべきだという意見(横井小楠や勝海舟など)もないわけではなかった。しかし,倒幕派,佐幕派を問わず,〈征韓論〉的主張が為政者の中で強く,それは近代日本の〈征韓論〉へと連続していくのである。そして,明治以降の日本では,前近代にみられる平和的,友好的な日朝関係や日本が朝鮮から受けた恩恵は無視されて,伝説にすぎない〈神功皇后の三韓征伐〉や,あからさまな侵略である倭寇とか,豊臣秀吉の対朝鮮戦争が日本の海外雄飛の事例として宣伝され,また,〈任那日本府〉などが,大和朝廷による南朝鮮植民地支配の疑う余地のない歴史的事実とされ,朝鮮を劣等視する蔑視観が醸成されることになった。朝鮮の植民地化(日韓併合)は,古代の〈偉業〉の復活であり,さらに原始・古代の日朝文化の共通性も〈日鮮同祖〉を示すもの(日鮮同祖論),日韓併合は分家が本家に戻るようなものとされるなど,ゆがめられた前近代の日朝関係史像は日本の朝鮮侵略,植民地支配に最大限に利用されたのである。
→日朝貿易
執筆者:矢沢 康祐
日本の侵略と植民地支配
自主的近代国家をめざす朝鮮社会の内在的発展の歩みは,開国前からすでに始動していた。ことに壬戌(じんじゆつ)民乱(1862)の後に登場した大院君政権(1863-73)は伝統的社会構造の変質に即応して統治基盤を大きく変えようとする過渡期的特徴を示していたといってよい。
外圧への対応
外圧の中での近代化という同じ課題において,客観条件の差ゆえにわずかに先行することとなった日本の,内的な弱さを外への侵略でカバーしようとする路線が,朝鮮社会の発展を大きく阻害,歪曲することとなった。欧米諸国は朝鮮の開国を求める圧力を1860年代に急速に強めたが(洋擾),大院君の強固な鎖国政策に直面して日本が突破口を開くのを期待する姿勢をとった。これを背景として明治政府は閔(びん)氏政権(閔妃)への交代による対外政策の軟化を利用しつつ,江華島事件を契機として朝鮮の近代世界への開国を意味する日朝修好条規を結ばせることとなった(1876)。この条約は幕末日本が強要されたのと同質ないしそれ以上の不平等条約であった。これに依拠して日本は,同質の路線を追求する清国とともに,原始的蓄積段階的な不平等貿易を推進し,またその商権を確保するための政治・軍事的介入を強行した。かくして朝鮮をめぐる日清間の対立が激化し,日清戦争(1894)にいたる。こうした危機的状況に対応せんとする自主的政治思想の潮流として,伝統的価値観に立つ両班(ヤンバン)たちの衛正斥邪(えいせいせきじや)思想,上からの近代国家への変革を構想する開化派の思想,そして民衆の変革意識の媒体としての東学思想の三者がある。いずれも1860年代に芽生え,開国後に大きく展開して,相互にからみあいながら朝鮮近代史の主体的側面を織りなしていった。しかし,金玉均ら開化派が政権奪取をめざした甲申政変(1884)は内外の困難を克服しえずに挫折を強いられた。一方,民衆の反封建・反侵略変革運動は,壬午の軍人反乱(壬午軍乱,1882)を先駆として,甲午農民戦争(1894)に大きく花開いていく。甲午農民戦争こそ朝鮮社会の近代への移行の決定的転換点となる可能性をはらんでいたのだが,日本の侵略の意図に立つ軍事力の行使がこの可能性を破壊してしまったのである。ただし,日本軍占領下で,開化派系の政治家たちが,農民軍に対応しながらかねての構想にそって遂行した甲午改革は,旧社会を支えてきた身分制度や租税制度を解体して,ブルジョア的発展に道を開く役割を果たした。だが,まだ幼い朝鮮の民族ブルジョアジーは,閔妃虐殺事件(1895)に代表されるような日本とロシアの強引な政治介入を排除しきれぬ王朝権力のもとで,国家の保護なしに外来商品との不利な競争を強いられ,しだいに地主的発展の方向へ追いこまれていくことになる。
こうした甲午以後の〈半植民地〉的局面のもとで,民衆運動の陣型は実力養成・国権回復(阻止された自主的近代国家としての一国的発展の道の奪回)を目標に立て直されていく。開化派の流れをくむ人々は1896年に在野の運動体として独立協会を組織し,民主主義的理念をふまえた大衆運動・民衆啓蒙運動に取り組むようになっていくが,その一方,抗日の実力闘争の面では衛正斥邪派の儒者たちが義兵闘争の口火を切った。日英同盟を背景に帝国主義世界体制の一角を占めんとする日本は,こうした状況にある朝鮮の支配をめぐって,同型の後進帝国主義国家である帝政ロシアと対立し,ついに日露戦争を引き起こすにいたった。そして,戦争の結果として列強が黙認するようになった状況を背景に,戦後の朝鮮で傍若無人に行動し,1905年末に実質的植民地化を含意する日韓保護条約(第2次日韓協約)を強要して,1906年初には〈韓国統監府〉を開設,さらに東洋拓殖株式会社の設立を急いだ。こうした国家の存亡の危機に際して朝鮮民衆は義兵闘争と国権回復をめざす愛国啓蒙運動に総力をあげて立ち上がった。特に1907年の第3次日韓協約強要,韓国軍隊解散(日本軍が直接的に民衆抗争を弾圧)以後は,義兵闘争においても,平民や旧韓国軍将兵が主流を占めるようになり,抗日闘争はしだいにブルジョア民族主義の理念のもとに統合されていく。かくして全土で日本軍と朝鮮民衆の悽惨な戦闘が繰り返されたすえ,1910年に形式的にも日本が直接統治する〈日韓併合〉が強行されたのである。
植民地化と朝鮮社会の変容
日本は,謀略でつくり出した一進会を利用して,〈併合〉を朝鮮民衆が望んでいるかのように装わせようとしたが,事実は,民衆の強い不同意の意志を,軍事力の優位によってかろうじて表面的におさえこんだ形にすぎなかった。帝国主義世界体制の中での,相対的に弱体な日本帝国主義と相対的に強力な朝鮮民族との支配・被支配の関係への分解は,日本の植民地統治の無謀な強圧性をきわだたせた。実際,植民地統治の初期10年間を特徴づける朝鮮総督府の〈武断政治〉(〈憲兵政治〉ともいう)は,宗教を除くいっさいの朝鮮人の自主的な団体,言論機関を認めず,占領軍政をそのまま延長したような体制であった。また,永久支配の願望(民衆の独立意識への恐れ)に根ざす〈併合〉当初からの〈同化主義〉の統治政策(〈自治〉すらの否定)は,植民地下の民衆生活をいっそう陰うつなものにした。1910年代の総督府の経済政策は〈朝鮮会社令〉と〈朝鮮土地調査事業〉に代表され,日本中心の経済循環に組み込む植民地経済への改編の基盤構築を意味するものであった。前者は〈併合〉前からの貨幣整理・財政整理事業(朝鮮貨幣整理事業)と連動して民族資本の活動を強権的に解体ないし改編し,朝鮮を日本資本主義のための商品市場化せんとするものであった。後者は,農民の土地所有権を確定することによってその分解を促し,同時に旧王室領有地を国有化してそれを払い下げ,日本人大地主の農場を創出することをねらいとしていた。総督府のこのような政策体系のもとで,人口の多数を占めていた小農民は全般的に没落への道に引き入れられた。こうした状況の下で民衆の独立思想が維持されむしろ強められていったのは必然であった。義兵や愛国啓蒙運動家たちは満州(中国東北),シベリアに根拠地を設けて長期抗戦の体勢をとった。国内の強圧体制下でも,志を曲げぬ人々の横の連係がひそかに保たれていた。
独立運動の展開
国権回復闘争の理念的枠組は,〈併合〉前から受け継がれた一国的発展の道の奪回をめざすブルジョア民族主義であった。この持続する志,蓄積された力量が,第1次大戦後の有利な国際条件に際会して一挙に噴出したのが,1919年の三・一独立運動である。全国津々浦々で民衆のデモ,蜂起が約1年間持続し,民族運動史上の輝かしいピークを形づくった。亡命政権としての大韓民国臨時政府もこの抗争のるつぼの中から生まれたものである。日本帝国主義も,一方で血なまぐさい鎮圧を遂行しつつ,一方では収拾策として〈文化政治〉への移行を表明せざるをえなかった。それは結局,事後の弾圧より事前に抗争の芽をつむ方策の講究,分割統治策の適用にすぎず,統治の暴力的性格の根本的変化はなかったが,自主的な社会活動や言論機関をある程度容認する譲歩を含まざるをえなかった。
この間,経済的には,第1次大戦期に急速に確立された日本独占資本の要求に即して,資本輸出による本格的な植民地経済圏の形成策が推進された。20年代のそれは安価な米を大量に日本に搬出するための〈朝鮮産米増殖計画〉を軸としており,資本輸出も主に農業部門に向けられた。そのことは植民地的商品経済下の農民層分解をいっそう加速させ,多くの農民が故郷を離れて遠くは満州等に移住し,日本に低賃金労働者として渡航することを余儀なくされた。反面,上層の民族ブルジョアジーは従属発展の道にしだいに引きこまれていった。〈文化政治〉はまた〈同化主義教育〉の推進に重点をおく側面ももっていた。こうした局面の変化を背景に,民衆(労働者,農民)が民族解放闘争の前面に立つ段階を迎える。外から,上から押しつけられる〈近代〉化(資本主義化)に対して,単純にこれに反発し,あるいは下からの自生的〈近代〉を対置するだけでなく,〈近代〉を超える民衆解放の理念の追求が志向されるようになったのも必然であった。20~30年代は,ブルジョア民族主義から民衆的民族主義への移行の時期ともいえる。社会主義のイデオロギーが青年知識人のあいだに急速に普及していったことも,こうした時代状況の一環として理解される。社会主義者と民族主義者(民族解放を志す非社会主義者)とは,一面では民族解放闘争のイニシアティブを争いつつも,新幹会の運動(1927-31)にみられるように協同戦線を組んで,民衆運動の高揚期をつくり出した。そして,30年代に入ると,社会主義の理念に導かれた農民組合運動が各地で激しく展開された。国境を越えた満州での抗日パルチザン闘争や中国大陸での抗日運動(朝鮮独立同盟など)の展開も,こうした国内民衆の闘いに呼応し,これを激励するものでもあった。30年代の闘争の中に,解放後の主体的歴史を担う思想がすでにはぐくまれていたのである。
皇民化政策
だが当面,日本帝国主義は,矛盾を回避しようとしていっそう矛盾を拡大していくその崩壊過程で,満州事変から日中戦争,太平洋戦争へと突入していき,その無謀な目的のために朝鮮の資源から人員までの総動員を図った。満州事変期には,官製の〈農村振興運動〉をもって大恐慌下の闘争の高揚に対応した総督府は,特に日中戦争以降の時期に全面的な総動員体制を強行していった。戦時労働力不足を埋め合わせるための強制連行から〈志願兵〉,軍属としての動員,ついには徴兵制の適用(1944)にいたるまで手段を選ばず強行した。朝鮮内でも1930年代以来〈大陸兵站(へいたん)基地〉として国策投資による軍需工業化が急激に進められたが,そのための労働力動員や産業統制・企業再編による実害も見落とすわけにはいかない。そしてこうした強制を維持するための精神動員策,すなわち皇民化政策が無謀にも民族固有の言語や姓名,文化の抹殺を図ったことは,深い傷痕を残した。戦時体制下,表面的には完全に沈黙を強いられた民衆は解放が近いことを予感していたのであった。
南北分断と統一問題
現在の朝鮮民族の最大の課題は,不条理な分断国家体制の自主的克服,統一の回復である。日韓関係をふくむ朝鮮現代史のすべての事がらは,この価値基準に立って評価されねばならない。
分断をもたらしたもの
南北朝鮮の分断は朝鮮人の誰一人夢にも思わなかったことであり,第2次大戦後の冷戦体制下の大国とりわけアメリカの思惑が,朝鮮半島を二つに引き裂いてしまった基本的要因である。1945年8月15日の解放直後の民衆意識は,1930年までの民族解放闘争が培ってきた思想の延長線上にあり,南北の差異はまだまったくなかった。その建国構想の最大公約数は,解放直後に主導権をとった朝鮮建国準備委員会や地方の人民委員会の動向から推して,土地改革と国家資本主義を基礎に民族主義者と社会主義者が広く結集した協同戦線の体制であったとみられる。もし,外力に妨げられずにこの構想が実現されていったなら,民衆の苦難がはるかに少なかったことは明白である。しかし,反共世界戦略に立つアメリカはこの構想の実現を容認できず,露骨な介入をあえてし,ソ連も,朝鮮の民族的利害よりその世界戦略を重視したためか,アメリカの動きを牽制する役割をほとんど果たさなかった。
南北分断が完全に固定化してしまうまでには,45年の米ソ分割占領,48年の二つの国家の成立,50-53年の朝鮮戦争の3段階があった。38度線を境界とする45年の米ソ分割占領は,ヤルタでの密約等によるものではなく,日本の敗戦まぎわに,橋頭堡を残したいアメリカ側がもちかけた米ソ交渉であわただしく決定されたものであることが明らかにされつつあるが,いずれにせよ分断の第1の遠因であることはまちがいない。次に,南朝鮮を占領したアメリカ軍は,政治動向が不利なことを知って建国準備委員会等の自主的な動きを一切否認し,直接軍政をしき,左翼勢力を猛烈に弾圧する一方,45年12月のモスクワ三国(米・英・ソ)外相会議で連合国から統一朝鮮の独立までのプロセスの決定を委ねられた米ソ共同委員会を決裂させて,アメリカの意のままになる国連総会に問題を移し(1947),48年には南朝鮮の単独選挙を強行して(〈朝鮮信託統治問題〉の項を参照),思惑どおりに反共親米に徹した李承晩政権の大韓民国を発足させてしまった(8月13日)。すぐ続いて北朝鮮では朝鮮民主主義人民共和国の樹立が宣言された(9月9日)。かくして二つの国家ができてしまい,分断は一段と深まったが,特に南の李承晩政権の基盤は弱く,情勢は流動的で南北再協商の可能性は十分にあると考えられていた。戦線がローラーのように南北を往復し,同胞同士が武器をとって闘いもした朝鮮戦争がこの可能性を完全につぶしてしまったのである。左翼系の活動家は人民軍とともに北へ移らざるをえず,反共意識に徹した〈越南者〉が南に移り,南北間のイデオロギー分化はいっそう顕著になった。〈国連軍〉の旗を使ってアメリカが介入した責任は明白だが,開戦責任の問題の究明も民衆の視点から強く要求される。
統一への志向
朝鮮戦争後,完全に越えがたいものとなった38度線沿いの休戦ライン(西部では38度線の南側,東部では38度線の北側に位置する)を背にして,南北それぞれに資本主義と社会主義という相異なる体制のもとで,分断を前提とする別個の歴史展開がみられることになった。分断が固定化した状況の中で分断を止揚する自主的思想が成熟してくるのには,長い時間を必要としたが,以後,南での矛盾の深化がその過程の焦点となった。李承晩政権を崩壊させた1960年の四月革命は,民主化から自主平和統一へという韓国民衆の希求を急速に具体化させ,北でもこれに南北連邦制提案をもってこたえたが,朴正熙政権を登場させた61年の五・一六軍事クーデタがいったんこの動きを遮断してしまった。しかし,以後,軍事政権下でも韓国民衆の民主化闘争はしだいに厚みを増し大きな力を蓄えつつ今日まで持続している(〈大韓民国〉の項を参照)。その間72年7月4日の自主的・平和的統一をうたった南北共同声明は,米中接近など多分に国際的条件に規定された一場のできごととみなされざるをえないが,そこで〈思想と理念,制度の差異を超越しての大団結〉が両政府間で確認されたことは,今後に生かしうる貴重な遺産として残っている。
しかし,この間1965年に民衆の反対をおしきって結ばれた日韓条約に基づく日韓支配層間の政治・経済的関係の深化が,統一問題にも大きく影を落としていることを重視しなければならない。それは,韓国経済の従属高度成長と産業社会化,そして不可避的に階級矛盾の深化を生み出しつつ,アメリカの軍事力と補いあいながら,軍事的〈開発独裁〉政権と財閥の支配を補強することによって,統一問題への接近に重圧を課していることを見落としてはならない。解放後の歴史の初発の時点で,外部から強引に育成された分断勢力が,その後の自己運動のなかで,分断を前提とする自己の基盤を補強しようとしてますます外力への依存を深めるという悪循環(いわゆる〈外部矛盾の内部転化〉)が,課題を複雑にしている。しかし,そうしたなかで,南での民主化・統一運動は学生,知識人のみならず矛盾を肌で感じている労働者に担われるようになり,拡大している。また分断の重圧は相対的規模の小さい北の内政にもいっそう大きなインパクトを及ぼしており,そのことが,70年代以降の北朝鮮における経済問題などの困難の一つの要因をなしていることも見落とすわけにはいかない。
こうした事情と中国のバック・アップ等国際条件の好転を背景として,84年初め北朝鮮は,朝鮮半島の平和問題に関する南北とアメリカの3者会談を提案するにいたった。そして84年10月北の水害救援物資を南が受け入れたことを契機に,11月,南北経済会談,南北赤十字会談再開(7年ぶり)等南北当局間の直接接触もはじまり,88年ソウル・オリンピック開催をめぐる不協和音をはらみつつも,統一をめざす動きもようやく活発化してきた。
執筆者:梶村 秀樹
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「朝鮮」の意味・わかりやすい解説
朝鮮
ちょうせん / チョソン
アジア大陸の東岸の中央部から南東方向の日本列島へ突き出た半島部と大小3300余の島嶼(とうしょ)からなる地域。半島部の南北間距離は840キロメートル、東西間の最長距離は島を含めて1200キロメートルである。総面積は22万0741平方キロメートルで、日本の本州から青森県を除いた大きさとほぼ同じである。半島部の北半部は北朝鮮、南半部は韓国(大韓民国)に分かれている。
本項目では朝鮮半島の自然の特色、およびそこにすむ民族とその文化について述べる。現在、朝鮮半島にある二つの国、韓国および北朝鮮については、それぞれの項目を参照のこと。
歴史は、朝鮮全般については「朝鮮史」の項目を、韓国および北朝鮮については、それぞれの項目の歴史のパートを参照されたい。同様に、日本との関係については「日朝交渉史」「日韓関係」「日朝関係」「日本と朝鮮半島との関係(第二次世界大戦後)」、および韓国、北朝鮮の項目のなかの日本との関係のパートを参照されたい。そのほか「朝鮮映画」「朝鮮演劇」「朝鮮語」「朝鮮舞踊」「朝鮮文学」「朝鮮民族」「朝鮮料理」などの項目もあわせて読まれたい。
[魚 塘]
自然
朝鮮の呼称
朝鮮の名は字のとおり「鮮(あざ)やかな朝」の意で、中国の古い文献『史記』や『魏略(ぎりゃく)』などに登場している。また李氏朝鮮(りしちょうせん)王朝500余年間も使われたなじみ深い国名である。「韓国」の韓も、古代朝鮮の南部地方に馬韓(ばかん)、弁韓(べんかん)、辰韓(しんかん)の三韓があったように、「朝鮮」とともに古代から使われていた。「韓」はアルタイ語のkkanの音写といわれ「大きい」「高い」の意をもつ。古代の三韓時代やいまの韓国の国名など身近に感じる名である。国名の異称として『韓国地名沿革考』によると194もあり、そのうち一般化されたのは雞林(けいりん)、青丘(ともに新羅(しらぎ)の別称)、槿域(くんいき)(ムクゲが咲く所)、三千里錦繍江(きんしゅうこう)山(南北が3000朝鮮里)などである。英語のKoreaは高麗(こうらい)の発音Koryoからとったものであろう。
[魚 塘]
地形
朝鮮の地体構造は、東部アジア大構造体の一部分である後期原生代の中国陸塊の東側縁辺部に属し、北東地塊はシホデアリン地向斜帯の上部古生代褶曲(しゅうきょく)帯であり、南東地域は環太平洋褶曲帯の中生代褶曲帯の一部地域に属している。
地形的特徴は、山地が全土の75%を占めているが、峻厳(しゅんげん)な山地は少なく、晩壮年地形を呈していて、北高南低であり、また東西が非対称性を示している。
朝鮮でもっとも高峻な地形をなしているのは北東部の咸鏡山脈(かんきょうさんみゃく)で、東海岸に沿いながら北東から南西方向に走っている。南東斜面は急傾斜をなし、北西斜面は緩やかである。朝鮮第二の高峰冠帽峰(かんぼうほう)(2541メートル)をはじめ渡正山(2201メートル)、机上峰(2333メートル)など30余の火山が玄武岩台地上に連なっている。南東部には吉州(きっしゅう)・明川地溝帯が形成されているが、その東側にアルカリ粗面岩と玄武岩からなる七宝山塊がある。
最高峰白頭山(2750メートル)は溶岩台地の中心を占めているが、南南東へ延びて摩天嶺山脈(まてんれいさんみゃく)となり、広大な白頭溶岩台地を形成している。この台地は第三紀から第四紀初めにかけて噴出した玄武岩アルカリ粗面岩で、噴出量は朝鮮だけでも4000立方キロメートルに達している。火山活動は、頭流山(2309メートル)、七宝山(906メートル)をつくり、海を渡って南下し、鬱陵島(うつりょうとう)の聖人峰(984メートル)に達する白頭火山脈となった。「朝鮮の屋根」といわれる蓋馬高原(かいまこうげん)は起伏量の少ない晩壮年期の地形で平均高度1200メートルである。蓋馬高原の南界は赴戦嶺(ふせんれい)山脈、西界は北~南に走る狼林(ろうりん)山脈である。狼林山脈は東西間の分水界をなしている。さらに西方へ江南、南西方向には狄踰嶺(てきゆれい)、妙香(みょうこう)の支脈が走っている。
白頭山麓(ろく)に発する朝鮮第一の大河鴨緑江(おうりょくこう)(790.7キロメートル)は、中国と国境を界し北西流し、開析谷を刻みながら、中江から黄海に向かっては構造谷を流れている。この地域は包蔵水力の豊富な所であり、水豊ダム、雲峰ダムをはじめ、長津江、赴戦江系の水力発電など重要な動力資源基地である。また豆満江(とまんこう)(520.5キロメートル)も白頭山麓より発し、東―北流して日本海に注ぐが、中流は嵌入(かんにゅう)蛇行しながら急下し、会寧(かいねい)からは側侵削剥(さくはく)により川幅を広め沖積地を展開している。この流域は代表的な褐炭埋蔵地である。
半島中部から南端にかけて東海岸沿いに走っているのが太白山脈で、南部の脊梁(せきりょう)をなしている。500キロメートルの長い山地で、東斜面は急傾斜をなし、西斜面は緩やかである。これは衝上運動による東西非対称の傾動地塊である。西斜面の嶺西高原は晩壮年期の地形で、忠州西部には低位準平原面を残している。太白山脈中には世界的な名山金剛山(こんごうさん)(1638メートル)をはじめ雪岳山(1708メートル)、太白山(1561メートル)などを連ねている。太白山脈の支脈である車嶺(しゃれい)・蘆嶺(ろれい)・小白山脈が南西に分かれて、それぞれ南海岸や南西の多島海に没しリアス海岸を形成している。
朝鮮半島の東部がほとんど山地地形であるのに反し、西部は準平原や沖積平野の優勢な地域である。典型的な準平原は平壌南方の力浦を中心とする約500平方キロメートルに達する平壌準平原(楽浪(らくろう)準平原)である。古来から穀倉地帯といわれる湖南平野は万傾江と東津江の広い沖積層と周辺の丘陵性平野からなっている。大同江(431.1キロメートル)下流地域の載寧(さいねい)平野、漢江(514.4キロメートル)下流の金浦平野、錦江(きんこう)(401.4キロメートル)下流の内浦平野、洛東江(らくとうこう)下流の金海平野がある。
南部を流れる河川はおおむね緩やかな地帯を流れるが、河床が高いので集中豪雨のときは水害を被ることが多い。
[魚 塘]
気候
気候の特徴は、ユーラシア大陸の小肢のように海中に南北に延びた半島なので、おおむね大陸性気候の支配下にあるが、南部の海岸地域は海洋性気候の影響を受けている。
冬はシベリア寒気団によって晴れた日が続き、降水量の少ない乾期であるが、夏は太平洋の熱帯性気団の波及により多量の雨量をもたらし、いわば湿潤な雨期である。
年平均気温は10℃内外である。北部の山岳地帯や蓋馬高原の年平均気温は10℃以下であるが、中央部は10℃内外、南海岸は14℃で、最暖地は済州島(さいしゅうとう)の14.6℃、釜山(ふざん)、麗水(れいすい)も1月の平均気温が零下に下がることはない。これは緯度上の位置や地形上の特性からくる影響と、季節風によってである。通俗的に三寒四温の国といわれているが、これは、大陸気団の強弱により気温が変化をきたし、三寒四温の現象が現れるもので、かならずしも周期的なものではない。
気候にもう一つ大きい影響力をもつものは、周期的な季節風である。冬季間の季節風は10月から3月にかけて大陸に発生した高気圧が北西風となって吹き、夏季は4月から8月にかけて南方から湿気の多い亜熱帯海洋性気団が上陸する。南東季節風である。両季節風によって、冬は寒波で気温が下がって晴れた日が続き、夏は気温が上昇し暑く、雨を多く降らせている。
朝鮮の年降水量は1000ミリメートル内外である。この60%は雨期である6、7、8月の南東季節風がもたらす降雨である。乾期の冬は年降水量の10%にも満たない。雨期の降雨の特徴は豪雨的で驟雨(しゅうう)性を帯び不規則である。そのため年によっては洪水や干魃(かんばつ)を招いている。多雨地域は南海沿岸地方の1400ミリメートル、寡雨地域は北部の豆満江上・中流の500ミリメートルである。
[魚 塘]
植物
植物帯は、北半球の同じ温帯地域に位置する他の地域より縦的構成が豊富で、多様な群落を形成しているのが特徴である。植物の種は約4200余種で薬用植物700余種、山菜類700~800種、特産変種1100余種、その他に野性飼料植物などがある。
植物分布は東北アジア亜区に属し、シベリア、中国の北部、東北部、南部、日本と共通するものが多い。朝鮮における植物分布区は次の4区に分けられている。
[魚 塘]
亜寒帯針葉樹林区
朝鮮北部の蓋馬高原、白茂(はくも)高原、白頭溶岩台地。モミ、エゾマツが優勢な群落をなしている。
[魚 塘]
温帯北部闊葉樹林区
咸鏡山脈と赴戦嶺山脈の南縁部から西南山地に至る地帯。おもな群落は小葉闊葉(かつよう)樹林、コナラ、シナノキ、アベマキ、クヌギなどである。
[魚 塘]
温帯南部闊葉樹林区
黄海南道南部、西南低地帯、小白山脈南部から金海平野を経て東南地帯に至る地域。モミ、ネズ、チョウセンマツの針葉樹林と、コナラ、サンショウ、アカシデなどの闊葉樹林である。金剛山には朝鮮で1属1種しかない特産種コゴメウツギと金剛チョロン(ハナブサソウ)がある。
[魚 塘]
常緑闊葉樹林を含めた亜熱帯区
3地区の残りの全地域で、済州島、鬱陵島を含む。雨量も多く温暖な地域で、ツバキ、ヒサカキ、マサキなど、いわゆる暖帯照葉樹林を形成している。済州島植物は海岸から漢挐(かんな)山(1950メートル)に向けて垂直に規則正しく分布している。山麓帯には亜熱帯のアカガシ、アラカシなど常緑闊葉樹林、中腹帯はアカシデ、イヌシデ、コナラなどの落葉樹林、山上地帯はダケカンバ、シラベとゲンカイツツジの大群落がある。
鬱陵島は300余種中特産植物40余種である。ブナ、オニイタヤは特産植物で、ユリ(原産地)、ササ、ツバキ、シャクナゲと、山麓にはイヌグス、シロダモ、モチノキなどがある。
[魚 塘]
民族と文化
朝鮮民族の形成
5000年の歴史と単一民族といわれているが、その歴史や言語、文化の跡をたどってみると、いろいろな紆余曲折(うよきょくせつ)がある。
朝鮮半島に人が住み着いたのは旧石器時代(咸鏡(かんきょう)北道屈浦里、忠清南道石壮里遺跡)で、約50万年前といわれる。明確な結論は出ていないが、朝鮮民族はアルタイ系といわれている。アルタイとは、中国とモンゴルの国境にあり、ロシア連邦に一部かかるアルタイ山脈からとった名であるが、古代朝鮮族は、アルタイ地方から東方へ移動した一派が満州を経て朝鮮半島に到達したものと推定されている。
中国の古い文献で東夷(とうい)族とよばれたのは、満州地方に住んでいた古代朝鮮族をさしたものである。時代は下るが『大明実録』「太祖実録」には「朝鮮は山でふさがれ海に没しているので、昔から独自な東夷族を形成している。中国で治めるべきでなく、声教は彼らの自由である」とあり、自立を認めている。東夷族の祖先が松花江(しょうかこう)、冬佳江周辺から南下し、一部は朝鮮半島へきたものと思われる。
東夷族には夫余(ふよ)族のほかに濊(わい)、貊(はく)(穢貊とも記載される)、韓族がいる。濊族は松花江、遼河(りょうが)、大遼河の沿岸平野が定着地であったが、戦乱を避けて朝鮮半島に南下し、太白山脈の海岸沿いには濊族、西方の嶺西地方(江原道、忠清北道)には貊族が進出している。東夷族の部族のなかでもっとも文化が進んでいたのは夫余族で、いまの長春西方の農安に進出し、3世紀ころには戸数8万、2000里四方を領有し、支配体制や身分制度も確立していたという。高句麗(こうくり)を創建した東明王とその第2子で百済(くだら)王になった温祚(おんそ)も夫余族の一員であったといわれる。
一方、朝鮮半島の南部には以前から馬韓(ばかん)、辰韓(しんかん)、弁韓(べんかん)の三韓があったが、馬韓の54部族中「伯済(はくさい)」に制覇され百済国に、辰韓の12部族中「斯廬(しろ)」によって新羅(しらぎ)国に統一された(『三国史記』)。これら南部地方の部族のなかには文身(いれずみ)の習俗があり、海洋文化の伝統の名残(なごり)であるといわれる。また言語学的にも三韓地方の古地名の研究から、南部の先住民は大陸より移動した民族でなく南インドのドラビダ系またはポリネシア諸島から移住したものとの説(ハルバート)がある。新羅の昔氏(せきし)始祖起源伝承や済州島の高・梁・夫三姓氏の伝説も南方からの移動を物語るものである。また新石器文化の遺物のうち有肩石斧(ゆうけんせきふ)、抉入(えぐりいり)石斧は海洋民族のものといわれている。
[魚 塘]
身体的特徴
朝鮮族はモンゴロイドに属しており、形質的にはアルタイ系諸族とは区別しにくい。世界諸民族の身長分布のうち、中等大身長のうち大きいほうで、首が比較的細く、背側深層筋群が発達しており姿勢が正しい。また下肢が長く身体各部の比率配分が、欧米人に比べて均衡がとれている。頭部は短頭で、長径の短い特異な短頭が多い。顔はモンゴロイドの特徴である広顔だが、長顔でもあり、頭腔(とうくう)容積も大きく脳重も重いほうであるといわれている。
[魚 塘]
原始宗教
原始社会における宗教には、霊魂を認めるアニミズムや呪術(じゅじゅつ)と、祖先を動植物と考えるトーテミズムがある。朝鮮における原始社会でもこれらの原始宗教や儀式が行われていた。
開国神話での檀君(だんくん)は、熊女を母に檀樹下で生まれたといわれる。夫余王や高句麗開祖の東明王や新羅開祖の赫居世(かくきょせい)誕生については卵生説話で、太陽に照らされて生んだという太陽神話に結び付いている。また高句麗では毎年10月、東盟という祭天儀式を行い、濊でも舞天という祭天を行い、昼夜飲食歌舞をしていた。また馬韓では5月、畑作の春耕が終わり神を祭祀(さいし)して、昼夜酒宴を開き歌舞を楽しみ、10月に収穫が終わったあとも神を祀(まつ)って歌舞飲食した。このほか山川、大木や風、雨、雲なども天に左右されるものとして、信仰の対象であった。また大木を立て(ソッテ=蘇塗)、その木先に鈴をかけて神壇として祈っていた。
路傍や郡界に立っているチャンスン(長 )は、男女一対で、男は頭部に冠をかぶり胴体に「天下大将軍」と刻み込み、女は「地下大(女)将軍」と書いたのがある。これは神域表示や逐鬼の意をもつ原始宗教である。ソナンダン(城隍壇)も村の入口の小高い所か峠に小石をたくさん積んであるもので、子供が生まれるよう祈願したり、福を招き厄除(やくよ)けを祈る原始宗教である。
)は、男女一対で、男は頭部に冠をかぶり胴体に「天下大将軍」と刻み込み、女は「地下大(女)将軍」と書いたのがある。これは神域表示や逐鬼の意をもつ原始宗教である。ソナンダン(城隍壇)も村の入口の小高い所か峠に小石をたくさん積んであるもので、子供が生まれるよう祈願したり、福を招き厄除(やくよ)けを祈る原始宗教である。
[魚 塘]
シャーマニズム
原始的宗教現象として今日も大きな影響力をもつものはシャーマニズムである。
朝鮮におけるシャーマン(巫覡(ふげき))は巫祭、医巫、予言者の三つの職能があり、原則としてムーダン(巫堂)がそのすべてをつかさどるが、予言者にはパンス(判数)という男の盲人がなる場合もある。巫祭のことをクッまたプリというが、この儀式でムーダンが神の意志を人間に伝達し、医巫は祭供と祈祷(きとう)によって悪霊を駆逐するものであり、予言者は直感と卜筮(ぼくぜい)で未来の吉凶を予言する役である。
巫俗信仰はいまも民間で盛んであるが、歴代王朝でも厚遇保護したり、あるときには排斥もした。新羅時代は2代王南解王が巫者で王を兼ね、高麗(こうらい)時代は巫俗信仰が王室や民間の生活面に広がり、治病や国家的な祈雨祭もつかさどっていた。李朝(りちょう)時代は政府専用の巫庁を置いた。しかしムーダンは民衆を眩惑(げんわく)し、狂信のあまり破産する民家も出た。政府はやむなくムーダンを城外に追放したことがある。
[魚 塘]
仏教
朝鮮の仏教はインドや中国仏教の単純な延長ではなく、朝鮮半島の風土と社会に溶け込んだ独特な発展をしている。
高句麗、百済、新羅の三国のうちいちばん早く仏教を取り入れたのは高句麗で、小獣林王の2年(372)に前秦(しん)王符堅(ふけん)が派遣した僧順道と仏像・経文を公的に受け入れ、それが朝鮮仏教の出発点となった。その後、百済は枕流(ちんりゅう)王の1年(384)に、新羅は訥祇(とつぎ)王の1年(417)に伝来しているが、仏教国家として基盤を整えたのは新羅の真興王5年(544)である。その年興輪寺が創建され、王は国民が出家して僧尼になる自由を国法で保障した。その後、皇竜寺、祇園(ぎおん)寺、実際寺などの寺院が創建された。統一新羅時代に入ってからの仏教はいっそう隆盛発展して支配的な思想になり、社会・文化的にも大きな役割を果たした。寺院は都城中心に建てられていたが、統一新羅以後は個人的な寺院が地方各地にも建てられた。また寺院経済も施納財産によって経済的基盤が強固になり、多くの田畑を保有するようになった。また元暁(がんぎょう)をはじめとする傑出した高僧が輩出し、仏典の著述も多かった。仏教文化が頂点に達し開花したのは景徳王代(742~764)である。慶州の吐含(とがん)山の仏国寺と石窟庵(せっくつあん)は寺院建築の代表的なものであり、仏像彫刻の精緻(せいち)な手法と線感覚は新羅美術の粋である。
高麗時代も仏教が国教になり、仏教を信仰していたが、崇儒政策を併用していた。成宗(在位982~997)は儒教を尊び、燃燈(ねんとう)会、八関会などの仏教儀式を廃したが、顕宗(けんそう)(在位1009~1031)のとき太祖王建の訓要10条の国是になっていた燃燈会、八関会を復活した。前者は4月8日釈迦(しゃか)生誕日を燃燈で祝い、後者は10月西京(平壌(へいじょう))、11月中京(開城)で土俗神に対する祭祀で、歌舞を伴う国をあげての大祭である。高麗中葉には僧侶(そうりょ)を優遇した結果、僧侶が民衆に横暴を極め人民の糾弾を受けた。民俗仮面劇『鳳山(ほうざん)タルチュム』はこのときの僧侶を風刺した内容である。しかしモンゴル軍襲来のとき、首都を開城から江華島に遷都させながら『高麗版大蔵経』の木版を完成させ、今日に残して貴重な民族文化遺産になった。
[魚 塘]
儒教
儒教が朝鮮へ伝来したのは仏教と同じく高句麗の小獣林王の2年といわれるが、儒教が国是になり開花したのは李朝時代である。
朱子学によって男女有別、長幼有序の上下の身分秩序をたて、仁をもってすべての道徳に通じる理念とし、修身、斉家、治国、平天下を目標にした一種の政治倫理の樹立である。
儒教を統治理念とした李朝500余年間に培われたものは、朱子家礼による冠婚葬祭をはじめ、人倫道徳や清廉節義の尊重など、朝鮮人の精神生活を今日まで大きく支配している。
[魚 塘]
キリスト教
キリスト教は、1869年9月イギリスのロンドン宣教会トーマスRobert J. Thomas(1839―1866)牧師が、シャーマン号に乗り込み平壌で殉教したのが開教の始まりである。トーマス殉教以来いろいろの布教活動はあったが、合法的な宣教開始は、1882年、アメリカと朝米修好条約を締結してからである。
聖書の朝鮮語訳も進み布教が進んだが、国教の儒教と背反する教旨から斥邪政策によって、宣教師や信者に多くの殉教者を出した。改新教(プロテスタント)は、アンダーウッドH. G. UnderwoodやアペンセラーH. D. Appenzellerらが1885年に来朝して始まった。そして彼らによって1887年9月最初の長老教(プレスビテリアン)新門内教会が、同年10月には最初の監理教(メソジスト)の貞洞教会が発足した。以後、釜山(ふざん)、大邱(たいきゅう)、平壌、義州へ拡大されていった。そして1896年には信者8000人を擁し、キリスト教の布教の基盤が固まった。布教と同時に医療・教育事業も進み、今日の延世(えんせい)大学の土台をつくったのはアンダーウッドやアペンセラー牧師らである。
天主教(カトリック)も神父の潜入布教から始まったが、1866年の大弾圧により2万5000人の信徒中1万余人が犠牲になった。1868年朝仏修好条約締結以後緩和され、1893年ソウル市を見下ろす丘の上に薬峴(やくけん)天主教堂、1898年には明洞大聖堂がつくられた。その後、大邱、元山と三教区を置いた。
[魚 塘]
天道教
民族宗教である天道教は、1860年崔済愚(さいせいぐ)によって創立された東学を継承した、輔国(ほこく)安民の宗旨の民族主義新興宗教で、西学の宗教(キリスト教)に対抗しての東学とし、儒、仏、道の三教を中心に、天主教を加味して創設したものである。
慶尚北道竜潭(りゅうたん)で始まった東学は、第2世崔時亨(じこう)のとき全国に布教された。しかし東学に対する政府の弾圧政策と悪政に対して、1894年全羅北道古阜(こふ)の信徒全琫準(ぜんほうじゅん)によって引き起こされた農民反乱(甲午農民戦争)は、輔国安民の旗印に社会制度と国家体制の改革を求めた一揆(いっき)で、湖南地方や嶺南地方の農民も加担した大規模のものであったが、日本などの外国勢力の干渉により失敗に帰した。一時沈滞を免れえなかったが、いまも多くの信徒を擁している。
このほかの新興宗教として南学系、甑山(そうざん)系、檀君系、覚世系、水雲教、仙道教、弥勒(みろく)教などがある。
[魚 塘]
民俗
朝鮮半島では夫余系の種族が南下して先住部族を制圧して新羅や夫余の国を建設した。先住民族の残した遺跡からは抉入(えぐりいり)石斧、有肩石斧のような海洋民族のものと思われる遺物が出土しており、言語学的にも南方系の名残とも思われる語彙(ごい)が残されていることから、先住民族は海洋文化系の民族であるといえる。しかし、民俗習慣として残っているものは北方系の原始宗教や文化の遺産であり、李朝時代に入ってはほとんど中国文化の影響による民俗である。
チャンスンやソナンダンは、北方系の原始宗教であり民俗である。これらのトーテミズムやアニミズムは、ツングース人やモンゴル人にも共通のもので、現在もわずかではあるが残存している。
民俗習慣でもっとも広範に今日まで伝承されているのは年中行事である。正月の茶礼(祖先に対する祭祀)、元日の雑煮の朝食、立春の日大門に「掃地黄金出」「開門万福来」などの春帖(しゅんちょう)字を貼(は)り、3月の寒食の墓参り、4月8日釈迦(しゃか)生誕日の燃燈会、5月端午のグネ(鞦韆、吊縄(つりなわ)の長いブランコ)など、12月まで伝承された行事があるが、洪錫謨(こうしゃくも)の『東国歳時記』に網羅されている。これらの民俗行事は歳時記の序文で引き合いに出されているように、中国南方の楚(そ)国の『荊楚(けいそ)歳時記』と比較していることから、朝鮮民俗の淵源(えんげん)が察知できそうである。
儒教思想から男女有別が判然としているが、家庭では女子はアンバン(内房)、男子はサランバン(舎廊房)を専有していた。年中行事でもノルティギ(板戯)、タルマジ(月迎)、グネは女子の遊びで、封建社会における女子解放の機会ともいわれていた。
古い民俗習慣でいまも現存するのはシプチャンセン(十長生)とトンサンレ(東床礼)である。シプチャンセンは一種の敬老民俗で、日、山、水、石、雲、松、不老草、亀(かめ)、鶴(つる)、鹿(しか)の長生不老のものを描いたり刺しゅうにして壁掛けにする風習で、一種のアニミズムである。トンサンレは、結婚式後、新婦宅に泊まる新郎に対して、新婦の親族、集落の若者、新郎の友人が新郎を縛り上げ、または足を吊り上げて乱暴し、新婦宅から酒食をせびる風習である。
衣食住の生活も古代朝鮮の遺習が今日まで残存している。朝鮮人の常用服であるチョゴリ(襦)、チマ(裳)、ツゥルマギ(周衣)は、古代朝鮮民族の居住地が亜寒帯に属していたことによって北方系の衣服である。住宅は朝鮮の気候風土にあう独特のものであるが、オンドル(温突)は、型は違うが満州の女真も使っていたものである。冠婚葬祭は朱子家礼によるものである。
[魚 塘]
言語と文字
朝鮮語は朝鮮半島および周辺の島嶼(とうしょ)や半島外の朝鮮民族の集団居住地(中国吉林(きつりん)省延辺朝鮮族自治州、アメリカのロサンゼルスなど)の約5000万朝鮮民族の言語である。朝鮮語は感情的な表現に富んでいる。
朝鮮民族と同様明確な結論はないが、朝鮮語はアルタイ語族に属しているといわれている。アルタイ山脈から発して東に進んでモンゴル語、ツングース語となり、さらに南下して朝鮮語となった。アルタイ語系のトルコ、モンゴル、ツングースの3語群は構造上母音調和があり、前置詞を用いず後置詞の助詞を用い、アクセント音の長短によって意味が変わる場合がある。膠着(こうちゃく)性があるのは日本語と同様である。
古代朝鮮語は、満州北西部にいた夫余族、咸鏡南・北道沿海地方の沃祖(よくそ)族、江原道一帯にまたがる穢貊族らの北方系朝鮮語と、慶尚南・北道東海岸一円の辰韓語と、洛東江(らくとうこう)下流を基点とする弁韓語、忠清道、全羅南・北道一円にわたる馬韓族の南方系といわれる朝鮮語とがある。『梁(りょう)書』の「百済伝」に「現在、その言語や衣裳(いしょう)は高句麗とほぼ同じ」とあり、『三国志』「弁辰伝」には「弁辰は辰韓と雑居している……言語や法俗もともに似ている」と述べ、類似性を指摘している。この北方系の民族が朝鮮半島へ南下して、生活土台が半島部に限られることにより、ことばの差は縮まり、新羅が三国を統一してからは新羅語を中心とした統一朝鮮語が形成されたものという。
古代朝鮮では、中国人との言語接触の結果、早い時期に漢字が輸入されて使われている。朝鮮語は話すことばだけで、記録を残すには漢字しかなかったのである。つまり文語漢字と口語の朝鮮語の2言語使用であった。その結果、漢字要素が大量に朝鮮語に浸透したので、今日の朝鮮語のなかには膨大な漢字語が混じっている。
高句麗以来、漢字によって自国語を表記する努力がなされた。新羅時代の吏読もその一つである。7世紀の薛聡(せっそう)の創案といわれ、漢字の音と意を借りて朝鮮語を表記した。この吏読は高麗、李朝を通じて19世紀まで使用されていた。そして1443年、李朝世宗(せいそう)のとき、表音文字の訓民正音(くんみんせいおん)(ハングル)の創製によって、言文一致の今日の朝鮮語と文字が完成された。
[魚 塘]
『中村栄孝著『朝鮮――風俗・民族・伝統』(1951・吉川弘文館)』▽『崔南善著、相馬清訳『朝鮮常識問答』(1965・宗高書房)』▽『金思燁著『朝鮮の風土と文化』(1976・六興出版)』▽『秋葉隆著『朝鮮民俗誌』(1980・名著出版)』▽『鎌田重雄著『朝鮮仏教の寺と歴史』(1980・大法輪閣)』▽『梶井陟著『朝鮮語を考える』(1980・龍渓書舎)』▽『魚塘著『朝鮮の民俗文化の源流』(1982・同成社)』▽『魚塘著『朝鮮新風土記』(1984・三一書房)』▽『姜在彦訳『朝鮮歳時記』(平凡社・東洋文庫)』
百科事典マイペディア 「朝鮮」の意味・わかりやすい解説
朝鮮【ちょうせん】
→関連項目朝貢貿易
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「朝鮮」の解説
朝鮮(ちょうせん)
Jo-s&obreve;n
朝鮮半島および周辺の島嶼からなる朝鮮民族の国。半島の歴史は,戦国から秦漢期にかけて半島西北部に移住定着した中国人がつくった植民国家である箕子(きし)朝鮮,衛氏(えいし)朝鮮に始まる。朝鮮の名もここに起こった。コーリア(Korea)の称は高句麗(こうくり),高麗(こうらい)の国号に由来する。中国の支配は武帝の楽浪郡の設置(前108年)以来定着し,約400年持続したが,この間漢文化の移植が半島住民の国家的活動を促した。東北に扶余(ふよ)族の高句麗が興り,南下して楽浪郡を滅ぼし(313年),同じ頃帯方郡を滅ぼした南方の韓族からは,三韓時代をへて,百済(ひゃくさい),新羅(しんら),加羅(から)諸国が成立し,562年の加羅滅亡(562年)後は,上記3国が半島に鼎立した。7世紀,百済,高句麗は唐・新羅の攻撃で滅び,新羅が北部を除き,初めて半島に統一国家を形成した。9世紀に新羅分裂のあとを再統一した高麗王朝は,半島西北部を開拓したものの,13世紀以降モンゴル軍の侵略と重圧に衰え,14世紀後半,元・明交替期のなかに半島には朝鮮王朝が成立した。朝鮮王朝は明・清に服事しつつも,東北部を領域化し,現在の国境線をほぼ画定し,単一民族文化の様相を提示した。1910年日本の支配下に入ったが45年独立し,現在の大韓民国,朝鮮民主主義人民共和国が成立した。朝鮮民族の歴史は,その地理的位置から,大陸勢力の侵入と圧迫の連続であるが,一方その制約下にあって中国文化を受容しつつ,農耕文化を持つ南方韓族の北方への絶えざる発展と民族国家形成の姿である。朝鮮語はアルタイ語の一系統で,特異な字母文字(ハングル)を持つ。宗教では仏教や儒教のほか,民間信仰に特色あるシャマニズムもみられた。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「朝鮮」の意味・わかりやすい解説
朝鮮
ちょうせん
Korea
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 日本史小辞典 改訂新版 「朝鮮」の解説
朝鮮
ちょうせん
チョソン。遼東から朝鮮半島北部には古朝鮮(檀君(だんくん)・箕子(きし)・衛氏(えいし))があり,漢の武帝の楽浪郡がおかれ,のち高句麗(こうくり)の支配下に入った。半島南部には韓族があり,三韓から百済(くだら)・新羅(しらぎ)が成立。この時期に朝鮮から日本に多数の渡来人があった。高句麗との三国時代をへて7世紀後半に新羅が半島を統一,さらに10世紀に高麗(こうらい)が建国した。英語のKoreaは高麗に由来する。朝鮮を国名とするのは14世紀末の李氏朝鮮からで,最も長期の王朝として栄えた。室町時代に日朝貿易が行われたが,豊臣秀吉の侵略で断絶。江戸幕府の国交回復後は朝鮮通信使が往来して平和的な国交が続いた。明治維新後,日本は利益線と目した朝鮮をめぐり日清・日露戦争を戦った。1897年国号を大韓帝国と改めたが,日露戦争後は日本が保護国化し,1910年(明治43)併合,第2次大戦終結まで植民地支配下にあった。日本の敗戦により,45年米・ソ両軍が38度線を境に分割占領したが,48年南半部に大韓民国,北半部に朝鮮民主主義人民共和国が成立,南北分断が続いている。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
旺文社日本史事典 三訂版 「朝鮮」の解説
朝鮮
ちょうせん
アジア大陸と日本を結ぶかけ橋として独自な歴史・文化を形成。古代,中国の戦国時代には箕氏 (きし) 朝鮮・衛氏 (えいし) 朝鮮が成立,前108年漢の武帝が衛氏を滅ぼし朝鮮4郡を設置。以後約400年間,中国の支配をうけたが,4〜6世紀にかけて百済 (くだら) ・新羅 (しらぎ) ・高句麗 (こうくり) の3国がおこった。のち隋・唐軍の侵入により百済・高句麗が滅んだが,新羅が全半島統一を完成。10世紀初め新羅に代わって高麗 (こうらい) 朝が成立したが,モンゴル(元)の侵略に悩まされた。ついで14世紀末李氏朝鮮がこれに代わり,初期にはかなり繁栄したが,日本および清の侵略をうけ衰退。19世紀後半から世界列強,特に日本・ロシアの抗争の場となり,1910年には日本に合併(韓国併合)。第二次世界大戦後,解放されたが,'48年南の大韓民国,北の朝鮮民主主義人民共和国に分割された。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...