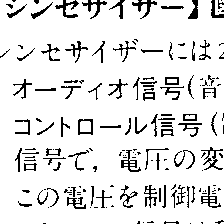精選版 日本国語大辞典 「シンセサイザー」の意味・読み・例文・類語
シンセサイザー
- 〘 名詞 〙 ( [英語] synthesizer 「統合、合成するもの」の意 ) 電子回路を用いた音の合成装置。多く、鍵盤を備えた楽器として使用される。〔マイ・コンピュータ入門(1977)〕
- [初出の実例]「当世風にエレキサウンドやシンセサイザーにしなかったところが大手柄だ」(出典:吉里吉里人(1981)〈井上ひさし〉終章)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「シンセサイザー」の意味・わかりやすい解説
シンセサイザー
しんせさいざー
(music)synthesizer
通常の楽器が特定の音の性格をもつのに対し、その名(「合成するもの」の意)のとおり、電子技術を利用してあらゆる音を自由に合成することを意図して考案された楽器。電子オルガンなどの電子楽器は音色その他の要素があらかじめセットされているのに対し、シンセサイザーはすべての要素を自由に調節できる点が異なる。シンセサイザー単独での使用だけでなく、従来の楽器とともに使われることも多い。
[前川陽郁]
歴史
シンセサイザーの源流は、1906年にアメリカのサディウス・ケーヒルThaddeus Cahill(1867―1934)が発表した「テルハーモニウム(ダイナモフォン)」にまでさかのぼることができる。これは抵抗器で倍音を調節できる仕組みになっていた。現在のようなシンセサイザーは、1950年代にアメリカRCA社から発表された、ハリー・オルソンHarry F. Olsen(1901―1982)らが製作したものが最初で、すでに「シンセサイザー」の名がつけられていたが、パンチ孔(あな)をあけた紙テープを入力に使用するなど、実験的な面が強かった。1960年代には、ドナルド・ブックラDonald Buchla(1937― )やロバート・モーグRobert A. Moog(1934―2005)らによって、実際の音楽に使用する楽器として実用的なものが開発された。とりわけ、モーグが1965年に商品化した「モーグⅢCシンセサイザー」を使って、作曲家ウォルター・カーロスWalter Carlos(1939― 、後のウェンディー・カーロスWendy Carlos)が制作した『スイッチト・オン・バッハ』(1968発表)によって広く注目されるようになった。日本では、冨田勲(とみたいさお)や喜多郎(きたろう)らによって一般化した。
[前川陽郁]
原理
実用化された当初のシンセサイザー(アナログ・シンセサイザー)は、基本的には、(1)加工する元になる信号を発生させる部分、(2)その信号の倍音を加減する部分、(3)音に時間的な音量変化(エンベロープ)を与える部分、の三つによって音を「合成」する。原理的にはどのような音でもつくれるとはいえ、現実的な制約から「シンセサイザーの音」にとどまりがちであったが、そのいわば「シンセサイザー臭さ」が一つの魅力にもなった。操作が複雑で、場合によっては多重録音を必要とするといった短所もあったが、技術の進歩によってやがて改善されることになる。1980年代にはデジタル技術が音づくりに取り入れられ、また、ほかの楽器などの音をデータ化(サンプリングsampling)し、それを多くの場合加工して用いることも主要な技術になる。それによって、既存の楽器の音を模倣するにしても、あるいはそれまでにはない新しい音をつくり出すにしても、より多彩で、電子技術によっていることをかならずしも感じさせない音を、高い自由度でつくることができるようになった。
[前川陽郁]
演奏法
シンセサイザーは、鍵盤(けんばん)を備えた形態が一般的だが、電気信号によって制御していることから、鍵盤によるのとは別の演奏法を行ったり、複数のシンセサイザーを同時に演奏することが可能であるばかりでなく、自動演奏にも適している。演奏する音をあらかじめ設定しておいて、それにしたがって電子楽器から音を出すシーケンサーsequencerは、初期のころからシンセサイザーとともに(あるいは内蔵されて)用いられ、その記憶容量が増えるにしたがって、複雑な音楽を自動演奏することが可能になった(演奏の情報を前もって入力しておくところから「打込み」とよばれる)。制御方法は、初めはメーカーによってまちまちであったが、1982年に統一規格であるMIDI(ミディ)(Musical Instrument Digital Interfaceの略)が制定され、電子楽器どうし、あるいは周辺機器との自由な組合せができるようになった。
[前川陽郁]
コンピュータの利用
さらに、パーソナルコンピュータが普及するにつれて、パソコンでシンセサイザーの音源(音源の機能までコンピュータが受け持つソフトウェア・シンセサイザーもある)を制御して音楽を制作、演奏するデスクトップ・ミュージック(DTM)も、音楽へのかかわり方の幅を広げている。1992年にはMIDIに音色に関する規格を加えたGM(General MIDI)規格が取り決められた。そのもとでは、再生する機器が異なっても、同じデータからは基本的に同じ結果が得られるため、音楽をMIDIデータのかたちでインターネットなどによって配信することが可能になり、また通信カラオケで使われるなど、音楽の新しいあり方をもたらしている。
[前川陽郁]
『H・A・ドイチュ著、梯郁太郎訳『シンセサイザー――その革命の歴史と理論』(1980・パイパーズ)』▽『新井純編著『シンセサイザー・セオリー』(1988・新人社)』▽『古山俊一著『シンセサイザーここがポイント 2』(1990・音楽之友社)』▽『安斎直宗著『シンセサイザーの全知識』(1996・リットーミュージック)』▽『田中雄二著『電子音楽イン・ジャパン 1955~1981』(1998・アスキー)』▽『梯郁太郎著『ライフワークは音楽――電子楽器の開発にかけた夢』(2001・音楽之友社)』▽『古山俊一著『はじめてのシンセサイザー』(講談社現代新書)』
改訂新版 世界大百科事典 「シンセサイザー」の意味・わかりやすい解説
シンセサイザー
synthesizer
ミュージック・シンセサイザーmusic synthesizerの略。いろいろな音を奏者の意図に応じて合成できる回路網をもち,音楽の演奏ができる特殊な電子楽器。ステージでの生演奏に向くポータブルのものから,スタジオに設置して複雑な手法で用いるものまで多種多様のものがある。機能に特定の限定が設定されているものではないが,最小構成機能としては電圧制御発振器(VCO),電圧制御フィルター(VCF),電圧制御増幅器(VCA),エンベロープ電圧発生器(Env),音階電圧発生器があげられる。音階電圧発生器にはオルガン風の鍵盤が最も普及しているが,ギターのような指板を用いるものやコンピューターにプログラムを入力して用いるものなどもある。従来の電子オルガンと違う点は音の成長・減衰の変化を奏者が自由に制御できる点である。これはVCO,VCF,VCAのそれぞれを時間的に変動する条件で制御できるためで,多様な音の合成が可能となっている。大型のものはそれらの基本的な機能回路を数多く備えており,多次元の制御が可能である。ミュージック・シンセサイザーの名は1950年代にアメリカのオルセンHarry OlsenらがRCAビクターの研究室で開発した穿孔紙テープ制御式合成装置(真空管式)に命名したのに始まる。64年アメリカのモーグRobert Moog(1934-2005)はトランジスターを用いた電圧制御式の機能回路を有機的に構成することに着眼し,大量に市販できる装置を開発した。68年にカーロスWalter Carlosがこれを用いてバッハの音楽を合成したLPレコードは新しい音の世界の到来を示し注目された。続いて日本の冨田勲(1932- )がドビュッシーの曲による合成音楽を作り,シンセサイザーの音は急速に世に広まった。最近では集積回路の出現により装置の改良とコストダウンが進み,小型化,機能の複雑化が見られる。電子オルガンにもシンセサイザーの基本回路が取り入れられるなど他楽器への影響も大きい。
執筆者:白砂 昭一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「シンセサイザー」の意味・わかりやすい解説
シンセサイザー
→関連項目ズーク|電子音楽|MIDI|ンドゥール
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
音楽用語ダス 「シンセサイザー」の解説
シンセサイザー[synthesizer]
出典 (株)ヤマハミュージックメディア音楽用語ダスについて 情報
世界大百科事典(旧版)内のシンセサイザーの言及
【電気楽器】より
…〈テレミン〉(1920),〈オンド・マルトノ〉(1928)が古い。パイプ・オルガンを見本として出発し,現在ではまったく独自の楽器となって急速に普及している電子オルガンの類や,多様な音が自由に合成できるように種々の機能回路を網羅したミュージック・シンセサイザー(シンセサイザー)の類があげられる。(4)自動楽器に応用しているもの。…
※「シンセサイザー」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...