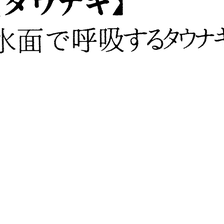タウナギ (田鰻)
rice eel
Monopterus albus
タウナギ目タウナギ科の淡水魚で1属1種。一見ウナギに似るが,頭が大きくて体の後部はしだいに細くなり尾端がとがる。体色は赤褐色で,黒い小斑点が散在する。全長70~80cmに達する。胸びれと腹びれがなく,背びれとしりびれが皮褶(ひしゆう)だけでできている点や,鰓孔(えらあな)が下面に開き,左右のものが接続する点も目だった特徴で,この仲間は系統上特異な群とされる。タウナギは東南アジアから中国,台湾,朝鮮半島にかけて分布し,おもに水田や浅い池沼に生息する。日本では沖縄を除けば,東京の上野の不忍池,京都の二条城の堀,その他の限られた場所でしか知られていない。しかも,もとからそこにいたものかどうかもわからない。
昼間は泥底や物陰に潜み,夜間に出てきて小動物や小魚をあさる。えらは著しく退化して役に立たない。その代わりに空気を吸い,口腔やのどの内壁を通じてガス交換を行う。水槽の中ではときどき水面上に頭を出して呼吸するのが見られる。冬に池沼の水がかれても,干上がった泥の中で生きのびることができる。雌から雄に性転換することも有名で,全長30cm前後まではすべて雌であるが,50cm前後になると雄に変わり,中間の大きさのものは雌雄同体で卵精巣をもつ。産卵期に雄は粘液に包まれた泡を吐き出して巣をつくり,雌の産んだ卵をここに集めて保護する。本場の中国では黄鱔(ホワンシヤン),または鱔(シヤン)と呼ばれ,油でいためるなどして賞味される。
執筆者:羽生 功
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
タウナギ
たうなぎ / 田鰻
swamp eel
[学] Monopterus albus
硬骨魚綱タウナギ目タウナギ科に属する淡水魚。東南アジア諸国、中国、朝鮮半島南部に広く分布する。日本には中国大陸から移入され、関東地方以西に局部的に分布し、とくに近畿地方に多い。目が小さく、背びれや臀(しり)びれが未発達で、胸びれ、腹びれ、鱗(うろこ)がまったくなく、一見ヘビを思わすのでカワヘビの名もある。体は粘液で覆われ、背面は黄褐色、腹面はオレンジ色、暗褐色の斑紋(はんもん)または斑点が散在する。全長80センチメートルになる。南西諸島のものは、環境省のレッドリスト(2013)で、ごく近い将来における野生での絶滅の危険性がきわめて高い、絶滅危惧ⅠA類に位置づけられている。
水田や池、川にすみ、夜間に昆虫や小魚、底生動物を食べる。退化的なえらによっても呼吸をするが、皮膚や食道の呼吸補助組織によって空気呼吸をするので、溶存酸素の少ない水中や乾燥にもよく耐える。乾燥した田の1~2メートル下から生きて掘り出されたこともある。多くは性転換をし、34センチメートル以下は雌、46センチメートル以上(4歳魚)はすべて雄である。しかし、少数のものは初めから雄であり、12センチメートルで成熟する。水田の畔(あぜ)に穴をあけてすむ習性があり、水を漏らすので嫌われる。しかし、国によっては食用や造血用の薬物として珍重される。
[落合 明・尼岡邦夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
タウナギ
学名:Monopterus albus
種名 / タウナギ
目名科名 / タウナギ目|タウナギ科
解説 / 水田や池などのどろの中にすみ、昆虫や両生類などを食べます。夜行性。空気呼吸を行います。性転換をします。
別名 / カワヘビ、チョウセンドジョウ
全長 / 80cm
分布 / 朝鮮半島、中国、マレー半島、東インド諸島原産/本州各地、鹿児島県などへ移入
人との関わり / 原産地では食用。漢方薬の材料
出典 小学館の図鑑NEO[新版] 魚小学館の図鑑NEO[新版] 魚について 情報
Sponserd by 
タウナギ
タウナギ科の魚。形はウナギに似て,全長70〜80cmに達する。体色は黄褐色で,暗褐色の斑紋をもつ。鰓は退化し,呼吸は主として消化管で行われる。東南アジア〜沖縄,朝鮮半島に分布。浅い池や沼の泥底にすむ。日本では東京上野の不忍池,京都の二条城の堀などで繁殖しているが,自然分布かどうか不明。中国では食材として珍重される。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
タウナギ
Monopterus albus
タウナギ目タウナギ科の魚。全長 1m。体は細長く,ほぼ円柱状で,尾部後端はとがる。眼はきわめて小さい。鰓孔は体の下面にあり,左右が一つになって 1個の裂孔をつくっている。胸鰭,腹鰭をもたない。本州各地(移入),中国,マレー半島,東インド諸島に分布する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by