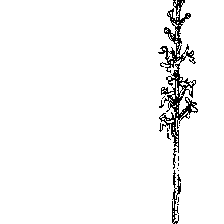トンボソウ
Tulotis ussuriensis Hara
盛夏のころ,黄緑色の目だたない小花をつけるじみな地生ラン。全草にいい香りがする。根茎および塊根は伸長して横走し,通常の植物の根とあまり異ならない。花茎は20~40cm。普通,葉は基部近くに2枚あり,狭倒卵形で長さ6~15cm,上部の葉は極端に小さくなる。7~8月に,やや密に10~20花をつける。花は黄緑色で,径約4mm。背萼片と花弁はかぶと状,側蕚片は開出する。唇弁は基部に小さな側裂片がある。距は細く,長さ5~6mm。北海道から九州までの温帯の湿地,草地,林縁に生える。朝鮮,中国,ウスリーに分布する。
植物体が大きく葉も広いヒロハノトンボソウT.asiatica Haraがおもに北海道に,葉がほそいソノハラトンボT.sonoharae Nachejimaが琉球に分布する。トンボソウ属は自然群であるが,広義のツレサギソウ属Platantheraに含まれる。
執筆者:井上 健
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
トンボソウ
とんぼそう / 蜻蛉草
[学] Platanthera ussuriensis (Regel et Maack) Maxim.
ラン科(APG分類:ラン科)の多年草。塊茎、塊根はあまり肥厚せず、横走する。茎は高さ20~30センチメートル、葉を数枚つける。下部の2枚の葉はやや対生状について大きく、上部の葉は小さくて目だたない。7~8月、径約4ミリメートルの目だたない黄緑色花を約10個開く。唇弁は基部の両側に小さな側裂片があり、5~6ミリメートルの細い距(きょ)がある。温帯の湿地や湿った林縁などに生え、北海道から九州、および朝鮮半島、中国東北部に分布する。名は、花の形がトンボを思わせるのでいう。
[井上 健 2019年5月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
トンボソウ(蜻蛉草)
トンボソウ
Tulotis ussuriensis
ラン科の多年草。日本全土の山地の林中に生える。根は紐状で,茎は細く高さ 15~35cm,なかほどに普通2枚の葉をつけ,上部にはごく小さな針状葉を数枚つける。7~8月,茎頂に総状花序をつくり,小さな淡緑色の花を 20個ほどつける。2個の側萼片は線形で左右に開出し,細長い距が垂れ下がって,花の全形がトンボを思わせるところからこの名がある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by