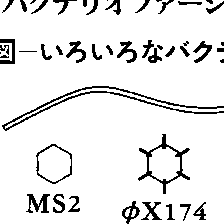精選版 日本国語大辞典 「バクテリオファージ」の意味・読み・例文・類語
バクテリオファージ
日本大百科全書(ニッポニカ) 「バクテリオファージ」の意味・わかりやすい解説
バクテリオファージ
ばくてりおふぁーじ
bacteriophage
細菌に寄生し、その菌体を溶かして増生するウイルス。細菌ウイルスと訳され、単にファージともよばれる。このウイルスは、カナダの細菌学者デレルF. d'Hérellによって発見され(1917)、「細菌を食べる」という意味からバクテリオファージと命名された。しかし、その後、これより2年前の1915年、すでにイギリスの細菌学者トウォートF. W. Twortによって同じものが発見されていたことが判明した。バクテリオファージの作用は、細菌の種に特異的に働く場合と広範な種にわたって働く場合とに分けられる。細菌に特異性があるバクテリオファージは、細菌のファージ型別(細菌の簡易的な鑑定)に用いられるし、作用が広範にわたるバクテリオファージでは、元来、溶菌しなかった細菌に対してこれを適応させ、より多くの細菌を感染させることができる。後者は、とくに分子生物学などでは意義をもつものである。
[曽根田正己]
増生のメカニズム
感受性細菌に感染したバクテリオファージは、その核酸を細菌細胞内に注入する。すると、細菌細胞内では、ただちにバクテリオファージの核酸が転写され、核酸が合成されていく。その後、細菌細胞においては、さらにコア・タンパク質(外殻のタンパク質)の合成が行われて、もとのバクテリオファージが形成される。このファージ形成がおこると細菌細胞は溶菌され、その結果、バクテリオファージは新たに遊離する。このようなファージ増生の機構は、宿主である細菌が増殖する間に進行するため、バクテリオファージによる溶菌作用は、急速な進行をみる結果となる。また、宿主の細菌を固体培地で培養し、バクテリオファージを感染させた場合には、これに特有の溶菌斑(はん)(プラークとよぶ)ができる。
[曽根田正己]
DNAファージとRNAファージ
バクテリオファージには、DNAファージとRNAファージの両者が知られている。大部分のDNAファージにおけるビリオン(細胞外で感染性を有するウイルス粒子)の核酸は、通常は2本鎖である(ときに1本鎖の例も認められる)。RNAファージの核酸は1本鎖であり、2本鎖は知られていない。また、バクテリオファージの多くのものは、ビリオンの核酸が多面体のカプシド(殻)の中に含まれている。多面体でないものはフィラメント状である。ビリオンの中の核酸は、螺旋(らせん)形のタンパク質構造体(いわゆる尾部)と連結している。これは吸着器官としての働きをもったものである。T系偶数ファージ(後述)の尾部は尾繊維からできており、付着装置(スパイク)となっている。
[曽根田正己]
病原性ファージと溶原性ファージ
バクテリオファージは、病原性ファージ(ビルレント・ファージvirulent phage)と溶原性ファージ(テンペレート・ファージtemperate phage)とに分類することもできる。病原性ファージは細菌細胞に感染するだけで、溶原化する(溶原菌になる)ことはできないが、ほとんどすべての感染した細胞(宿主細胞)を破壊することができるため、プラークは透明である。大腸菌を宿主とするT系ファージは病原性ファージの代表的なものである。一方、溶原性ファージは溶原菌から誘発し、生成されるファージであるため、宿主細胞を破壊することなく、宿主染色体1個当りに1個存在する。また、溶原性ファージは、細胞の増殖と同調して増生する遺伝因子プロファージ(潜在ファージ)となることがある。これは遺伝子の運搬者であり、ときには遺伝子そのものとしての意味をもつ場合もある。このようなプロファージをもつ細菌がいわゆる溶原菌であり、細菌が遺伝的なバクテリオファージを生産し、放出する性質を溶原性という。また、プロファージは、たいへん低い頻度ではあるが病原性ファージとなり、細菌細胞内で増生し、溶菌をおこし、成熟ファージを生ずることがある。
[曽根田正己]
T系ファージ
大腸菌病原ファージをT系ファージといい、T1からT7までの7種がある(Tはタイプの意)。T2、T4、T6の偶数番号のついたファージ(T偶数ファージという)は、偶然にも性質や形態に類似点が多く、また、DNA分子の多くの部分についても相似性のあることが証明されている。しかし、T1、T3、T5、T7の奇数番号がついたファージ(T奇数ファージ)についてはあまり相似性がみつかっていない。
[曽根田正己]
ラムダ・ファージ
λ(ラムダ)ファージと書く場合が多く、1953年、アメリカの微生物遺伝学者レーダーバーグJ. Lederbergらによって、大腸菌K12株に溶原化しているバクテリオファージとして発見された。λファージは、2本鎖DNAをもち、六角形の頭部と棒状の尾部により構成される。宿主は特定の大腸菌であり、感染後、溶菌経路をとる場合と、溶原経路をとる場合の二つがある。それぞれの経路の概要は次のようになる。(1)溶菌経路 〔1〕ウイルスDNAが健全な大腸菌に注入する。〔2〕そのDNAは環状となる。〔3〕環が転がるような状態をとりながら、多数のウイルス遺伝子のコピーを含む紐(ひも)状のものを形成する。〔4〕ウイルス遺伝子の情報によって、頭部や尾部のタンパク質を合成・集合し、1単位のDNAを頭部の中に詰め込む。〔5〕頭部と尾部が集合し、ファージ粒子が構成される。〔6〕感染後、約60分が経過すると、宿主の細菌細胞は溶菌し、100個以上のウイルス粒子が外に放出され、他の大腸菌に感染する。以上が溶菌経路であるが、この過程のなかで、条件によっては、ファージのDNA粒子は宿主細胞の中で生き続けることがある。これが溶原経路に入った状態であり、次のような経路をたどる。(2)溶原経路 〔1〕ファージDNAが宿主の細菌染色体の半永久的な一部に組み込まれる。〔2〕細胞分裂に伴ってDNAが複製され、娘(じょう)細胞へ分離継承されていく。〔3〕そのまま代を重ねて細菌細胞へと受け継がれていく。これがプロウイルス(潜在ウイルス)とよばれるもので、溶菌を誘起する能力を備えている。このようにみると、λウイルスはプロウイルスをもつ溶原性細菌といえる。なお、このプロウイルスをもつ細菌に紫外線やX線を照射、またはナイトロジェン・マスタード(窒素イペリット)や有機過酸化物などで処理すると溶菌経路へ移行する場合がある。
[曽根田正己]
バクテリオファージの採集と分離
バクテリオファージの採集と分離は、プラーク形成法によって行われる。この方法は特定の細菌の種類または菌株に対して、感染能力をもつバクテリオファージを自然界から採集し、分離するのに最適である。まず、自然界から特定の細菌が多く生息していると考えられる材料をとり、これを滅菌水に入れ、揺り動かしたあと、その上澄みを細菌濾過(ろか)するか、またはクロロホルム処理を行う(細菌や菌類はクロロホルムに対して弱いが、ファージビリオンは抵抗性がある)。これによって細胞性生物は取り除かれる。細胞性生物のなくなったものを特定の細菌の浮遊液と混合・希釈し、平板培養基上に接種する。これによって細菌集落が出現し、その集落表面にプラークが出現すれば、自然界から、その細菌に対するバクテリオファージを採集したこととなる。次に、このプラークから少量のものをとり、さらに平板培養をする。このような操作を繰り返すことによって、単一のバクテリオファージによるプラークの形成と分離が可能となる。
[曽根田正己]
改訂新版 世界大百科事典 「バクテリオファージ」の意味・わかりやすい解説
バクテリオファージ
bacteriophage
ウイルスのうち細菌に感染して増殖するものの総称。略してファージともいう。語義は,バクテリア(細菌)を食べる(ギリシア語phagein)ものという意味である。バクテリオファージは,トゥオートF.W.Twort(1915)とデレルF.H.d’Hérelle(1917)によりおのおの独立に発見された。はじめ,細菌性の伝染病の治療に役立つのではないかという点で注目されたが,まもなくこれは実用的でないことがわかり,バクテリオファージに対する人々の熱は冷めた。これを,1930年代に基礎生物学の研究材料として取り上げたのが,M.デルブリュックらのいわゆるファージ学派である。彼らは,生物の増殖原理を研究するための最も単純な材料という観点から,バクテリオファージを用いたのであった。この学派は,生体高分子の構造研究などの他の流れと合流し,今日に至る分子生物学の隆盛を築くことになる。また,1970年代以降では遺伝子工学に有用な道具としてファージ(とくにλファージ)が用いられている。
図に示すように,バクテリオファージにはいろいろな種類があるが,共通の構造上の特徴として,中心に遺伝子の本体である核酸(通常1分子)が存在し,その周囲を多数のタンパク質分子から成る外被がおおっている。細胞をもつ生物では遺伝子となる核酸はすべて二重鎖DNAであるが,バクテリオファージでは種類により,二重鎖DNAをもつもののほかに,単鎖DNA,二重鎖RNAや単鎖RNAをもつものもある。また,この核酸に含まれる遺伝子数は,小さなもので三つ,大きいものでは200余りである。
バクテリオファージは,外被タンパク質の一部により細菌細胞の外側に吸着する。吸着後,ほとんど核酸部分のみが細菌細胞内に入る。増殖の初期段階では,まずファージ遺伝子によりいくつかのタンパク質が合成され,これが細菌のタンパク質と協力して,ファージ核酸の複製を行う。次に,後期段階では,ファージの外被タンパク質や細菌細胞壁を溶解する酵素などが合成される。複製されたファージ核酸が外被タンパク質に包まれた後,溶菌が起こり,子孫ファージは細胞外に出る。このような一連の増殖過程を通じて,1匹のファージは数百匹に増える。
細胞をもつ通常の生物が,栄養分を吸収,代謝し,エネルギーを得て運動,化学合成などを行うのに対し,バクテリオファージを含むウイルスの仲間では,これらの働きはすべて宿主に依存している。バクテリオファージは,裸の遺伝子である核酸と,それを保護しかつ宿主細胞内に注入する外被タンパク質のみが独立した,生命の特殊な存在形態といえよう。
執筆者:桂 勲
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
化学辞典 第2版 「バクテリオファージ」の解説
バクテリオファージ
バクテリオファージ
bacteriophage
細菌に感染するウイルスのこと.細菌ウイルス,あるいは単にファージともいわれる.タンパク質と核酸(DNAまたはRNAのどちらか一方)とからなる.核酸としてDNAをもつものはDNAファージとよばれ,F.W. Twort(1915年),F. d'Hérelle(1917年)により発見された.RNAをもつRNAファージは,1961年,T. Loeb,N.D. Zinderにより発見された.ファージ粒子の大きさは直径20~90 nm 程度のもので,正多面体頭部と尾部よりなるおたまじゃくし形のもの,球状(正多面体)のもの,ひも状のものなどがある.おたまじゃくし形のT系ファージはとくに構造が明らかにされ,頭部にはDNAが格納され,注射針の役割をもつ尾部を通ってDNAが細菌中に注入される.このDNAは感染後複製するとともに,宿主菌のタンパク質合成系を自分自身のなかに保持する遺伝子の命令に従わせて,ファージ固有のタンパク質合成を行わせる.合成されたファージ核酸とファージタンパク質が結合して,完全なファージ粒子となり,同じくファージ合成の際につくられるファージリゾチームにより,宿主菌の細胞膜を壊して(溶菌),ファージが放出される.T偶数系ファージ以外では,この増殖機構が明らかになっていない部分も多い.また,入ったファージの核酸が,ある条件下でそのまま宿主菌細胞の染色体に組み込まれて,そのまま生存しつづけ(溶原化),誘発を受けるまで,菌染色体とともに複製され,子細胞に伝えられていく現象も見いだされている.このようなファージはテンペレートファージとよばれる.テンペレートファージは宿主菌に感染すると,そのときの条件によって溶菌させるか,また溶原化するかの二つの様式のどちらかの状態をとる(エピソーム).溶原化を起こさないファージはビルレントファージとよばれる.
出典 森北出版「化学辞典(第2版)」化学辞典 第2版について 情報
百科事典マイペディア 「バクテリオファージ」の意味・わかりやすい解説
バクテリオファージ
→関連項目エピソーム|形質導入|ジフテリア菌|プロファージ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「バクテリオファージ」の意味・わかりやすい解説
バクテリオファージ
bacteriophage
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
栄養・生化学辞典 「バクテリオファージ」の解説
バクテリオファージ
世界大百科事典(旧版)内のバクテリオファージの言及
【ウイルス】より
…そして53年のJ.D.ワトソンとF.H.C.クリックによるDNAの二重らせん構造の解明を契機として,分子生物学の飛躍的な発展がもたらされる。50年代に取り扱われたウイルスはバクテリオファージが中心であったが,60年代以降,これらの分子生物学の知見と,培養細胞によるウイルスの培養方法の確立とともに,動物ウイルスにも研究の目が注がれてきている。今日,ウイルス学が取り扱う範囲は,ウイルス自体についての形態形式,遺伝子構造と遺伝子の機能発現などだけにとどまらず,宿主細胞の側での遺伝子の構造と機能,発癌やウイルスの病原性を定めている遺伝子とその機能,ウイルスに対する防御機構などの研究にも及んでいる。…
※「バクテリオファージ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...