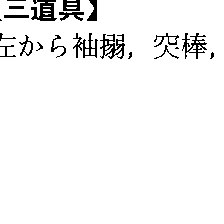みつ‐どうぐ‥ダウグ【三道具】
- 〘 名詞 〙
- ① 江戸時代、罪人を捕えるのに用いる三つの道具。突棒(つくぼう)・刺股(さすまた)・袖搦(そでがらみ)の称。
- [初出の実例]「同心等が三道具(ミツダウグ)を衝き立てて」(出典:最後の一句(1915)〈森鴎外〉)
- ② 拘禁に用いる三つの道具。手枷(てかせ)・足枷・首枷の称。
- ③ 三つの懐中道具。錐(きり)・小刀・鋏(はさみ)の称。
- ④ 三つの農具。鋤(すき)・鍬(くわ)・鎌(かま)の称。
- ⑤ 鯛の頭部にある、鋤・鍬・鎌に似た三つの骨。三つ骨。
- [初出の実例]「江戸浦の鯛を一枚進ぜるが、其三(ミ)つ道具(ダウグ)の鋤鍬をとった腕ぢゃあ切りにくからう」(出典:歌舞伎・群清滝贔屓勢力(1867)大切)
- ⑥ 和船が使う多数の船道具のうち、最も重要な三つのもの。近世の廻船ではふつう帆柱・帆桁・舵。また、帆桁の代わりに伝馬船を入れる場合も多く、幕末期以後はこの四つをもって「四つ道具」と呼ぶ。〔和漢船用集(1766)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
三道具 (みつどうぐ)
江戸時代における犯罪者逮捕のための3種の武器。袖搦(そでがらみ)(錑(もじり)),突棒(つくぼう),刺股(さすまた)をいう。いずれも長柄の捕道具(とりどうぐ)で,激しく抵抗する犯人を取り押さえるのに,六尺棒,梯子(はしご)などとともに用いた。警察権,刑罰権を象徴するものとして,見付,関所や辻番所に常備,また磔(はりつけ),火罪(火焙(ひあぶり))などの執行前にする引廻し(ひきまわし)の行列に連なった。晒(さらし)や獄門(ごくもん)の際にも,晒場(さらしば),刑場に飾り置かれた。(図)
執筆者:加藤 英明
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by