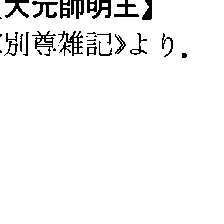関連語
精選版 日本国語大辞典 「大元帥明王」の意味・読み・例文・類語
だいげん‐みょうおう‥ミャウワウ【大元帥明王】
改訂新版 世界大百科事典 「大元帥明王」の意味・わかりやすい解説
大元帥明王 (だいげんすいみょうおう)
サンスクリット名Āṭavaka。大元帥阿吒薄俱(あたばく),阿吒婆拘鬼神大将などと漢訳されており,曠野の鬼神の意味である。大元明王ともいう。一切の悪鬼,悪毒獣,悪人による災難を衆生のために排除する夜叉大将であり,もとは外道神であったが後に密教にとり入れられて明王とされた。大元帥明王像は839年(承和6)に唐から帰国した常暁(?-865)によって初めて日本にもたらされた。大元帥法(だいげんのほう)は本像を本尊として護国,怨敵調伏のために行う修法であり,9世紀中ごろからは,真言院後七日御修法に準ずる国の大法となった。形像は四面八臂像が《阿吒婆拘鬼神大将上仏陀羅尼神呪経》に説かれ,善無畏訳の同経には四臂像も見られるが,これらとは異なる六面八臂像が常暁将来の像として伝えられている。黒青色の肉身,髑髏の首飾,手足にからませる蛇の臂釧(ひせん),忿怒(ふんぬ)の表情などにより表現される本尊は,最も畏怖を覚える忿怒像である。
執筆者:関口 正之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...