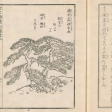精選版 日本国語大辞典 「花卉園芸」の意味・読み・例文・類語
かき‐えんげいクヮキヱンゲイ【花卉園芸】
- 〘 名詞 〙 花卉を対象とした園芸。観賞を主目的として、草、樹木などを栽培すること。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「花卉園芸」の意味・わかりやすい解説
花卉園芸
かきえんげい
花卉の栽培から観賞に即した利用までをいう。花卉の語句は従来いろいろと論議されてきたが、「花」は花を観賞する草本(草花)と木本(花木)を、「卉」は花に限らず、茎葉、枝条をも観賞する場合をさす。後者の範囲は観賞植物ということが多い。観賞の対象は、全植物体(個体と集合体)や切り枝などにつき、花、果実、茎葉、枝条その他の色彩、形状、香気などに及び、また利用は、切り枝によるいけ花、盛り花、コサージュ、花輪、一ないし数個体を器物に植える鉢物、集団の美観や教育に役だてる花壇、広場、街路、公園などへの植栽にわたる。前述の花壇ということばは長く定着してきたが、これは枠に囲まれ、限られた一部のスペースをさした。しかし現在では枠組みのないスペースも積極的に花を植え、広がりのある平面・空間・立体利用がされるようになり、花スペース、フロリスケープなどと表現されることが多くなりつつある。古代から食糧となる作物が第一で、花卉は副次的とされていたが、その後観賞の面が加わり、現代では、花卉の生産と消費が一国の文化を測る尺度であるとさえいわれるほどに進展した。日本では1983年(昭和58)開園の東京ディズニーランドに植えられた花と緑、同年から行われている全国都市緑化フェアの花展示、1990年(平成2)に大阪で開催された国際花と緑の博覧会での花展示と、その後全国で展開された花のまちづくり運動、そしてガーデニングブームの到来があった。
[川上幸男]
分類
花卉園芸は栽培の目的と利用の方途によって、次のように分類される。
[川上幸男]
営利栽培
生計をたてるため、専業または副業として経営する場合をさす。かつては副業としての小規模栽培が主体を占めていたが、1980年代からは、需要の増大、良質・安価を求める動向、生産費の低減化などを反映して、生産適地の選定、温室やビニルハウス・冷蔵施設の活用、電灯照明・暗幕被覆・薬剤処理その他による生育調節が進展し、また空輸も加わって、専業化は目覚ましく進んできた。1990年代以降の傾向として、日本では南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、南ヨーロッパ、中・南米など亜熱帯地域の花が輸入され、国内生産ともに年々増加していることが注目に値しよう。また国内においても栽培適地の北上がますます進んでいくと予想されている。1990年代末からはIT(情報技術)の普及により花に関する情報が広がり、今後の消費者サービスに大きな変化を求められている。それゆえ的確な学名表示の徹底と和名呼称の統一が迫られていよう。園芸、造園、植物各界の団体・個人が総合的にこの問題を解決することが肝要である。
[川上幸男]
趣味園芸
趣味として家庭で栽培する場合をいう。人々は花卉の栽培と観賞の過程で心がいやされ、生活に反映されるようになっている。また季節を追う生育状態に接して、自然の仕組みを体得し、そこに、趣味栽培の極致ともいうべき、自然との融和を感じ取り、精神的充足感が得られる。
[川上幸男]
公共利用
多数の人々を対象に、景観構成、教育、研究、慰楽などにわたる多様な目的をもたせて、公園、植物園、広場、斜面、遊休地、道路空間、森林空間などに植栽する場合であり、近年、その方面の重要性が一段と認められてきた。
[川上幸男]
歴史
日本
日本における花卉園芸の歴史は奈良時代にさかのぼることができる。『万葉集』には、「わが屋戸(やど)(宿)、わが庭前(にわ)」などとして、庭植えを明示した詩や歌が散見される。万葉人が詠み込んだ花卉は、日本原産のハギ、サクラ、カエデ、タチバナ、ツツジ、ヤマユリ、ササユリ、ボケ、サクラソウ、フジバカマ、渡来したシダレヤナギ、センダン、セキチク、ケイトウその他で、約160種に上る。平安時代に成立した多彩な王朝文学、とりわけ『枕草子(まくらのそうし)』と『源氏物語』にはそれぞれ100種に余る草木や花卉が四季の風物詩的に記されている。『源氏物語絵巻』にも庭植えの多くの花卉が図写された。王朝人はそれらの多種多様な草木を殿舎の前栽(せんざい)や壺(つぼ)(中庭)などに配植して、四季の眺めとした。
鎌倉時代には、入宋(にっそう)・入元した多数の僧侶(そうりょ)によって、仏教の新派(浄土宗、禅宗)、思想、文学、芸術その他の文化とともに、盆栽賞玩(しょうがん)の風習が導入された。室町時代にも盆栽は支配階層の間で珍重され、能楽『鉢の木』の曲譜にも郷士の好尚として取り上げられている。8代将軍足利義政(あしかがよしまさ)は、唐物(からもの)(大陸の文物)、茶事(さじ)、水墨画(すいぼくが)、立花(たてはな)(いけ花の古名)、作庭、盆栽、水石、盆景、盤景などの数奇(すき)に凝った。立花の流行は池坊(いけのぼう)専慶(初代、生没年不詳)、山科言国(やましなときくに)(1452―1503)、立阿弥(りゅうあみ)、台阿弥などの名手を生み、また花材の生産と集荷、新花の探索を促して花卉園芸の振興につながった。
江戸幕府の将軍徳川家康、秀忠(ひでただ)、家光(いえみつ)3代の無類の花好きは、大名、旗本の追随、奇花の献上を誘発し、参勤交代に伴った大名相互の交流がこれに拍車をかけた。4代家綱(いえつな)の治世以降、生活に余裕をもつようになった庶民も花卉を手がけるようになり、寛永(かんえい)のツバキ、元禄(げんろく)のボタン、ツツジ、サツキ、享保(きょうほう)のキク、カエデ、寛政(かんせい)のカラタチバナ、サクラ、サクラソウ、文化(ぶんか)の変化アサガオ、ユリ、文化・文政(ぶんかぶんせい)の斑入(ふいり)物、葉替り物、文政・天保(てんぽう)のマツバラン、フクジュソウ、セッコク、嘉永(かえい)・安政(あんせい)の変化アサガオなどが現れた。その結果、日本の園芸を世界的に特徴づける多彩な花卉が成立し、また多様な園芸書が版行された。その園芸書の一つ、長生舎主人(ちょうせいしゃしゅじん)(本名栗原信充(くりはらのぶみつ)、(1794―1870))編の『金生樹譜別録(きんせいじゅふべつろく)』(1830)は盆栽・庭樹の栽培法や各地の巨樹名木を解説した本であるが、そのなかには、文化・文政のころに大名から庶民に至るまでが、一攫(いっかく)千金の夢をかけて「金生樹(かねのなるき)」である珍花異木を求めて奔走した世情が如実に記されている。多くの園芸書は、辺地の山野、離島に産する希種、珍種をも収載したが、その背景には本草(ほんぞう)学(現在の系統分類学)の隆昌(りゅうしょう)があった。文政のころにはいけ花が公家(くげ)や武家ばかりでなく、町人の間にも広まった。その結果、花材の生産と集荷の組織化が進み、また、冬越し用の唐窖(からむろ)、煉瓦(れんが)窖、穴窖、フレーム温床や掘抜き井戸水の掛け流しなどによる早出し、冷温な井戸内を活用する晩(おそ)出しがくふうされた。
明治の新政府が打ち出した文明開化の施策により、伝統的な花卉の多くが、美術品その他とともに、欧風化の波、好事家の没落などによって消え去った。その反面、欧米人が日本独自の花卉を高く評価したところから、日本人はそれらを再認識することになり、文化遺産のかなりのものが、からくも消滅の危機を免れた。明治初期には、日本で最初のガラス温室が西欧人によって建てられ、熱帯性のランや観葉植物の栽培も始められた。大規模な営利栽培は、大正の中ごろ、シクラメンの鉢物、バラとカーネーションの切り花などの需要が急増したのを受けて、温室村で知られた多摩川畔の田園調布に専業の大温室が林立したところから始まった。第二次世界大戦後、人々の生活が豊かになってからは、花卉の栽培と利用は、営利、趣味、公共利用の多様な面に行き渡り、その展開を裏づける指導と研究も目覚ましく進んできた。
[川上幸男]
外国
外国における発達はギリシア・ローマ時代にさかのぼる。ホメロスの『オデュッセイア』では、オデュッセウスがフェイシアンの王アルキノオスの庭を訪れているが、その庭は囲まれた緑の園で、真っ赤なリンゴが輝いていたというから、この王が伝説的な園芸のパイオニアではないかといわれている。この園はいまのイタリアのコーク島にあったという。紀元前1600年ごろのクレタ島の壁画には、庭と公園があり、アイリス、クロッカスなどが見える。前373年ごろに生まれたテオフラストスは植物学の父といわれるが、実際に園芸家でもあった。1世紀にはディオスコリデスが『薬物誌』De materia medicaでいろいろな木、草、果樹などを紹介した。とくにアイリスの記述はすばらしいといわれている。この書はルネサンスの時代を経てもなお強い影響力をもった。
13世紀にはベネチアのマルコ・ポーロが長年中国に滞在して園芸技術を修得していたのではないかといわれている。16世紀にはコルテスがメキシコを征服し、その際の記録によると、多数の樹木、草花、ラン、バラやテラスのある庭があった。これによると、メキシコの庭にはヨーロッパにはないような薬草、花卉、芳香木などがあった。メキシコ原産のダリア、ヒャクニチソウ、マリーゴールド、コスモス、ランなどは後年ヨーロッパへ花卉として移入された。たとえば、マリーゴールドはフレンチ種が1573年に、アフリカン種が1596年にヨーロッパへ、日本へは前種が1684年(貞享1)、後種が寛永年間(1624~1644)に渡来している。今でもスウェーデンのウプサラにあるリンネガーデンには、この二つの原種が保全・栽植されている。
1597年にはジョン・ジェラルドJohn Gerard(1545―1612)が独自の本草書を出した。彼はエリザベス1世に仕えて多くの園芸種のコレクションをもっていた。マリーゴールド、東洋産の最初のヒヤシンス、南ヨーロッパ産のアネモネ、グラジオラス、ライラックなどが有名である。
世界でもっとも古い植物園の一つはイタリアのベネチアの近くにあるパドバ大学植物園(1545年創設)であるが、18世紀に至る間、初期のヒヤシンスやチューリップなどがこの植物園を通じてヨーロッパ各地に紹介された。北アメリカからのモクレン属の一種も1750年には植えられていた。1635年にはフランスにパリ植物園の前身の薬草園ができた。
1621年のイギリスのオックスフォード大学植物園のカタログには1600に及ぶバラエティーに富んだ草花の種類が載っており、とくにプリムラなどはよくそろっていた。いかに花卉園芸の技術の水準が高かったかがうかがい知れる。1673年創立のイギリスのチェルシー薬草園も花卉園芸の発達に大いに貢献し、とくに優れた園芸家フィリップ・ミラーPhilip Miller(1691―1771)を生んだ。ミラーは球根の水耕栽培や昆虫による受粉を重視した最初の人であり、園内の自生のワタの種子をジョージア州に送り、現代のアメリカをワタの国にまでした人でもある。1670年ごろ、薬草園として創立のエジンバラ王立植物園も1683年に園内植物2000種のカタログを出し、園芸のパイオニアとしての基礎をつくり、のちに多くの高山植物やプリムラ属、リンドウ属、ユリ属、シャクナゲ属などを主として中国から取り寄せ、花卉園芸の発達に大いに貢献した。
ロンドン郊外のキュー王立植物園は1759年にジョージ3世の母、オーガスタ皇太妃が広大な王室の庭を植物園の基礎として築いたことから世に知られるようになったが、その後多くの園芸家が輩出し、現在でも世界の園芸植物の記録や紹介の中心となっている。有名なウィリアム・アイトンWilliam Aiton(1731―1793)が創刊した『ホルトス・キューエンシス』(キュー植物譜)は1789年に初めて刊行された。この本の歴史的価値が高いのは、移入された植物の日付を克明に記していることにある。ウィリアム・カーチスWilliam Curtis(1746―1799)が創刊した『ボタニカル・マガジン』(1984年~1994年は『キュー・マガジン』、1995年に元の『ボタニカル・マガジン』と誌名変更)は原色図入りの記載で、『キューエンシス』とともに現在でも連綿として続刊されている花卉園芸の貴重な文献といえよう。
現代ではオランダのチューリップの例でみられるような高度の園芸が発達し、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカなどのバラの新品種の育成、カーネーション、キク、ダリアなどの花卉の改良が進んだ。定期的に開催されるイギリスのチェルシー・フラワー・ショーやオランダのフロリアードなど年ごとの進歩発展の姿も著しい。
今日では各種の施設、設備の発達と、生物学、遺伝子工学などの急速な進歩に伴い、花卉園芸植物の組織培養、水耕栽培などが一般化され、近い将来には遺伝子融合などによる画期的な新品種創出が夢みられている。
[川上幸男]
花卉の生産動向
日本の花卉生産は第二次世界大戦前からわずかに行われていたが、本格的に生産が広まったのは戦後である。消費地に近い都市近郊と冬季温暖な暖地、夏季冷涼な高冷地から花卉の栽培が始まった。最初は露地栽培が主であったが、1953年(昭和28)ころビニルが開発されてビニルハウスが普及し、さらにガラス温室も加わり施設園芸が増加した。
1960年代に入ると、日本の経済成長と国民生活の安定により花卉の需要も増加し、国の花卉振興対策や農業団体の指導援助もあって全国的に花卉産地の育成に力を注ぎ、農園芸のなかでも成長産業として伸び続けた。栽培の多い切り花を中心に、国内各地に農業協同組合(JA)などの指導団体が生産者をまとめた集団産地や、生産者による産地組合などいわゆる大型産地が育成されて共同で品質別に格付けして荷造りし、出荷する共選共販体制が出現した。このように産地別に大量の花卉が大都市に出荷されるため、取引する卸売市場も、大型化した中央卸売市場が東京都や大阪府など、消費の中心都市に生まれた。1964年の全国の花卉生産額は146億円であったが、1980年には1565億円、1998年(平成10)には6346億円に達している。1998年における日本の花卉生産の内訳は切り花が42%、鉢物が17%、花木類が35%、花壇苗は1.2%などである。
この間、世界的に技術も急速に進歩し、花卉の生産体制も大きく変わってきた。なかでも細胞組織から個体を無菌的に大量増殖する組織培養が1970年ころから普及し、ガーベラ、リモニウム、観葉植物などは短期大量増殖で無菌苗が供給され、栽培が容易になった。また、セル成形苗生産システム(プラグ苗システム)はセルトレイに自動的に播種(はしゅ)し、育苗する播種育苗を自動化したシステムで花卉栽培の繁殖育苗を画期的に改善し、育苗と仕上げ栽培を分業化した。さらに花卉産業の発達により、新しい品種の開発も進んだ。従来の育種技術に加え新しい分子育種では異種間の遺伝子を組み替えることで新花色の品種が開発されている。1995年にサントリーが開発した青いカーネーションなどはその例である。また花卉の多くの品種は一代雑種(F1)品種になるが、カーネーション、ガーベラなどの植物体の一部分を用いて殖やすことのできる栄養繁殖系花卉のなかには育成者の権利が保護される登録品種(一般にパテント品種などともいう)など知的財産権で世界的に権利が保護されるようになった。この背景には花卉生産のグローバル化がある。南米のコロンビアやアフリカのケニアなど開発途上国を中心に国際的な切り花大産地が1980年ころから生まれ、前者は北米、後者はヨーロッパへ多量の切り花を周年輸出するようになった。また近年は日本近隣の中国、韓国、東南アジア各国にも国際花卉産地が育成されて日本の花卉生産者に脅威を与えている。
需要とともに伸び続けた日本の花卉生産も、1990年のバブル経済の崩壊により花の業務需要などが極度に落ち込んだ。そのため、もっと家庭消費を増やすため一般の人々が手ごろな値段で買えるようなカジュアルフラワーが提唱された。同時期に家庭消費が伸びだし、1995年ころにはガーデニングブームが到来した。従来の花や野菜などを育て楽しむ趣味の園芸から、花や緑で演出して住まいや暮らしを楽しむガーデニングに変わり、女性を含む若い層がその牽引(けんいん)力になったことが特色である。また、イングリッシュ・ガーデンやコンテナフラワー、ハンギング・バスケットなどが普及した。サントリーが1989年に発売したサフィニアもこれらのブームの引き金になったともいわれている。これにより花壇苗の需要が伸び、ホームセンターやガーデンセンターなどの量販店のフラワービジネスも発展した。もちろん花壇苗生産も各地に増加した。
21世紀に入って花卉園芸も、地球環境の保全や景観形成に寄与する産業に発展するものとして世界的に期待されている。
[鶴島久男]
『最新園芸大辞典編集委員会編『最新園芸大辞典』全13巻(1982~1984・誠文堂新光社)』▽『塚本洋太郎著『花卉総論』第21版(1992・養賢堂)』▽『川上幸男著『花の造園――都市空間のフロリスケープ』(1996・経済調査会)』▽『鶴島久男著『新編花卉園芸ハンドブック』第7版(2000・養賢堂)』▽『山田幸子著『12カ月花づくり庭しごと――ガーデニングカレンダー』(2000・講談社)』▽『大川清著『花卉園芸総論』改訂版(2009・養賢堂)』
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「花卉園芸」の意味・わかりやすい解説
花卉園芸
かきえんげい
floriculture
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の花卉園芸の言及
【園芸】より
…果樹,野菜,観賞用植物などを資本と労力をかけて集約的に栽培することで,対象とする作物の種類によって,果樹園芸,野菜園芸,花卉(かき)園芸に分類される。また,生産物の販売を目的とする園芸を生産園芸,趣味として行う園芸を趣味園芸,または家庭園芸という。…
※「花卉園芸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...