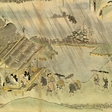精選版 日本国語大辞典 「雨具」の意味・読み・例文・類語
あま‐ぐ【雨具】
- 〘 名詞 〙 雨の日に身につけるレインコート、傘、雨靴、高げたなど、雨よけの衣類や道具の総称。
- [初出の実例]「天に雲ないに雨具(グ)を持たせられたぞ」(出典:詩学大成抄(1558‐70頃)一)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「雨具」の意味・わかりやすい解説
雨具
あまぐ
雨や雪の際に用いる衣類や道具類の総称。雨着類、雨傘(笠(かさ))類、雨靴類の3種に大別できる。日本では古くから蓑(みの)を雨具として用いていたが、これは『信貴山縁起(しぎさんえんぎ)』をはじめ、いろいろの絵巻物からも知ることができる。蓑のことを「けら」とよんでいたのは、昆虫のケラにその形態が似ていたことによる。雨具としてはこのほか油衣(ゆい)あるいは桐油紙(とうゆがみ)を用いていた。雨具に大きな変化がもたらされたのは、16世紀に入って南蛮の服飾文化が導入されてからである。なかでも羅紗(らしゃ)製の合羽(かっぱ)が伝えられ、広げると円形をなすところから、これを丸合羽あるいは坊主合羽とよんで戦国武将の間で用いられた。羅紗は輸入品であったので、のちに布帛(ふはく)を用いて、日本的に仕立て、これを引き回し、あるいは回し合羽と称して道中用に多く用いた。また紙製のものは、紙に柿渋(かきしぶ)を引き、上から桐油(きりゆ)を塗って桐油(とうゆ)合羽あるいは赤合羽と称して徒士(かち)以下の低い身分の者が用いた。参勤交代のおりには道中のにわか雨に備え、これを入れた合羽籠(かご)を担いで歩いた。
丸合羽は、袖(そで)の長い日本の着物には不便なところから、着物仕立てのものが考案され、これを袖合羽とよんだ。最初は羅紗仕立てであったが、のちに高級織物を用いてつくられ、被布(ひふ)と称した。この袖合羽は身丈(みたけ)の長短により、長合羽、半合羽といい、丈にも流行の変化があった。それとともに裂地(きれじ)も布帛に移り、金持ち以外は木綿を用いることが多かった。また衿(えり)の形にも変化があり、餌差(えさ)し(鳥刺し)の着るものを鷹匠(たかしょう)合羽といい、その衿は今日の道行衿(みちゆきえり)の源となった。
幕末に開港してから欧米文化がもたらされて、新しい服装文化が入り、雨具界にも新風がおこった。明治初頭の鳶(とんび)合羽(略してトンビ)は、腰蓑と背蓑とをあわせて羅紗で仕立てたものである。これはのちに二重回しと変わり、丸合羽はマントに転じていった。また日本人の服装が洋装化するにつれて、外套(がいとう)が軍人の間で用いられると、雨用としてレインコートが生まれ、和服用は雨ゴートといわれるようになった。その素材も絹、木綿、化繊さらにビニルまで各種のものが用いられる。雨ゴートの特色は対丈(ついたけ)の道行仕立てで、当初はサージやセルの素材を用いたが、のちには専用布地ができた。雨をはじくように細い番手の糸を緻密(ちみつ)に織り、繻子(しゅす)、玉虫(たまむし)織、紬(つむぎ)類、夏用には紗(しゃ)などのほか着尺(きじゃく)地を防水加工したものが用いられる。服飾全体の好みにあわせてその形態、色彩、模様、素材は時代とともに変化していくようである。
[遠藤 武]
世界の雨具の歴史
降水量が比較的少ないヨーロッパでは、雨よけのみを目的とする雨具類は、それほど必要とされなかった。したがって、外出や旅行の際に着られた外衣や被(かぶ)り物が、防寒や防風や防塵(ぼうじん)だけでなく、防雨の役目もしてきたわけである。雨具の必要性が高まったのは、人々が戸外生活を楽しみ始め、スポーツが盛んになった19世紀のことであり、雨傘が発案され普及したのもこのころである。
古代や中世を通じて肩にかけられた四角形や半円形の毛織物の布は、寒さや雨を避けてくれたうえ、夜は毛布がわりにもなった。このようなマント形式の外衣や頭巾(ずきん)やショールの類が活用された範囲は広く、歴史も古い。さらに、時代によってさまざまなスタイル変化をみせた羅紗や皮革製の男性コート類や、ブリムのある帽子なども、適宜この目的に使用されたことはいうまでもない。
毛織物は確かに水よけに適した材料だったが、水の浸透は避けられなかった。この点を改良するためのくふうは、防水布の需要が高まった19世紀に盛んになり、1823年にはイギリスのチャールズ・マッキントッシュが、ゴム引き布(インディア・ラバー・クロス)の特許をとり、コートをつくった。しかし、ゴム引きは通気性がないために蒸れやすく、においも強くて着心地はよくなかった。その後も防水技術の改良は進み、20世紀初めには通気性のあるウォータープルーフ商品をバーバリー社が開発している。戸外スポーツやドライブ(当初は無蓋車(むがいしゃ)だった)の際はもとより、戦場の軍服にも防水加工は必要だった。第一次世界大戦中の長期にわたった塹壕(ざんごう)戦で、イギリス軍が採用した綿ギャバジンの防水コートは、トレンチ(塹壕の意味)・コートとよばれて戦後急速に市民服に広まり、レインコートやダスターコートの基本スタイルとして現在も定着している。
[辻ますみ]
現在の雨具
合成繊維の開発から生まれたナイロンやビニルのシートやフィルムは、通気性がないために湿気がこもるという欠点はあったが、防水性に優れて軽く、加工もしやすかったために、レインコートをはじめ、レインハット、レインシューズ、雨傘の材料として利用されてきた。衣類の防水加工は、通気性があったほうが快適であるから、水をはじく撥水(はっすい)加工が一般的である。繊維表面に疎水(そすい)性物質を付着させる(一時的防水)か結合させる(永久的)加工法で、ピリジウム塩、シリコン樹脂、フッ素樹脂などが用いられる。糸のすきまをビニル系やウレタン系の樹脂で固めてしまう加工は、完全防水になるが通気性はなく、袋物や帆布に用いられる。
[辻ますみ]
『喜多川守貞編『類聚近世風俗志』(1934・更生閣)』
改訂新版 世界大百科事典 「雨具」の意味・わかりやすい解説
雨具 (あまぐ)
雨降りの外出や労働のさい身に着ける外衣,かぶりもの,履物などの総称。蓑,合羽,笠,傘,レインコート,帽子,足駄(高下駄),雨靴などがある。わら,スゲ,海藻などの植物,防水加工を施した紙や布,ゴム,ナイロンなど撥水性のある素材で作られる。雨具は気候,風土により素材,種類に変化がみられる。降水量の多い日本では,雨具は必需品で,古くは《日本書紀》に蓑笠が記されている。水を吸うと膨張し,乾燥すると縮む植物の性質を利用した蓑や笠は,雨具が洋装化する今日まで農山漁村での労働,外出に着用された。また白絹に油を引いた雨衣(あまぎぬ)は,中世の貴族たちが装束の上から着け,修験者は油紙製の雨皮(あまかわ)を用いた。雨皮は油単(ゆたん)とも呼ばれ,牛車や輿にも掛けられた。16世紀にポルトガルからカパが入り,ラシャ,木綿の合羽や和紙に桐油を塗った紙合羽が用いられた。しかし町人,農民はラシャの合羽を着ることは禁じられた。雨皮,雨羽織(木綿の合羽)などが庶民の雨具で,女性は江戸中期まではゆかたを雨よけに用いていたが,後に女合羽というものがつくられた。油紙を張った傘は江戸時代には広く雨傘として用いられ,蛇の目傘,番傘が流行した。明治初期にはこうもり傘が輸入された。
西欧では日本と同様,蓑などの植物性雨具が原初的なものであったが,多くはケープやマント類が雨具としての役割を兼ねていた。近代に入り,イギリスのマッキントッシュやバーバリーによるゴム引布,防水布の発明から今日のレインコートが生まれてきた。現代では合成繊維や防水技術の進歩に伴い,雨具の素材,デザイン,色調など多様になり,携帯用のものもあらわれている。
→笠 →傘 →合羽 →蓑 →レインコート
執筆者:池田 孝江
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
普及版 字通 「雨具」の読み・字形・画数・意味
【雨具】うぐ
字通「雨」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...