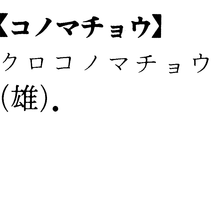コノマチョウ (木の間蝶)
鱗翅目ジャノメチョウ科コノマチョウ属Melanitisに属する昆虫の総称。主として木陰に生活する。アフリカ大陸からアジア南部,ニューギニアにかけて12種が知られ,日本にはクロコノマチョウM.phedimaとウスイロコノマチョウM.ledaの2種を産する。クロコノマチョウは開張7~8.5cm。ヒマラヤ,東南アジアから日本まで広がり,日本ではほぼ静岡県から南九州にわたって暖地の森林に生息する。年2~3回発生し,10~11月に羽化する最後の世代が秋型となって成虫のまま越冬する。翅の裏面の色彩は,夏型では樹皮状,秋型では枯葉状で,それぞれ止まる場所の環境に溶けあってみごとな保護色をしている。幼虫の食草は,おもにススキ,ジュズダマなどのイネ科植物。分布の北限付近では個体数が大きく変動し,静岡県下では,1955~60年と80年に大発生が見られた。ウスイロコノマチョウは開張6~7cmとやや小型で色彩は明るく,熱帯に広く分布し,日本では南西諸島に土着している。
執筆者:高橋 真弓
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
コノマチョウ
Melanitis
鱗翅目ジャノメチョウ科コノマチョウ属の昆虫の総称。昼間はほとんど活動せず,日没前後にせわしく飛立つ性質がある。前翅端はやや後方に突出し,後翅は尾状の突起をもつ。東南アジアに広く分布する。日本では,南から北上し静岡県まで分布するクロコノマチョウ M.phedimaと,南西諸島のウスイロコノマチョウ M.ledaとが知られる。いずれも暗褐色で,前翅の中央と先端の間に2白紋を含んだ大きな黒紋がある。お互いによく似ており区別がむずかしいが,ウスイロコノマチョウの夏型では裏面の眼状紋が大型で発達しているなどの違いがある。クロコノマチョウは3化性で6~11月にみられ,幼虫の食草はススキ,ジュズダマなど。ウスイロコノマチョウは多化性で一年中みられ,幼虫はサトウキビ,イネ,オヒシバなどを食べる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
コノマチョウ
このまちょう / 木間蝶
昆虫綱鱗翅(りんし)目ジャノメチョウ科のメラニティス属Melanitisの名称。第二次世界大戦前に日本でコノマチョウとよんでいたものは、現在のウスイロコノマチョウのほかにクロコノマチョウの一部(秋型)を誤って含んでおり、これを明確にするためにコノマチョウの名はメラニティス属の基名として使用され、種名としては用いられなくなった。
[白水 隆]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by