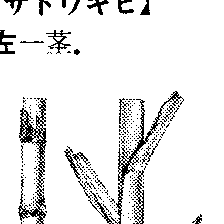サトウキビ
さとうきび / 砂糖黍
[学] Saccharum officinarum L.
イネ科(APG分類:イネ科)の熱帯生の多年草。カンショ(甘蔗)ともいう。温帯で栽培されるサトウダイコンと並んで、砂糖をとる植物としてもっとも重要な作物である。高さ3~6メートルで、茎は根元で直径3~5センチメートルになる。茎には10~20センチメートル置きに節があり、各節から長さ1メートル以上もの葉がつく。葉は堅く、その両縁はかみそりのようで、皮膚を傷つける。秋、茎頂に長さ50センチメートルもある大きい穂を出し、多数の小花をつけると、花穂が灰白色になり、巨大なススキの花のようになる。種子は長さ1ミリメートルに満たない小粒で、発芽しにくい。茎は堅い薄皮に包まれ、内部は白い柔組織が充満している。穂が出る前、茎の柔組織細胞の汁液にショ糖が蓄えられ始め、成熟時には汁液の10~20%に達する。発芽から10~15か月が収穫期で、鉈(なた)で地際から茎を切り倒し、茎の頂部と葉を切り除いたのち、圧搾機で汁液を絞り取る。
収穫後の刈り株からふたたび芽を出させて栽培を続けるほか、新植には茎を2~3節の長さに切って横たえて植え付けると、節から芽と根が出る。
サトウキビは北回帰線(北緯23度27分)のやや北から南回帰線(南緯23度27分)あたりまでが栽培範囲で、現在はブラジル、インド、中国、タイ、パキスタン、メキシコが主産地であり、全世界で年産18億9066万トン(2016)ほどの茎が収穫される。日本では沖縄県や奄美(あまみ)大島で栽培されるが、生産は少なく、157万トン(2016)程度で、外国から粗糖を輸入して需要の大部分をまかなっている。
[星川清親 2019年8月20日]
ニューギニアとその周辺が起源地で、紀元前1万5000~前8000年に栽培化されたとしているが、栽培化の根拠はない。祖先種はボルネオ島からニュー・ヘブリデス諸島に自生するローバスタム種S. robustum Brandes et Jeswiet(サトウキビ属の1種)である。本種は広く東南アジアに分布するスポンタニウム種(和名はサトウキビ属のワセオバナ)とススキ属のトキワススキMiscanthus floridulus (Labill.) Warb.との自然雑種によってニューギニアで成立した。このローバスタム種から、糖分が多く繊維質が少ないノーブル・ケインと称する品種群がつくられた。これが前500~後1000年に太平洋の島々に伝播(でんぱ)した。
またこの品種群は前20世紀ころインドに伝播し、スポンタニウム種との自然雑種によってシネンセ種(カラサトウキビ)S. sinense Roxb.が、インド在来種として成立した。これはシン・ケインとよばれ、インド北東部と中国南部で、モンスーンの季節によく繁茂し、砂糖生産の実をあげた。このシン・ケインは前3世紀にヨーロッパへ、後7~8世紀に地中海沿岸地域へ伝播し、さらに10~15世紀に地中海沿岸からアフリカ東部および西海岸に伝播した。
アメリカ大陸へは、コロンブスが1494年に西インド諸島に導入し、その後16世紀以降、中南米地域に伝播した。中国大陸へはインドから1世紀ころに、台湾へは17世紀のオランダ統治時代に、日本へは17世紀初めに奄美大島に入った。
19世紀に入って、ジャワのパスルアン試験場において、オランダ人によって、マレーシア先住民が栽培していたノーブル・ケイン系の品種群と野生種などとの交雑育種が進められ、その結果、優良品種群の作出に成功した。現在これらの品種群が世界各地のサトウキビ栽培地域に再導入されている。
[田中正武 2019年8月20日]
サトウキビは、野生のサトウキビの一種であるローバスタムと、トキワススキとの雑種起源という説が近年出されている。1880年以降は、ワセオバナなど5種の相互交雑により品種が改良された。中国ではカラサトウキビ(チュウゴクサトウキビ)S. sinensis Roxb. emend. jeswietを唐時代から栽培しており、その栽培技術や砂糖の製法は厳重な管理下に置かれていた。これが日本へ伝えられたのは明(みん)の時代で、一説によると、船が難破して福建省に漂着した奄美(あまみ)大島の直川智(すなおかわち)という人物が、ひそかに製法を学び取り、1610年(慶長15)に3本の苗を隠して持ち帰ったのが最初と伝えられる。奄美大島の大和(やまと)村には、直川智を祀(まつ)る開饒(ひらとみ)神社がある。また江戸後期、サトウキビは薩摩(さつま)藩の重要な財源となり、明治維新を裏で支えた。
[湯浅浩史 2019年8月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
サトウキビ (砂糖黍)
sugar cane
Saccharum officinarum L.
別名カンショ(甘蔗。かんしゃの慣用読み)。糖料作物として重要なイネ科の大型の多年草。茎は円柱形で直立し,多くの節をもち,高さ2~4m,直径は太いものになると4cm以上となり,外皮は蠟物質でおおわれる。葉は各節に互生し,葉鞘(ようしよう)は茎を抱き,葉身は長さ0.5~1m,幅1.5~5cm。成熟すると茎頂に長さ50~60cmになる大型の円錐花序をつける。1穂に2万4000~3万の小穂があるが,一般に自家不稔である。小穂は両性の1花からなり,種子はきわめて小さく,長さ1mmにみたない。
原産はインドのガンジス川沿岸と考えられていたが,ニューギニア原産で,熱帯太平洋の島々や東南アジアに古くに栽培が広がり,各地で種間雑種が生じ,現在の栽培サトウキビnoble caneが作り出され,それが現在では全世界の熱帯で広く栽培されるようになったと推定される。企業的なプランテーションで大規模栽培されているのも,そのような交雑によって育成された品種群である。しかし,1609年に,中国福建省から奄美大島に初めて渡来したサトウキビは,やや細い茎で繊維も多いチクシャ(竹蔗)S.sinense Roxb.と中国で呼ばれる型のもので,この種はインドから中国大陸南部で古くから栽培されていたものである。明治時代台湾を領有した日本は,台湾製糖会社を設立して,台湾でのカンショ栽培を企業化して,国内の砂糖の需要に応じた。そのため内地での栽培はすたれたが,第2次大戦後,鹿児島県の島嶼(とうしよ)部や沖縄地域で栽培がさかんになった。主要生産国はインド,ブラジル,キューバ,パキスタン,メキシコ,中国など。日本の生産量は需要の1/10にみたず,年間約270万tを輸入している。
サトウキビは年平均気温が20℃以上必要で,17~18℃の等温線が栽培の限界といわれ,現在の栽培分布域は北緯35°から南緯37°の間にある。また年間降雨量は1200~2000mmぐらいが最適で,生育期間に多く,成熟期にはやや乾燥することが必要である。茎を2~3節に切って植えつけると,節から発芽,発根する。また収穫後の切株から再び芽をもえ出させる株出し法も行われる。一般に,植えてから1年ないし1年数ヵ月で収穫期となる。出穂前,茎の成熟につれて糖濃度が高まり,10~20%になった時期に刈り取る。収穫はなたで地ぎわから刈る。最近は機械(ケーンハーベスター)が普及してきた。刈った茎から葉をとり除く作業を省力化するため,ハワイなどでは畑に火を放って葉を焼き払ってから機械で刈る。頂部と葉を除いた茎は,ただちに工場に運ばれ,汁液(粗糖汁)を絞りとる。粗糖汁はいくつかの工程を経て精製,結晶化され,精製砂糖が生産される。
サトウキビの野生種には,ボルネオからニューギニア,さらにニューヘブリデスに分布するS.robustum Brandes & Jesw.ex Grassl.とアフリカからインド,東南アジア,南西太平洋諸島にまで広く分布するS.spontaneum L.の2種がある。前者はマレーシアからポリネシアに栽培されていたサトウキビnoble caneの,また後者はインドから中国大陸や東南アジアの一部で栽培されていたサトウキビ(竹蔗)のもとになった種であるが,現在の栽培サトウキビは栽培の2種と野生2種との間の交雑がくり返された結果作り上げられたもので,その染色体数も80本から140本をこえる倍数性や異数性を示している。
→砂糖
執筆者:星川 清親
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
サトウキビ
カンショ(甘蔗。かんしゃの慣用読み)とも。インド原産のイネ科の多年生作物で,テンサイとともに砂糖の重要原料。茎は直立し,高さ3.5m内外,径2〜4cm,多数の節と節間からなり,節間には多量のショ糖をたくわえる。栽培は熱帯の年平均気温24〜25℃,降水量1500〜2000mmの所が最適で,キューバ,ブラジル,インドなどで生産量が多い。茎のしぼり汁から砂糖をとり,副産物として得られる糖蜜はラム酒やアルコールの原料,しぼりかす(バガス)は燃料,パルプ原料,飼料とする。
→関連項目砂糖|製糖業|糖料作物|バレンシア(ベネズエラ)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
サトウキビ(甘蔗)
サトウキビ
Saccharum officinarum; sugar cane
イネ科の多年草。東アジアの熱帯原産と推定される。砂糖の原料植物としてキューバ,オーストラリア,台湾をはじめ南方地域で大規模に栽培されている。日本でもかつて四国 (特に香川) や熊本で栽培され,また南西諸島や小笠原諸島でも栽培されたが,現在はほとんどを輸入原糖に頼っている。茎は高さ2~4m,直径2~5cm,中実の円柱状で表面は緑色,黄緑色,紅紫色などで,さらに白色のろう物質でおおわれる。茎は 10~20%のショ糖を含み,そのまま噛んで甘い汁を吸うこともある。出穂直前の時期に茎を刈取り,圧縮してそのしぼり汁から原糖をとる。この原糖から煮沸,濃縮,結晶化を繰返して精製し,白砂糖をつくる。しぼり汁を発酵させた酒を糖酎といい,さらにこれを蒸留したものがラム酒で,西インド諸島で多く産する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
サトウキビ
[Saccharum officinarum].カヤツリグサ目イネ科サトウキビ属の植物で,茎からショ糖(カンショ糖)をとる.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のサトウキビの言及
【砂糖】より
…
【種類】
砂糖は原料植物,製造法,製品などによって,それぞれ異なった分類がされる。
[原料による分類]
原料植物による分類で,カンショ糖([サトウキビ]),テンサイ糖([テンサイ]。ビート糖ともいう)が代表的なもの。…
【マデイラ[諸島]】より
…雨は冬に集中し夏は乾燥する。1420年ごろポルトガル人により発見され,数年後植民が行われてからサトウキビ,ブドウ,小麦の栽培が盛んとなり,砂糖が重要な貿易品となった。発見以来,南アメリカ,アフリカとポルトガルを結ぶ航路の中継港として重要な役割を果たした。…
※「サトウキビ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by