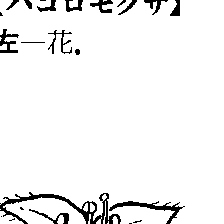ハゴロモグサ (羽衣草)
Alchemilla vulgaris L.
円心形の葉をつけるバラ科のまれにみられる高山植物。根茎はやや太い多年草で,根出葉は長柄がある。草丈10~30cmで,全体に毛が生えている。夏に散房状集散花序を出し,直径3mmくらいの小さい花をつける。花弁はなく,萼片および副萼片は4枚で,黄緑色である。おしべ4本,めしべ1本。果実は瘦果(そうか)で,萼筒につつまれたままである。この種は北半球の周極地方に点在的に分布し,日本では北海道の夕張岳と本州の南北アルプス高山帯の草原にみられ,氷河時代の残存植物とみなされている。和名は,英名のlady’s mantleを意訳し,牧野富太郎が考えだしたといわれている。ヨーロッパの植物と日本のものが同じ種かどうか,再検討される必要があると思われ,その結果,学名が変更される可能性もある。
執筆者:鳴橋 直弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ハゴロモグサ
はごろもぐさ / 羽衣草
lady's mantle
[学] Alchemilla japonica Nakai et Hara
バラ科(APG分類:バラ科)の多年草。根茎は太い。高さ約30センチメートル。葉は単葉で円心形から腎臓(じんぞう)形、縁(へり)は浅く7~9裂し、両面に毛を密生する。長い葉柄がある。7~8月、茎の先に径約3ミリメートルの花をやや密に開く。花弁はなく、黄緑色の4枚の萼片(がくへん)と副萼片がある。雄しべは4本。名は英語名に由来するといわれる。果実は痩果(そうか)。中部地方の高山、北海道の夕張(ゆうばり)岳に分布する。
ハゴロモグサ属は、おもに温帯の高山に250種ほどあり、花弁はなく、雄しべは2本または4本、雌しべは1~4本。子房は下位で、萼筒に包まれる。
[鳴橋直弘 2020年1月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ハゴロモグサ(羽衣草)
ハゴロモグサ
Alchemilla japonica
バラ科の多年草で,本州中部と北海道の夕張岳の高山草原にまれに生える。夏に黄緑色の小花を集散状につける。バラ科には珍しく4数性の花をつけ萼片4,副萼4,花弁はなくおしべも4本である。ヨーロッパアルプスをはじめ北半球の亜寒帯や温帯の高山に同属のものが数十種あり,その1種に対するヨーロッパの俗名レディズマントルを意訳したのが和名である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by