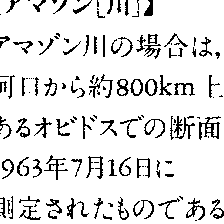翻訳|Amazon
精選版 日本国語大辞典 「アマゾン川」の意味・読み・例文・類語
アマゾン‐がわ‥がは【アマゾン川】
- ( アマゾンはAmazon ) 南アメリカ北部の大河。アンデス山脈に源を発し、ブラジル北部を東流して大西洋に注ぐ。流域は熱帯多雨で密林を形成。全長六三〇〇キロメートル。流域面積約七〇五万平方キロメートル。水量、流域面積は世界第一位、長さは世界第二位。
日本大百科全書(ニッポニカ) 「アマゾン川」の意味・わかりやすい解説
アマゾン川
あまぞんがわ
Amazon
南アメリカのアンデス山脈に発し、ほぼ赤道に沿って東流して大西洋に注ぐ大河。ポルトガル(ブラジル)語ではRio Amazonas、スペイン語ではRío Amazonasという。延長6300キロメートルはアフリカのナイル川よりわずかに短いが、約650万平方キロメートルという流域面積(トカンティンス川流域を除く)は世界一で、第2位のコンゴ川(ザイール川)の2倍に近い。その下流域(全流域の約3分の2)はブラジル領内にあるが、本・支流の上流域はボリビア、ペルー、エクアドル、コロンビア、ベネズエラ、ガイアナの諸国に及んでいる。本流上流部のペルー領内では、マラニョン川とウカヤリ川の二大肢節が合流してアマゾン川になる。しかし、下ってブラジル領内に入ると、しばらくの区間ソリモンエス川とよばれたのち、マナウスにおけるネグロ川との合流点以下でふたたびアマゾン川となる。主要な支流としては、北岸からくるナポ川、プトマヨ‐イサ川、カケタ‐ジャプラ川、ネグロ川、南岸から流入するマデイラ川、プルス川、ジュルアー川、タパジョス川、シングー川などがある。
1541年エクアドルのキトからアマゾン川上流部の探検に入ったゴンサロ・ピサロGonzalo Pizarro(スペインの征服者、フランシスコ・ピサロの弟、1506?―1548)の部下であるフランシスコ・デ・オレリャーナFrancisco de Orellana(1511―1546)が、図らずもその上流から河口までの航行に成功し、この川の存在が世に知られるようになった。その途中、先住民を率いて来襲してきた色白の女戦士の集団があったとの報告が人々の興味をひき、これがギリシア神話に出てくる女性の集団アマゾンに似ていることから、アマゾン川の名が生じた。
[松本栄次]
自然
アマゾン川本流の川幅は、ソリモンエス川とよばれる区間では1~4キロメートル、マナウスより下流部では平均4~5キロメートル、最大で10キロメートルほどである。ただし、増水期には川沿いの低地(バルゼア)が冠水し、川幅は著しく拡大して、所によっては50キロメートルにもなる。本流の水深は大きく、河道の横断面中の最深部の水深は一般に60~90メートル、所によっては120メートル近くに達する。水面の勾配(こうばい)はきわめて緩やかで、水面高度は河口から約1450キロメートル上流のマナウスで22メートル、3450キロメートル上流のイキトスで約100メートルに達するにすぎない。流域の中心部には、標高200メートル以下の低平なアマゾン平原が東西に広がり、流域北部のギアナ高地と南部のブラジル高原とを隔てている。アマゾン平原はおもに新生代の堆積(たいせき)物よりなるのに対し、ギアナ高地とブラジル高原は先カンブリア時代の結晶質岩よりなる古い地塊である。アマゾン平原は流域西部では南北に幅を増し、不明瞭(ふめいりょう)な分水界をもって北のオリノコ平野および南のラ・プラタ川流域の平野と接する。とくに支流ネグロ川へは、オリノコ上流の水の一部が天然の運河カシキアレ水路を通じて流入しているほどで、両水系上流部の分水界は画然としない。流域の西端部には6000メートル級の高峰を多くもつアンデスの褶曲(しゅうきょく)山脈が横たわり、本流の源流部をなす。
アマゾン川流域のうち、ネグロ川、プルス川以西アンデス山麓(さんろく)までの範囲は、年間を通じて高温多雨の典型的な赤道雨林気候の地域であるが、このほかの地域には大なり小なり乾季が介在する。しかし、乾季が2~3か月以下の地域は、赤道雨林に覆われている。ブラジル高原の中心部にあたる流域南部とギアナ高地の一部(ロライマ地方)は乾季が4~5か月に及ぶサバナ気候で、セラードとよばれるサバナ植生が生育している。流域周辺部のこのような雨季と乾季の交替を反映し、アマゾン川の水位には著しい季節変化がみられる。5~6月が最増水期、10~11月が最渇水期となる。水位変化は、中流部のマナウスでは、平均10.8メートルである。アマゾン川の流量については1963年と1967年の増水期にオビドス付近で実測がなされ、それぞれ毎秒21万6340立方メートルおよび22万7075立方メートルであった。したがって河口部における増水期の平年流量は毎秒25万立方メートル前後と推定されている。
アマゾン川の本・支流沿いには、増水期には水没するバルゼアvárzeaとよばれる沖積低地が続いている。バルゼアには無数の湖沼や水路があり、これらは地域住民の交通路として重要であるとともに漁業資源の宝庫でもある。とくに、世界最大の淡水魚といわれるピラルクーは動物タンパク源として利用価値が高い。本流沿いのバルゼアの幅は河口部では200キロメートル以上もあるが、ほかでは、ウカヤリ、マラニョン両川の合流点付近で約80キロメートルある以外あまり広くなく、所によって数百メートルから約50キロメートルの間を変化する。
アマゾン川の支流には、本流と同様、多量の泥を浮遊させ黄色に濁った水の川(地元では「白い川」とよぶ)と、有機物の分解したコロイドを含み、しょうゆのような色を呈するが澄んだ水の川(「黒い川」)とがある。後者の例としては、イキトス、マナウス、サンタレンでそれぞれ本流に合流するナナイ、ネグロ、タパジョスの諸河川などがあげられる。「黒い川」の水には川沿いに堆積すべき泥がほとんど含まれていないため、川沿いにバルゼアや中州の発達が悪い。このため、川の流路は常時水に浸った森林(イガポ林)中を蛇行して流れるか、あるいは一見堰止湖(せきとめこ)を思わせる「リアス河岸」ともいうべき入り江の多い河岸をもった幅広い水面をなしていることが多い。バルゼアの背後には、テラ・フィルメterra firmeとよばれる、急な崖(がけ)をもち増水時にも水に浸ることのない台地が横たわり、これがアマゾン平原の大部分を占めている。この台地は一般に川の水面より10~30メートル程度高く、第三紀の陸成堆積物で構成されている。この台地上には、テラ・フィルメ林とよばれる典型的熱帯雨林が生育し、その下に黄色ラトソルをはじめとする各種のラトソルや赤黄色ポドゾルなどの酸性土壌が発達する。
[松本栄次]
産業・交通
アマゾン川流域全域で普遍的な生産活動としては、キャッサバ、トウモロコシ、米を主体とする自給的農業と、天然に自生するゴム、ブラジルナッツ、ヤシ、木材などの植物資源の採集とが主要なものである。とくに流域の天然ゴムはパラ・ゴムとよばれ、20世紀初頭までは世界で独占的地位にあり、その積出し港であったベレン、マナウス、イキトスなどは当時ゴムブームでにぎわった。商品作物ではベレン周辺とくにトメ・アスーなどの黒コショウ栽培と、中流部のバルゼアで広く行われているジュートの栽培が重要であり、ともに日本人移住者の努力により当地に導入されたものである。また同じ地域のバルゼア、マラジョ島の低湿地草原、ロライマ地方およびベレン周辺では牧畜が盛んである。鉱産物では、河口部北岸アマパ直轄領のマンガン、マデイラ川流域ポルト・ベーリョ付近の錫(すず)の採鉱がおもなものである。河口部南岸、シングー、トカンティンス両水系間には莫大(ばくだい)な埋蔵量をもつカラジャス鉄山があり、開発計画が進められている。タパジョス川中流、グルピ川、ジャリ川上流などではときどき砂金の採取ブームがおこる。上流域のアンデス山脈東麓(とうろく)沿いには20世紀後半になって油田が相次いで発見され、アンデス諸国の経済を潤している。おもな油田地域としては、コロンビア、エクアドル国境付近のプトマヨ川、ナポ川流域、ペルーのマラニョン川北部流域とプカルパ付近、ボリビアのサンタ・クルス周辺などである。
アマゾン川流域は全般的に人口希薄地域であり、ブラジルのアマゾン地方(北部地方)全体で1平方キロメートル当り2.92人(1996)、ペルーのアマゾン低地地方(セルバ地方)で1.9人前後であるが、源流部のアンデス山中では1平方キロメートル当り10~40人と人口密度は高い。アマゾン低地では従来水上交通が唯一の交通手段であったため、集落はすべて川沿いに分布している。しかし、近年主要都市間の航空路の発達が顕著であるとともに、道路交通網の整備も進みつつある。ブラジルでは、1960年代から1970年代にかけてベレン、サンタレン、マナウスの三大都市がブラジル南部の中心地域と道路で結ばれたほか、アマゾン川南岸を東西にペルー国境近くまで延びるアマゾン横断道路も完成した。ペルーでは、ウカヤリ川沿岸のプカルパからアンデス山脈を越えて太平洋岸に至る道路が通じている。
[松本栄次]
植物
アマゾンの植生は、温暖な気候と豊富な水によって、質、量ともに他に類をみないほど豊かである。森林の高木層を構成する樹種は、アメリカやヨーロッパの落葉広葉樹林の14倍以上にも達する。マナウス地方で、1メートル以上の高さをもつ植物を調べたところ、草本種を除くと、100平方メートルに935の個体が生育し、21科61種の植物からなることがわかった。さらにマナウス地方の植物相は77.6%が木本種(25科69種)で、草本種は6.7%(6科11種)にすぎないことも調査された。アマゾン流域を空から見ると、森林は青緑色の波のうねりのように見え、そのなかに灰色(落葉した樹木)、黄色や紫色(開花している樹木)の点が見られ、相観的には非常によく似た林相であるが、構成種は地域によって大きな違いがあるようである。
アマゾンの多雨林は、ドイツの自然科学者フンボルトによってヒラエア・アマゾニカとよばれ、ときには樹高が90メートル(平均46~55メートル)、周囲が12メートルを超す巨大な太さになるものがある。つるを樹木に絡ませて、まっすぐに伸びているものと、地表面をくねくねとはっているものとがあり、森林全体がつる植物に絡まれているように見えるが、樹幹に害を及ぼすようなことはない。つる植物のなかには、ガラナPaullinia cupanaのような有用植物(種子から、多量のカフェインを含むガラナ飲料をつくる)もある。そのほか、アマゾンの経済に重要な役割をもつ種が多く、ヤシの仲間のオオミテングヤシMauritia flexuosaは、果実を食用、果汁からワイン、髄はパンの代用、繊維は漁網、綱、ハンモックとして、葉は屋根葺(ふ)き用、幹は建材に用いられる。さらに、低地の多湿地にはカカオTheobroma cacao、ブラジルナッツBertholletia excelsaをはじめ、ゴム原料となる植物(科はいろいろ分類される)などがある。現在、アマゾンには原生林がわずかしか残っておらず、ほとんど人間の手で破壊されてしまっている。
[大賀宣彦]
動物
アマゾン川には、固有の水生哺乳(ほにゅう)類であるアマゾンマナティー、アマゾンカワイルカ、コビトイルカ、爬虫(はちゅう)類で淡水カメのアラウ、淡水魚のピラルクー(別名アラパイマ)などがすむ。コビトイルカはクジラ類中最小であるが、アラウとピラルクーは、この川にすむ哺乳類のオオカワウソ、齧歯(げっし)類のカピバラ、大蛇のアナコンダとともに、それぞれの類で世界最大の種として名高い。このほか爬虫類では、ワニ類のカイマンとカメ類のマタマタ、両生類ではコモリガエル(別名ピパ)、肺魚のレピドシレン、猛魚のピラニア、熱帯魚として知られるネオンテトラなどのテトラ類、水鳥のヒロハシサギ、ジャノメドリなどがみられる。
川を縁どる森林には、クモザル、ホエザルなど30種以上の広鼻猿類、3種のナマケモノ、ヒメアリクイ、コンゴウインコなど40種以上のインコ類、オオハシ、ヘビ類のエメラルドボア、ツルヘビなど樹冠層で生活するものが多い。地上生の有蹄(ゆうてい)類はブラジルバク、シカ類のマザマジカとオジロジカ、2種のペッカリーと、ほかの地域に比べて少なく、大形のものをみない。このほか、パカ、オオアリクイ、数種のアルマジロ、コミミイヌ、マーゲー、オセロット、ジャガー、チスイコウモリほか約100種の翼手(よくしゅ)類、有袋(ゆうたい)類のオポッサム類(8属約35種)、サルを捕食するオウギワシ、アブラヨタカ、多くのハチドリ、アリドリ、マイコドリ、ツメバケイ(ホアチン)、巨大な毒蛇ブッシュマスター、猛毒のヤドクガエル、トリトリグモ、華麗なモルフォチョウなどが森林を彩っている。
[今泉吉典]
流域の先住民
アマゾン盆地(アマゾニア)の先住民は多岐にわたる。言語の分布だけをみても、大きな語族だけで、トゥピ・グァラニ、ジェ、アラワク、カリブ、トゥカノ、パノ、タカナと並べ立てることができ、その他これらの大語族に分類されていない言語を話す集団が多数ある。このうちジェはブラジル中央高原、トゥカノはコロンビア、パノとタカナはペルー、ボリビアと比較的地域的にまとまっているが、他は広い地域に分散し、他の語族のものと境を接している。また、社会構造や宗教観念も部族ごとにさまざまで、アマゾン先住民という一つのタイプを抽出するのはなかなかむずかしい。しかし、アマゾン先住民にはある共通性が存在するのは確かであり、氾濫原(はんらんげん)(バルゼア)か、高台(テラ・フィルメ)か、また熱帯雨林かサバナかといった居住地の地勢、植生によって程度の差はみられるものの、基本的な同質性を指摘することができる。
その第一は、生業が焼畑耕作に、狩猟、漁労、野生食物の採集を組み合わせたものであるということである。土地の条件がよいバルゼアでは、焼畑耕作の比重が高く、森が川のそばの狭い範囲に限定されるサバナ地域では狩猟採集の重要性が増すが、上記の四つの生業を組み合わせて初めて生活が成り立つ。とくに、多くの地域でおもな作物である有毒マニオクは、成分がほとんど純粋のデンプンであるため、タンパク質は狩猟や漁労で得た獲物からとらなければならない。また有毒マニオクの根には多量の青酸が含まれているため、擦りおろし、絞り、乾かすという手続が不可欠で、この技術も有毒マニオクを栽培する部族の間ではほとんど共通している。
第二は、村落連合を超える大きな政治組織が存在しないことである。生産力が高いバルゼアや海岸部では、集落の人口が1000人を超える場合もあったが、通常は人口500人以下の小さなものであった。村落どうしはしばしば敵対し、襲撃や女性の略奪も起こった。このため、アマゾン先住民の人口密度は低く抑えられ、生態系を破壊するような土地利用は行われなかった。
最後に、アマゾン先住民は、白人侵入以後の外圧に対し非常にもろかった。組織された大きな抵抗は起こらず、各個撃破され、免疫のない伝染病のために多くの者が死んだ。現在では、アマゾン先住民の多くが固有の文化を失いつつあり、一部はラテンアメリカ混血社会の最下層に沈んでいこうとしているが、民族としての意識を高め、文化を復興し、先住民区の設定を求める文化社会運動も多くの地域で行われている。
[木村秀雄]
『多田文男編『アマゾンの自然と社会』(1957・東京大学出版会)』▽『ハードン著、泉靖一訳『世界探検全集 6 アマゾン探検記』(1977・河出書房新社)』▽『A・R・ウォレス著、長沢純夫・大曽根静香訳『アマゾン河探検記』(1998・青土社)』▽『神田錬蔵著『アマゾン河』(中公新書)』▽『西沢利栄・小池洋一著『アマゾン――生態と開発』(岩波新書)』
改訂新版 世界大百科事典 「アマゾン川」の意味・わかりやすい解説
アマゾン[川]
Rio Amazônas
南アメリカ大陸の大河で,その流域面積は日本の国土の約18倍,650万km2ほどもあって,世界第1位である。ペルー・アンデスに源をもつこの川は,多くの支流とともに山脈の東斜面を激しく開析し,深い峡谷を通ってアマゾン低地へと流れ下り,大西洋にそそぐ。河口までのその長さについては,いくつもの数値が発表されているが,本流ぞいで約6770km,ナイル川に次ぐ世界第2の長さである。
この大河は,1500年2月ポルトガル生れのピンソンVicente Yáñez Pinzón(?-1515)によって発見されたのであるが,ピンソンは大西洋を大陸ぞいに航海中偶然に淡水の流れに遭遇し,川の流れのあることを知り,〈あまい海(マール・ドゥルセ)〉と名付け,約80km上流までさかのぼったという。その後,スペイン生れのフランシスコ・デ・オレリャーナFrancisco de Orellana(1511-46)は,エクアドルのキトを出発,雪のアンデスを越え,ナポ川の支流コカ川を下った。河口に達した1542年8月26日までの約9ヵ月間,エル・ドラド(黄金郷)を求めての苦難に満ちたアマゾン探索であった。この間オレリャーナの探検隊一行は左岸から合流するインキのように黒い大きな川を発見し,これにネグロ川と名を付けた。さらに,1542年6月24日には,2時間足らずではあったが,インディオと壮絶な戦いをした。この戦いでインディオの女たちがあまりにも勇敢であったので,彼女たちはギリシア神話のアマゾン(女戦士)ではないかと考えたことが,同行したカルバハル神父の記録にみられる。そしてこの話が本国などに伝わり,アマゾンがこの大河の名前になったのである。
一般に,アマゾン川の名で呼ばれているこの大河は,本流ぞいにアンデス山地の源流からイキトスまでをマラニョン川,ここからネグロ川の合流点までをソリモンエス川,そして河口までをアマゾナスと呼んだりする。また支流もさまざまで,その長さが1000kmを超えるものが20にも及び,中でもマデイラ川は全長3350km,ジュルア川は約3300km,プルス川は約3150km,ネグロ川とタパジョス川はともに約2000kmと,長大な支流が多い。さらにアマゾン川は,その勾配がきわめて小さく,河口から1450km上流のマナウスで標高が約30mであるし,3800km上流のペルーのイキトスでさえ標高は約80mにすぎない。そのうえ,この川は川幅も広く,河口付近では約100km,オビドスやサンタレンでは約30kmと狭くなるが,マナウス近くでは80~90kmと再び川幅は広くなる。加えて水深も大きく,川幅が狭いところでは90mにも達するが,平均すると10m前後である。以上のように勾配が緩やかで,水深も大きいため,本流はもちろんのこと支流でも大型船舶の航行が可能で,喫水6mの船はマナウスまで,喫水4mの船でさえイキトスまでも遡航することができる。また,マデイラ川でも1290kmまで大型船の航行が可能である。なお,大型船の航行が頻繁で川幅の広いアマゾン川では,水上のガソリン・ステーションが見られる。
このように大型船舶の航行が可能であるとはいえ,年間の水位変化は大きく,マナウス港ではそれが10m以上にもなるので,桟橋はこの水位変化に対応できる浮桟橋になっている。水位の最高は,マナウスやベレンなど中・下流域での雨季が盛りを過ぎた6月ころに出現し,11月の初めに水位は最低になる。このような水位変化は,バルゼアと呼ばれる氾濫原をつくり,その面積は日本の国土の約7分の1の5万km2にも達する。
アマゾン川水系の水の色は,3種類に分けられる。第1はネグロ川に代表されるような〈黒い水〉の川である。この黒褐色の水は川ぞいの湿地で有機物が分解してできたコロイド状の溶存物質が多いためで,酸性も強く,栄養塩類の少ない不毛の川で〈飢餓の川(リオス・デ・フォーメ)〉とも呼ばれている。第2は〈白い水〉の川で,これらの川はアンデス山地やその山麓地域の土壌を浸食し,粘土などを豊富に溶かしていて透明度は小さく,中性ないし弱アルカリ性の川である。アマゾン川本流および支流のマデイラ川に代表され,〈満腹の川(リオス・ファルトス)〉とも呼ばれる川で,豊富な浮遊物質を毎年バルゼアに堆積させて土壌を若返らせている。この〈白い水〉の本流と〈黒い水〉のネグロ川は,マナウスの下流で合流するのであるが,両方の水は4kmも混合することなく流下し,両川の色の対照はみごとである。第3は〈透明な水〉または〈緑の水〉で,タパジョス川に代表され,ギアナ高地やマト・グロッソ高地から流れてくる川である。タパジョス川では,6mもある川底の物がはっきりと見ることができるほど透明である。この種の川は,〈黒い水〉の川と同様に栄養塩類に乏しく,酸性ではあるが,酸素を消費するような微生物が少ないので,水中生物の生存に好適である。
アマゾン川には,身長が5mにもなるという淡水魚として世界最大のピラルク,獰猛な殺し屋ピラニアなど約1300種の魚が生息している。魚の種類が多いこともさることながら,アマゾン川が世界のどの川をも近づけないのは,流量の多いことである。その量はザイール川の4~5倍,ミシシッピ川の約8~12倍,ナイル川の約40倍もあり,世界における全河川流量の15~20%を占めると推定されている。
→アマゾニア
執筆者:西沢 利栄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アマゾン川」の意味・わかりやすい解説
アマゾン川
アマゾンがわ
Amazon River
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
山川 世界史小辞典 改訂新版 「アマゾン川」の解説
アマゾン川(アマゾンがわ)
Amazonas
オリノコ川,ラ・プラタ川とともに,南アメリカの三大水系をなす大河。全長約6400kmでナイル川に次ぎ,流域面積は705万km2で世界第1位。1541~42年に支流のナポ川から河口まで航下したオレリャナが,途中で交戦した長髪の戦士をギリシア神話の女戦士アマゾンだと思って命名したという。19世紀後半から20世紀にかけて,流域は世界最大のゴムの産地であった。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報
世界大百科事典(旧版)内のアマゾン川の言及
【アマゾニア】より
…アマゾン川流域のアマゾニアは,西はアンデス山脈,北はギアナ高地,そして南はブラジル高原に囲まれた地域で,その面積は約650万km2の広大な地域を占める。
【自然環境】
アマゾン河谷は上流へ漏斗状に大きく開き,第三紀層の堆積物でおおわれた平野である。…
【バルゼア】より
…川が運んでくる浮遊物質が堆積し,土壌が更新されるのでよく農業に利用される。ブラジルのアマゾン川流域のものが世界的に有名で,その面積は6万4400km2もあると推定され,これはベルギーの国土面積のほぼ2倍に相当する。雨量は多いが,乾季と雨季で水位の変化が大きいアマゾン川,流域の大半が半乾燥地帯で占められ,乾季と雨季が明瞭なブラジル北東地域を流れるサン・フランシスコ川やパルナイバ川の流域では,バルゼアを利用した農業が行われている。…
【ラテン・アメリカ美術】より
…エクアドルでは前3000年ごろのバルディビア文化以来土器の伝統が長く,チョレラ,グアンガラ,エスメラルダスなどの地方様式が生まれている。 オリノコ川やアマゾン川流域の熱帯低地ではメソアメリカからアンデスにかけての高文化地域に比べ見劣りがするが,バランコイド,マラジョアラ,サンタレンなどの文化伝統のもと,手のこんだ装飾土器が作られた。また16世紀のアマゾン中流部では,彩色土器が作られ,その見事さはスペイン人を驚かせている。…
※「アマゾン川」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...