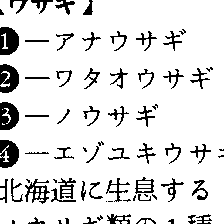日本大百科全書(ニッポニカ) 「ウサギ」の意味・わかりやすい解説
ウサギ
うさぎ / 兎
hare
rabbit
広義には哺乳(ほにゅう)綱ウサギ目に属する動物の総称で、狭義にはそのうちのウサギ科の総称であるが、一般には、さらにそのうちのノウサギ亜科に属する仲間をよぶことが多い。ウサギ類という総称でもよばれる。ウサギ目Lagomorphaは最近まで齧歯目(げっしもく)Rodentiaのなかの亜目とされていたが、齧歯類が4本の切歯(門歯)、すなわち、のみ歯があるのに対して、上あごの大きな1対の切歯の背方に小形に退化した1対の切歯が余分にあることを最大の特徴として区別され、現在では別の目とされている。ウサギ目にはナキウサギ科Ochotonidae(英名パイカ)とウサギ科Leporidaeがあり、ウサギ科にはムカシウサギ亜科Paleolaginaeとノウサギ亜科Leporinaeがある。
一般にウサギとよばれているノウサギ亜科にはノウサギやカイウサギが含まれる。イエウサギの名でもよばれるカイウサギrabbitはこの亜科に属するが、いわゆるノウサギhareと属を異にし、本来ヨーロッパ中部および南部、アフリカ北部にかけて生息していたアナウサギrabbit(ヨーロッパアナウサギOryctolagus cuniculus)を馴化(じゅんか)したもので、世界各地で改良、飼育されている。
[澤崎 徹]
野生のウサギ
ノウサギ類は、アナウサギ類に比べ前肢がやや長いため、座ったときの姿勢が斜めになる。穴を掘らずに地上に巣をつくり、そこに子を産む。生まれたばかりの子は、毛が生えそろっていて、目も見え、すぐに歩き回ることができる。ノウサギ類は、オーストラリア、ニュージーランドなどを除き、世界中ほとんどの地域でごく普通にみられる。たとえば、北極圏やアラスカにはホッキョクノウサギLepus arcticusやアラスカノウサギL. othusが、また、ヨーロッパに共通のノウサギとしてヨーロッパノウサギL. europaeusが分布するなど、多種が広く生息する。日本には、北海道にエゾユキウサギ(エゾノウサギ)L. timidus ainuがいるほか、ノウサギL. brachyurusの4亜種、すなわち、本州の日本海側と東北地方にトウホクノウサギ(エチゴウサギ)L. b. angustidensが、福島県の太平洋沿岸地方より南の本州、四国、九州地方にキュウシュウノウサギL. b. brachyurusが、さらに隠岐(おき)島と佐渡島に、それぞれオキノウサギL. b. okiensisとサドノウサギL. b. lyoniがあり、合計5種が生息する。エゾユキウサギと他の4種とは異なるノウサギ亜属に属し、エゾユキウサギは、ヨーロッパ、シベリア、モンゴル、中国東北部、樺太(からふと)(サハリン)など亜寒帯から寒帯にかけて広くすんでいるユキウサギの亜種である。ユキウサギは本種、亜種とも冬になると被毛が純白になる。一方、別の亜属に分類されるトウホクノウサギ、サドノウサギも冬毛は純白になるが、白くならないキュウシュウノウサギ、オキノウサギと同一グループとされる。世界でこれと同じ亜属に属するウサギは、中国東北部の東部とウスリー地方の狭い地域に分布するマンシュウノウサギL. mandchuricusだけである。
アナウサギ類は、ノウサギ類に比べ前肢が短いため、座ったときの姿勢が低く、体が地面と平行になる。さらにアナウサギの名のとおり、地中に穴を掘って巣をつくり、群れをなして生活する。この地下街は、「ウサギの町」と称されるほど大規模な巣穴となる。妊娠した雌は分娩(ぶんべん)用の巣をここにつくり、生まれた子は、目が開いていず、赤裸であることもノウサギと異なっている。
ローマ人たちは、壁に囲われた庭に、とらえたヨーロッパアナウサギを飼育していた。アナウサギはノウサギと異なり、このような人為的な環境下でも子を産み育てるから、数は増え、食肉用として飼育された。中世になると、帆船によって広く世界の各地に運ばれていった。これは、航海中の食糧を求める手段として、各航路の島々にヨーロッパアナウサギをカイウサギとして土着させるためであった。一般的環境、つまり気候や、餌(えさ)となる植生が適し、さらに害敵(肉食獣など)がいない土地では急速にその数を増していった。オーストラリア大陸には元来アナウサギ類は生息していなかったが、1859年にビクトリア州に導入されると、たちまちその数を増やし、1890年ごろには、この地域におけるアナウサギの数は2000万頭と推定されるようになった。アナウサギの餌は草や若木の樹皮、畑の農作物であるから、被害は膨大なものになり、手に負えぬやっかい者になった。害を防ぐため、さまざまな手段が実施されたが、効果はなかった。1950年ごろからウサギの粘液腫(しゅ)ウイルス(全身皮下に腫瘤(しゅりゅう)を形成し、死亡率が高く、伝染力も強い)を用いた駆除法が成功し、近年はその被害も少なくなってきている。
日本には、奄美(あまみ)大島、徳之島特産のアマミノクロウサギPentalagus furnessiがおり、特別天然記念物に指定されている。穴を掘って巣をつくるところはアナウサギ類に似るが、耳の長さは半分以下で、体全体もずんぐりしている。アマミノクロウサギは「生きている化石」とよばれる動物の1種で、近縁としてメキシコ市近くの山にいるメキシコウサギRomerolagus diazziとアフリカ南部にいるアカウサギ属のプロノウサギPronolagus crassicaudatusなどとともにムカシウサギ亜科Palaeolaginaeに分類されている。
[澤崎 徹]
家畜としてのカイウサギ
カイウサギは、ヨーロッパアナウサギを馴養することに始まった。その後、大きさ、毛色、毛の長さ、毛の手触りなど、多様な変異を利用し、選抜淘汰(とうた)を繰り返して、多くの品種を作出してきた。用途によって、毛用種、肉用種、毛皮用種、肉・毛皮兼用種、愛玩(あいがん)用種に分けられる。
毛用種としてはアンゴラAngoraがよく知られている。トルコのアンゴラ地方が原産といわれ、イギリスやフランスで改良されたものが現在飼養されている。体重は、前者が2.7キログラム、後者が3.6キログラムである。全身が長い毛で覆われており、年に3~5回の剪毛(せんもう)で約500グラムの産毛量がある。白色毛がもっとも商品価値が高く、高級な織物や毛糸に加工される。
肉用種としてはベルジアンノウサギBelgian hareや、フレミッシュジャイアントFlemish giantなどがある。前者はベルギー原産で体重3.6キログラム、ノウサギに似た毛色をしているのでこの名がある。後者は「フランダースの巨体種」の名のとおりフランス原産で、体重は6.7キログラムにもなる。毛色は鉄灰色、淡褐色などさまざまである。
毛皮用種としてはチンチラChinchillaやレッキスRexなどがある。両者ともフランス原産。前者は、体重3キログラムほどの小形種、4.5~4.9キログラムの中形種、6.1~6.5キログラムの大形種がある。毛色は、南アメリカ産の毛皮獣である齧歯類のチンチラに似て黒と白の霜降り状で、息を吹きかけると黒と白の輪状の紋が現れる。後者は体重3.5~4キログラムで、毛はきわめて短く直立しているので、ビロードのような感触があるため、高級毛皮の代用品として珍重される。毛色には白色、黒色など多種があるが、カスターレッキスのものはカワウソの毛皮に似る。
兼用種は肉・毛皮両方を目的につくられた。兼用種にはニュージーランドホワイトNew Zealand whiteや日本白色種がある。前者はアメリカでつくられた白色種で、体重4.5~5キログラムで前躯(ぜんく)がよく発達し、肩幅と腰幅の差が少なく角形の体形を示す。後者は日本でもっとも多く飼育されている白色種である。起源は明らかではないが、おそらく明治初期に輸入された外来種との交配によってつくられたアルビノと考えられている。そのため以前は地方によって体形、大きさに差があり、大形をメリケン、中形をイタリアン、小形を南京(ナンキン)とよんでいたが、第二次世界大戦後統一され、体重は生後8か月で4.8キログラムを標準とする。肉と毛皮との兼用種として改良されてきたため、毛皮の質と大きさの点で優秀な品種である。
愛玩用種としてはヒマラヤンHimalayanやダッチDutchがある。前者はヒマラヤ地方原産といわれており、体重1.3キログラムの小形で、白色毛に、顔面、耳、四肢端が黒色の毛色である。後者はオランダ原産で、黒色、青色、チョコレート色などの被毛であり、胸の周りには帯をかけたような白色毛がある。体重は2キログラム前後である。
[澤崎 徹]
飼養
飼育箱は、幅、奥行が60センチメートル、高さが最低40センチメートルぐらいのものを使用し、ここに1頭ずつ飼育する。木製や金属製を用いるが、ウサギは大門歯が持続的に成長し、物をよくかじるから、木製の場合は頑丈につくる。床面は、ウサギを健康かつ清潔に飼育するために簀子(すのこ)にして、排出物が下に落ちるようにつくる。いずれにせよ、清掃が容易で清潔さを保てる点から、金属製の飼育箱が優れている。飼育法としてほかには、放し飼い、群れ飼いなどもある。
餌(えさ)は青草、乾草、野菜、穀類を与える。水は自由に飲めるようにする。とくに乾草給与時や、夏季、分娩後や哺乳中には水分が不足しやすい。ウサギは体に比べて大きな胃と盲腸があって大食である。成長期には1日に体重の1~3割の餌を食べる。ウサギの奇妙な習性に食糞(しょくふん)がある。普通にみられる糞と、ねばねばした膜に包まれた糞を交互に排出するが、後者が排出されると、自分の口を肛門(こうもん)に近づけて吸い込み、かまずに飲み込む。この糞を食べさせないようにすると、しだいに貧血症状を呈し、やがて死亡する。これからもわかるように、排出物というよりも餌といえるほどにタンパク質やビタミンB12が多く含まれていて、ウサギの健康維持にたいへん役だっている。
ウサギをつかむときには、背中の真ん中よりやや前方の皮を大づかみにする。両耳を持ってつり下げるようなことをしてはいけない。粗暴に扱ったり、苦痛を与えると、普段鳴かないウサギも、キイキイと甲高い声を出す。おそらく恐怖のための悲鳴であろう。
[澤崎 徹]
繁殖
ウサギは生後8か月から繁殖に用いられる。野生のウサギには繁殖季節があるが、カイウサギには認められない。また、自然排卵をしないで交尾刺激によって排卵が誘発される。この型の排卵はネコやイタチ類にみられる。妊娠期間は31~32日で、1回の分娩に6、7頭の子を産む。母親は分娩後、非常に神経質になり、興奮して子を食い殺すこともあるので安静にしておく。ウサギの乳汁は牛乳より栄養に富み、12.3%のタンパク質、13.1%の脂肪を含むから、赤裸の子も早く育つことができ、6~7週齢で離乳する。
ウサギは暑さに対して弱いばかりでなく、病気に対する抵抗力が一般的に弱い。とくにかかりやすい病気として、原虫によるコクシジウム症、細菌による伝染性鼻炎、ぬれた草(とくにマメ科植物)の多食による鼓張症などがある。
[澤崎 徹]
利用
日本において家畜としてウサギが飼養されるようになったのは明治時代からで、中国やアメリカなどから輸入され、当初は愛玩用として飼われていた。防寒具としての毛皮、食用としての肉が軍需用物資として使用されるようになって急激に飼育数が増大した。これはアメリカへの毛皮輸出を含めた1918年(大正7)の農林省の養兎(ようと)の奨励による。飼育数増大とともに各地で毛皮・肉兼用種への改良が行われ、現在日本白色種とよばれるものができた。日本におけるウサギの飼育頭数は、軍の盛衰と運命をともにし、一時は600万頭も飼育されていたが、第二次世界大戦の終戦とともに激減した。なお、日本ではウサギ類を古来「1羽、2羽…」とも数えるが、これは獣肉食を忌み、鳥に擬したためである。
毛皮は軽く保温力に富むのでオーバー、襟巻などに、アンゴラの毛はセーターや織物になる。肉もよく利用されるが、ほとんどは輸入されたものである。利用面で近年忘れられないことは、医学、生物学、農学などの研究に供試されることで、年間数十万頭が利用されている。
[澤崎 徹]
食用
ウサギの肉は食用としてもよく用いられる。野ウサギの肉はやや固く一種の臭みがあるが、家ウサギの肉は柔らかく、味も淡白である。ウサギ肉のタンパク質は、粘着性や保水性がよいので、プレスハムやソーセージのような肉加工品のつなぎとしてよく使われた。ウサギの肉は、鶏肉に似ているので、鶏肉に準じて各種料理に広く用いることができる。ただ、においにややくせがあるので、香辛料はいくらか強めに使うほうがよい。栄養的には、ウサギの肉はタンパク質が20%と多く、反対に脂質は6%程度で他の肉より少ない傾向がある。
[河野友美・大滝 緑]
民俗
『古事記』にある「因幡(いなば)の白兎(しろうさぎ)」の説話や、『鳥獣戯画』に描かれているおどけたウサギなど、古来ウサギは人間と密接な関係をもつ小動物と受け取られてきた。「かちかち山」や「兎と亀(かめ)」などの動物説話が広く知られている一方、一見おとなしそうなウサギが逆に相手をだます主人公となるような類話も少なくない。その舞台を語るのか、赤兎山(あかうさぎやま)、兎平(うさぎだいら)、兎跳(うさぎっぱね)など、ウサギにちなむ地名が全国各地に分布する。また時期や天候の予知にも関係し、山ひだの雪形が三匹ウサギになると、苗代に籾種(もみだね)を播(ま)くとする所や、時化(しけ)の前兆となる白波をウサギ波とよんでいる所が日本海沿岸に広くみられる。ウサギの害に悩む山村の人々は、シバツツミとよばれる杉葉を田畑の周囲に巡らしたり、ガッタリ(水受けと杵(きね)とが相互に上がったり落ちたりする仕掛けの米搗(こめつ)き臼(うす))の発する音をウサギ除(よ)けとした。雪国の猟師たちは、新雪上に描かれたテンカクシ、ミチキリなどと特称される四肢の跡を目安に狩りをしたが、なかでも、棒切れあるいはワラダ、シブタなどといわれる猟具をウサギの潜む穴の上へ投げ飛ばし、空を切る音と影の威嚇(いかく)効果によって生け捕りにする猟法は、注目に値する。また、ウサギは月夜の晩に逃げるとか、その肉を妊婦が食べると兎唇(としん)(口唇裂)の子が生まれる、などの俗信も少なくない。
[天野 武]
ヨーロッパ、とりわけフランスでは、家畜ウサギは食用としてニワトリと並び賞味されているが、一方の野生のノウサギは、世界各地で民話の登場人物として親しまれてきた。そのイメージの多くは、すばしこくて少々悪賢く、いたずら好きだが、ときには人にだまされるという共通性をもっている。アフリカ(とくにサバナの草原地帯)の民話では、ウサギはトリックスターとして活躍し、ハイエナなどがウサギにかつがれる。ナイジェリアのジュクン人の民話では、ウサギは王の召使いとして人々との仲介者となったり、未知の作物や鍛冶(かじ)の技術を人々にもたらす文化英雄の役割を演じるほか、詐術によって世の中を混乱させたり、王の人間としての正体を暴いてみせたりする。またいたずら者のウサギは「相棒ラビット」などのアフリカ系アメリカ人の民話にも生き続けている。
[渡辺公三]
『ワイスブロス、フラット、クラウス編、板垣博他訳『実験用ウサギの生物学――繁殖、疾病と飼育管理』(1978・文永堂)』▽『高橋喜平著『新版 ノウサギの生態』(1982・朝日新聞社)』▽『斉藤久美子著『うさぎ学入門』(1998・インターズー)』▽『大竹隆之・桜井富士朗監修『くわしいウサギの医・食・住』改訂新版(2004・どうぶつ出版)』▽『スタジオ・ニッポニカ編『百分の一科事典 ウサギ』(小学館文庫)』