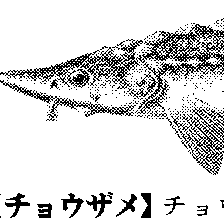出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
Sponserd by 
チョウザメ
ちょうざめ / 蝶鮫
sturgeon
硬骨魚綱チョウザメ目チョウザメ科の魚類の総称、またはそのなかの1種。チョウザメ類は、「サメ」の名があるが、軟骨魚類のサメ類ではなくて硬骨魚類である。このなかではきわめて原始的な形質を備えた一群で、「生きた化石」といわれている。北半球にだけ分布する。ヨーロッパとアジアからおよそ15種と北アメリカから約9種が知られている。
体は円筒形に近く、吻(ふん)はとがる。体には大きい板状の硬鱗(こうりん)がある。口は頭の下面に開き、上下両顎(りょうがく)には歯がない。口の前には4本のひげが横1列に並ぶ。尾びれの上葉は下葉より大きい。背びれ、臀(しり)びれおよび腹びれは体の後部に位置する。体の鱗(うろこ)の形がチョウ(蝶)が羽を開いた姿に似ていること、口の位置、ひれの形と位置などがサメを連想させることが、チョウザメの名前の由来である。陸封型と降海型とがある。前者は生涯淡水域にのみ生息し、後者は海と淡水にすむことができ、産卵期には生まれた川を遡上(そじょう)する。おもに貝類、節足動物、ゴカイ類などの底生生物を食べる。成長はきわめて遅く、成熟するまでに6~25年を要するが、毎年成熟するとは限らない。
この類の卵の塩漬けがキャビアであり、ロシア連邦、イランなどは著名な生産国である。養殖も行われている。この類の最大のものはヨーロッパ産のベルーガbeluga/Huso husoで記録され、体長8.5メートル、体重1.3トンで、100歳以上であった。卵巣以外に、肉は生鮮、あるいは薫製、冷凍、乾燥して利用する。頭部軟骨はスープ、浮き袋は糊、鱗は装飾品にするところもある。養殖のために活魚が取引される。近年、公害、乱獲、ダムなどの人的な要因によってこの類の個体数は著しく減少し、絶滅危惧種に指定されている種が増えている。
和名チョウザメgreen sturgeon/Acipenser medirostrisは、日本では本州の北部から樺太(からふと)(サハリン)にかけて分布し、かつては4、5月ごろには北海道の石狩川(いしかりがわ)や天塩(てしお)川に産卵のため多数遡上したが、現在はほとんどみられない。体は細長く円筒状。吻は長く、先端は丸い。口は小さく、頭の側面まで届かない。左右の鰓膜(さいまく)は体の側面と癒合する。ひげの断面は円形。背びれより前に7~10枚の鱗板(りんばん)がある。卵は小さく、水草や砂礫(されき)などに産み付ける。約1週間で孵化(ふか)し、秋に川を下って海に入り成長する。全長2メートルを超える。北海道各地の定置網でまれにとれる。卵はキャビアに、肉は薫製、刺身、バター焼きなどにする。近縁種のカラチョウザメとは背びれ条数、臀びれ条数、鱗板数などが少ないことで区別する。
[尼岡邦夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
チョウザメ
sturgeon
チョウザメ目チョウザメ科Acipenseridaeの魚の総称。サメという名がついているが硬骨魚であってサメ(軟骨魚)の仲間ではない。体は延長した紡錘形で,吻(ふん)は突出して長く,先端がやや扁平になっている。口は吻の腹面にある。上下両あごとも歯はない。口の前方には左右2対のひげが1横列をなして並んでいる。外鼻孔は吻の各側に2個あり,内鼻孔はなく,噴水孔がある。腹びれは腹の位置にある。背びれは1基で体の後方にある。尾びれは歪尾で,上葉が長い。体表には背中線,体側および腹側に大きなひし形板状の硬鱗が5縦列をなして並んでいる。うろこは中央に突起があり,その形がチョウ(蝶)に似ていて,チョウザメの名もこれに由来するとの説がある。骨格はほとんど軟骨性で,脊椎には椎体がなく,脊索は成魚になっても円筒状をなしている。
ユーラシア大陸と北アメリカの寒帯から温帯にかけて分布し,亜寒帯以北に多く,24種が知られている。川や湖にすむ種類と海にすむ種類とがあり,比較的小型のものは終生河川内にすみ,産卵期には細流に遡上(そじよう)するが,海洋にすむものも産卵期になると河川を遡上する。産卵期は春から初夏の候で,粘着性の卵を水底の水草などに産みつける。孵化(ふか)した仔魚(しぎよ)は吻端の吸盤で地物に吸着して,水流中で流されるのを防ぐ。チョウザメ類はすべて底生性なので,底生のイトミミズ,カニ,エビ,貝,小魚などを餌として捕食する。日本付近にすむ種類はさして体の大きいものがないが,旧ソ連地域のHuso属のチョウザメには全長8mを超すものもあることが報告されている。卵巣卵の塩蔵品はキャビアとして珍重され,カスピ海産の製品が最高級品とされている。肉は薫製,煮物などとして食膳に供される。
チョウザメAcipenser medirostris(英名green sturgeon)はミカドチョウザメとも呼ばれる種類で,本州北部から北海道,サハリン海域に分布する。体はやや円筒形で,背側は青灰色を呈し,腹側は淡色。全長1.5m内外。昔は産卵期の4~5月には北海道の石狩川,天塩川に群れをなして遡上したが,近年は著しく減ってしまった。川にさかのぼった親魚はひげで底生生物の所在をさぐり貪食(どんしよく)する。卵は約1週間で孵化(ふか)し,稚魚は秋まで川で過ごして海に下る。日本付近にはそのほかカラチョウザメ,アムールチョウザメ,ダウリチョウザメなどが知られている。
執筆者:日比谷 京
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
チョウザメ
チョウザメ科の魚の総称。サメと呼ばれているが硬骨魚で,サメ(軟骨魚)のなかまではない。ユーラシア大陸と北アメリカの寒帯と温帯に分布し,世界中で24種が知られている。ロシアには全長8mを超すものもある。日本付近では,チョウザメ,アムールチョウザメなど数種が知られている。チョウザメは,全長1.5m内外。鱗は硬鱗で,背中線,体側,腹面にそれぞれ1列に並ぶ。かつては北海道の石狩川,天塩川などに産卵のためさかのぼったといわれる。チョウザメ類はいずれも肉は美味で,卵は塩漬にしてキャビアとされる。また釣の対象とされるなど旧ソ連,北米などでは水産上重要。
→関連項目カスピ海
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
チョウザメ
Acipenser medirostris
チョウザメ目チョウザメ科の魚。大きな鱗の形がチョウに似るのでその名がある。体長は普通 1.3m。体はやや円筒形で,吻はやや延長し,口は下面にある。2対の口ひげがあり,それで砂泥中を探りながら餌をとる。体の背面は灰青色で,腹面は白色。群れをつくって川を上り,夏に砂礫底や水草などに産卵後,海に下る。卵は 1週間内外で孵化し,稚魚は秋に海へ下る。肉は美味で,卵は高級食品キャビアとして珍重される。東北地方以北,北太平洋に分布する。日本ではかつて北海道の天塩川,石狩川を遡上していたが,今日では絶滅したと考えられている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
チョウザメ
学名:Acipenser medirostris
種名 / チョウザメ
目名科名 / チョウザメ目|チョウザメ科
解説 / 主に底にすむ小動物を食べます。成魚は、春ごろ川をさかのぼり、夏ごろ産卵します。海での生活はよくわかっていません。
別名 / カワザメ
全長 / 150cm
分布 / 東北地方以北、日本海/太平洋北部
絶滅のおそれのある種 / ★日本の河川では絶滅
出典 小学館の図鑑NEO[新版] 魚小学館の図鑑NEO[新版] 魚について 情報
Sponserd by 
チョウザメ
[Acipenser medirostricus].チョウザメ科の魚.卵の塩蔵品がキャビア.
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のチョウザメの言及
【キャビア】より
…チョウザメ類の卵の塩蔵品。卵巣をとり出してもみほぐし,卵膜を除いてばらばらにした卵粒を塩漬にして熟成させる。…
※「チョウザメ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by