翻訳|tent
精選版 日本国語大辞典 「てんと」の意味・読み・例文・類語
てん‐と
- 〘 副詞 〙 ( 「てんに」「てんで」などと同語源か )
- ① すっかりその状態であるさま、疑問に思う余地のないさまなどを表わす語。まったく。十分に。ほんとうに。
- [初出の実例]「おちやの日をまつかさの、かさねてと契つつ、そわでとしふるてんと身ぞつらき」(出典:評判記・野郎大仏師(1667‐68)序)
- ② ( 打消表現を伴って ) 物事をまったく否定するさまを表わす語。さっぱり。まるきり。一向に。てんで。
- [初出の実例]「てんときこゑぬ」(出典:狂言記・釣女(1660))
- ③ きちんとしたさまを表わす語。
- [初出の実例]「厭はぬ心にてんと結ふた髪を」(出典:歌謡・松の葉(1703)二・狭ごろも)
テント
- 〘 名詞 〙 ( [英語] tent ) 解体して持ち運びのできる、骨組と布製の覆いからなる軽便家屋。移動生活を営む牧畜・狩猟民族では日常の住居として用いる。露営用として、またサーカス・芝居などの掛小屋として用いられるものもあり形態は多様である。天幕。《 季語・夏 》
- [初出の実例]「山の間の涼しさうな平地へ天幕(テント)を張り本陣を居(すへ)て」(出典:寄笑新聞(1875)〈梅亭金鵞〉六号)
改訂新版 世界大百科事典 「てんと」の意味・わかりやすい解説
テント
tent
天幕ともいう。移動式の家屋で解体して持ち運びのできる簡易なものを指す。獲物や家畜を追って移動する狩猟民,牧畜民の住居として,北アジアの狩猟民や北米インディアンの用いた3本の木を組み合わせた形や2本ずつ組み合わせた上に1本を渡し,さらにその上に皮や草で編んだマットを覆ったものやモンゴル,キルギスの遊牧民のユルタやゲルのような柳の枝などで組んだ笠状の屋根にフェルトをかぶせたもの,西南アジアの遊牧民の長方形のブラックテントなど,現在も用いられているものもあるが,一般的には日常的住居としてではなく,臨時の露営,キャンプ用として軍事,探検,登山などで用いられる布製のテントを指すと考えてよかろう。運動会用や工事用に用いる野外の日よけ,雨よけに用いるものもテントと呼んでいる。軍事用,野外音楽,演劇やサーカスなどに用いる特殊な大規模なテントもあり,これらも仮設的な移動可能施設として用いられている。
テントの形には三角型,ウィンパー型,片流れ型,かまぼこ型,ドーム型などもあるが,普及しているのは屋根型,家型である。目的によって重量,居住性,耐風性などが問題とされるが,夏季に用いるものは軽量で居住性の良いものが好まれ,日本では1人分の広さの基準を180cm×45cmとしている。冬季は耐風・耐雪性が問題となり,広さも衣類などが多いので20%増しとする。材料は古くは厚手の平織りの麻や綿であったが,現在ではナイロン,ビニロン,テトロンなどが多く用いられている。
テントの設営
まず,しわなく張ることで,どんな良いテントも,しわがあれば漏水する。長期間の場合にはフライシート(覆い)を用いる。キャンピングには高さの高い居住性の良いものが適している。テントの設営は,洪水,雪崩などの危険がなく,できるだけ平たんな乾燥した草地を選び,次の順序で張る。(1)テントの部品,とくに張り綱やペグ(杭)の数などを確かめる。(2)敷地をならし,石などを取り除いて平らにし,できれば草などを敷く。(3)4隅を固定する。(4)ポールを立てる。(5)腰綱を張り,しわの寄らないように固定する。(6)グランドシートを張り,湿気の遮断につとめる(これは最初にしてもよい)。(7)テントの周囲に排水溝を掘る。(8)炊事設備,便所の設備がないときには,風下に設置する。(9)撤収のときには,ペグ,張り綱の数を確かめ,泥などをよく落とす。(10)下山後,テントは1度干してからしまう。冬季はテントの周囲に雪で防風垣をつくる。テント内では整理を十分にし,換気と火の元に留意する。
→キャンプ
執筆者:徳久 球雄
遊牧民の生活とテント
アラビア語でテントはハイマkhaymaと呼ばれ,定住家屋でも,遊牧民のテントが基層構造となっている。テントの屋根と壁は,多くは動物の毛で織った30~50cm幅の帯を張り合わせてつくられている。形は,中央アジアの丸型のものとは異なり,西アジアでは総じて長方形で,東または南向きに張られる。支柱は,側面からみて主柱,前柱,後柱の3種類が3列に並ぶ。中央に垂直に高く主柱を立て,その前後に,前幕を支える前柱と,後幕を支える後柱を置く。前幕は,ハレム(女部屋)を除いては日中は開けておき,後幕は,下部を土に埋め込んだり,石を置いてまくれあがらないようにして後壁とする。前・後柱は垂直ではなく少し倒す形になっている。
テントの規模は,中央の主柱の数で決まる。正面からみて両端の側壁を支える柱を除いた主柱の数で,〈2本柱テント〉〈3本柱テント〉などと呼ぶ。通常は前者で,その場合3部屋構成となる。向かって右の部屋が客間兼男部屋で,左の2部屋がハレムと台所となる。客間とハレムの間には,以前は色彩豊かで上質な仕切り幕がつるされていたが,今日では簾(すだれ)に薄絹を張った簡便なもので代用されている。客間では,ラクダの鞍が据えられた場所が主座であり,その鞍のできばえ,およびハレム内にあるハウダジュ(女性用担いかご)のできばえが,その家の地位,豊かさの尺度とされた。テントの幕を織ることやその設営は,女,子どもの役割である。主柱には家宝が掛けられ,また前柱に付けられる旗やロープは,プライドの高い遊牧民同士の間で,テントを通過する者への無言の信号・意思表示となっている。
執筆者:堀内 勝 おおくの遊牧民にとって,固い壁に囲われた家で寝ることは恐怖の種である。壁や天井が崩れおちてこないかと心配なのも一つの理由であるが,外界と絶ち切られた状態が彼らの不安感をかきたてるようだ。テントは,居住空間の外皮の機能をになっている。外皮は,外界との境界でありながら,そのいぶきを微妙に伝える役目ももつ。大地を直接の床とするテント生活は,自然との一体感に根ざした一種の安心感を遊牧民たちにもたらす。
遊牧民のテントを,素材と形態に基づいて大別すると,(1)織布-ブラックテント,(2)フェルト-ユルタ(ゲル),(3)その他,の3種類になるだろう。織布-ブラックテント型の分布はもっとも広い。東はチベットから西は北アフリカまで,乾燥地域に広くみられる。チベットでヤクの毛を素材として用いる以外,ほとんどの地域では黒ヤギの毛で織った織布をテント地として使用している。北アフリカなど一部の地域では,ヤギの毛にヒツジやラクダの毛をまぜて使うこともある。ブラックテントの形態は多様だが,一定の幅で織りあげた織布を数枚から十数枚縫い合わせる手法は共通している。形態の差異は,おもに支柱,張り綱,側壁などの形に基づく。アラブ,ペルシアのブラックテントは数本の支柱(中央の支柱と2本の側柱が基本形)で支持されるが,張力帯の有無という点で相違点がある。アラブ遊牧民のブラックテントには,長方形の短辺に並行して数本の弾力帯が縫い合わされていて,張り綱はこの先端にとりつけられた索具に結ばれる。こうしたくふうは,強風に対する弾力的な対応力を生んでいる。フェルト-ユルタ(ゲル)型のテントは,モンゴル高原から中央アジアにかけて分布する。おもにトルコ系およびモンゴル系の遊牧民が使用している。チベット,アフガニスタン,イラン,トルコを結ぶ地域の周辺では,ブラックテントとユルタ(ゲル)型のテントが混交してみられる。ユルタ(ゲル)型のテントは円形で,蛇腹式になった側壁で天蓋を支え,全体をフェルトで覆った形になっている。防寒性と気密性という点では,ブラックテントにまさる。第3の類型にはいるテントは,獣皮製や木皮製などのものである。北アフリカの一部やシベリアなどにおいてみられる。北アフリカのトゥアレグ族では,なめしたヤギ皮やヒツジ皮を地上に固定した支持棒や支持枠の上に張りめぐらせてテントにする。
遊牧民のテントは,いずれも移動生活を前提としてつくられている。ブラックテントやユルタ(ゲル)型テントは,ラクダやヤクの背,牛車など運搬手段を確保してから初めて実用化されたものであろう。こうした運搬手段を欠いたながい前史が,遊牧生活にはあったはずだ。その時代,まったくの野営から獣皮や木皮,枝,草などを用いたテントの原形まで多様な生活形態がみられたにちがいない。
→住居
執筆者:松原 正毅
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「てんと」の意味・わかりやすい解説
テント
てんと
tent
現在ではテントということばは日常的住居でなく、臨時の露営用として、軍事、探検、登山、キャンプなどに用いられるもの、そのなかでもとくにキャンプ、登山などに用いられるものをさしていると考えるのが一般的である。運動会など野外の日よけに用いるものもテントとよばれている。軍事、学校キャンプなどに用いられるのは、20人用、30人用など大きなものがあり、また野外音楽、演劇、サーカスなどに使われる特殊な大規模のものがあるが、登山、キャンプ、小旅行に用いられる一般的なものは、5人から10人用ぐらいまでの、自分で持ち運びできるものが多い。
[徳久球雄]
種類
三角型、屋根型、家型、ウィンパー型、片流れ型、かまぼこ型、ドーム型、およびその変形があるが、屋根型、家型がもっとも普及している。重量、居住性、耐風性などが目的によって問題とされるが、夏季に用いるものは軽量で居住性のよいものが好まれ、片流れ型、家型が多く、日本では規格として180センチメートル×45センチメートルを1人分の生活スペースと考えて設計されている。冬季は耐風・耐雪性が問題となり、生活スペースも衣類などが多いので20%増しとなる。材料は古くは厚手の平織の麻や綿であったが、現在ではナイロン、ビニロン、テトロンなどが、重さ、防水性、強度の点で優れていることから多く用いられている。
[徳久球雄]
テントの設営
現在はキャンプ場が指定されているが、元来は洪水、雪崩(なだれ)などの危険がなく、できるだけ平坦(へいたん)な乾燥した草地を選び、夏はとくに燃料・水の得やすい所、冬は風当りの弱い所に設営する。設営方法は、(1)整地、(2)用具・備品の点検、(3)底面の位置を決めて固定する(その場合、入口を風下にすること)、(4)ポールを立てる、(5)主張り綱を張り、ペグ(杭(くい))で留める、(6)グランドシーツを敷く、(7)排水溝を掘る、(8)炊事場・便所・物置などを必要に応じてつくる、(9)フライ(覆い)をもっていたら張る(とくに長期の場合は必要)、という順序で行う。
冬季は排水溝の必要はないが、保温のために、内張りを張り、テントの周囲に雪で防風垣をつくる。テント内の生活は不潔になりがちなので、整理を十分にし、とくに冬季はベンチレーション(換気)に留意しなければならない。炊事は、夏季は外で薪(たきぎ)により行うことが多いが、冬季はテント内でこんろによる。この場合こんろなどの不始末で火災を起こしたりすることがあるので、火気には十分注意する。オートキャンプ用などのテントではキャンバスベッドを利用すればよいが、その他の場合はエアマットを敷くなど湿気を遮断することに注意しないと、健康を害する。
テントは使用後は十分に乾燥させ、部品、布部の損傷を点検し、湿気の少ない所に保存する。張り綱、杭などは予備を用意しておくことが必要であり、ポールも強風によって破損することがある。
[徳久球雄]
住居としてのテント
遊牧民、狩猟民の間で日常的に用いられる住居。木製の骨組と、布、フェルト、皮革、樹皮などの覆いからなる。骨組の一部が放置される場合もあるが、多くの場合、覆いとともに移動のたびに持ち運ばれる。したがって、家畜を飼い、車、橇(そり)、ボートなどの運搬具をもつ人々でないと使えないといわれる。形、構造は地域、民族によってさまざまであるが、大別すると、西アジア、北アフリカの黒テント、中央アジア、北アジアの円筒円錐(えんすい)型のテント(ゲル、ユルタ)、極北地域の円錐型またはドーム型のテント、北アメリカの平原インディアンの円錐型テント(ティピ)などに分けられる。
黒テントは西アジアのベドウィンを中心に、北アフリカからチベットまでの広大な範囲でさまざまな遊牧民に使用されている。基本的にはヤギの毛で織った黒い長方形の布を綱で強く張り、それを下から木の柱で支える構造をもつ。乾燥地帯では屋根が平らであるが、雨の多い地方では山型にして、水を流すようにする。側壁には別の布が屋根から吊(つ)るされるが、夏季に莚(むしろ)を用いたり、冬季に土や石で側壁を築くこともある。ベドウィンなどでは屋根布に張力帯をつけて強度を増すくふうをしている。
中央アジア、北アジアのモンゴル系、チュルク系の人の使うテントは骨組だけでも独立して立つことができる。つまり、細い棒を矢来(やらい)組にし円筒形の側壁をつくり、その上に棒を円錐形に立て並べて屋根の骨組をつくる。そして全体をフェルトで何重にも包み、いちばん外側に防水用の厚織綿布をかけて綱で締めてできあがる。天井には煙出しと採光のために丸い穴があり、雨や雪を防ぐために蓋(ふた)がついている。モンゴルのゲルとチュルクのユルタの構造上の違いは、屋根材にあり、前者がまっすぐな棒を利用するのに対し、後者では多少湾曲している点である。
極北のタイガ、ツンドラの狩猟民とトナカイ遊牧民の間では円錐型のテントが使われる。構造は比較的単純で、中心となる数本の柱を上部を接合して立て、その接合部に立てかけるように他の木材を円錐形に立て並べる。そしてその上に夏はシラカバの樹皮、冬は動物の毛皮を巻き付ける。最上部は煙出しと採光のためにあけられていて、蓋はない。東シベリアのチュクチ、コリヤークなどの民族ではゲルに似た形の獣皮テントが使われ、北アメリカではドーム型のものも使われる。極北地域では、壁となる獣皮、樹皮、中心となる柱は移動時には持ち運ばれるが、他の木材はその場で調達されることが多い。
北アメリカの平原インディアンのティピも基本構造は極北の円錐型テントと同じであるが、より洗練されている。つまり、頂上に煙抜き幕を取り付けて、風向きによって向きを変えることで換気をよくし、側壁の内側にさらにもう一枚幕を張ることで湿気を防いでいる。壁材にはかつては美しい文様を描いたバッファローの革が使われたが、現在は厚織綿布を使っている。
一般的に核家族単位で居住しているが、大型のものでは数家族が合同して使用することもある。内部は人や家具の位置が厳格に決められている。とくに男女の住み分けは明瞭(めいりょう)で、黒テントでは布で仕切って完全に区分する。現在、遊牧民、狩猟民は各国政府の定住化政策などにより、急速に減っているが、彼らのテントの利点、構造は現代建築や、キャンプ用テントなどに生かされている。
[佐々木史郎]
『トーボー・フェーガー著、磯野義人訳『天幕』(1985・エス・ピー・エス出版)』
百科事典マイペディア 「てんと」の意味・わかりやすい解説
テント
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
普及版 字通 「てんと」の読み・字形・画数・意味
【 都】てんと
都】てんと
字通「 」の項目を見る。
」の項目を見る。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
デジタル大辞泉プラス 「てんと」の解説
テント
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「てんと」の意味・わかりやすい解説
テント
「天幕」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内のてんとの言及
【キャンプ】より
…キャンピングcamping,野営または露営ともいい,野外における一時的な生活をすること。テント利用のほか,バンガロー,コテージ,ヒュッテなどを利用するものや岩小屋など自然の地物を利用するものがあり,また登山の場合,簡単なツェルトザックなどでビバークするもの,積雪期に雪洞やイグルー(雪や氷のブロックを積み上げてつくったドーム型の住居)を利用するもの,宿泊設備を何も持たない野営なども広義には含んでいる。軍隊の一時的居住などを称することもある。…
【住居】より
…農耕社会でも焼畑を経営する人々の住居は多少なりとも移動性を伴う。遊牧民ベドウィンのテントやモンゴルのゲルに代表されるような移動式住居は,われわれにもう一つの住居観を教えている。それは一ヵ所に定住しない世界であり,家船(えぶね)を住居とする漂海民にも通じていく。…
【中央アジア】より
…遊牧民はこれらの動物とともに,夏の居住地(夏営地)と冬の居住地(冬営地)の間を,定期的・周期的に季節移動する。移動を容易にするために,彼らは普通固定家屋をもたず,組立て式の,羊毛を圧縮して作ったフェルト製のテントに暮らす。食生活も,主としてドライ・ヨーグルト,バター,チーズなどの乳製品でまかなわれ,その財産である動物の肉が食用に供されるのは,祭りや客の接待,冬季の保存食など,特別の機会・用途のために限られる。…
【登山】より
…50年フランスのM.エルゾーグ隊は鎖国を解いたネパールにはいり,アンナプルナ主峰(8091m)に初めて登頂した。これが人類初の8000m峰登頂であり,またこの隊はナイロン製のテントやロープなどを最初にヒマラヤで使用した科学的装備の隊であった。これから登山装備は急速に進歩した。…
【ベドウィン】より
…
[生活文化]
ベドウィンの生活は,古来からあまり変化がなく,移動を軸とした文化がみられる。住居は移動に適したバイト・シャアルbayt sha‘ar,あるいはハイマkhaymaなどと呼ばれる黒っぽいテントである。ヤギまたはラクダの毛で,通風が良いように織られ,雨が降ったときには毛糸が膨張して雨水を下に通さないようにできている。…
※「てんと」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...


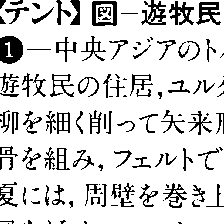
 途】てんと
途】てんと 」の
」の