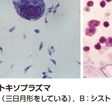精選版 日本国語大辞典 「トキソプラズマ症」の意味・読み・例文・類語
トキソプラズマ‐しょう‥シャウ【トキソプラズマ症】
内科学 第10版 「トキソプラズマ症」の解説
トキソプラズマ症(原虫疾患)
トキソプラズマ(Toxoplasma gondii)による感染症である.マラリア原虫・クリプトスポリジウムと同様にアピコンプレクサ門に属する.
原因・病因
トキソプラズマは有性・無性生殖を行う.ネコ科の動物が終宿主であり,そのなかで有性生殖を行う.ヒトを含めたその他の動物のなかでは,トキソプラズマは無性生殖のみを行う.中間宿主のなかでは急増虫体(tachyzoite)と緩増虫体(bradyzoite)の2つの形をとり,前者がトキソプラズマ症の病因となる.急増虫体は宿主細胞内で分裂・増殖し,細胞を破壊して放出され新しい細胞に侵入する.急増虫体は筋肉や中枢神経系などで緩増虫体(bradyzoite)に分化・被囊化し,囊子(シスト,cyst)を形成する.栄養型(図4-15-5A)は長さ約4~7 μm,前端には胞子虫特有のapical complexをもつ.囊子(図4-15-5B)は通常径数十 μm に達し,内部には多数の緩増虫体を含む.終宿主への感染はネズミなどの体内の緩増虫体の経口摂取により起こる.ネコにはじめて感染した虫体は小腸の粘膜上皮細胞に侵入し,メロゴニー(merogony),ガメトゴニー(gametogony)とよばれる数段階の分化の後受精し,オーシストを形成する(図4-15-5C).オーシストはネコの糞便内に排出され,外界で成熟し,感染能力をもつスポロゾイト(sporozoite)が形成される.ヒトへの感染は,ブタ・ヤギ・ヒツジなど食肉中の囊子の経口摂取によることが多い.ネコ糞便中のオーシストも感染源となる.ヒトで最も重篤な結果を生む先天性感染は妊娠中に初感染した場合にのみ起こり,経胎盤的に急増虫体が胎児に移行することで起こる.
疫学
感染は鳥類・齧歯類・家畜を含めた温血動物に広くみられる.わが国では成人の10~15%が抗体を保持している.アフリカやヨーロッパなどでは感染率はより高い.一般に好んで羊・牛・豚肉などの生食をする地域で感染率が高い.遺伝子型別から大きく3つの群(タイプⅠ〜Ⅲ)に分けられ,ヒト・動物における宿主域,地域分布,病原性が異なる.
病理・病態
免疫機能が正常な感染者の大多数は無症状キャリアである.AIDS,悪性リンパ腫,白血病,臓器移植時など免疫不全を伴う際に,組織内囊子からの播種性の全身感染が起きたり,脳炎などがみられる.すなわち本症は日和見感染症(opportunistic infection)の1つである.急性期には急増虫体は心臓を含めた全身の筋肉・肝臓・脾・リンパ節・中枢神経系を含めた全身の臓器にみられる.感染局所では変性した虫体周囲の炎症,類上皮細胞の小肉芽腫形成を認める(図4-15-6).感染制御には液性免疫は不十分で,IL-2,IL-12,IFN-γなどサイトカインの協調作用とともに,CD8+
ヘルパーT細胞依存的な細胞性免疫が重要である.
臨床症状
先天性トキソプラズマ症の4主徴は網脈絡膜炎(retinochoroiditis),水頭症(hydrocephalus),または小頭症(microcephalus),脳内石灰化(intracranial calcification),精神・運動障害(psycho-motor disorder)である.さらに肝腫大,貧血,黄疸,リンパ節腫脹を呈する.先天性トキソプラズマ症の場合,妊娠の時期により胎児の感染リスクおよび重症度は異なる.妊娠初期の母体感染の場合,胎児の感染リスクは低いが,感染した場合の多くは流産の帰結をたどる.一方妊娠後期に感染した場合,胎児の感染の可能性は高く,出産時の見かけの重症度は低いものの,その後症状を示すことが多い.主症状は,中枢神経系の壊死・結節形成,血管周囲壊死による病的反射,痙攣性の四肢麻痺,髄液圧の亢進である.後天感染で最も多い病型は頸部・腋窩などのリンパ節炎で,自然治癒することが多い.AIDSなどの免疫不全の場合は,多巣性壊死性脳炎(multifocal necrotizing encephlitis)とともに肝炎・肺炎・心筋炎などの全身感染を伴う.
診断・鑑別診断
血液中やリンパ節からの原虫の検出は検出率が低く通常行われない.急性,亜急性病変には免疫診断を用いる.ラテックス凝集反応や間接蛍光抗体法,ELISAなどがキット化されている.また,色素試験(Sabin-Feldman’s dye test)は特異性が高いが生虫体を使用するため一般検査室では実施できない.母体の感染の診断には,ペア血清(妊娠時・前と妊娠後)が必要である.妊娠前には陰性であり,妊娠中に陽転した場合には胎児が先天性トキソプラズマ症となる可能性がある.慢性病態である先天性トキソプラズマ症の多く,特に網脈絡膜炎の場合は抗体価も低く信頼度は下がる.EBウイルス,サイトメガロウイルス,HIVを含めたウイルス感染,結核・梅毒など細菌感染,真菌感染による脳炎・リンパ節炎・網脈絡膜炎との鑑別が必要である.
治療
通常リンパ節炎のときは相助作用をもつサルファ剤(スルフォナマイドなど)とピリメタミンを投与する.サルファ剤,ピリメサミンは催奇形性をもつため妊婦に投与してはならない.先天感染を疑った妊婦あるいは眼症状のある場合はアセチルスピラマイシンを投与する.効果はサルファ剤とピリメタミンに劣るが,先天感染と発症を軽減するとされている.
予防
獣肉はよく加熱調理されたものを摂取し,感染の可能性のあるネコ(特に子猫)との接触を避ける.未感染の妊婦は注意が必要である.[野崎智義]
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報
改訂新版 世界大百科事典 「トキソプラズマ症」の意味・わかりやすい解説
トキソプラズマ症 (トキソプラズマしょう)
toxoplasmosis
人獣共通伝染病の一つ。病原体は2~4μm×4~7μmの三日月形をした原虫の1種トキソプラズマ・ゴンディイToxoplasma gondiiである。固有宿主はネコ科の動物であるが,ネコ以外でも,イヌ,ウシ,ブタ,メンヨウ,ヤギ,ニワトリ,ウマ,ネズミなどにも感染し,これらの動物の組織内に寄生する。原虫の生活環にみられる各発育形態のうち,ヒトや動物の感染源となるものは増殖型,シスト(囊子),オーシスト(卵囊子)の3種で,ヒトの場合はシストとオーシストが感染源となるが,胎内感染では増殖型が原因となる。感染は,ブタ,ウシ,ヒツジ,ウマなどの肉を十分加熱しないで食べた場合や,ネコの便によって直接に,またはハエや昆虫を介して汚染された食物を食べた場合に,虫体が経口的に侵入することによって起こると考えられている。原虫は世界中に分布し,年齢とともに感染の機会が多くなる。日本人では地方によっては平均50%前後の抗体保有率を示すところもある。感染を受けても,たいていは無症状であり,ときにリンパ節炎,発熱,発疹などがある。問題になるのは妊婦がはじめて感染を受けた場合で,虫体が胎盤を通って胎児に移行し,胎児に脳や眼をはじめとする全身感染を起こすことが知られている。これは先天性トキソプラズマ症といわれるが,初感染を受けた妊婦の約1/3の胎児に起こるといわれる。妊娠初期に感染すると多くは流産,死産となるが,妊娠後半に感染すると,生まれた新生児に脈絡網膜炎,水頭症,脳内石灰化がみられたり,ときには痙攣(けいれん),貧血,黄疸遷延,肝脾腫などがあらわれる。また,新生児期に異常がなくても,だんだん水頭症,知能障害などが起こってくることもある。
診断は,酵素免疫測定法や蛍光抗体法を用いた血清抗体試験による。治療の必要性や継続期間は,症状の重症度や症例(とくに妊娠時の感染など)によって決められ,治療にあたってはサルファ剤,ピリメサミン,スピラマイシンなどが用いられるが,これらの薬は副作用も強く治療は難しい。
予防としては,肉は十分に熱を通して食べること,食前の手洗いの励行が肝要であり,ネコとの過度の接触を避けることが望ましい。
執筆者:松村 武男+奥山 和男
家畜のトキソプラズマ病
家畜では,ブタ,ヒツジ,イヌ,鳥類に自然感染を起こし,とくにブタへの感染率が高い。ブタに感染すると,高熱,食欲減退,元気喪失,呼吸困難,鼻汁の流出,眼結膜の充血,下痢などの症状がみられる。また,てんかん様発作,嘔吐,起立不能などの神経症状を呈することもある。病豚の解剖所見では,肺水腫,点状出血,巣状壊死(えし),肺炎,肝臓・脾臓の腫大,腹水の増大,リンパ節の腫大がみられる。血清診断として色素試験が応用されている。予防には感染動物の筋肉中の囊胞とネコの腸から排出されるオーシストの排除が必要である。
執筆者:本好 茂一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
家庭医学館 「トキソプラズマ症」の解説
ときそぷらずましょう【トキソプラズマ症 Toxoplasmosis】
哺乳類(ほにゅうるい)や鳥類に寄生するトキソプラズマ原虫(げんちゅう)が人に感染したときにおこる病気です。ネコの内にあるオーシスト(休止状態の原虫)や、豚肉、牛肉、羊肉内に含まれるシストという嚢子(のうし)を摂取することで感染します。
胎児(たいじ)に胎盤感染(たいばんかんせん)することもあります。
[症状]
妊婦が初めてこの病気にかかると、流産、早産の原因になるほか、感染した時期によっては、赤ちゃんに脳水腫(のうすいしゅ)、精神運動異常などの障害がおこることがあります。
成人になって感染した場合は、大部分の人は無症状ですが、発熱、発疹(ほっしん)、脳脊髄炎(のうせきずいえん)、リンパ節炎(せつえん)、脈絡網膜炎(みゃくらくもうまくえん)、肺炎などがおこることもあります。
とくにエイズなどで免疫不全(めんえきふぜん)状態の人に感染すると、激しい脳炎や脳腫瘍(のうしゅよう)などをおこし、重症化します。
慢性化すると、リンパ節の腫(は)れと眼底の異常変化が残ります。
[検査と診断]
診断を確定するには髄液(ずいえき)などの中に原虫の存在を証明しなければなりませんが、簡単には検出できないため、ふつうは血清(けっせい)検査で診断します。
なお、妊娠中に感染した可能性があるときは、産婦人科で血清検査を受けましょう。
[治療]
ピリメタミンやサルファ剤の内服を約1か月間続けます。抗生物質も内服します。早めの治療が必要です。
ペットの糞便(ふんべん)に直接、触れないようにし、豚肉はよく加熱して食べるようにします。
妊婦や、豚肉を扱う人は抗体(こうたい)検査をときどき受け、感染が証明されたら早く治療を受けてください。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「トキソプラズマ症」の意味・わかりやすい解説
トキソプラズマ症
トキソプラズマしょう
toxoplasmosis
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「トキソプラズマ症」の意味・わかりやすい解説
トキソプラズマ症
ときそぷらずましょう
栄養・生化学辞典 「トキソプラズマ症」の解説
トキソプラズマ症
世界大百科事典(旧版)内のトキソプラズマ症の言及
【ネコ(猫)】より
…そのほかにはコクシジウム症があげられる。この病原虫は3種類が知られており,そのうちの一つはあまり多くはないがトキソプラズマ症と同じ病原体である。これらはいずれも検便で診断でき,治療も可能で恐れる必要はない。…
※「トキソプラズマ症」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...