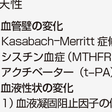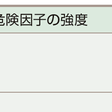内科学 第10版 「肺血栓塞栓症」の解説
肺血栓塞栓症(肺循環障害の臨床)
定義
肺塞栓症(pulmonary embolism)は,塞栓子が静脈血中に入り肺でとらえられ肺動脈の血流障害を起こした状態をいう.塞栓子の90%以上は血栓,特に骨盤内や下肢の深部静脈血栓(deep vein thrombosis:DVT)であり,肺血栓塞栓症となる.肺血栓塞栓症と深部静脈血栓症をあわせ静脈血栓塞栓症という.肺血栓塞栓症は血栓性塞栓子による急激な肺動脈閉塞に起因する急性肺血栓塞栓症と器質化血栓が肺動脈を慢性的に狭窄閉塞する慢性肺血栓塞栓症に分類され,また慢性肺血栓塞栓症の経過中に急性の血栓塞栓症症状をきたす遷延性肺血栓塞栓症がある.塞栓子によって末梢肺動脈が完全に閉塞し出血性壊死が起こった状態を肺梗塞という.肺血栓塞栓症のうち10~15%で肺梗塞を起こす.
血栓形成の危険因子
血栓の成因にはVirchow以来3つの因子(Virchowの3徴候)が知られている.血管壁の変化(血管内皮細胞の障害),血液性状の変化(血液凝固能の亢進)および血流のうっ滞である.それぞれに,先天性および後天性の因子(表7-10-4)がある.
急性期の治療と長期管理の観点から骨盤内や下肢の深部静脈血栓の有無が重要である.静脈血栓塞栓症の発症における付加的な危険因子の強度を表7-10-5に示す.
病理
大量あるいは中等量の血栓は肉眼的に診断可能である.小血栓特に微小血栓は組織学的にはじめて診断される.肺動脈には種々な段階の血栓の器質化,血管壁の弾力線維層の増殖肥厚と筋層の肥厚,細胞浸潤がみられる. 肺梗塞の合併は10~15%でみられる.肺動脈と気管支動脈の吻合部より末梢の閉塞で発症しやすい.肺組織は出血性壊死を起こす.経過とともに肉芽組織による器質化,線維化の過程を経て瘢痕化する.
病態生理
急性肺血栓塞栓症では,肺動脈の機械的閉塞,セロトニンなどの血管作働性物質が血小板から放出されることにより,肺動脈圧およびPVR(pulmonary vascular resistance)が上昇する.これが急性肺性心や右心不全および重症例での心原性ショックの原因となる.閉塞側より末梢の肺胞は死腔となり換気血流不均等分布が助長され低酸素血症となる.一方,反射性に気管支収縮も起こり気道抵抗が上昇する.肺梗塞を合併すると,血痰,胸痛,胸水や発熱などが出現する.
臨床症状
突然の呼吸困難が高頻度にみられる.広範囲の肺血栓塞栓症では失神やショック状態となることがある.ときに喘鳴が出現する.胸膜近傍の肺血栓塞栓症では胸膜痛もみられる.呼吸困難,胸痛および頻呼吸は,肺血栓塞栓症の97%にみられ,肺血栓塞栓症の3徴候とされている. 身体所見では,頻脈,頻呼吸,頸静脈怒張,Ⅱp成分の亢進,右室拍動などがみられる.
検査成績
動脈血ガス分析では低酸素血症および呼吸性アルカローシスをきたす.FDP,D-ダイマーの上昇は肺血栓塞栓症の90%以上でみられ診断に有用である.末梢血白血球数の増加や血清LDHの高値がみられるが特異的ではない.
脳部X線写真が正常であっても肺血栓塞栓症を否定する根拠とはならない.局所の乏血所見(Westermarkサイン),右肺動脈下行枝の拡張(Pallaサイン)や横隔膜上の三角錐の陰影(Hampton’s hump)などは有名な所見である.
心電図は頻脈,右脚ブロック,V1からV3の陰性T波などがみられる.正常所見のこともある.SⅠ,QⅢはまれである. 心臓超音波検査では,右心不全をきたすと心室中隔の扁平化や右室拡大を示す. 肺換気・血流シンチグラムでは,換気が正常であるにもかかわらず楔状を呈する区域性血流欠損像がみられる.
肺動脈造影では造影欠損(filling defect)や血流途絶(cut-off sign)などの所見を認める.最近では, 診断のみを目的とした場合には必ずしも必要とされなくなってきている.
胸部造影CT(図7-10-7)は機器の性能向上がめざましく,診断における有用性が高い. また造影MRIも有用である.
診断
急性で胸痛を伴う呼吸困難では本症を念頭におく.従来は,肺換気血流シンチグラムおよび肺動脈造影が診断に不可欠であったが,最近は造影CTあるいはMRIで診断可能となっている.
治療
1)抗凝固療法:
a)非分画(通常)ヘパリン:最も基本的な治療であり,活動性の出血がなければ適応となる.一般的には初回5000~10000単位を静注し,引き続き18単位/kg/時(ただし,1600単位/時をこえない)を持続静注する.5~7日間使用する.ヘパリンの効果はPTT 60~80秒あるいはAPTTを基準値の1.5~2.5倍に維持するよう使用量を調整する.
b)低分子ヘパリン:1日1~2回の皮下投与で,APTTのモニターの必要もなく,ヘパリンの持続静注と同様の効果があり,欧米では,治療のみならず予防的にも使用されている.
c)ワルファリン:効果発現までに数日を要するためにヘパリン終了の4~5日前より投与を開始し,トロンボテスト10~20%,PT-INRを2.0~3.0に維持するよう投与量を調節する.
2)血栓溶解療法:
広範囲の肺血栓塞栓症,心原性ショック例,血行動態の不安定例では有効とされ,ヘパリンなどの抗凝固療法を行ったうえで組織型プラスミノーゲンアクチベーター(t-PA)であるモンテプラーゼを投与する.
3)肺動脈血栓除去術:
カテーテルによる方法と手術療法がある.
予防
再発例が多くまた発症すると致死的になることがあり,適切な予防法および慢性期の長期管理を行うことは重要である. 肺血栓塞栓症や深部静脈血栓の危険因子を有する症例に予防的処置を行うことが,肺血栓塞栓症や深部静脈血栓の発症を明らかに予防する.抗凝固療法にはワルファリン経口投与および低分子ヘパリンの皮下投与がある.少量のアスピリン(160 mg)投与が有効との報告もある.薬物療法以外にも,手術中に下肢を間欠的に圧迫する器具の使用,弾性ストッキングの使用,早期離床など深部静脈血栓を予防する試みも重要である.
下大静脈フィルター(inferior vena caval filter:IVCF)は広範囲の肺血栓症を予防するのに有用である.本法の絶対的な適応は,肺血栓症症例で,活動性の出血のある場合,十分量および長期間の抗凝固療法を施行中にもかかわらず肺血栓症を繰り返す場合である.恒久的IVCFと一時的IVCFがある.症例に応じて使い分けが可能である.[木村 弘]
■文献
安藤太三:肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断・治療・予防に関するガイドライン.循環器病の診断と治療に関するガイドライン(2002-2003年度合同研究班報告),Circ J, 68 suppl Ⅳ, 1079-1134, 2004.
Goldhaber SZ: Pulmonary embolism. N Engl J Med, 339: 93‐104, 1998.
Stein PD: Silent pulmonary embolism in patients with deep venous thrombosis. Am J Med, 123: 426, 2010.
出典 内科学 第10版内科学 第10版について 情報