日本大百科全書(ニッポニカ) 「ダービン‐ワトソン比」の意味・わかりやすい解説
ダービン‐ワトソン比
だーびんわとそんひ
Durbin-Watson ratio
計量経済学における線形回帰モデルについて、確率攪乱(かくらん)項に自己相関があるかどうかを検証する際に用いられる統計量のこと。線形回帰モデルに関する基本的な仮定の一つとして、確率攪乱項には自己相関が存在しないことが規定される。もし、現実に作成される線形モデルの確率攪乱項に自己相関が存在することになれば、推定される係数の値の信頼性に疑問が生ずることになり、作成されたモデルにおいて、なにか重要な説明変数が見落とされていたり、モデルの関数型に問題があることになる。このことを検証するために、推定された回帰方程式から得られる残差項etを用いて次の統計量を作成する。
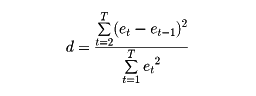
これがダービン‐ワトソン比とよばれるものであり、その値は、残差の系列に自己相関(一階の)が強くなるにつれて、正の相関のときは0に、負の相関のときは4に近づく。確率攪乱項に系列相関がまったく存在しないという仮説のもとでのダービン‐ワトソン比dの厳密な分布型は、自由度や説明変数の数、さらに説明変数の観測値の状態によっても変動する。そこで、J・ダービンとG・S・ワトソンは、系列相関0の仮説のもとでの分布について、特定有意水準に対する下側パーセント点の下限dLと上限dUの数値を作成した。モデルについて計算されたdと仮説との関係は、d<dLならば仮説は棄却され(すなわち、系列相関が存在するということ)、d>dUならば仮説は棄却されない(すなわち、系列相関不存在との仮説はいちおう維持される)ということになる。しかしdL<d<dUの場合には、dの分布が説明変数の観測値に影響されるために、系列相関の仮説については、なんらの結論も得られない。残差の自己相関が負であるときにはdの値は2より大となり、この場合にはdのかわりに4-dとして検定手続を行うことになる。
[高島 忠]

