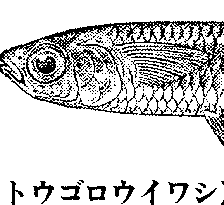トウゴロウイワシ
Allanetta bleekeri
スズキ目トウゴロウイワシ科の海産魚。別名トウゴロイワシ。この科は系統的にはボラやカマスに近く,世界中の温帯・熱帯水域から150種ほどが知られている。トウゴロウイワシは本州中部以南,黒潮流域の沿岸にふつうに見られる。体は細長くて青灰色,体側に銀白色帯が縦走する。頭部の背面と吻端(ふんたん)は黒い。一見イワシに似るが,背びれが前後の2基に分かれ,うろこも硬くはがれにくい。体長15cmに達する。海の表層を群れて泳ぎ,物に驚くとそろって空中に跳び出し,きれいな弧を描いて水面に突っ込む。夜間灯火に集まる性質が強い。産卵期は夏で,稚魚の群れは内湾でもよく見かけられる。小骨が多く不味なので食用にはされないが,まれにはカツオ釣りの餌として使われる。東京でキイワシ,浜名湖でカワイワシ,三重県尾鷲でドボなどと呼ばれる。
日本沿岸では,ほかにオキナワトウゴロウ,ムギイワシ,ギンイソイワシなどの近縁種を産するが,いずれも体長10cm内外の小型魚である。
南カリフォルニア産の近縁種グラニオンgrunionは特異な産卵生態で知られる。本種は2~9月の間,新月か満月の後の2~3夜,満潮時に大群をなして岸に押し寄せ,壮観を呈する。その中の雌がまず波打ちぎわに上がり身をよじって砂中に潜り,深さ5~6cmのところに産卵すると,続く雄は雌に巻きついて放精する。産卵後親魚は波とともに去るが,卵は砂中にとどまり,卵発生が進む。約2週間後,次の大潮の満潮時に再び波がやってくると数分以内に卵は孵化(ふか)し,仔魚(しぎよ)は波に乗って漂い去る。孵化は波の振動に刺激されて起こるという。カリフォルニア湾に産する別種のグラニオンは,やはり月齢に合わせた産卵周期を示すが,産卵行動を昼間に行う。外国産の若干の種は汽水~淡水域にすみ,なかには体型や体色がおおいに異なるもの,大型で食用魚として重要なものも含まれている。1967年,神奈川県の津久井湖に試験放流されたペヘレイは全長60cmに達する。原産地のアルゼンチンでは釣魚として人気がある。
執筆者:羽生 功
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
トウゴロウイワシ
とうごろういわし / 藤五郎鰯
[学] Hypoatherina valenciennei
硬骨魚綱トウゴロウイワシ目トウゴロウイワシ科の海水魚。トオゴロイワシともいう。新潟県以南の日本海、青森県以南の太平洋、西太平洋、インド洋に広く分布する。鱗(うろこ)が粗雑で硬く、体に密着して離れないことから、地方によりトンゴロ、カワイワシ、コワイワシなどとよばれる。ボラに近縁であるが、それより細長く、全長16センチメートルの小魚である。体側に1本の広い銀白色帯(ホルマリン固定後は黒色)が縦走し、第1背びれが小さく、胸びれが鰓孔(さいこう)上部の後方に位置し、側線がない。日本から5種が報告されているが、肛門が腹びれの基部と後端の間に開くことで他種と区別できる。日本では6~10月の間、内湾や入り江などに群れをなして泳ぐ。動物性プランクトンを主食とする。ほとんど産業利用価値がない。
北アメリカのカリフォルニア沿岸に生息する同じ科のグルニオンLeuresthes tenuisは、春から夏にかけて夜間高潮時に砂浜へ群遊し、砂の中に卵を産み付けるので有名である。この卵は10日前後砂の中で発育し、次の高潮のときに孵化(ふか)して海中へ運ばれる。
[落合 明・尼岡邦夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
トウゴロウイワシ
学名:Doboatherina bleekeri
種名 / トウゴロウイワシ
目名科名 / トウゴロウイワシ目|トウゴロウイワシ科
解説 / 岸に近い岩礁や堤防の周りを、群れで泳ぎ回るのがよく見られます。
解説 / 魚を食べる大型魚のえものとして、重要な種類です。
全長 / 20cm
分布 / 新潟県および青森県以南/朝鮮半島、南シナ海、オーストラリアをのぞく西太平洋、インド洋
出典 小学館の図鑑NEO[新版] 魚小学館の図鑑NEO[新版] 魚について 情報
Sponserd by 
トウゴロウイワシ
Hypoatherina valenciennei
トウゴロウイワシ目トウゴロウイワシ科の海水魚。全長 15cm内外。体は細長く長紡錘形。背鰭は二つあり,その間隔は広い。腹鰭は 1棘 5軟条で腹位。側線は不完全。肛門は左右の腹鰭の間に開く。体は青灰色で,体側には胸鰭基底から尾鰭基底に達する銀白色縦走帯があり,その上縁は暗色である。南日本,インド・西太平洋域に分布する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by