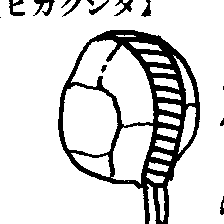ビカクシダ
Platycerium
コウモリランともいう。温室などでしばしば栽培される,ウラボシ科の常緑多年生シダ植物。狭義にはP.bifurcatum C.Chr.をさすが,園芸などではこの属(約18種および多数の園芸品種を含む)の植物の総称として使われることも多い。いずれも樹幹などに着生する中型から大型の植物で,短い根茎に相接してつく葉に2型あり,鱗状に変形した葉は腐葉土などを集める特異な形態の分化を遂げている。もう1種の葉は二叉(にさ)分岐をくりかえし,その裏面に胞子囊がつくが,特定の集りとはならない。ビカクシダの場合,鱗状の葉は長さも幅も30cmまで,胞子囊をつける葉は長さが1mに近づくこともある。葉には一面に星状毛がつく。温室などでよく栽培されるものとしてはマレーシアからフィリピンにかけて分布するP.grande J.Sm.が有名である。栽培にあたっては,ヘゴ材に着生させたり,ミズゴケで鉢植えにする。ビカク(麋角)はオオシカの角で,胞子葉の形にちなむ。英名のelkhorn fern,staghorn fernも同様である。
執筆者:光田 重幸
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ビカクシダ
びかくしだ / 麋角羊歯
[学] Platycerium bifurcatum C. Chr. var. bifurcatum C. Chr.
ウラボシ科の熱帯性着生シダ。コウモリラン(蝙蝠蘭)ともいう。また属名のプラチケリウムの名でよばれることもある。基部に重なり合う円形葉は栄養葉で、水分や腐植質を蓄える。胞子葉は長さ40~60センチメートル、先端部の裏側に胞子を密生し、熟すと褐色になる。無霜地帯では戸外で育ち、乾燥地ほど栄養葉が木に密着する。オーストラリア東部原産。「麋(び)」はオオジカのことで、胞子葉の形がオオジカの角(つの)に似るので名がついた。コウモリランの名は、栄養葉の形をコウモリに見立てたものである。
プラチケリウム属は、アジア、アフリカ、オーストラリア、ポリネシアなどの熱帯地域に17種分布する。栄養葉の巨大なオオビカクシダP. grande(Fée)J. Sm. ex K. Preslや、胞子葉が長く垂れ下がるナガバビカクシダP. willinckii T. Mooreなどが観賞温室で栽培される。ヘゴ材につけて、吊(つ)り鉢にして観賞される。多くの種類は、高温多湿を好み、冬は10℃以上を維持する。繁殖は一般には一株の株分けによるが、このほか胞子葉による繁殖も可能である。
[高林成年]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ビカクシダ(麋角羊歯)
ビカクシダ
Platycerium bifurcatum; staghorn fern
ウラボシ科の常緑性の着生シダ植物で,コウモリランともいう。南半球の熱帯に分布し,日本では観賞用としてヘゴ材などにつけてつるし,温室で栽培されている。葉は長さ 50cm以上にもなる。根茎には腎臓形で中央部が木化した葉が多数つき,栄養葉は2~3回二叉分岐して垂れ下がり,裂片の先端は鈍頭。葉の下面には星状毛が多い。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ビカクシダ
コウモリランとも。オーストラリア原産のウラボシ科の着生シダ。観葉植物として温室内で栽培。裸葉(栄養葉)は皿状で樹幹に重なり合って密着し,そこからシカの角状に先の分岐した,胞子をつける実葉を出す。ジャワ原産のナガバビカクシダは長さ1mにもなる実葉を下垂する。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by