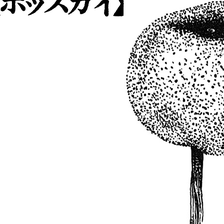ホッスガイ (払子貝)
Hyalonema sieboldi
六放カイメン綱ホッスガイ科の海綿動物。深海に産するカイメンで,相模湾や駿河湾の水深300~500mから得られている。高さ10~15cmの円筒状の体から長い珪糸(けいし)の柄(把束(はそく))をだして海底の泥中に立ち,全長50~80cmになる。この柄が僧のもつ払子(ほつす)に似ているというのでこの名がある。体の上端は平らで篩状(しじよう)板があり,体内の広い胃腔をおおっている。胃腔は放射状に並ぶ隔壁で四つの室に分かれている。珪糸は細長く,多少よじれながら束になっていて,表面にカイメンスナギンチャクEpizoanthus fatuusが共生している。骨片は錨状盤で大きさは3通りある。近縁種にオウストンホッスガイH.owstoni,ホウザワホッスガイH.hozawaiなど。
執筆者:今島 実
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ホッスガイ
ほっすがい / 払子介
[学] Hyalonema sieboldi
海綿動物門六放海綿綱ホッスガイ科に属する海産動物。外形が僧侶(そうりょ)の用いる払子(ほっす)に似たところがあるのでこの名がついた。本体は10~15センチメートルのコップ状で、その下部に長大な骨片の束があり、それで深海底に突き刺さっている。この骨片の束にはかならずカイメンスナギンチャクが共生している。コップ状の中腔(ちゅうこう)は隔壁が縦にできて内部が4室に分かれる。ホッスガイ類は微小骨片として両盤体がある。この種類では大小3種類の両盤体があり、両端の錨(いかり)状盤には葉片が8個ある。フタナシホッスガイ、オウストンホッスガイ、ホウザワホッスガイなど、日本からは数種のホッスガイ類が知られている。
[星野孝治]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ホッスガイ
六放カイメン類ホッスガイ科の海綿動物。長さ10〜15cmのコップ状の体の下に,ケイ質繊維でできた40〜70cmの細長い柄があり,白色。僧のもつ払子(ほっす)に似るのでこの名がある。体の上端はふるい状の板でおおわれる。柄の表面にはカイメンスナギンチャクが共生。相模灘や駿河湾の水深300〜500mの海底に分布し,柄で泥底に固着して生活する。
→関連項目カイメン(海綿)
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
ホッスガイ
Hyalonema sieboldi; glass-rope sponge
海綿動物門六放海綿綱ホッスガイ科。全長 50~80cm。長さ 10~15cmの釣鐘をさかさまにしたような円筒形の体と長い把束から成り,海底に立っている。体の上端は扁平で,篩状板が胃腔をおおい,胃腔は縦の隔壁で4室に分れる。骨片は三軸型。把束は細長いケイ酸質の糸から成り,その上部は細く,カイメンスナギンチャク Epizoanthus fatuusが着生している。相模湾の水深 300~500mから採集される。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by