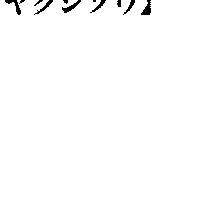ヤクシソウ
Youngia denticulata (Houtt) Kitam.
崩壊地,路傍など,日本全土の低山の陽地に普通に見られるキク科の一・二年草。朝鮮,中国,インドシナにも分布する。全体に無毛。茎は多数分枝して,高さ30~100cmになり,やや細く,堅い。葉は膜質で柔らかく,裏面は粉白を帯び,切ると白色の乳液が出る。有柄の根出葉は花期にはなく,茎葉はさじ形で粗い牙歯があり,基部は茎を抱く。8~11月ころ,上部の葉腋(ようえき)から出た散房花序に,径1.5cmほどの黄色の頭花が多数つく。小花は舌状の両性花のみからなる。総苞は黒緑色。頭花は花後,下を向き,果実が熟すと脱落して散布される。これは,本種の属するオニタビラコ属Youngiaの特徴である。瘦果(そうか)は黒褐色,披針形でざらつき,純白の剛毛状冠毛がある。和名は茎葉が薬師如来の後背に似ることに由来するという説がある。若菜をゆで水にさらし,食用とする。
執筆者:森田 竜義
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
ヤクシソウ
やくしそう / 薬師草
[学] Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak et Kawano
Youngia denticulata (Houtt.) Kitam.
キク科(APG分類:キク科)の一、二年草。全体に無毛で、切ると乳液が出る。茎は高さ0.3~1メートル、やや細く堅い。葉はさじ形で茎を抱き、質は柔らかく、裏面は粉白を帯びる。8~11月、黄色で径約1.5センチメートルの頭花を多数つける。頭花は舌状花のみからなり、花期後に下を向く。果実には白色の剛毛状冠毛があり、風により散布される。日当りのよい低山に普通に生え、北海道から九州および朝鮮半島、中国、インドシナに分布する。名は、葉形が薬師如来(にょらい)の光背に似ることによる。若葉をゆでて水にさらし、食用とする。
[森田龍義 2022年5月20日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ヤクシソウ(薬師草)
ヤクシソウ
Lactuca denticulata(Youngia denticulata)
キク科の越年草で,アジアの温帯から熱帯に分布する。日本各地の日当りのよい山地や路傍に普通にみられる。全体に無毛で茎は直立し,高さ 30~120cmでよく分枝する。根出葉はさじ形で長い柄があり,茎葉は長楕円形で低い鋸歯があり,柄はなく基部で茎を抱く。夏の終りから秋遅くまで,散房状に頭状花序を多数つける。頭花は黄色の舌状花だけから成り,総包は暗緑色である。花後,花柄は下を向き,痩果は黒褐色に熟する。冠毛は白色である。なお葉が羽状に裂けるものをハナヤクシソウと呼び,区別することもある。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
ヤクシソウ
キク科の二年草。北海道〜九州,東アジアの暖〜温帯に分布し,日当りのよい山地にはえる。茎はよく分枝し,高さ30〜120cm。根出葉はさじ形で柄があるが,茎葉は無柄で茎を抱く。全体に無毛で柔らかく,ちぎると白い汁が出る。8〜11月,枝先に黄色の舌状花のみからなる径1.5cmほどの頭花を開く。果実は黒褐色で白い冠毛がある。葉の羽裂するものをハナヤクシソウという。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by