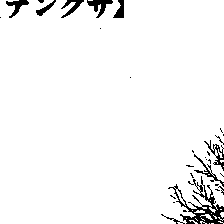日本大百科全書(ニッポニカ) 「テングサ」の意味・わかりやすい解説
テングサ
てんぐさ / 天草
[学] Gelidium
紅藻植物、テングサ科の海藻。広義には、寒天製造の主原料となるテングサ属数種の総称であるが、狭義にはそれらの代表種であるマクサG. amansii Lamourouxをさす。
マクサは暗紅色で、針金を柔らかくしたような細い体枝が密に分岐し、ふさふさとした形状となる。体高10~30センチメートル、茎枝の太さ1ミリメートル内外、小枝の太さ0.2~0.3ミリメートル。干潮線下から深さ20メートルまでの海底に叢生(そうせい)する。周年生育の多年生海藻であるが、とくに5~10メートルの深さに多産し、5月から7月にかけて繁茂する。温海性海藻のため、太平洋岸では房総半島、伊豆七島、伊豆半島、紀伊半島東半部、室戸岬などの周辺が主産地となる。日本海では能登(のと)半島、隠岐(おき)諸島や佐渡島周辺に多産する。
テングサ属中の主要種には、マクサのほかにオオブサG. pacificum Okam.、キヌクサG. linoides Kütz.、オニクサG. japonicum Okam.、ヒラクサG. subcostatum Okam. (Beckerella subcostata Kylin)などがある。オニクサは干潮線下あたりの浅所に生ずるが、ほかの3種は10~30メートルの深所に生じ、なかでもヒラクサは伊豆七島南部の島々、紀伊半島から宮崎県下あたりまでの温暖海に多産する。なお、形態がテングサ属によく似て寒天原料とされるものにオバクサPterocladia capillacea Bornet et Thuretがある(品質はやや劣るといわれる)。オバクサの生育域がほぼオニクサと同じで、体形はマクサに似る。
[新崎盛敏]
テングサ利用の歴史
テングサ類の体細胞間隙(かんげき)には10~20%の寒天質が含有されているため、その煮だし汁は熱いうちは糊(のり)状のゾルであるが(流動性を保持しているコロイド粒子)、37~35℃くらいに冷えると凝固してゲル(流動性を失ったコロイド粒子)になる特性をもっている。テングサの古名である凝海藻(コルモハ)は、すでに701年(大宝1)制定の大宝律令(りつりょう)の賦役にかかわる部分にその名が出ている。ちなみに、属の学名であるGelidiumもラテン語のgelidus=凝固に由来する。また、凝固したものを心太(こころぶと。現在のところてんにあたる)とよぶが、この名も927年(延長5)に撰進(せんしん)された『延喜式(えんぎしき)』のなかで、「京都の市場で売る」という表現で記載されている。このように、日本でのテングサ利用は長い歴史をもっているが、心太のままでは原藻体中のタンパク質や臭気成分が含まれるため、腐りやすく、運搬にも不便であった。やがて、偶然の機会から、今日につながる寒天の精製法が発見された。1658年(万治1)の冬、参勤交代の途上にあった島津藩主が京都市外伏見(ふしみ)の旅宿に泊まったおり、心太の食べ残りを旅宿の者が戸外に捨てたところ、後日それが干物のような凝質になったという。その干物は、煮ると元のように糊状液となり、やがて凝固するが、味は元のとは違って無色・無臭の美味なものであった。のちに、これに工夫・改良を加えた品を帰化僧の隠元禅師(いんげんぜんじ)が寒天と名づけたとされる(1660年前後)。心太から寒天ができた過程を今日的に解釈すると、「冬季夜間の低温で心太が凍結し、その際に寒天質と他の雑物とが分離する。翌日の昼間、解凍して水溶性の雑物が除去される。このような凍結と解凍とを繰り返して寒天質だけになる」ということになる。こうしたことから、長いこと、寒天製造に適した土地は、雪が少なく、夜間の気温が零下10℃内外の気象条件の山間地とされてきた。つまり、原料は海岸で夏季に採取され、これを遠く離れた山間地に送って冬季に製造するという状態が続いたわけである。しかし、冷凍・冷蔵の技術が進んだ今日では、場所・時期を問わず、いつでも、どこでも寒天製造が行える方式が開発されている。なお、長野県茅野(ちの)市周辺では、現在でも昔どおりの天然寒天の製造が続けられている。
[新崎盛敏]