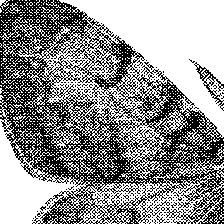マイマイガ (舞々蛾)
gypsy moth
Lymantria dispar
鱗翅目ドクガ科の昆虫。翅の開張は雄4~5.5cm,雌6~8cm。雄は黒褐色,雌はごく薄い灰褐色。色彩や大きさには個体変異があるばかりでなく,地理的な変化も著しい。ヨーロッパからシベリア,中国を経て日本全国に分布し,北アメリカには今から100年以上前にヨーロッパ産が移入され,全土に広がっている。一般に北海道産は小型で淡色,四国,九州の南部から南西諸島のものは白みが強い。年1回の発生で,成虫は夏に出る。雄はきわめて活発に昼間活動するが,雌は羽化した付近からあまり移動しない。
幼虫はサクラ,リンゴなどバラ科,クヌギ,クリなどブナ科,ハンノキなどカバノキ科,その他多くの植物の葉を食べ,しばしば大発生して山林,果樹園,庭園に大害を与える。若齢のとき糸を吐いて垂下するので,ブランコケムシと呼ばれている。老熟すると体長約6cm。黄色帯と黒色帯の縞模様で,各節に隆起があり,ことに背面隆起に生えているとげは鋭く,指先などに突きささると痛いが,毒はない。雌は,交尾後,樹幹など比較的低いところに300粒くらいの卵塊を産み,尾端の淡褐色の毛できっちりとおおう。卵のまま越冬し,4月ころ孵化(ふか)した幼虫は,若齢の間群がっているが,のちに分散する。春の終りから夏の初めに枝や葉間に糸を吐き,尾端部を固定して垂下し蛹化(ようか)する。アメリカでは森林への被害が大きいため,日本などから天敵の移入を盛んに試みている。
執筆者:井上 寛
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
マイマイガ
まいまいが / 舞々蛾
gypsy moth
[学] Lymantria dispar
昆虫綱鱗翅(りんし)目ドクガ科に属するガ。はねの開張、雄は40~55ミリメートル、雌は60~80ミリメートル。触角は櫛歯(くしば)状であるが、雄のほうが枝が長い。雄のはねは丸みをもち、一般に褐色あるいは黒みを帯びるが、雌のはねは細長く、灰黄白色で、雌雄の大きさや色彩の差は著しい。ほとんど北半球全域に分布し、日本では北海道から沖縄本島にまで生息範囲が広く、地理的変異もみられる。夏に成虫が羽化し、雄は日中活発に飛び回るが、大形で太い腹中に卵を内蔵している雌は、幼虫の食樹付近に静止し、交尾のため飛来する雄を待っている。卵で越冬し、春に孵化(ふか)した幼虫は、バラ科、ブナ科など多くの植物の葉を食べ、しばしば多発して、山林、果樹園、庭園に大害を与える。弱齢幼虫は、しばしば糸を吐いて垂下する習性をもつところから、ブランコケムシとよばれる。北アメリカ大陸には、100年ほど前にヨーロッパから移入され、全土に広がって重要な森林害虫となってしまった。日本産は、北海道のものが一般に小形で淡色、本州、四国、九州のものは濃色、ことに雄は黒褐色であるが、四国、九州の南端部では雄の後翅がすこし白みを帯び、種子島(たねがしま)や屋久島(やくしま)では、雄の後翅の大部分が純白となる。沖縄本島産はもっとも大形で、前翅まで白くなり、雌は薄いクリーム色となる。琉球(りゅうきゅう)諸島では、幼虫がモクマオウにも寄生することが知られている。
[井上 寛]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
マイマイガ
鱗翅(りんし)目ドクガ科の一種。日本全土,中国,シベリアを経てヨーロッパに広く分布。雄は開張50mm内外,暗褐色,暖地のものは灰白色を帯びる。雌は開張80mm内外,黄褐色を帯びた白色。幼虫はよく糸を吐いて下垂するのでブランコケムシと称され,カキ,リンゴ,ナシなど各種植物の葉を食う害虫。成虫は夏に現れ,雄は昼間上下に舞うような飛び方をするのでこの名がある。卵で越冬する。
→関連項目ゴールトシュミット|ドクガ
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
マイマイガ
Lymantria dispar; gypsy moth
鱗翅目ドクガ科。前翅長は雄 24~32mm,雌 35~45mm。雌雄で翅形や色彩が著しく異なる。雄は小型,全体黒褐色で,翅には黒色の斑紋があり,触角は櫛状。雌は大型で体は太く,全体淡灰色で翅にわずかな黒色斑があり,触角の櫛歯はきわめて短い。成虫は夏季出現する。雄は昼間活動し,ぐるぐる舞うように飛ぶのでその名がある。幼虫は各種の広葉樹を食害する大害虫で,ぶらんこ毛虫,ハンノキ毛虫と呼ばれている。ユーラシア大陸に広く分布し,多数の亜種に分けられていて,本州,四国,九州に産するものは L. d. japonicaという。北アメリカへはヨーロッパ産のものが入って定着し,大害虫となっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
マイマイガ
学名:Lymantria dispar
種名 / マイマイガ
解説 / オスは昼間活発に飛びます。幼虫はブランコケムシとよばれます。卵で越冬します。
目名科名 / チョウ目|ドクガ科
体の大きさ / (前ばねの長さ)♂25~30mm、♀35~45mm
分布 / 北海道~南西諸島
成虫出現期 / 7~8月
幼虫の食べ物 / サクラ、クヌギ、ハンノキなど
出典 小学館の図鑑NEO[新版]昆虫小学館の図鑑NEO[新版]昆虫について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のマイマイガの言及
【ガ(蛾)】より
… アメリカシロヒトリをはじめ,いくつかの害虫の中には,害虫や餌が入手しやすく,飼育も簡便なので,生態,生理など純生物学的な研究に役だっているものも多い。マイマイガはヨーロッパから北アメリカにかけて,重要な森林害虫であるとともに,遺伝学の実験材料として利用され,また性誘引物質の研究にも役だっている。
[環境指標としての利用]
公害や自然環境の破壊が各地で深刻な問題になるにつれ,環境調査も全国で行われている。…
※「マイマイガ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by