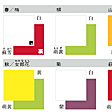精選版 日本国語大辞典 「色彩」の意味・読み・例文・類語
しき‐さい【色彩】
日本大百科全書(ニッポニカ) 「色彩」の意味・わかりやすい解説
色彩
しきさい
色、または彩(いろど)りのこと。色の科学としての色彩学の始まりは、光がスペクトル色で成立しているというニュートンの発見(1666)にさかのぼるが、大きな進展をみるのは19世紀後半以降であり、比較的新しい学問分野である。しかし自然を含めて生活環境のなかにみられる数々の色彩が、さまざまな意味で人間の目と心を刺激し、ついには色彩に心を託す形での生活文化の発展を促してきた歴史には古いものがある。
アメリカの人類学者バーリンBrent BerlinとケイPaul Kayは、ニューギニアやアフリカの原住民のなかには、その服飾の色数が豊富でありながら、白・黒・赤に相当する色彩語しかもっていない種属が21もあると指摘している。このことは、日本のもっとも古い色彩語が明(あけ)(赤)、顕(しろ)(白)、暗(くろ)(黒)で、その他の色を総括的に漠(あお)(青)と表現していたことと似ている。その後長い年月をかけて、生活文化の高まりとともに色彩語数も増えてゆき、色彩の氾濫(はんらん)とまでいわれる現代を迎えるのであるが、色彩に関する科学的・光学的な見方が普遍化した今日においてもなお、色彩は生活のなかで感性的に認識される度合いが強い。そこで、色彩を、種々の色が集まってあやなす美しい彩りという視点でとらえ、わが国における色名(しきめい)の変遷を中心にその歴史をたどると次のようになる。
[江幡 潤]
古代社会の色彩
『魏志(ぎし)』の「東夷伝(とういでん)」倭人(わじん)の条に「朱丹(しゅたん)(赤土の意)を以(も)ってその身を塗る云々」と記されている。これは呪術(じゅじゅつ)的立場とか、自分が別格の存在であることを顕示しようとした人々が、その身体を赤系統の色料で塗彩粉飾したことを表しており、色彩を意識的に生活に取り入れた原初的な形である。また、この時代にもっとも恐れられたのは肉体や魂を破壊するとされた悪魔であり、そのため黒を穢(けがれ)の色と見立て、この色には悪魔も近寄らないと考えて、黒色の布や糸を身につける俗信が生まれている。『万葉集』に「倭文手纏(しづたまき)数にもあらぬ命もてなにかここだくあが恋ひ渡る」(巻4・672歌)とあるが、ここにある倭文手纏は、人々が病魔除(よ)けとして腕に巻いた黒い糸、または腕輪状の黒い布であった。
一方、当時の厚葬思想と相まって、死者に近寄る悪魔を威嚇する色として丹砂(たんさ)(天然朱)、または中国伝来の水銀朱(硫化水銀で防腐効果もある)の朱色が珍重された。これは発掘調査された古墳内部の遺骸(いがい)安置部に多用された跡が認められることからも明らかである。色彩学の塚田敢(いさむ)は、原始時代のヨーロッパ大陸で人類が色料を使い出したのは15万~20万年前の氷河期であると推測し、当時は遺骸を赤土に埋めたり、骨を赤くしたのではないかと述べている。それは、赤い血が流れて死ぬことから、赤い色そのものに生命力があると信じたためであるとしているが、これも赤色に対する一つの認識態度であったといえる。
[江幡 潤]
万葉びとの色彩感覚
生活に色彩を取り入れるもっとも素朴な形として、野にある草や花木(かぼく)の色をそのまま利用する道がある。『万葉集』に「鴨頭草(つきくさ)に衣そ染(そ)むる君がため綵色(まだら)のごろも摺(す)らむと念(おも)ひて」(巻7・1255歌)とあるのは、鴨頭草(ツユクサ)の紫色の花汁を衣に摺り付けて、その色合いを楽しもうとしたものであろう。同じく「思はじといひてしものを朱華色(はねずいろ)の移ろひやすきあが心かも」(巻4・657歌)の朱華色は、ニワザクラとかニワウメともいわれる花の色に由来する色名であるが、この場合は紅花(べにばな)染めの紫がかったピンクをさしている。前者のただ「摺る」ことから、抽出した染液で「染める」というくふうがなされていたことがわかる。このような染色の染め上がりをよくするために、何回も染めることも行われた。「紅(くれない)の八入(やしお)の衣朝(ころもあさな)旦なれはすれどもいやめづらしも」(巻11・2623歌)の八塩は、「八入(やしお)」とも書き、何回も染液に浸すことの形容、紅はベニバナである。染色の技法の一端を伝える歌はほかにもあり、たとえば「紫は灰さすものそ海柘榴市(つばきち)の八十(やそ)のちまたにあへる児(こ)や誰(たれ)」(巻12・3101歌)の場合は、紫染めにはツバキの灰を媒染剤にするのがよいというのである。他面では高価なベニバナの使用が、布1匹(絹布2反、約20メートル)について1斤(きん)(約600グラム)と制限される事態も到来した。そのため、ごく薄いピンクしか望めないとなると、この色名を「一斤(いっこん)染め」とするだけでなく、これを契機に限りある色料の効果的な利用を考え、色の明度差、彩度差による階調美の表現に努めるようになった。この所産が繧繝(うんげん)彩色であり、のちの十二単(ひとえ)装束の袖口(そでぐち)や襟元(えりもと)などにみる配色となったのである。また季節感を考慮して、衣装の「表色」と「裏色」の組合せをくふうした「襲色目(重色目)(かさねいろめ)」という方法が創案され、そのそれぞれに自然の風物にちなむ名称をつけて、男女ともども季節にあった服装をする雅(みやび)な色彩生活が流行した。
たとえば、表色は白、裏色は青という組合せに付けられた「松雪(まつにゆき)」という名称は、季節的風情からのものであるが、多くは草木や花の名がよりどころとなっている。この発想は色名についても同じであり、その78%は動植物の名に由来している。こうすることにより、たとえば「さえた青紫」は野に咲く桔梗(ききょう)の花になぞらえて「桔梗色」と表現でき、だれもが見慣れた色だけに容易に共通の理解が得られることになる。
[江幡 潤]
中世・武家社会の色彩
『万葉集』には「橡(つるばみ)の衣(きぬ)は人皆ことなしといひしときより着欲しく念(おも)ほゆ」(巻7・1311歌)ともあり、橡色はどんぐりの毬(いが)(殻斗(かくと))の煮汁を染料とした暗い褐色みの灰色で、庶民の衣服の色であった。この歌には、身分相応の色を考えねばならなかった当時の「服色の制」や、「襲色目」をわきまえた「雅(みやび)」の心得などの煩わしさから解放されたいとの思いが読み取れるが、こうした因襲を打破して自由闊達(かったつ)な色彩文化をつくりあげていったのが武家社会の人々であった。
つまり、鎌倉時代から戦国期にかけては実力で覇をなす時代であって、つねに自己の存在を顕示しておく必要があり、日常生活においても剛直さの象徴としての「張り」と、「威(おど)し」の象徴としての豪快華麗な趣味性が強調された。前者は厚手の堅い布を直線的に仕立てる「強装束(こわしょうぞく)」を生み、後者は「鎧威(よろいおどし)」の例にみるように、明快華麗で端的な色調表現をした武具全般のデザインを生んだのである。
その一方で、武士階級から離れて、生活の内面化と新しい文化の創造に関心をもつ気運も台頭した。これらの人々は、不如意(ふにょい)ながら隠栖(いんせい)の境地を楽しみ、渋みと落ち着き、さらには枯淡の趣味に身を置いて「わび・さび」を求め、鋭敏な感性的精緻(せいち)と洗練さによって、ものの奥に潜むかすかな表情を尊んだのである。たとえば白・黒・灰色の無彩色を、その濃淡の度合いによって「清(せい)・淡(たん)・重(じゅう)・濃(のう)・焦(しょう)」の5段階に識別して「墨に五彩あり」と悟ったり、あるいは黒中心の意匠に控え目なアクセント・カラーを添えてわずかな変化を期待するにとどめ、禅宗が説く「多即一、一即多」または「色即是空」の理想と合致させようとした。あるいはまた、色の調子を弱めた濁色系に対する認識こそ、望ましい審美態度であるとする発想もあった。
千利休(せんのりきゅう)は、茶室の構成と茶道全般にわたり、数寄(すき)の趣味を強調している。『南方録(なんぽうろく)』の草庵(そうあん)の茶の湯の条に「終(つい)にかねをはなれ、わざを忘れ云々」とあるように、物理的空間の尺度を超越し、非日常的で感覚的な空間の実現に努めたのである。また、相阿弥(そうあみ)の『茶伝書』の「数寄次第」には「客之目ウツラヌガヨシ。御茶ニ精ヲ入レ名物ニ心ヲ付シメンタメ云々」とあるのは、視界を極力限定して、室内への外光を遮り、薄明の中で一期一会(いちごいちえ)の精神を満足させようとする計らいである。このような生活空間をよしとする感覚によって醸成されるものは、当然、薄明に包まれたおぼろなものを尊ぶ美意識である。もっとも、日本人にはその風土的条件もあって、野外の風景にしても霞(かすみ)にけぶる中でいままで見えていたものがしだいに明確さをなくし、二次元的情景に変わっていく情趣に心ひかれる審美眼がある。このような美的感覚が、ついには何事も「あからさま」なことを避けようとする生活感情に結び付く。これを色彩の面に置き換えると、明度・彩度ともに低く、かつ濁色系の色相が好まれるということになる。これらの色からは、沈潜した精神性が感じられる。そこで利休はこの色彩群を「わび」の心にかなうものと理解し、やがて世人もそれを利休好みの色と認めるに至る。とくにこのなかの灰色は「利休鼠(ねずみ)」と色名がつけられて、明治中期まで通用した。茶書『長闇堂記(ちょうあんどうき)』に「世にねすミ色(=鼠色)とてもてはやせり云々」とあるのは、このことをさしている。
[江幡 潤]
近世・町人社会の色彩
武家政治のなかで営々と蓄積された庶民の生活文化は、やがて江戸期を迎えて大きく開花した。江戸のいわゆる「町人文化」の特徴は、支配階級に対しては謙虚さを装いながら、意気地の人生観と洒脱(しゃだつ)さを踏まえて「粋(いき)」とも「通(つう)」ともいわれる趣味性を発揮することであった。たとえば多色刷りの華麗な錦絵(にしきえ)が禁じられると、一色刷りであることを口実にして藍(あい)刷りの特殊な錦絵を出したり、衣装にしても目だたない下着や裏地に趣向を凝らし、色彩のうえでは紫根(しこん)染めの紫色が「禁色(きんじき)」(お留(と)め色(いろ))となって使用禁止になると、蘇芳(すおう)染め(色相はにぶい紫みの赤で、灰汁(あく)を媒染にすると紫に近い色になる)による紫色をくふうし、あえて「偽(にせ)紫」とも「江戸紫」ともいいかえてなにげなくさらりと世間を納得させるなど、しゃれたことをやってのけている。日常生活での民衆の色彩を着物の一般的傾向でみると、鼠や茶や藍系統のなかから自由な配色を選び、繊細な縦縞(たてじま)模様か小紋の意匠が多用されている。これは一見じみではあるが、よく見ると瀟洒(しょうしゃ)で、着る人の心意気がうかがわれるというものであった。
[江幡 潤]
色彩の認識と表現
前述したように、科学としての色彩学の歴史は古いものではないが、ニュートンの光の分散の発見や、ゲーテやショーペンハウアーによる色彩論の試み、ヤングの三原色説の発表(1801)やヘルムホルツによるその実証(1852)などを経て、欧米においては色彩学への関心が高まった。そうしてこの影響は画家たちにも及び、とくに印象派の画家たちは新しい知見に基づく実験的な試みを繰り返している。つまり、物の色彩は一定のものではなく、光の種類や強さ、またそれを見る人によって変わるものであるとし、明確な輪郭をもつ形よりも色彩そのものを描こうとしたのである。モネの『印象―日の出』はその代表作であるが、さらに続く新印象主義や点描主義の画家たちは、スーラやシニャックの絵で理解できるように、たとえば細かな点のような色の粒で画面を構成し、見る人の「視覚混色」による鑑賞を期待するような作品を残した。
こうした色彩学の成果を表現技法に取り入れる試みは、その後も抽象絵画や商業デザインの世界で盛んに行われているが、1920年代以降、アメリカを中心に色彩調節(カラー・コンディショニング)の研究が進み、心理学との対応を通じながら建物内外の色彩設計がなされ、またデザインやファッションの世界にも積極的に応用されている。またカラー写真などの映像や、染色・塗料などの産業の諸分野や医療面においても、色彩学の研究と応用が盛んである。
[江幡 潤]
『江幡潤著『色名の由来』(1982・東京書籍)』▽『塚田敢著『色彩の美学』(1978・紀伊國屋書店)』
改訂新版 世界大百科事典 「色彩」の意味・わかりやすい解説
色彩 (しきさい)
→色(いろ)
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「色彩」の意味・わかりやすい解説
色彩【しきさい】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の色彩の言及
【色】より
…身近なものでネコやイヌやウシなど,白黒の世界に生きている。色覚色彩調節
〔色の科学〕
人間は幸いにして色を見ることができるので,色から得ている恩恵は非常に大きい。色を科学的にとらえ,より積極的にこれを活用しようという姿勢が生まれてくるのも当然といえる。…
※「色彩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...