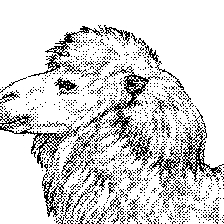改訂新版 世界大百科事典 「ラクダ」の意味・わかりやすい解説
ラクダ (駱駝)
camel
背にこぶがある大型の草食動物。偶蹄目ラクダ科ラクダ属Camelusの哺乳類の総称。背のこぶが二つのフタコブラクダC.bactrianusと一つのヒトコブラクダC.dromedariusの2種がある。ヒトコブラクダの野生種は生息せず,すべて家畜であり,フタコブラクダはモンゴルとゴビ砂漠に少数が野生するが,ほとんどのものは家畜である。体長2.2~3.5m,尾長約55cm,肩高1.8~2.1m,体重450~690kg。体は砂漠での生活によく適応し,脂肪が体になくこぶに集中する。これは食料不足のときのエネルギー源となり,また照りつける太陽の熱をさえぎる効果がある。四肢は長く,体を熱い地表から遠ざける。前後の足は幅が広く,裏側は厚い肉質で,柔らかな砂地を歩くのに適する。耳介の内側に毛が生え,まつげが長く,鼻孔が自由に開閉できるが,これらは砂が体内に入るのを防ぐのに役だつ。前胸や四肢のひざには角質化したたこがあり,荒れ地での休息に適する。硬い植物を食べられるじょうぶな舌と唇をもち,胃は4室に分かれ,反芻(はんすう)して食物をよく消化する。体毛はヒトコブラクダのほうが短く柔らかいが,両種とも体色は淡黄褐色で,赤色,黒色,白色などの色あいが強いものも多い。
ヒトコブラクダはアラビアで家畜化されたとみられ,以来,〈砂漠の船〉と呼ばれて砂漠で生活する人々に利用されてきた。人間を乗せても1日に約160kmも歩けるといわれ,130~180kgの荷をつけて時速約5kmで何ヵ月も旅ができる。食物と水の欠乏によく耐え,135kgの荷をつけ,熱い砂漠を1日40kmの割りで3日間も続けて歩けるという。ヒトコブラクダは熱い日中でも体温が40℃に上がるまで汗をかかない。尿は濃く,その量も1日1lと少ない。必要な水分は人間のように血液からではなく体組織から供給されるため,体重の40%の水分を失っても生存でき,その直後でも10分間に92l以上の水を飲むことができる。フタコブラクダではこうした機構の存在は確認されていない。
フタコブラクダの野生種は家畜種に比べこぶは小さく,四肢は長く細く,足も小さく,ひざにたこがない。体色は変異があるが,ふつう赤褐色。日中活動し,ふつう6頭,ときに単独かつがい,あるいは12~15頭でくらす。群れは一般に1頭の雄を中心に雌と子からなり,夏には標高3300mまでの山地に移動し,冬には砂漠へ戻る。塩水も飲むことができ,ほとんどあらゆる種類の植物を食べる。現在,わずか300~500頭が生息するのみとみられている。
両種とも春に出産のピークがあり,妊娠期間は370~440日で,1産1子,まれに2子を生む。4~5歳で成熟し,寿命は50年に達する。なおラクダは荷役用だけではなく,腱や骨に至るまで,ほとんどすべてが利用されている。
ラクダ科Camelidaeにはラクダのほか,南アメリカのアンデス地方やパタゴニアなどに野生するグアナコLama guanicoe,家畜として飼われるラマL.glama,アルパカL.pacosおよび生息数がきわめて少ない野生種のビクーナVicugnavicugnaが含まれる。これらの背には脂肪のこぶは見られず,ふつうラクダとは呼ばれない。
執筆者:今泉 忠明
家畜としてのラクダ
ラクダは家畜の中でもっとも乾燥につよく,塩分を含む砂漠地の植物,また灌木性の小枝や葉をもよく食べ,粗食に耐えるため,極乾燥地での飼養にもっとも適応している。他方,湿潤には弱いために,牛に比べるとその飼養の分布は,より乾燥度の高い砂漠地にかたむく結果になっている。そのうえ大家畜として乗用はもちろんのこと,物資の長距離運搬によく耐えるため,乳用家畜というよりはむしろ,乾燥地における長距離交易になくてはならない搬用家畜としておおいに用いられた。ユーラシア大陸での東西交易,サハラ砂漠を南北に走るブラック・アフリカとの交易,そしてアラビア半島での遠距離通商など,もしラクダがなければこれらの交易は不可能であり,海上交易での帆船に匹敵する役割を果たし,歴史的にみて,まさに文明間の文物交流に欠かせぬ地上搬送手段であったといってよい。たしかに馬やロバも搬用家畜として,人類史に貢献したことはたしかではあっても,砂漠を越えるキャラバンには耐ええない点で,ラクダの果たした役割には及ばない。もしラクダの家畜化がなければ,内陸アジアの歴史の見取図もおそらく別様になったであろう。
家畜化されたラクダは,ヒトコブラクダとフタコブラクダに分けられ,ヒトコブラクダは北アフリカのサハラの砂漠地帯からアラビア半島,そして北はカスピ海南岸から西北インド,オーストラリアの地域にわたって飼養されている。フタコブラクダはゴビ砂漠から南ロシアそしてモンゴルの地を主たる分布域とし,南はイラン,アフガニスタン,バルーチスターンにまで及んでいる。
ラクダの家畜化の年代および起源地はまだ明確になっていないが,他の家畜に比べれば家畜化はおそく,早くみつもっても前3000年ころ以上にはさかのぼらないとされている。そしてフタコブラクダはたぶん北イランからトルキスタンにかけての地域,ヒトコブラクダはたぶんアラビア半島で馴化(じゆんか)されたろうと考えられている。
古代においてラクダをおおいに乗用に用いた例として,バビロニア帝国を建てたセム系の人々がいる。同じセム系のイスラエルの民もラクダをもっていたことが,旧約聖書の記述から知られる。ヒッタイト人が乗用として馬をもたらしたあとも,アラビアでは軍用獣として,ラクダの利用は盛んで,ペルシア帝国の拡大のさい,ダレイオスやクセルクセス1世は,ラクダを操るアラビア兵をおおいに用いたといわれる。ローマ時代に入るとともに北西アフリカでラクダの使用は一般化し,犂(すき)をひくラクダも現れ,北アフリカからスーダンやニジェールにむけての交易も,ラクダ・キャラバンによってひらけている。中央アジアの絹の道もまた,ラクダの隊商によっておおいに促進された。
現在,このような長距離交易のためのラクダの使用は,自動車によってとってかわられ,東アフリカの一部,アラビア半島,北アフリカ・サハラ砂漠でのラクダ遊牧民を除くと,その飼養は,中近東や中央アジアの遊牧民の下での,移動時の搬用家畜として,数頭ずつ飼われるというかたちで,その飼養が存続しているにすぎない。
→牧畜文化
執筆者:谷 泰
中東におけるラクダ
世界の遊牧文化の諸相の中で,アラブのそれを特徴づけているのは,ラクダが家畜の主体をなし,文化の基層と深く関連していることである。ラクダの呼称としては,ジャマルjamal(総称,雄),ナーカnāqa(雌),バイールba`īr(単数総称),イビルibil(複数総称)がある。非アラブ世界には英語のcamelの語源となったことによりjamalがもっとも知られるが,アラブにとっては使用頻度および概念的にも後3者のほうが圧倒的に多い。バイールは雌雄の別なく1頭のラクダの意味で用いられる。
家畜化した(前3000年ころ)のもこの地域が最初だし,その後荷駄用,また乗用として広く利用したうえ,さらに戦闘用にまで訓育したのはアラブのみであった。これは他のラクダ遊牧民と比較して特筆すべきことである。アラブの大征服の歴史も,イスラム化の歴史も,ラクダの存在を抜きにしては語れない。アラブのラクダはヒトコブ(一瘤)であり,寒さと荒れ地に慣らされたフタコブラクダと異なり,暑く乾燥した気候に耐える体質をもっている。このため,広大な砂漠を渡る〈砂漠の船〉とすることができた。また長く豊かなまつげ,開閉自在な鼻,平たく大きな足裏は,砂塵,砂地に対して強く,がんじょうな歯・歯茎,それに反芻胃は粗食に耐えうる力を与えている。人間にとっては乳と肉は食用に,毛と皮は衣と住にそれぞれ有用で,ラクダ遊牧民にとって生活必需品の中でラクダからは得られないのは,穀類と金属類だけである。砂漠的環境において尚武の精神をもつラクダ遊牧民の自立的世界は,都市中心の王朝世界と競合していた。ラクダが,財貨としてはザカートや血の代償額を,またラクダ荷として重量を,ラクダ日として距離行程を測る基準単位に用いられたことも,それがアラブの生活の中に占めていた地位を示している。
執筆者:堀内 勝
象徴
ラクダについてもっとも一般的な印象は従順なことである。人が近づけば首を低くし,ひざをついて,どんな重い荷物でも背に乗せる。したがってキリスト教では,ラクダは人類の罪を背負ったキリストになぞらえられるほか,水を飲む姿が〈倹約〉の,砂漠に立つ姿が〈忍耐〉の象徴とされた。たとえばノートル・ダムやアミアンなどの大聖堂では,ラクダを描いた寓意装飾を見ることができる。バプテスマのヨハネはラクダの毛皮を着けていたので,この獣を持物(じぶつ)とする。
しかし古代から中世に流布した古い動物学では,ラクダを獣類のうちもっとも高い体温をもつ種類とみなした。毛を取り除くと体全体がやせこけて見えるのも,その熱でいつも衰弱しているためだという。またアリストテレスは《動物誌》で,ラクダは一日中交尾しつづけると述べ,ここからこの獣を好色の代名詞とする通念が生まれた。中世の人々は,キリン(ジラフ)は好色なラクダがヒョウと交わって生んだ動物とし,カメレオパルドcameleopardと呼んだ。なお,《マタイによる福音書》19章24節には,〈富んでいる者が神の国にはいるよりは,ラクダが針の穴を通るほうがもっとやさしい〉という有名なイエスのことばがあり,難事のたとえにしばしば引用される。
執筆者:荒俣 宏
らくだ
落語。明治中期に3代柳家小さんが上方の《らくだの葬礼》を東京へ移入したもの。〈らくだの馬〉と異名をとる乱暴者がフグにあたって死んだ。仲間のやくざ者半次が,通りかかったくず屋の久六をおどして,通夜に酒と煮しめを届けるように大家に掛けあわせ,断られると嫌がらせに大家のところへ行き,死骸にカンカンノウ(看々踊)を踊らせる。おどろいた大家が届けた酒を,半次と久六が飲みはじめるが,酔いがまわるにつれて,はじめおとなしかったくず屋の久六が,逆に半次をしかりつけておどかす。ふたりで空樽(あきだる)に死骸を入れてかつぎ出すが,途中で底がぬけて死骸を落とす。火屋(ひや)(焼き場)に着いてから気がついて引き返し,酔って道に寝ていた願人(がんにん)坊主をまちがえてかついで来る。目覚めた坊主がどこだと聞くと,〈ここは火屋だ〉〈なに,ひやだ。ひやでもいいからもう一ぱいくれ〉。変化に富む長編で,芝居や映画にも脚色された。
執筆者:興津 要
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報