翻訳|yield
改訂新版 世界大百科事典 「利回り」の意味・わかりやすい解説
利回り (りまわり)
yield
利回りは債券,株式等の有価証券における金利に相当する概念である。債券(公社債)は額面価格と発行価格に差(発行差額)があることが多いので表面金利のみでは債券の生み出す利子を捕捉できないので,表面金利に発行差額を加えたものと発行価格の比率である債券利回り(公社債利回り)を金利相当概念として用いる。また株式は額面価格と市場価格が異なることが普通であるので,配当の市場価格に対する比率を株式利回りと呼び,金利相当概念として用いる。
執筆者:落合 仁司(1)公社債利回り 公社債から得られる1年間の収益を買入価格で割って求められる応募者利回りと,発行者が支払利息,発行差金または償還差金および諸費用などの発行コスト総額を手取り発行額で割って求められる発行者利回りとがある。応募者利回りには償還差損益を計算に入れない直接利回りと,これをも含めた最終利回りがあるが,一般には後者が用いられる。発行者利回りは発行者の資金調達コストを示し,公社債を発行するか否かの判断基準として用いられるものである。
(2)株式利回り 通常1年分の配当金を株式時価で割って求められるが,配当金の数値は,今後の投資妙味の判断材料とする場合には予想配当金が用いられる。このような一般的な表面利回りに対して,増資後予想配当金を新株権利落理論株価で割って求められるのが裸利回りである。額面発行増資,中間発行増資などの増資採算の判断に用いられるが,近年頻繁に行われている時価発行増資の場合には関係ない。利回りは投資対象ごとの個別銘柄利回りだけでなく,複数の銘柄の平均利回りを計算して,個別銘柄との比較を行ったり,利回り水準の動きを分析したりすることも多い。平均値の計算の方法には,(a)各銘柄の1株当り配当金の平均値を各銘柄の1株当り時価の平均値で割って得られる単純平均,(b)各銘柄ごとの支払配当金総額の和を当該銘柄の時価総額の和で割って求められる加重平均がある。単純平均利回りには東証第一部全銘柄平均,同有配会社平均,東証第二部300銘柄平均,東証第二部有配会社平均があり,加重平均利回りには東証第一部全銘柄平均,東証第二部全銘柄平均がある。さらに単純平均,加重平均ともに業種別平均がある。これらはすべて東京証券取引所が発表している。一般的に利回りは高ければ高いほどよいが,配当の安定性の度合によってその水準もおのずから変わってくる。株式に対する配当は企業収益の変動に大きく左右され,確定利付きの公社債の利子に比べると安定性で劣る。その不安定性を補塡(ほてん)する分だけ利回りは高いのが通常の状態である。ところが,こうした古典的な考え方に対して,1958~59年ころ以降,株式利回りのほうが低くてもよいとの考え方が出てきた。これを利回り革命と称している。株式投資の果実は受取配当金にとどまらず,値上がり益をも含めるという考え方が支配的になったためである。この場合は企業収益の安定的成長が前提となっており,利益成長によって将来の配当金が増加することを期待したものである。84年3月時点の東証第一部上場全銘柄の予想単純平均利回りは1.07%にすぎず,このような考え方が定着していることを示している。
執筆者:山下 一宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
日本大百科全書(ニッポニカ) 「利回り」の意味・わかりやすい解説
利回り
りまわり
yield
有価証券への投資の結果生じる配当・利子などの有価証券の買入れ価格に対する割合。証券市場のように有価証券の売買を通じて資金の貸借が行われる場合、資金の貸し手、つまり有価証券の買い手は、有価証券を額面価格とはかならずしも一致しない一定の価格で購入し、有価証券が債券であるときはその満期を通じて(株式の場合は満期がないが)、その債券の券面に記載された表面利子(株式の場合は発行者の業績に応じての配当)を獲得する。この表面利子はクーポン利子ともいわれ、これに対する証券の額面価格の割合を表面利率またはクーポン・レートという。そして、表面利子に対する証券価格の割合を利回りとよぶのである。
新規証券の発行市場において、証券はかならずしも額面価格で発行されるわけではない。証券発行者の債務償還の信頼度が高いほど額面に近い価格で発行することができる。一般に公共債は民間債より信頼性が高く、民間債でも発行企業の業績に応じて格付けがなされる。発行者にとっての発行者利回りは、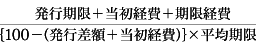
によって算出される。他方、証券の購入者にとっての応募者利回りは、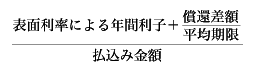
によって算出される。
株式の場合には、新規株式は額面価格で発行されることもあるが、多くの場合はその時の株式流通市場での株価に基づいて発行される、いわゆる時価発行が多い。したがって利回りは配当に対する上のような意味での株式発行価格の割合となる。
既発行の債券や株式が売買される証券流通市場においては、証券の価格はその時その時の需給を反映して変動する。したがって、流通利回りは利子あるいは配当に対するその時々の流通市場における証券価格の割合となる。流通利回りは応募者利回りに密接に反映する。投資家は新規発行証券の利回りとその証券の流通市場での利回りを比較して、有利なほうを選好するからである。
1960年ごろには、本来高位にあった株式利回りが、債券、預金の利回りより低くなった現象をとらえて「利回り革命」ということばも誕生した。また、利回りと市場利子率は一致する。各金融資産の市場間に裁定が働くからである。したがって、市場利子率が上昇すると証券価格は低下し、逆に下落すると上昇するという関係が生ずる。
[原 司郎・北井 修]
『阿達哲雄著『金利』(1975・金融財政事情研究会)』▽『原司郎編『テキストブック金融論』(1980・有斐閣)』
不動産用語辞典 「利回り」の解説
利回り
出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報
投資信託の用語集 「利回り」の解説
利回り
投資元本に対する収益の割合のこと。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「利回り」の意味・わかりやすい解説
利回り
りまわり
「金利」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
世界大百科事典(旧版)内の利回りの言及
【株価収益率】より
…1920年代のアメリカで生まれた株価評価の考え方であり,今日まで主流を占めて使用されている。株式投資の採算は従来,株主配当すなわち利回りを基本としてきたが,企業基盤の確立,高度経済成長時代での投資活発化を背景に,企業の収益力,安定性に加え成長性を重視する傾向が強くなり,58年前後の,いわゆる利回り革命前後より普及が始まり,今日では株価評価上,最も代表的な指標となっている。株価収益率が高いということは会社の利益に比べ株価が相対的に高く,逆に低いということは株価が利益に比べ割安ということになる。…
【金利】より
…(4)貸出金利 金融機関の貸出しに対する金利で,従来は銀行,信託銀行等の貸出金利には臨時金利調整法によって上限が存在したが,1979年以降しだいに緩和され,94年10月に金利規制は廃止された。(5)債券利回り 債券は額面価格と発行価格に差(発行差額)があることが多いので,表面金利に発行差額を加えたものと発行価格の比率である債券利回りによって金利を表す。また債券は債券市場において流通するので,売却価格と取得価格の差(キャピタル・ゲインあるいはキャピタル・ロス)が生じうる。…
※「利回り」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...

