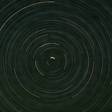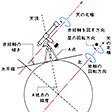精選版 日本国語大辞典 「天体写真」の意味・読み・例文・類語
てんたい‐しゃしん【天体写真】
- 〘 名詞 〙 天体に存在する星などを撮影した写真。
- [初出の実例]「今度の写真に至ては〈略〉我国天体写真の嚆矢と云ふべきなり」(出典:郵便報知新聞‐明治一六年(1883)一〇月一八日)
日本大百科全書(ニッポニカ) 「天体写真」の意味・わかりやすい解説
天体写真
てんたいしゃしん
astronomical photography
天体の位置、形状、その分布状態などを写真によって記録するものをいう。フランスのダゲールが銀板写真技術を1839年に発明し、その翌年にアメリカのドレーパーが月の写真撮影に成功したが、それ以後天体の写真撮影は急速に発達した。1845年にはフィゾーらによって太陽の写真が写され、1851年にはベルコウスキーJohann Julius Friedrich Berkowskiによって皆既日食の写真が写された。太陽や月よりも一段と暗い恒星の写真も1850年にアメリカのボンドWilliam Cranch Bond(1789―1859)によって写されている。
写真術がいち早く天体観測に取り入れられた理由は、客観性のある記録を残せることである。それまでは眼視観測をしており、観測者の経験や能力により見え方が異なっていたので問題が多かった。初期のころの写真は非常に感度の悪いものであったが、長い年月の間に次々と改良が加えられ、現在では目の感度に匹敵するものがつくられるようになった。
写真観測を行う利点は、(1)露出時間をかけることにより光のエネルギーを蓄積できる、(2)短時間露光によって太陽のような明るい天体も撮影できる、(3)光の量を肉眼より精度よく測定できる、(4)肉眼に感じない紫外線や赤外線でも撮影できる、(5)人間が行くことがむずかしい大気圏外での観測を可能にした、(6)客観性のあるデータを長期間保存できる、などである。
このような特徴があるために、次のような天体観測の分野で写真観測が行われて、数多くの成果を生み出してきた。(1)時刻観測や緯度観測(写真天頂筒など)、(2)天体の精密位置の測定と星図、星表の作成(アストログラフなど)、(3)惑星や月、流星、彗星(すいせい)などの平面形状の観測(惑星写真儀など)、(4)天体のスペクトル観測(分光写真儀など)、(5)星団や星雲、銀河内での天体の分布や位置の観測(シュミット・カメラなど)など。しかし、天体写真では明るさの測定精度が0.1等級程度しかなく、一つ一つの星のよりよい精度の観測のために光電子増倍管を使った観測が行われるようになった。また、近年の電子技術の発達により、写真と同様に二次元の受光面をもった受光素子が使われるようになってきた。これは感度と精度が写真よりよく、入射光量に比例した出力が数値データとして得られ、コンピュータによる画像処理が直接できるので、近代的な天文台では多く使われるようになっている。
ただ、1枚の写真乾板に含まれる受光乳剤の数は何億個を超える膨大な数になっており、データを記録しておく点においては、画素数が百万程度の当時の受光素子より優れていた。そのため広視野を同時に観測するようなシュミット・カメラなどによる観測には写真が有効であった。一方、CCD(電荷結合素子)に代表される受光素子の感度は目の感度を凌駕(りょうが)するまでに向上し、1000万画素規模の大型のものも供給されるようになった。そのため、1990年代には、大型の写真乾板やフィルムの製造が中止された。以後、半導体技術の進歩に伴い、受光素子の性能は飛躍的に向上している。多数のCCDをモザイク状に並べて受光面積の広いカメラがつくられるようになってきた。たとえばハワイ観測所のすばる望遠鏡に搭載されている超広視野カメラHSC(Hyper Suprime-Cam。116個の高感度CCDからなる合計8億7000万画素の巨大なデジタルカメラ)は、満月9個分の広さの天域を一度に撮影できる。2013年にアンドロメダ銀河M31のほぼ全体を一視野でとらえたファーストライト画像が公開された。
風景や人物を写す普通の小型カメラでも天体写真を撮ることができる。カメラを夜空に向けて固定しておいただけで、天体の日周運動を写すことができる。カメラを望遠鏡に取り付けて撮影すると拡大して写せる。ただし、恒星は非常に遠いので1秒角より小さく、いくら拡大しても大気の揺らぎによる広がりしか写らない。カメラや望遠鏡を赤道儀などを用いて日周運動にあわせて動かしながら撮影すると、星野(せいや)写真や星団・星雲・銀河のきれいな天体写真を撮ることができる。惑星の撮影のためには、それぞれの惑星の固有の動きにあわせたり、露出時間を短くする必要がある。
[磯部琇三・宮内良子 2015年5月19日]
改訂新版 世界大百科事典 「天体写真」の意味・わかりやすい解説
天体写真 (てんたいしゃしん)
19世紀半ばに写真が発明されるとすぐ天文学への応用が始まった。M.ウォルフやE.E.バーナードの活躍が著しい。技術的には写真用色消しの長焦点屈折鏡,広視野のアストログラフ,さらに広視野をねらったシュミットカメラを生み出した。写真利用の一つの頂点としてパロマーの48インチシュミット望遠鏡によるパロマー写真星図がある。現在,ヨーロッパ南天天文台やイギリス・オーストラリア連合天文台のシュミット望遠鏡による南天の写真が追加されている。分光観測でも写真が主流で,初期にはヘンリー・ドレーパー星表というスペクトル分類の金字塔を作った。その後の天体大気の観測はすべてスペクトル写真に多くを負っている。しかし近年,天体観測での写真の比重は下がっている。光電観測が一般的になってきたし,二次元固体素子の発達に期待が寄せられている。この傾向は測光が光電管で行われることから始まり,飛翔(ひしよう)体による観測とコンピューターの発達が拍車をかけた。しかし,写真が完全になくなるのは近いこととは思えない。記憶容量の多さと保存の安定さ容易さは代えがたいものがある。
写真は像を直接目で見るだけでも多くの研究作業ができる。だが多くの場合,乾板上の像の位置や写真粒子の黒みを測る。写真観測は露光,測光,また位置測定用較正,現像,測定の段階を経る。露光前に乳剤とフィルターの選択が必要である。日本では天文用乾板の製造は中止され,コダック社がほとんどの需要をまかなっている。乾板は大きさ,厚さのほかに分光感度,粒状性などが選択の基準である。暗いものを見るにはフィルターとの組み合わせで,背景光との対比をあげることが大事である。現在,可視光ではⅢaj増感乾板に5000Å以短をおとしたフィルターをかけた写真がいちばん深いところをとらえている。天体用乳剤は相反則不軌(光化学反応量が作用する光の強さと時間の積で決まらない)の小さいものである。スペックル写真のように1/100秒より速い露光をする場合はふつうの写真と同じでよい。また電子写真では粒子の細かい,ラチチュードの広いものが使われる。増感の方法は,非整色乾板ではフォーミングガス(数%の水素を混ぜた窒素)を流してのベーキング,色素乾板では硝酸銀浴が使われる。露光時の冷却法も有効である。現像には乳剤ごとに指定があるが,用途に応じた選択が効果的である。乾板関係はコダック社のパンフレット《科学技術用写真乾板》が有用である。
星野写真における天体の位置は,精密に位置の測られた標準星に基づいて測る。明るさも明るさの標準星につき,像の直径や黒みと明るさの関係を調べそれから目的星の明るさを知る。空の低いところでは大気の厚さによる吸収を補正しなければならない。分光乾板では,露光時に放電管などのスペクトルを星のスペクトルの上下に焼き込み,これにより波長を測る。また明るさの比のわかった光源を焼き込み,黒みと明るさの関係を乾板ごとに測って用いるのがふつうである。
執筆者:近藤 雅之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「天体写真」の意味・わかりやすい解説
天体写真
てんたいしゃしん
astrophotograph; celestial photography
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
百科事典マイペディア 「天体写真」の意味・わかりやすい解説
天体写真【てんたいしゃしん】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の天体写真の言及
【科学写真】より
…顕微鏡や分光撮影装置(分光写真)なども同様で,この分野の光学機器は種類が多い。天体撮影では星のスペクトルの研究や,位置の測定,明るさ(等級)の測定など,写真(天体写真)によって初めて研究が可能になる。ホログラムによる立体像,魚眼レンズやパノラマカメラによる空間の解析,ガストロカメラによる消化器官内部の観察なども代表例といえる。…
※「天体写真」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...