関連語
精選版 日本国語大辞典 「秉燭」の意味・読み・例文・類語
へい‐しょく【秉燭】
ひょう‐そくヒャウ‥【秉燭】
ひん‐そく【秉燭】
普及版 字通 「秉燭」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
世界大百科事典(旧版)内の秉燭の言及
【行灯】より
… 行灯の内部には油皿をおき,これにナタネ油などの植物性油をつぎ,灯心を入れて点火したが,この油皿の中の灯心をおさえ,また灯心をかき立てるために,搔立(かきたて)というものが用いられ,これには金属製や陶製の種々な形態のものがあった。また灯心を皿の中央に立てるようにくふうした秉燭(ひようそく)とよぶものが作られたが,これはふつうの油皿よりも火のもちがよく,しかも油が皿裏にまわることもないので,多く掛行灯などに使用された。油皿は古くは路次行灯のように底板におかれたが,小堀遠州が丸行灯を作って以来,火袋の中央に蜘手(くもで)を設けて,ここに油皿をおいたという。…
※「秉燭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
関連語をあわせて調べる
[名](スル)1 人から受けた礼・贈り物に対して行為や品物で報いること。また、その行為や品物。「地酒を贈って返礼する」2 仕返しをすること。また、その仕返し。意趣返し。返報。[補説]書名別項。→返礼[...


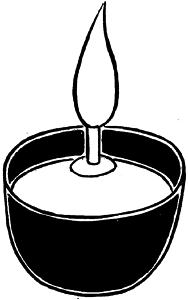
 世
世 の
の (ごと)し、
(ごと)し、 を爲すこと
を爲すこと 何(いく
何(いく ぶ。良(まこと)に以(ゆゑ)
ぶ。良(まこと)に以(ゆゑ) るなり。
るなり。