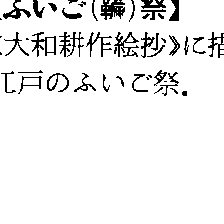精選版 日本国語大辞典 「鞴祭」の意味・読み・例文・類語
ふいご‐まつり【鞴祭】
- 〘 名詞 〙 =ふいごうまつり(鞴祭)《 季語・冬 》 〔俳諧・誹諧初学抄(1641)〕
改訂新版 世界大百科事典 「鞴祭」の意味・わかりやすい解説
鞴祭 (ふいごまつり)
旧暦11月8日の行事。鍛冶・鋳物師・たたら師・白銀屋など,ふいごを使う職人のあいだで行われ,さらに風呂屋・のり屋・石屋など,広く火をたく職人のあいだにも普及していた。この日は天からふいごが降ってきた日だといい,業者はふいごにいろいろのもの,とくにミカンを供えて,これを集まって来る子どもたちにまいてやるふうがあった。京都を中心に盛んになり,のち江戸に移り,やがて全国的に広まった。その起りについて,知恩院の鎮守賀茂明神の祭りに始まるとの説があるが信じ難い。仲冬のころは日の光が衰えるころであり,これを復活させるために火をたいて祈念するというふうが古くからあり,〈御火焼き(おひたき)〉といって今も伏見稲荷をはじめ京都の諸社では盛んであるが,そうした信仰と,稲荷神が鍛冶神として信仰されだしたこととが相まって,火をもっぱら用いる職業者のあいだで成立したものと考えられる。
執筆者:石塚 尊俊
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
百科事典マイペディア 「鞴祭」の意味・わかりやすい解説
鞴祭【ふいごまつり】
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
世界大百科事典(旧版)内の鞴祭の言及
【ふいご(鞴∥吹子)】より
…最も著名な国内の産地は大坂天満で,鞴屋町という町名があったが,ふいごのことを別名〈伝馬〉と呼んだのも,産地天満がなまったものである。旧暦11月8日には,ふいごを使う職人によって〈鞴祭〉が行われており,当日は仕事を休み,ふいごを清めて祭る民俗行事となっている。【葉賀 七三男】
[未開社会のふいご]
未開社会で用いられている原始的な形式のふいごには,獣皮を縫い合わせて作った一つないし二つの皮袋を手または足で圧して送風する皮袋型,木製の円筒にピストンをしっかりはめたポンプ型,2枚の木板を獣皮でつないだアコーディオン型などがある。…
※「鞴祭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...