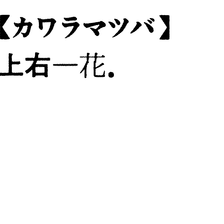カワラマツバ
Galium verum L.var.asiaticum Nakai f.nikkoensis(Nakai)Ohwi
河原の土手や山野の日当りのよいところに普通にみられるアカネ科の多年草。名前は河原松葉の意味である。若芽を食用とする。根はひげ状で,アカネのように赤くなる。茎は高さ60~80cm,四角くて堅い。葉は松葉に似て長さ1~4cm,茎の上部のものは短くなる。6~12枚の葉が輪生しているが,このうち2枚だけが真の葉で,他は托葉が分裂して葉のようになったものである。花は4数性で小さく,茎の上部の真の葉の葉腋(ようえき)から出た枝に多数つき,夏に咲く。花冠は直径2.5mm,白色。子房は下位,2室で各室に1胚珠がつく。子房室がそれぞれふくらむため,果実はひょうたん状となり,熟すと二つに割れる。北海道から九州,さらに朝鮮に分布する。花の黄色いものをキバナカワラマツバf.asiaticumという。子房に密に毛があり花が淡黄色のものをエゾノカワラマツバvar.trachycarpumといい,北海道から東アジアに広くみられる。なお種としてはヨーロッパまで分布していて,ヨーロッパでは根を赤色染料に,茎の搾り汁をチーズ製造に利用した。英名をbedstrawという。
執筆者:福岡 誠行
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
カワラマツバ
かわらまつば / 河原松葉
[学] Galium verum L. var. asiaticum Nakai f. nikkoense (Nakai) Ohwi
アカネ科(APG分類:アカネ科)の多年草。茎は高さ60~80センチメートル。葉は細く、長さ1~4センチメートル。6~12枚の葉が輪生するが、真の葉は2枚で、他は托葉(たくよう)が分裂し葉状となったもの。花は白く、夏に開く。向陽地に群生し、日本と朝鮮に分布する。名は、河原に多く、葉が松葉に似ることによる。花が黄色い品種をキバナカワラマツバ、淡黄色の品種をエゾノカワラマツバという。
[福岡誠行 2021年5月21日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
カワラマツバ(河原松葉)
カワラマツバ
Galium verum var. asiaticum
アカネ科の多年草。いたるところの山野や草地に生える。茎は直立し高さ 60cmになる。葉は線形で長さ2~3cm,輪生のようにみえるが本来の葉は2枚で対生し,他の6~8枚は托葉の分れたものである。夏,茎頂や葉腋に円錐花序を出し,白色の小さい花を密につける。花冠は深く4裂し,おしべは4本,めしべは1本ある。若い苗は食用にする。花の黄色のものをキイロカワラマツバといい北半球の温帯に広く分布する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「カワラマツバ」の意味・わかりやすい解説
カワラマツバ
北海道〜九州,東アジアの日当りのよい山野の草地にはえるアカネ科の多年草。茎は直立し,高さ50〜70cm。葉は線形で,8〜10枚輪生する。夏,花冠が4裂する白色の小花を円錐状に密につける。黄花品もある。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by