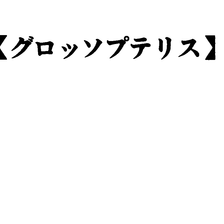グロッソプテリス
Glossopteris
約2億8000万年前の二畳紀に南半球のゴンドワナ大陸で繁栄をきわめ,次の三畳紀まで生きながらえたシダ種子類の葉に与えられた形態属名。舌状の単葉で二次脈が細脈となって網目を作っているのが最大の特徴で,これを含む植物群はグロッソプテリス植物群として知られている。カタイシア植物群のギガントプテリスは主脈から出る二次脈が羽状を示し,それより出る三次脈,四次脈が細脈となって網目を作るが,グロッソプテリスでは主脈から出る二次脈がすぐ網目を作るので,同じ単葉でも一見して両者の区別がつく。この植物の生殖器官は第2次世界大戦後,南アフリカで発見されたのがきっかけとなって,アフリカはもちろんゴンドワナ大陸の他の地域インドからも次々と発見されたが,形態は種々さまざまであった。そのためこれらの植物はグロッソプテリス1属の下にまとめられないとして,現在ではグロッソプテリス目として,その中にグロッソプテリス属をはじめ多数の属が設定されている。北半球から報告されたものは系統の違うものと思われる。
執筆者:浅間 一男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
百科事典マイペディア
「グロッソプテリス」の意味・わかりやすい解説
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
グロッソプテリス
学◆Glossopteris
裸子植物グロッソプテリス類の基準属。ゴンドワナ植物界を代表する植物。200種以上が知られるが,分類は混乱している。葉は舌状の単葉で長さ3~40cm。規則的で遊離脈のない網状脈をもつ。生殖器官は多様だが,栄養葉の向軸面につくという共通点がある。多くは氷河周辺の湿地生で落葉性。ペルム~三畳紀にかけて産出。一部は精子受精したことがわかっている。
執筆者:徳永 重元・西田 治文
出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報
Sponserd by 
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内のグロッソプテリスの言及
【アンガラ大陸】より
…大葉類のAngaridium,Angaropteridium,イチョウ類に近い形のGinkgophyllum,Rhipidopsis,有節類のRhyllotheca,Paraschizoneuraなどが産出する主要な植物化石である。アンガラ植物群にテチス海をへだてて対立する南半球のゴンドワナ植物群は単葉のグロッソプテリスGlossopteris類が9割も占めて,きびしい気候下に生じたことを示しているが,アンガラ植物群の中の大葉類には単葉がなく,羽状複葉性の植物ばかりで,これは単葉は羽状複葉から環境の悪化が原因して生ずるという原則からみて,ゴンドワナ植物群よりもゆるやかな気候下に生じたことを示している。しかし,ときにアンガラ植物群の中に南半球ゴンドワナ植物群の特徴属であるグロッソプテリスやガンガモプテリスGangamopterisが報告されることがある。…
【シダ種子類(羊歯種子類)】より
…中国や朝鮮ではスフェノプテリス,ペコプテリス,アレソプテリス,エンプレクトプテリスEmplectopterisなどの葉に種子のついた化石が報告されているが,日本では古生代の植物の産地は少なく,種子をつけた葉は発見されていない。 南半球ゴンドワナ大陸の主要植物であるグロッソプテリス目Glossopteridalesもシダ種子類で,葉は[グロッソプテリス]Glossopteris,ガンガモプテリスGangamopterisの2形態属にまとめられているが,繁殖器官は種々さまざまで,とても2属にまとめられない。グロッソプテリス類は単葉で2次脈が細脈となり網目をつくる。…
【大陸移動説】より
…今日まで大陸移動の証拠としてあげられているものに次のような事実がある。(1)石炭紀(約3億年前)の植物分布 たとえば,グロッソプテリス,ガンガモプテリスなどのシダ種子類の1属の化石は南アメリカとアフリカの南部,マダガスカル,インド,オーストラリア,南極大陸にわたって見いだされる。(2)二畳紀初期(2億8000万年前ころ)の淡水生爬虫類の一種メソサウルスの化石分布 南アフリカと南アメリカ南東部だけに産する。…
※「グロッソプテリス」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by